
書評|アーロン・S・モーア著 『「大東亜」を建設する 帝国日本の技術とイデオロギー』
「総合技術」の失敗とその幻影
評者|楊光耀(@00ur0b0r0s)
日本の近現代史を考えると、戦後の民主主義的な社会の成長に対し、戦前の帝国主義的な国家の失敗は対比的に描かれがちである。非合理的で抑圧的な国家主義が、敗戦によって合理的で自主的な民主主義へと大きく転換したといったように、先の大戦が歴史の断続として浮かび上がることが多い。これに対し本書は、戦後と戦前の二つの時代に通底する社会構造を、社会と技術の関係に迫真することで連続的に総括せんと試みる野心的な研究である。そこで焦点があてられるのは「総合技術」といわれる、戦前日本の国家計画や対外戦略の背景にあった社会に対する技術である。同時に筆者はそこから補助線を引き、戦後から今に至るまでの社会問題の根本を暴きだそうと企図する。
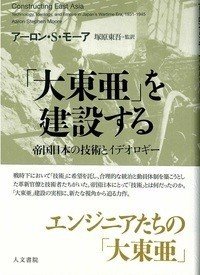
「大東亜」を建設する: 帝国日本の技術とイデオロギー
戦前当時、社会と技術の関係や意味を巡って、政治家、官僚、技術者、知識人の間で多くの議論が交わされていた。技術は政治家にとって強固な共同体を支える基盤であったし、官僚や技術者にとって様々な社会問題を解決するための鍵であった。一方、知識人にとっては、社会発展のために人々の生活に組み入まれるものであり、同時に発展の目的を問う存在であった。これらの複数の技術論は、やがて「技術的想像力」と呼ばれる思想へと発展していく。それは単なる技術の合理化と生産効率を最大化のみならず、同時に技術による社会・経済・文化の発展を射程に含めた社会主義的営為であった。そこで要請される技術が、複数の専門分野の技術を統合した「総合技術」であり、「総合技術」を通して日本の発展、さらにはアジア全体の発展が推進されていく。
ここで特筆すべき著者の視点は、先述のように戦前と戦後といった時代の断絶を超越した技術的視点である。「総合技術」は戦前の帝国主義と結合して対外進出戦略を鼓舞し、戦後には経済発展の骨格となって国土総合開発を推進していった。著者は、戦前の国家の生産体制から戦後の民間の経営主義までの地続きの構図を「総合技術」を介して描き出している。そして、このように「総合技術」と政治思想や対外戦略が結合されることを、著者は「テクノ・ファシズム」と称している。(「ファシズム」は異なる二つの意識形態・構造の統合という意味で用いられており、帝国主義の反近代的イデオロギーが「総合技術(=テクノ)」の近代的システムと結び付けられている。)
本書中では、「テクノ・ファシズム」の具現化として、南満州や朝鮮半島における豊満ダムと水豊ダムの建設や北京郊外の新都市計画といった土木技術の対外的実践に注目する。これらの対外的土木事業は多くの技術官僚たちの野心的計画であり、当時の日本最先端の「総合技術」の対外的発揚でもあった。豊満ダム建設においては、日本の技術によって当時のアジア随一の貯水量を誇るダムの建設が可能になり、ダムによって周辺一帯に多大な電力供給と農耕用地をもたらすと宣伝された。また、北京郊外の新都市計画においては、日本の都市計画によって中国の伝統の保存とインフラの近代化によって都市の発展をもたらすと宣伝された。しかし、これらの計画は実現化の過程において、現地の不確かなデータや条件に基づくものであったり、また現地住民との政治的、経済的対立や多くの犠牲を伴うものであったり、必ずしも計画当初通りに実現されたものではなかった。
これらの「テクノ・ファシズム」政策を考案し、推進したのはイデオローグである「革新官僚」と呼ばれた技術官僚たちであった。彼らは技術官僚でありながらも、同時に政治的影響力を持ち、「総合技術」によって国家統治のシステムや対外戦略を考案し、多くの政治家のブレインとなっていた。なお「革新官僚」たちは当初決して単なる専門技術による生産体制の向上といった官僚主義的・全体主義的な国家像を描いていた訳ではなく、先述の「技術的想像力」の影響から、あくまでも生産効率向上の結果、国民一人一人による主体的創造性の向上による国家発展を志向していた。
二つの異なる意識形態・構造の統合された「テクノ・ファシズム」は、理想的な「総合技術」が生産効率の最大化によって計画発展の合理化を進め、技術による社会問題の解決と国家統治を行い、さらには日本の発展によって中国含めた東アジア全域の共存繁栄を企図する社会主義的な「テクノ・ユートピア」を志向する一方で、現実的には帝国主義的な対外侵出において様々な政治的・経済的対立をもたらし、現地の労働力の搾取や住民の抵抗といった「ディストピア」として露呈した。また結果的には、対外侵出、戦争突入、戦線拡大、敗戦といった現実によって、日本国民やアジア諸国民に多大な犠牲をもたらし、「テクノ・ファシズム」は失敗に終わる。
さらに、著者は「テクノファシズム」がもたらした植民地搾取による対外的な対立問題は、戦後には日本国内での国土総合開発や経済成長の際に社会的弱者に対する公害問題、移住問題、さらには近年の原発問題へと、対内的に転換されたものであると喝破し、その根本にある「テクノ・ファシズム」的構造は変わっていないと論難しており、そこから戦後日本の経済成長に伴う負の側面や、戦後日本のODAが発展途上国にもたらした諸問題に対して鋭利な批判を向けている。
著者の戦前体制の史実へ肉薄する姿勢と、一貫した「テクノ・ファシズム」への厳しい視点にはもはや執念すら感じる。そもそも、先の大戦においては、日本のみならず、当時の植民地の満州国や朝鮮半島、戦勝国のアメリカといった、様々な国の視点と立場が複雑に入り乱れている。通例的には、複数の国家間の様々な政治的立場と各国間の文化的優劣観は、史実を歪め本質を曇らせてしまう。しかし、著者の一貫した視点は、これらの複雑な史実を相対化し、戦争によって分断されたと見られがちな日本の両時代を超越して真相を告発しようとしている。それは、国家の合理主義的な社会体制と技術至上主義的立場に対する、筆者の強い反省でもあるように思われる。
ところで本書の命題になっていた、社会統治のための技術が統合されて高度にシステム化された「総合技術」は、その名前から容易に「総合芸術」としての建築の概念を連想させる。事実、霞が関ビルの建設といった、戦前に軍需産業に関わっていた人々が戦後の建設業界の技術発展を支えていた。建築家が「総合芸術」としての建築といった概念を持ち出すとき、そこには、「総合技術」の幻影がどこかに見え隠れするようにも思える。なぜなら、原理的に建築には、あらゆる条件や技術や思想や環境を一つに統合しがちな「総合」的思考を持ち合わせているからである。
ただ、最近の現代建築においては「総合技術」に見られた政治的野望は、すっかりどこかへ行ってしまったようだ。だが、それは逆説的に日本の戦後の近代建築が徐々に政治の表舞台から影を潜めて行ったことを映し出しているようにも思われる。つまり、かつて建築家は国家的象徴や先進的技術を志向していたが、やがてその役割が薄れていったために、当時の幻影を抱きながらも、実体としては言説遊戯への矮小化、経済活動への従属化といった現状の乖離があるのではないか。
しかし、戦時中の設計競技から終戦直後の国土計画や70年代の建築運動の頃までは「総合技術」的傾向があったことは忘れてはならない。建築が国家を先導し、その象徴や技術を担っていた時代があったことは遠い昔のことではない。それは今も建築の記憶の片隅に眠っており、現在は時代錯誤に思われても、今後どこかで真に「総合性」が呼び覚まされる時がやって来るかもしれない。その時、建築家はようやく付き纏っていた幻影から解放されるだろう。同時にかつての失敗も再び起こり得る。その懸念の払拭のためにも、本書は遠い彼方へ声を投げかけているような気がしてならない。
書誌
著者: アーロン・S・モーア
翻訳:塚原 東吾
書名:「大東亜」を建設する: 帝国日本の技術とイデオロギー
出版社:人文書院
出版年月:2019年12月
評者
楊光耀(@00ur0b0r0s)
1993年中国西安生まれ東京育ち。2018年東京大学工学部建築学科卒業。2020年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。2020年度より都内設計事務所勤務。
・・・
ニュースレターあります
メニカンの最新情報を受信箱へおとどけします。是非ご登録ください。
メニカンの活動を続けるため、サークルの方でもサポートいただける方を募っています。良ければよろしくおねがいします..! → https://note.com/confmany/circle
