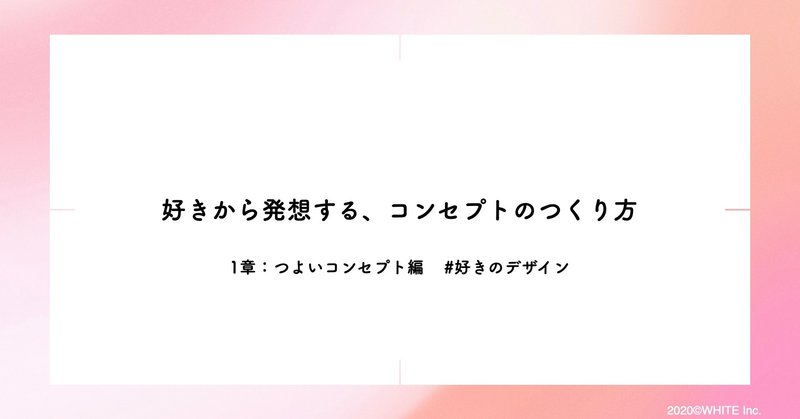
「好きから発想する、コンセプトのつくり方」 1章:つよいコンセプト編 #好きのデザイン
大学生頃、卒論のテーマに選んだのが、「いいコンセプトのつくり方」でした。しかし、当時のぼくはそのテーマで書き上げられませんでした。"いい"とは何かで、手が止まったのです。人によって考え方がこんなにもちがうのに、”いい”コンセプトを定義するのはとても難しく、タイピングできずにそのテーマはやめました。
月日は流れたいま、「つよく、とおくにいく、コンセプトのつくり方」を書いてみようと思います。今でも変わらず、”いい”は定義はできませんが、つよく、とおくにいくために大切なことはなんとか書けそうです。この第1章では、"つよく、とおくにいく、コンセプト"の"つよさ"について書いていこうと思います。最後までお付き合いいただければうれしいです。
1 、コンセプトに重要なこと
コンセプト(concept)は英語ですが、意味としては、概念、観念、考え方として訳されることが多いです。コンセプトの語源となったラテン語は「concepto」と言われ、諸説はありますが、やどす、というニュアンスをもつとも言われています。ビジネスシーンでは、アイデア、案、目論見、切り口、観点など、プロダクトやサービスの価値を定義し、その考え方を示す言葉として使われています。
では、コンセプトをつくる際に重要なことは何か。それは、意思です。つくったコンセプトに自分(個人)の意思があるか、それが一番重要なことだと考えています。
職業柄、アイデアをつくる仕事があります。が、どんなにたくさん考えて、どんなに時間を費やしても、そこにじぶんの意思がなければ見事に消えてしまいます。打ち合わせで反対意見が出ても、うまく応対しようとする活力がでない。そして、そのアイデアがなくなっても悲しさはあまりないのです。じぶんの意思はそんなにないのですから。一方で、意思があれば悔しいのです。そのまま消えてしまうのはあまりにも惜しい。そのため、粘り強く考えます。どうしたらこのアイデアを残せるかと。そういうときは打ち合わせまで粘りに粘って、説得材料を集めるのに必死なっています。"つよいコンセプト"はそうやって生まれます。
現在は、ぼくは新規事業開発の支援を行う仕事をしています。その中で、新しい事業、サービスを考える際に、その手法として有名なものはいくつかあります。ご存知の方も多いかもしれませんが、人間を中心にしてアイデアを考えるDesigh Thinkingや、確実性のあることを積み上げ、不確実性のある極端な未来をつくり、アイデアを考えるシナリオプラニングなどがあります。
他にも様々アイデアを考える方法はありますが、つよいコンセプトを作るには上記の他にもつくり方があると思っています。それが好きから発想する、好きのデザインです。(具体的な方法については「5、好きの引きだし方」で詳細を書いています)
2、プロジェクトで意識していること
新規事業を考えていく上でサービスデザイナーとして常々意識していることがあります。それは、プロジェクトを動かしている方の意思がどれぐらい反映されているかです。プロジェクトにおいて意思が反映されている状態であれば、そのプロジェクトは中長期的に進んでいく可能性が高いです。なぜなら、本人の意思によってプロジェクトの分岐を決断できる状態であるならば、主体的にプロジェクトに取り組めていると考えられるからです。本人の主体性があることはプロジェクトを進めていく大きな原動力になります。
新規事業開発のご支援をさせていただいている立場で言うと、極論、ぼくらとの関係性がなくなったとしても、企業が自走していく状態がベストだと思っています。企業側にはコンセプトをつくり、どう実現するかを一番に考えてもらいたい、そう考えるからです。企業単体でのプロジェクトの進行に大きな兆しが見え、こちらとのお付き合いがなくなったとしても、それはよかったと思えます。自走するほどの没頭力を作れたことがぼくらの価値だと思えるからです。
本人の意思が反映されていない場合は、すこし心配な気持ちになります。その企業にとって、消えてしまうプロジェクトになっている可能性があるからです。「1 、コンセプトに重要なこと」でもすこし触れましたが、コンセプトを支える意思がなければ、コンセプトを前進させる力は生まれにくいという話をしました。ですが、担当された方が好奇心を持ち、主体的にそのプロジェクトについて調べあげ、自信をもって意見する場合もたくさんあります。そういったケースがほとんどと言っても過言ではないのでしょう。進めていく中で、自分の意思をプロジェクトに込めていくことは、仕事のおもしろさを設計するために重要なことに感じます。ただ、中長期的に見れば、本人にとって本当に力を注いでいけるものなのか、そこに歪みが出てきてしまう場合もあります。もちろん、本人にとってそれがいつの間にかやりたいことに変わる場合もあります。が、消えてしまうリスクが発生していることもあるのです。
3、意思のないコンセプトは消える
※引き続き、新規事業開発の話(自分の仕事の話)を交えながら話を進めていきます。
前章、前々章とコンセプトをつくるために、意思の話をしました。人の意思がコンセプトを、持ち上げる力になると言いたかったからです。
サービスデザインの仕事をしていると、アイデアを考える際に、社会に文脈を捉えてアイデア発想したりします。ソーシャルコンテクストを捉えて、そこを起点に目指していくビジョンを作ったりするのです。また企業の文脈からアイデア発想をすることもあります。企業にとっての経営課題を洗い出し、その解決策からアイデアを考えるのです。さらには、もっと、ユーザー/ターゲットに寄り添って、アイデア発想することもあります。ユーザーインタビューやユーザーを観察して、そこで得た一次情報(不安要素、心配事:ペイン)から発想するケースもあります。
こうやって進めていくとプロジェクトはうまく行っているように見えます。すこしずつ情報が集まり、プロジェクトの最初よりは、何かが見えてきたかもしれません。
しかし、この時点でもう、大事なことが消えてしまっているケースもあります。それは、コンセプトを考えている本人の意思です。社会の文脈や、経営課題、ユーザーの情報からコンセプトを考えることに、自分とだんだん距離が生まれてしまっていることがあります。アイデア発想したはいいが、時間を置いてそのアイデアは見たときに、どこか足りない、頭で考えた感じがする。一見するとよく見えるが、あまりアイデアには感情移入はしていないことがあります。
その正体は、自分と、発想の起点にしているテーマに距離があるからです。そして怖いのが、この距離が、プロジェクトの中でとくに上申の段階で現れてしまうことです。たくさん時間もお金もかけたものの、いよいよお金をかけようとするときにコロッと、上申で止まってしまう。ケースとしては、発案者の意思がよわいコンセプトでプレゼンをし、パッションレスな内容になってしまうことです。そして上申で止まっても、そのコンセプトに自分の意思はあまりないため、なんとかしてもう一度会社に掛け合ってみよう、粘ってみようする力が、そのコンセプトでは湧いてこないのです。もっと手前で、社内の合意形成(コンセンサスデザイン)をしておくべきだっと、後ほど話が上がったりします。もちろん、それも大事なのですが、それよりもっと大切なことがコンセプトにあると思うのです。
新規事業を担当されるほとんどの方が、はじめて担当されることが多いです。日々の業務でアイデアを考える仕事をするプロでも本音を言えば、アイデアを作ることは大変です。(ですので、発想するテーマに距離が出ないように、サービスデザイナーは、勉強熱心で好奇心がつよい方がとても多いです。驚くほど、熱心です。もうそのテーマについて調べ上げているんですか、とよく驚いています。)新規事業担当者になり、自分との距離が遠いテーマでの事業アイデアをいきなり作れるかと言うと、正直、不安な気持ちになると思います。ですから、まずは自分と距離が近いテーマから発想していくのもありではないかと思うのです。
4、合言葉は、「じぶんの顔色をうかがおう」
”つよいコンセプト”には、個人の意思がとても大切なことだとここまで繰り返し言ってきました。すこし生意気に自分がCEOだと思うぐらいが丁度いいと思っています。はじめから、上司の顔色は意識しない。まず自分の顔色を気にしましょう。そうすることが意思を生みます。そうでなければ強風からコンセプトを支える、しなやかな意思は持てません。
新規事業を行う企業の立場で言うと、企業は、個人の意思(担当の方、そこにコミットする人)を尊重しなければなりません。なぜなら、プロジェクトを進めていく本人の意思がなければ、つよいコンセプトは生まれにくいためです。ですので、企業の文脈と、社会の文脈、経営の文脈、ユーザーの文脈とはすこし離れて考えさせる機会を与えることも必要だと考えています。そして、その覚悟を企業はもたなければいけません。逆に言えば、その覚悟を持つことが難しいようであれば、新規事業開発はやらないほうがいいです。企業にとっては、消えていくコンセプトをつくることになります。企業として、一任をした方を信じて任せてみましょう。(そういう意味で言えば、企業は新規事業開発の担当者として、どんな方を選ぶのかとても重要な決断になると思います)いきなり横槍は禁物です。コンセプトが生まれて、本当にそこにコストを割いて実現していくのか、その段階で企業が判断すればいいのです。
では、個人の意思あるコンセプトを作るために、発想のよりどころとするテーマについてお話しようと思います。
意思あるコンセプトを作るために、発想の源を何にするか。それは好きです。あなたが好奇心をもてるもので、興味や関心を注げるもの。それを発想のよりどころにしてみてください。誰かに言われず、自分から動けるもの。それがあなたの意思を生みます。
でも、『急に「好きから発想せよ」って言われても、まず自分の好きが案外わからない』と思われる方も、いらっしゃると思います。次の章で、好きの引きだし方のお話をさせてください。
5、好きの引きだし方
では、好きの引きだし方についてです。意思あるコンセプトを作るために、好きを起点に発想できるようにしたい。それが、ここでの意図です。
では、まず協力してくれそうな友人や知人、同僚ににランチをご馳走しましょう。すべてはそこからはじまるかもしれません。そして、次に、その方と30分程度、好きについて話す時間を作りましょう。下に、シートを用意しています。ご利用ください。使い方は下記です。
※各々、時間が足りない部分があれば調整していただいてけっこうです。

1. 3〜5分をタイマーにセットし、好きなこと、もの/ついついやってしまうこと(本当に自分が好きなことが眠っていることがあります)を書き出します。終わったら、すこしお互いに見せて話してみてもいいです。
2. 次に書きだしたもの、ひとつひとつに自分が惹かれているポイントを横に書いていきます。これも同じく3〜5分で行ってください。ポイントが同じものについては書かなくてもけっこうです。
(そうするとこちらの表のようなものができます。)

3. 次に好きなものの探り合いです。順番を決めて好きなこと/ものについてインタビューをお互いにしましょう。インタビュワーのコツとしては、これって本当に好きなのかな???と探りを入れる感覚を持つといいかもしれません。機能や利便性で好きっていうことよりは、なんか好き(情緒性)を見つけることを意識してください。
「洋服が好きなんですね、どんなところが好きなんですか?」
「うーん、洋服を着ると自分を武装しているような気がして、」
「なるほどなるほど(これは、ちょっと本当に好きじゃないかもな。機能的、、、)。あ、でもTさんゴロゴロが好きなんですね」
「そうなの。なんか、ふとんは好きなんだよねー!」
「(あ、ふとんが好きなんだ。見つけた)」
相手の表情をよく観察して、表情や声、テンションが変わったり、そのものについて饒舌になったりするかどうかをヒントにしながら見つけていきます。
4. 一通り、聞き終わりましたら次に発想する問いかけをつくります。ここが一番大切なところです。

つくり方は、インタビュワーが聞いてきた好きなこと/ものと、その人らしさを感じた、ユニークだと思ったポイントを組み合わせて問いかけをつくります。
構造的には形容詞+名詞になるようにします。問いかけの事例は下です。

5. 問いかけができましたら、その問いにむかって一週間〜10日でアイデアを考えます。そして、その後にお互いに発表し合いましょう。発表を聞いて、共感したこと、惹かれたところをフィードバックしてあげてください。あなたがそのアイデアの最初の共感者です。
Tさんのアイデアは下のものになりました。

6.ここでアイデアは一旦完成です。おつかれさまでした。そして、今回の章でご紹介でできることもここで終わってしまいます。このあとは、そのアイデアを磨いたり、実現にむけての方法を模索していきましょう。もし、本当にそのアイデアにあなたが惹かれているのであれば、あなたは意思をもって行動できるはずです。
+α 機会があれば、アイデアをもっていろいろな方とブレストしてみましょう。あなたのアイデアに共感してくれる人や、批判してくれる人がそれぞれいるでしょう。その意見を聞いて、自分でいいと思ったところは取り入れ、自分の好きとちがうと思った点は、忘れましょう。そのアイデアはあなたのためのものですから。
7.実際のプロジェクトでは、その後も続きがあります。ビジネスデザイナーとお金と価値について、サービスデザイナーとコンセプトと体験について、テクニカルディレクターと現実可能性と理想可能性についてなどなど、ブレストを通してアイデアを磨いていきます。そして、最終的につくり上げたアイデアをもって受容度調査、POC(Proof of Concept)=概念実証、事業化準備へと移っていきます。
6、ぼくが想うコンセプトのおもしろさ
最後にぼくが想うコンセプトのおもしろさを書いて締めさせていただきます。
コンセプトのおもしろいところは、それが言葉であるということです。これだけ読むと何を言ってるのかわかりづらいと思うのですが、先があります。コンセプトは、言葉がゆえに、カタチが仮になくなっても残ると言うことです。偉大な建築物はなくなっても、その建築物をつくった人のコンセプトは言葉として残る。それは建築物でなくても、アートや哲学、そして企業もそうだと思っています。カタチであるハードがなくなっても、ソフトである言葉、コンセプトは残る。ここがとてもおもしろいところだと思っています。
一時、カタチが失われても、コンセプトがあれば、それはまだ失われていないと思います。人の意思が残こっていれば、またカタチが現れる可能性がある。企業に務め新規事業担当者となり、その仕事の中で個人の意思をもってつくったコンセプトが、経営の文脈と合わないことはあります。諦めざるを得ない場面に、サービスデザインの仕事していると遭遇することは残念ながらあるのです。心血を注いだ個人としては、とてもつらいことです。しかし、コンセプトは言葉であるがゆえに残ります。企業にとっては、そのコンセプトは消えたものでしょうが、汗水垂らした個人に意思があれば、それは残る。また異なるところで、自分の文脈で挑戦してみることも、コンセプトは可能なのです。意思あるコンセプトは、言葉であるがゆえに、簡単には消えない。そこがおもしろいと思っています。
最後にここまでの要点を簡単にまとめます。
「つよく、とおくにいくコンセプトのつくり方」における、
つよさをつくるためには、
1. 自分の意思を大切にしよう。
2. 企業は、個人の意思を尊重をしよう。
3. そして、コンセプトは、好きから発想しよう。
以上です。
ここまで長文になってしまいましたが、最後までお付き合いいただまして本当にありがとうございます。(次の2章では、つよいコンセプトが"とおくにいく"方法について書く予定です。またお付き合いいただければ幸いです)
"つよく、とおくにいく、コンセプト"をつくる挑戦をされる、皆さまの、ご検討を心からお祈りしています。
最後までありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
