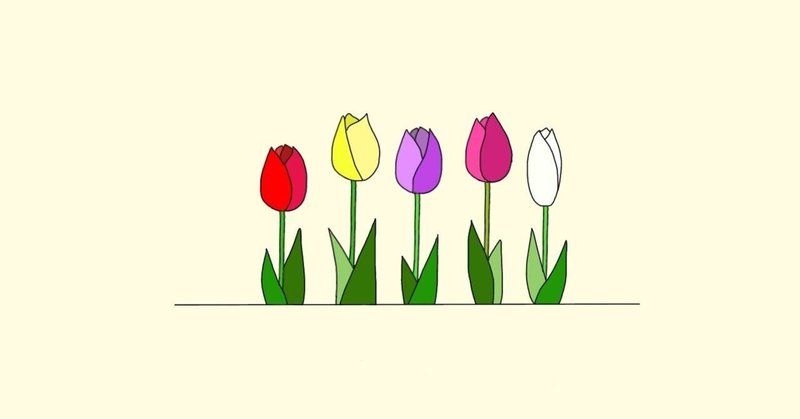
カーフ・ブランディング
うろ覚えだったのをネットで調べて、北原白秋の「歌ひ時計」であることを発見した。
けふもけふとて氣まぐれな、
晝の日なかにわが涙。
かけて忘れたそのころに
銀の時計も目をさます。
ぼくがそういう昼寝から銀の時計のように目ざめると、父親が、お母さんでていっちゃったぞ、といった。ぼくは立ち尽くしながら、お父さんといればきっと帰ってくる、とヘンな確信があったから、もしかしたら母親がでていったことはそれ以前にもあったのかもしれない。
まだ乳飲み子だった妹は母におぶわれていたはずで、その場には父と自分しかいなかった。すっかり記憶から抜け落ちているが、母はすぐ帰ってきたと思う。まだ3歳になっていなかったと思う。
根にもつタイプの父は、このときのことをあとあとまでおぼえていて、酔っ払った折など、***(ぼくのこと)を捨てただろ、と子供のいるまえで蒸し返し、母はマサカというけわしい顔つきで、捨ててないよ、と即答したが、当の子供はどう思っていたかといえば、捨てられたと感じていた。
暗くなるまで遊んで家に帰ったらカギがかかっていてだれもいない、泣きながら方々をさがしまわり、見知ってはいるが一度も話したことのないような近所の大人たちに出会えば「ぼくのお父さんとお母さん知りませんか」と聞いてまわったのは、小学校低学年のころだ。
心当たりが尽きてもなお走るのをとめられず、小学生にもなってひとりでいることに耐えられないなんて、将来どうなるのだろうと不安になったものだ。やがて通りのむこうから階段を降りてこようとする両親たちのシルエットを見つけて涙をふきながら近づいていった。なかなか帰ってこないから保育園に妹を迎えに行っていたと母は説明したが、息子の顔を見て察したらしく終始まじめな表情だった。
母にはむしろ愛されたほうだと思う。その愛につねに不満をいだいて、すねたりいじけたりして母を困らせた。
カーフ・ブランディングというプロレス技があって「仔牛の焼き印押し」と訳されていたと思うが、捨てられたという感じは焼き印のようにぼくの心の奥底にのこって忘却されているにちがいない。忘却されている、というのは、焼き印(記憶)はあるが思い出されないことをいいたいためである。
思い出せない、忘れたというのは、脳内から失われたという意味にとられる傾向があるが、思い出せないからといって記憶がなくなったわけではないことをベルクソンがヒユを使っていっていた。さまざまなモノが置いてある部屋で明かりが消えてなにも見えなくなったからといってモノがなくなったわけではないように、記憶も思い出されないからといってそれがなくなったわけではない、と。あるいはベルクソンではないかもしれない。
ベルクソンがいっていたのはたしか、記憶は脳にないということだった。じゃ、どこにあるんだ? と聞かれたベルクソンは、あえていうなら精神に、と答えていたと思う。そもそも記憶のような非物質的なものについて、「どこに」と問うこと自体がおかしい、というのがベルクソンの言い分であった。
婚礼のスピーチのなかで「結婚は賭けである」という言葉をベルクソンのものとして引用した時の都知事がいた。会見で、ベルクソンではなくパスカルではないかと記者から疑義が呈されると、作家でもある知事は、証拠があるなら出すようにと反論していた。あの話は結局どうなったのか。
ぼくなど自己肯定感が低い者は、それはあんた、ベルクソンではなくパスカルの間違いじゃないの? いいのかい、スピーチでまちがったこと広めちゃって。挙証責任はいったいどっちにあるのかね、などと追及されたら、さっと白旗を挙げて退場したことだろう。
ついでにいえば、この自己肯定感というのも、ものの本によると(『あたりまえを疑え! 臨床教育学入門』)二種類あって、社会での成功体験によってはぐくまれる相対的なものと、そのもっと根本にある、親や家族という生まれてきてから最初に出会うような他人から手厚く世話されることによってはぐくまれる基礎的なものとがあるそうで、後者の自己肯定感がより重要らしい。
この基礎的な肯定感がじゅうぶん大きければ、失敗してもいつまでもくよくよしたり心がカンタンに折れたりしないで再チャレンジしていかれるが、小さいと、バケツの穴から水がモレるように、成功体験をいくら重ねても自信として蓄積していかないそうで、後者の場合が自分にあてはまるようだ。
三回つづけて失敗したくらいであきらめてはだめだ、とたしかアランが書いていた(あるいはカール・ゴッチだったか)。ぼくはこの言葉がすきで、ひとに色紙を頼まれたらぜひ書き添えたいと思うくらいだが、じっさいは、一回失敗すればあきらめるには十分だと考える傾向がある。もし、それでも諸々の事情でトライしなければならないというようなことになると、トライの先にある目的をめざすことから、トライする行為そのものが目的となってしまって、やっぱりいつまでたっても成功体験に至らない(笑)。
そういうわけで、ぼくの焼き印によるバケツの穴はいまもふさがっていないようなのだが、かといってそれを苦にしたり生きづらさととらえたことはないのである。それが、なにかがモレているのが自分であるという感じ。その感じというか受け取り方、認識のしかたがすでに(基礎的)自己肯定感のなさに影響されているのかもしれないが。
