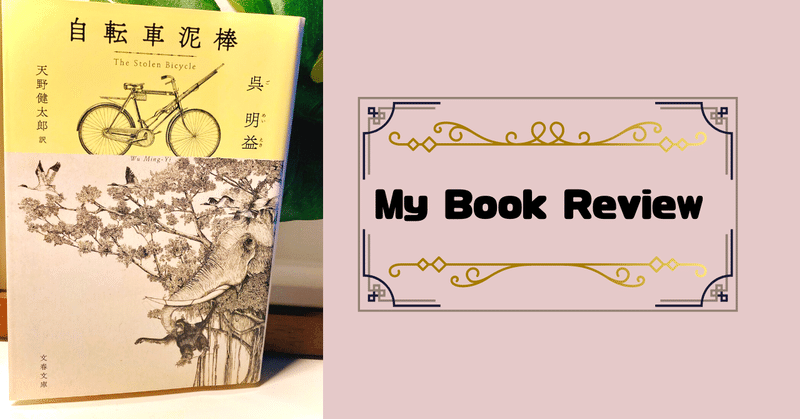
暑苦しいほど人間的で、興奮するほど知的な自転車の本【ワタシのshort review】
始まりは、田舎の1人の少女が自転車で家に戻ろうとする場面からスタートするのだが、少女の自転車をこぐ音や背丈に合わない巨大な鉄の馬にもめげずに食らいつこうとする映像がパーッと頭の中に広がる。ただ、実はこの内容は、本編の内容とは関係しない。たぶんこれには、本編に向けて作者にとって読者の焦点を”自転車”に釘付けさせたいがために、田舎と少女と自転車の3者の要素が最適だと判断し、それらを結びつける映像的描写を作品のあたまに持ってきたわけなのだろうと考える。私は、この感傷的なデジャブ体験から一気に作品に飲み込まれてしまった。
主人公の生まれた場所は、台湾は台北の中華商場という市場近くの日用品雑貨店兼住宅であった。5人の姉がいて、1人の兄がいる、年の離れた兄弟の中では最底辺の末っ子として生まれたのであった。早朝から活発な市場と所狭しのお家の2者の存在感が、むさ暑苦しさをビシビシッ、伝えてくる。この本を真夏に読んでしまったら最後。なぜなら、たとえ室内であっても、本から身体全身へ熱気が伝わり、ついには下着が湿ってくいく始末になってしまうからだ。
ひとつ前の【ワタシのshort review】で、本が主役となった作品を扱ったのであるが、今回の
「自転車泥棒」は、タイトルにもあるように自転車が何が何でも中心にいる作品となっている。ただ少し違うのは、もともと主人公の父が所有していた自転車(作品の設定された時代は第2次世界大戦後間もないころで、事実として、この時期の自転車の価格は、現在の私たちが知るメルセデス・ベンツの市場価格よりも高かったようだ)が様々な事情で知らない者たちの手元へ次々と渡っていく(作品中に、訳あり泥棒がたくさん潜んでいる)。父が生前とても大事にしていた自転車をどうしても、取り戻したい作者は、その自転車が誰の手にいつ渡り、今はどこにあるのか、ジャーナリズム的猛進な姿勢で家宝を探していく。やがて、父の自転車の所有者履歴がつかめていき、それに追従する流れで、それぞれの泥棒の正体やその時自転車がどう扱われていたのか、小ストーリがゆっくりと一つずつ展開されていく。とても、文学的にも話の展開方法としても、見事な作品であると思った。いくつかの時間的に連続した短編集がその主役である”自転車”の下でまとめてあげられていくと表現したら、多少分かりやすいだろうか。
また、作者は現役の学者でもある故、テーマとした自転車それ自体を構成する細かいパーツや生産場所、ブランドに関する説明にも余念がない。つまりは、作品中に無駄に感じられる部分が見当たらない。こうした自転車の説明にしても、相当調べられたのであろう、圧倒的な情報量でむしろ、興奮したぐらいだから。
まだまだ日本で馴染みの薄いジャンル、台湾文学。
台湾文学の作品を未だ1度も読んだことのないという方、それじゃ是非、この「自転車泥棒」からお読みになってみてください。
私から強くお勧めさせていただきます!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
