
日めくり5分哲学『自由の哲学』を読む はじめに
ルドルフ・シュタイナーの『自由の哲学』を読むマガジン。
日々少しずつ読む理由
シュタイナーの入門書でありながら、かなり難解な部分があります。およそ100年前に、魂の領域に真摯な態度で臨み、霊性と魂の世界を雄弁に語ったルドルフ・シュタイナー。その姿勢に熱い想いを感じ、何回となく読み返しました。今回、自分なりにポイントを踏まえ、1日5分でまとめ、アタマを整理していきます。土日は休み。
本文は下の枠内に、
〈考察〉は普通スタイルで綴る。
本文中の論説を独自の『命題』として<命1-3-1>など符号で記す。この場合、第一章3回の命題1の意。
人智学の父、ルドルフ・シュタイナーと共にあれ。
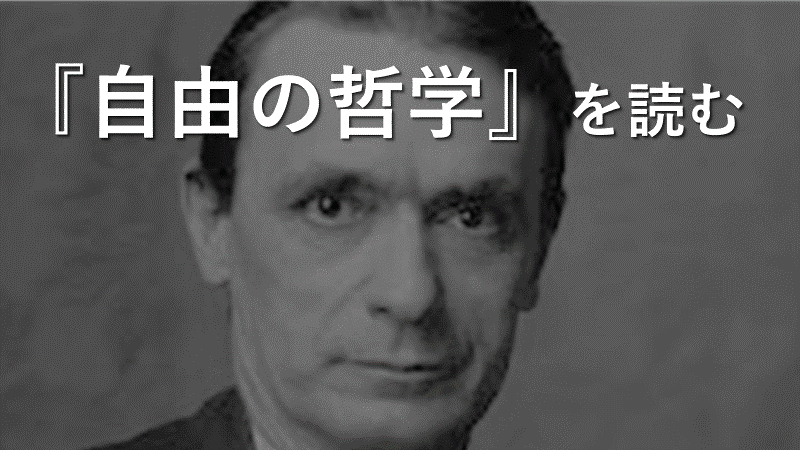
『自由の哲学』
ルドルフ・シュタイナー(高橋 巌 訳)
ちくま学芸文庫
なお、このコンテンツは、自らのために執り行う「まとめ」であり、あくまでも個人の楽しみと学習の一環として行います。
また、現状で規定されている著作権法第35条ならびに38条の以下の趣旨に基づき本著作物を公開します。
著作権法第35条 教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。また,「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に,主会場で用いられている教材を,副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
著作権法第38条 [1] 営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。
[2] 営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
以上
ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。
