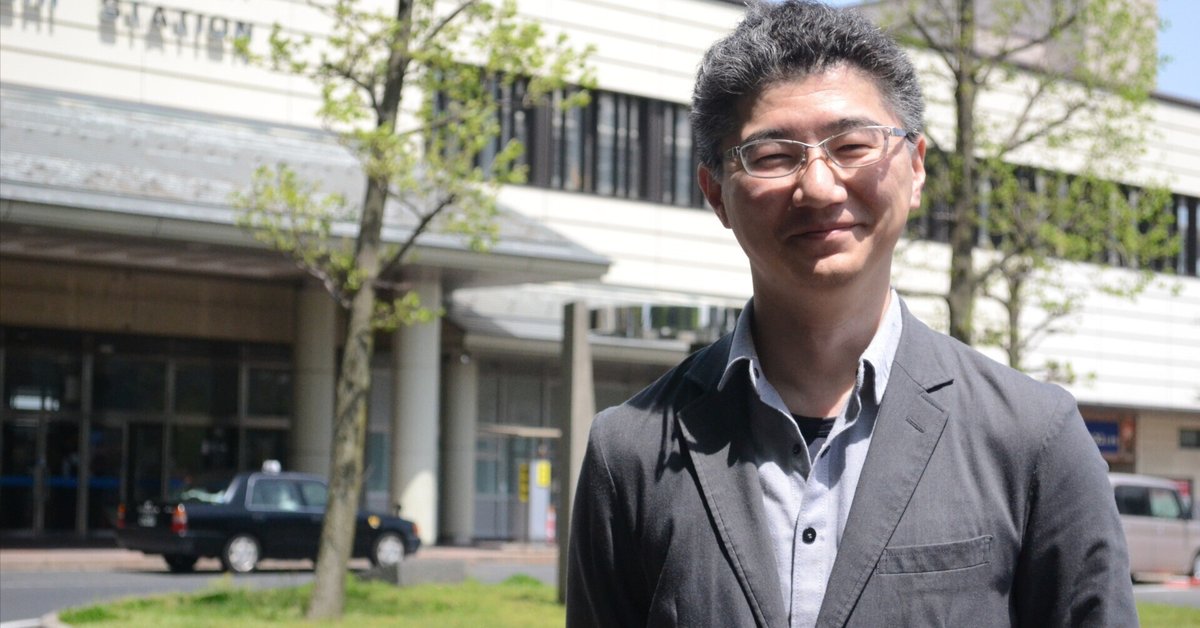
ユース出雲かわらばん~岩下義明さんインタビュー~
コミュニティナースカンパニーが運営する新しい拠点が出雲に出来ました。
出雲でどんな人がどんな思いで何を起こし、どんな未来へ向かっていくのか。
「ユース出雲かわらばん」では、ユース出雲の今をお届けします。
第7回は、島根大学医学部救急科教授の岩下義明さんにインタビューしました。
岩下先生ってどんな子どもでしたか?
田舎でわるいことばかりしている「やんちゃ」な子どもだったんです。人の家の柿の木を揺すって食べたり、空き家に入って秘密基地をつくったり、女の子の上履きを隠したり。小学生の頃は、友達とそんなことばかりしていました。だから小学5年生のときに学校1怖い先生がクラスの担任になりました。仲がいい子たちもきれいにバラバラにさせられたんです。「岩下と〇〇が集まると悪いことをする」って思われてたんだと思います。毎日怒られ続けました。
転機は6年生のときです。一人ひとりの可能性を信じてくれる担任の先生と出逢ったんです。その先生は「努力したら報われる」が口癖で、「みんなそれぞれにいいところがあるはずだから、1人1つ1位をとろう!」って言ってたんです。絵もちゃんと描かない、大会的なものもサボる自分だったんですけどいろいろやってみることにしたんです。そしたら、詩とか俳句ですごく褒められて。努力しよう!ってのめり込んでいました。「やんちゃな子」から「努力する子」に変わったんです。
だから、中学校は順風満帆でした。何でも頑張る子だったんです。小学校の時から、「勉強はできる子」だったんですよ。小学5年生のときに、でも歴史の勉強は好きで、壁一面に貼れるような大きい年表を自由研究でつくったりしていました。「あの子は足が速いな」「あの子は絵が上手いな」と同じようにぼくは勉強ができたんですよね。
中学に入ってからは「世界が見たい」という想いが強くて、英語に夢中になりました。英語をきっかけに勉強にものめり込んでいって、はじめは中の上くらいだった順位がどんどん上がっていって、最後は一桁になったんです。それがすごく楽しかったです。勉強を教えることがきっかけに女の子と仲良くなって、話をする関係性になったこともありました。年賀状を交換したりもして、勉強を核にしながら、友好関係も充実していましたね。
反対に、高校生活はいい思い出がない暗黒期です。
中学までは、埼玉県熊谷市にいたのですが、親に「こんな田舎の閉鎖的なところにいたらダメだ。東京へ行きなさい。」と言われて、東京の附属高校に進学したのですが、内部進学生が多くてうまく馴染なかったんですよね。
中3の時の担任の先生と馬が合わず、進路決定の時、第一志望の高校に「ダメだ、お前は絶対行けない」って言われて、別の高校にしたんです。担任の先生に「お前オレのこと嫌いだろ?」と聞かれて、「はい嫌いです」と答える間柄でした。それで「しょうがないだろ!」ってキレられてましたね。
本当は大学で、考古学や政治学を勉強しよう思っていたのですが、高校受験で「数学が苦手だから数学を伸ばそう!」と思って必死で勉強したんです。すると、ものすごく数学ができるようになって、文系に行くのが、もったいないくらいになっちゃったんです。でも当時、理系の仕事でやりたいことがなかったので、医学部に入れるくらい勉強するか!と思って大学の、医学部に入りました。
岩下先生が「ひらいた」瞬間はいつでしたか?
ぼく、子どもの時からあんまり変わっていないなと思うんです。子どもの時から、自分の好奇心に従って生きていたと思います。小学生の時読んでいた「コロコロコミック」の広告を見て「どっかの国に旅行したい!」と思ったり、新聞の端っこに書いてあったノーベル賞受賞者の講演会を聴きに行ったりしていました。そういう行動を取れていたのは親に小さいときから「やりたいことをやりなさい!」と言われていたからだと思います。親は葬儀屋をやっていたのですが「忙しいばかりで稼ぎがない。自分のやりたいことをやりなさい」と言われたんです。「自分の道は自分で見つけなきゃいけない」という想いが常にあったんです。
小学生の時から、自分で考えたい!という想いが人一倍強くて、授業参観の日に「紙ヒコーキ大会」をしたのですが、前日に先生が「絶対よく飛ぶ飛ばし方教えてやる。みんなでめっちゃ飛ばそうな。」と言ってよく飛ぶ折り方を教えてくれたんです。だけど、「みんなが同じ折り方・飛び方って嫌だな」って思ったんです。だから自分でよく飛ぶ折り方を考えて当日飛ばしたんです。結果、一人だけ紙ヒコーキが飛ばなかったんですけど、「やり切った!悔いはない!」清々しい気持ちでした。
社会人になってからも、常識は「そういうものなんだな〜」おかしい気持ちも大切にしながら、そのまま捉えつつ、「これは譲れない!」と思うことは粘り強く考えてきたんです。社会では課題を見つけて、解決することが評価されるので、業務改善などを、積極的に起こすことができ、周りの方に評価もいただきながら仕事ができています。
・コミュニティナースやユース出雲の取り組みに影響を受けていることや可能性を感じていることはありますか?
病気だけをみるんじゃなくて、その「人」の周りの環境を含めて観察して、オーダーメイドで医療を組み立てられる医療人材を育てたいんです。
田舎にいると誤嚥性肺炎など、同じ病気で診察に来る患者さんが多いんです。「また同じ病気か!」と思ってしまうとやりがいが湧かないと思うんです。だけと、Aさんの誤嚥性肺炎とBさんの誤嚥性肺炎は家庭環境が全然違うから、Aさんは1週間で帰れるけど、Bさんは2週間かかるというような診察ができるようになると、日常の診療も楽しくなると思うんです!
そのためには、医療者がもっとまちへ出るべきだって思っていたんです!
代表の矢田明子さんに出逢ってコミュニティナースの考え方を聞いたとき、「なんだ、同じことを考えている人が、すぐそばにいたんだ!」と感動したんですよね。自分が理想としていた社会が、雲南市で実現されている!と知ったときは本当に驚きました。
コミュニティナースの取り組みがユースに広がっていくのはとても可能性を感じるし、面白いなって思うので、医学部の学生も合流してほしいなって思います。いろんな人と交流し、多様な価値観を自分の中に取り込めたとき、医療にもいろんな見方や考え方が入ると想像します。その学生たちが大人になったとき、オープンイノベーションを起こっていく。そんな未来にワクワクしています!
『地域と大学を結び、世界に向けて発信する』拠点:出雲Base
若者応援サポーター募集!
プロジェクトの詳細は、以下のリンクからご覧ください!

インタビュアー ひびき
愛媛県出身。能登地方で夏は塩づくり、冬は酒造りの季節労働でお金を稼ぎながら、田舎暮らしで、生きる知恵を身に着けている20歳。塩づくりがはじまるまで、コミュニティナースカンパニーのお手伝いをしていた。今は能登にいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
