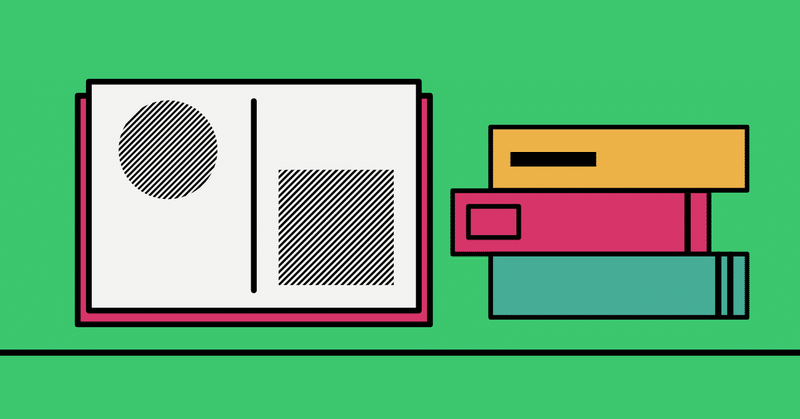
2021年11月に読んだ本(#161)
少し早いですが、もう少しで11月も終わるので今月読んだ本を振り返ります。
今月も目標としていた3冊を超え、4冊読めました。
もし興味を持つものがあったら読んでみてください。
一般意志2.0 ルソー、フロイト、グーグル
こちらは以前noteで紹介しました。
最近また東浩紀さんの著書に魅力を感じているのですが、思えばこの本が出た時も東日本大震災の後で、今回も新型コロナウイルスによるコロナ禍。
なにか時代が変わる節目のようなタイミングで読みたくなる著作が多いのかもしれません。
父として考える (生活人新書)
こちらも東浩紀さんの著書。
宮台真司さんとの共著(対談集)です。
自分にまだ子どもいないこともあり、共感するまではいきませんでしたが、「親」になると世界の見え方が変わるということを再確認しました。
この言葉が印象に残りました。
そもそも学歴や資格は、どこに行っても通用するけれど、そのぶん薄っぺらな数字でしかない。裏返せばそれらの数字は、本来の固有の才能が華開かなかったときのためのリスクヘッジの道具でしかない。ほとんどのひとがそれを誤解している。
人生というのは、それぞれの人間の固有のものなので、定式化できないところに豊かさがある。それがなかった場合、仕方がないから呼び出すものとして学歴や資格がある。そう考えるべきです。学歴は、なにかを達成するためのステップではなくて、なにかを達成できなかったときに、しかたなくしがみつく緊急避難先としてあるべきなんですよ。
進化思考――生き残るコンセプトをつくる「変異と適応」
Amazonで高評価だったので読みました。
後半はちょっと読むのに疲れてしまって飛ばし読みになってしまいましたが、生物の進化とわたしたちの生活の進化(変化)を紐解いていく内容です。
アイデアを考える方に取っては、頭の整理に良いかもしれません。
序盤に出てきたこの言葉が好きです。
創造性とは、「狂人性=変異」と「秀才性=適応」という二つの異なる性質を持ったプロセスが往復し、うねりのように螺旋的に発揮される現象である
NHK「100分de名著」ブックス サルトル 実存主義とは何か: 希望と自由の哲学
まだわたしには早かったかもしれません。
わかったようなわからないような。
わたしの勉強不足ゆえ、理解しきれなかった気がします。
大きく噛み砕いたわたしの理解では
どのような環境で生まれ育ったかよりも、自分の責任においてなにをするかが大切
=自分で自分を作り上げることが必要
と理解しましたが、あっているのかわかりません。
一見すると当たり前の主張のように見えてしまって、世界での出来事や情勢がわかってないと、主張の革新性に気付けないと感じました。
最後に
最近はずっと複数の本を並行して読んでいます。
日々Amazonで安くなっている&気になる本をポチポチしているので、積読が溜まっていくばかりです…。
ちょっとだけ、12月にかけて読もうとしている本を紹介して終わりにします。
みずほ銀行システム統合、苦闘の19年史 史上最大のITプロジェクト「3度目の正直」
三島由紀夫: なぜ、死んでみせねばならなかったのか;ナゼシンデミセネバナラナカッタノカ (シリーズ・戦後思想のエッセンス)
以上、おしまい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
