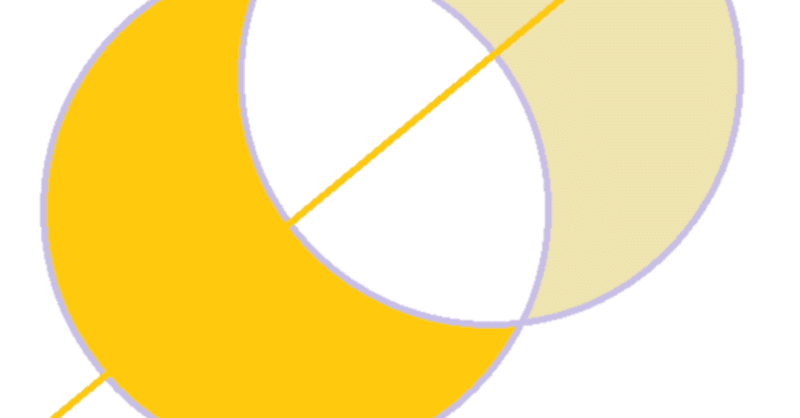
【超短編小説】ドバイ
その赤ん坊が生を受けたのはマンハッタン島のちょうど真ん中あたり、蒼穹の高みに向かって林立する摩天楼の谷間のどこかだった。エレベーターの中に捨てられたか、自殺者の置き土産か、あるいはおじけづいた誘拐犯のしわざか、そのあたりのことは誰にも分からない。
赤ん坊が入ったバスケットは地上200メートルのビル外壁の手すりの上で揺れていた。それを見つけた三人の窓拭き清掃人は仕事の手を休め、バスケットをそっと床に置いた。安らかに眠るピンク色の赤ん坊を囲む彼らの姿は東方の三賢者さながらだった。その中のひとりパウラ・メイは、赤ん坊の顔を見るなりこう言った。「エディーだわ、この子の名前はエディー。顔を見れば分かるでしょ」
この瞬間から、彼女は赤ん坊の母親がわりになった。父親がわりは大勢いたけれども、パウラ・メイはたった一人の取替えがきかない存在になったのだ。そして彼女は十分にそれを自覚し、エディーの育児に関してどこまでも愛情深い権威者となった。パウラ・メイと窓拭き清掃人たちは、彼ら以外誰も近寄ることができない目もくらむ高みの中で赤ん坊を育てることに決めた。でなければ、赤ん坊はすぐにどこかの施設に取り上げられてしまっただろう。そんなわけでエディーは、ただの一度も地上に降りることなく成長していった。そのことが、彼のメンタリティをだんだんと鳥類に近づけていったと言う者もいる。
寝台代わりのバスケットは地上200メートルの高みでビルの谷間を吹き抜ける風に揺れ、そのまわりを燭台を思わせる無数のガラス窓のきらめきが取り囲んでいた。朝は雲の切れ間から六角形の曙光が差し、夜は冷たい星屑の瞬きがクライスラービルの壁面に砕け散った。地上の喧騒から遠く離れ、それはなんと美しく清澄な光景だったことか。なんと荘厳な心震わすスペクタクルだったことか。
昼間になると幼いエディーはビル外壁のガーゴイルに腰かけ、飽きることなく窓拭き掃除人たちの仕事ぶりを眺めた。やがてパウラ・メイがモップとロープと洗剤のボトルを与えた時、エディーの窓拭き掃除人としてのキャリアがスタートした。すぐにどんなベテラン職人よりもすばやく、確実に、やすやすと、水面をすべるミズスマシさながらにビルからビルへと移動できるようになった。危険きわまりない反射光も突風も、彼にとっては無害だった。そこが彼のゆりかごであり遊び場だったことを思えば、驚くには当たらない。
十二にもならないうちに、エディーは完璧なプロフェッショナルになった。パウラ・メイの手ほどきによって、彼の身のこなしは窓拭き掃除人というよりむしろアクロバットの曲芸師に近づいていった。ロープを自在に操り出し、ゴンドラの上で踊るようにステップを踏む陽気なエディーの姿を、私たちはいつまでも記憶にとどめるだろう。小鳥みたいに摩天楼の谷間を飛び回りながら、左手の洗剤と右手のモップを正確に操り、窓ガラスという窓ガラスをピカピカに磨き上げていくエディー。空の高みで生きることに尽きせぬ喜びを見出したエディー。
やがて窓拭きエディーはマンハッタンのオフィスワーカーたちの間で都市伝説となった。彼らは誰一人としてすばやいエディーをその目で捕捉することはできなかったが、ガラス窓の中に閉じ込められて人生を送る者たちはいつどんな時も、語るべき何かを欲しているものなのだ。空をよぎる影をふと目にした時、今のは目の錯覚だろうかといぶかしみつつ、彼らはそれをパーティージョークか何かのネタとして胸中にしまいこみ、時々語り合った。
その噂を聞きつけてニューヨークのTV局がやってきた。彼らは窓拭き掃除人たちを集めてインタビューした、まるでエディーがビルとビルの間に張ったロープの上を渡る綱渡り芸人や、素手でビルをよじ登るクモ男たちの仲間であるかのように。私たちが全員「知らない」と首を横に振ったのは当然だった。TV局のクルーは意気消沈して帰っていった。もし真実を口にしたら、エディーはどこか遠く離れた場所に連れていかれただろう。ただ私たちがエディーにすまない気がしたのは、もしかしたら彼は有名になれたかも知れない、そしてあのビルの綱渡り職人やクモ男たちと一緒にTV番組に出演できたかも知れない、と思ったからだ。
しかし当のエディーはそういう連中のことを軽蔑していた。エディーは言った、ぼくは仕事をしているんだ、ビルの窓ガラスをキレイにするというまっとうな仕事を。ぼくはちゃんとこの世界の役に立ってるんだ、ただ見世物になっているあの連中とは違う。その時私たちは、ビルの外壁から突き出した彫刻の上に思い思いの恰好で腰かけ、昼食のマスタードサンドイッチをぱくついていた。空は青く澄み、スクラッチノイズを思わせる雲が薄くたなびいていた。エディーはその時夢を語った。ぼくはいつかドバイに行くだろう。そして世界一高いビルの壁面を駆け上がって、ガラス窓を磨き上げるだろう。隅から隅まで。
ドバイ。そして世界一高くそびえるビル。それはなんと美しい夢だったことか。私たちは全員うっとりと夢見心地になったが、しかしエディーがドバイに行くことは絶対にないと全員が知っていた。第一、彼はパスポートが取れない。しかしそれが問題になるのはまだまだ先のことだと、私たちは信じていた。誰よりもパウラ・メイがそう信じていた。その時この地上でエディーに残された時間があと三か月しかないなどと、一体誰が予想しただろうか。
その日エディーはいつものようにすばやく仕事を終わらせ、キューピッド像によりかかってドクターペッパーをラッパ飲みしていた。空は神秘的なまでに高く深かった、まるで目をこらせば降り注ぐ宇宙線をひとつひとつ数えられるとでもいうように。エディーはまだ見ぬドバイに思いを馳せ、それからふと窓の中を覗き込んだ。
それはとてもきれいに整頓されたオフィスだった。パステルカラーのデスクとコート掛けとパイプ椅子、細長いソファー、デスクの上にはウェハースみたいなモニター。壁際にはコーヒーメイカーとサボテンの鉢。その時エディーの目がその娘の上に止まった。肩のところで切りそろえた金髪、紫水晶みたいな瞳、真珠色のブラウスと濃い色のタイトスカート。
エディーの横隔膜のあたりを右から左へと甘いうずきが駆け抜け、心臓がクレッシェンドで打ち始めた。エディーが人生最初で最後の恋に落ちるまで、きっかり三秒しかかからなかった。私たちは、そしてパウラ・メイは当然予想するべきだったのだ、いつかこの日が来ることを。幼年期の優しいまどろみが終わって、苛烈な覚醒が訪れることを。エディーの目は娘の姿を追った。彼女が会話を交わし、赤い唇が開いたり閉じたりし、その細い指先がパントマイムみたいにひらめく。彼女の白い手は政治家のように雄弁だったが、その視線は幼子のように物問いたげだった。
その時エディーは悟った、彼の姿が娘の目に映ることは決してないのだと。なぜならば彼は窓の外の存在だから、ツバメかミズスマシのような影、あるいは都市伝説のパーティージョークに過ぎないのだから。
そしてエディーは自分もオフィスの中に入りたいと思った。生まれて初めて、この窓の内側に生息する人々の一員となってネクタイとスーツを身に着け、彼女の前に歩み出て、真正面からその視線を浴びたいと願った。それは避けがたいことだったと、パウラ・メイでさえ認めるだろう。それは罪ではない。永遠にビルとビルの狭間で生きるのではなく、ガールフレンドと一緒に明るいオフィスで働き、夕方になったら地上の街灯の中にまぎれ込み、心安らぐざわめきに満ちたカフェでビールとカラマリを注文したいと願ったとしても。
浮き立つような高揚感が彼を捉えた。エディーは足を一歩踏み出した。しかしその下に、ゴンドラはなかった。ブザマに足を踏み外し、エディーは両手をバンザイの形に広げてまっすぐに落下していった。
ツバメのすばやさ、ミズスマシの軽やかさ、重力を無視した敏捷さはどこへ行ったのか? たったこれだけのことで、人は罰を受けなければならないのか? 私たちには分からない。いずれにしろエディーは墜落した。その小さな体は54番街の舗道に叩きつけられた。彼の魂はさよならも言わずに、この世界から秒速500メートルで飛び去っていった。
私たちは彼を悼む。彼の夢を、運命を、そしてそのかなわぬ願いを。なぜならば、エディーはもう決してドバイに行くことはないからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
