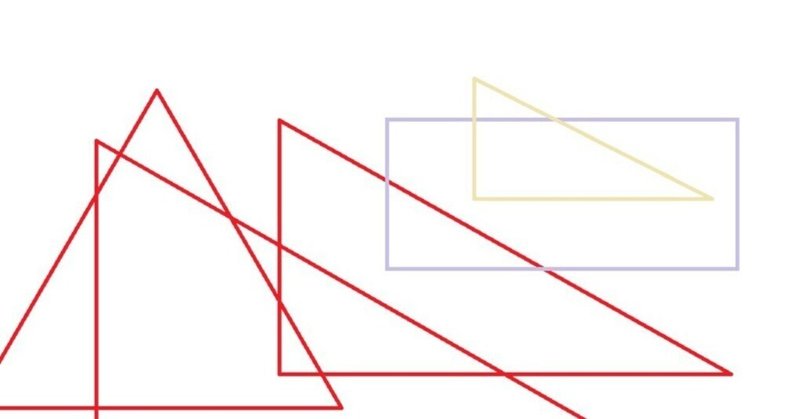
【超短編小説】ナイルでは
古代エジプトの女王クレオパトラは蛇に噛まれて死んだあと、輪廻転生の複雑きわまりないプロセスをくぐり抜けて、現代のニューヨークで暮らすアルバニア人女性イレーンとなった。イレーンはグリニッジ・ビレッジで油絵を勉強しているごく平凡な画学生だったが、ちょうど20歳になった誕生日の翌週、オリーブオイルの瓶を踏みつけてアパートの階段から転げ落ち、そのはずみに前世の記憶をすっかり取り戻した。幸い、ひじを軽くすりむいた以外にケガはなかった。
イレーンは自分の心の中に生じた大きな変化に戸惑い、自分が本当は誰なのかという哲学的問いにしばし身を委ねた。燃えるような体を抱えて煩悶したあげく、結局自分は自分であるというしかなく、それ以外のことはただ気分の問題なのだと結論づけた。ようやく気が楽になり、アパートから戸外の陽気の中へと歩み出た。すぐ上の階に住む年下の男子学生(ミュージカル演出を勉強中)が窓際から声をかけてきた。「イレーン、次の土曜日にデートしてくれよ!」
イレーンは叫び返した。「いいわよ! でもそれまでに髪を切ってよ!」「なんで!? これすごくイケてるドレッドヘアなのに」
でももうそこにイレーンの姿はなかった。
彼女は大学のアトリエの中に、油絵具がプンプン匂うアーティストたちのひめやかな工房の中にいた。窓からさしこむ光と幾重にも折りたたまれた影が床の上に複雑な幾何学模様を描いている。そこには何かしら崇高なものが感じられた。そしてそれはイレーンをいつになく内省的なムードへと、渇望にも似たアーティスティックな使命感へといざなった。衝動に突き動かされてこれまで描いた絵を壁に沿ってずらっと並べてみると、どれもこれも救いようもなくつまらない出来に思えた。
失意と悲しみがやってきて、ベタつく霧みたいに彼女を包み込んだ。何か新しいものを描かなければダメだわ、と独白し、気を取り直して白いキャンパスに向かった。やがて焦燥が消え、めくるめく忘我がやってきた。彼女の中からかつて自分が神となって支配したナイルの記憶、古代エジプト人たちの苛烈な生の情景の数々がほとばしり出た。ナイルのほとりでくつろぐ兵士と女たち、ピラミッドの建設に駆り出された奴隷たち、涼しげな宮殿のパティオ、醜い占い師たち、ローマ軍との激しい戦いの光景、堂々たる馬上のアントニウス。彼女は衝動のままに絵の具を叩きつけ、絵筆で掻き回し、パレットナイフで切り裂いた、これまでとまったく違う荒々しいタッチに自分でも驚きながら。
イレーンは完成した新しい絵を何枚か持ってワシントンスクエアに行った。地面に並べ、誰かがやってくるのを待った。やがてオードリー・ヘプバーン風のサングラスをかけオレンジ色の口紅を塗った30歳ぐらいの金髪の女がやってきて、それらの絵を眺めた。腕組みをし、やがてサングラスをとって、また眺めた。
「すごくエキゾチックね。個性的だわ。誰に教わったの?」
「誰にも。描きたいように描いただけよ」
「これ全部想像?」
「想像じゃないわ、私の記憶」
「古代エジプトの絵に見えるけど」
「私、クレオパトラの生まれ変わりなの」
「へえ、そうなんだ」
女はイレーンをじろじろ眺めて、アートディーラーの名刺を差し出した。「あなた見込みあるわ。私のロフトに来ない? あなたを売り出してあげるわ」
女の仕事場兼居住スペースらしいソーホーのロフトに入ると、立ち並ぶイオニア式の石柱と白い壁を背景に現代アート作品が所狭しと並べられていた。油絵は一つもなかった。スタッフらしい若者が何人か無言で仕事をしていた。イレーンはいくつかの作品をじっくり眺めたが、退屈と空虚以外の何も感じない。肩をすくめて言った。「悪いけど、私こんな作品は作れないわ」
女は笑った。「いいのよ、どんな作品でも。現代アートにルールはないわ。油絵でもオブジェでも落書きでもなんでも、それがクールだと思わせる新しい視点を提供すればいいの」
そしてイレーンの肩に手を回して付け加えた。「あなたには、すごく新しいものを感じるわ」
女はイレーンをダイニングルームへ連れて行って、そこで珍しいクレオール料理を振る舞った。髪を青く染めたメイドが次々と皿を持って来て二人の前に並べた。どの料理もスパイシーで、素晴らしく美味だった。やがてキッチンから背の高い黒い肌のシェフが出て来たが、彼の無限に落ち着き払った双眸には王侯貴族を思わせる高貴さがあった。
「料理は全部彼に作ってもらってるの。とても上手なのよ」
「住み込みなの?」
「違うわ。毎日通ってもらってるの。彼は売れっ子だから高くつくけど、それだけの価値はあるわ」
イレーンはシェフに言った。「手を見せて」
シェフは手を差し出した。「ピカソの手によく似てる」とイレーン。シェフはイレーンの顔をじっと見つめ、一礼してキッチンに戻っていった。
「ピカソとはね」と女が言って、笑いながらパチパチと拍手した。
女はイレーンを連れて地下のワインセラーに入った。穴蔵のようなその場所は薄暗くひんやりしていて、宵闇迫るヴェニスの裏水路みたいに秘密めいていた。女はアモンティラードを注いだグラスをイレーンに渡した。
「私は一流のものが好きなの。身の回りに一流のものを集めるのが生き甲斐。私と一緒にいれば、あなたも女王のような生活ができるわよ」
「女王なら一度なったことがあるわ」
「そうだったわね」
「信じないんでしょう」
「信じるわよ、もちろん。あなたの言うことならなんでも」
それから女はゆっくりとイレーンの唇にキスした。
「ひとつ質問させて。エジプトの女王だった時、あなたは幸福だったかしら?」
イレーンはしばらく考えた。「分からないわ。ただ必死に生きていただけ」
「でも絶大な権力を持っていたんでしょう?」
「いくら権力を持っていても、さだめには逆らえないもの」
「さだめって何?」女が笑った。「現代にそんなものはないわ」
「いいえ、現代にもあるわ」とイレーン。「さだめとは死。誰も死からは逃れられないし、その時を選ぶこともできない」
女はイレーンにゲスト用の寝室を一つ、自由に使いなさいと言って与えた。まるでリッツカールトンホテルのスイートルームみたいに広々としていて、趣味のいい家具と柔らかい照明があって、ベッドと枕はホイップクリーム並みにふわふわだった。イレーンはその上に大の字になって、今夜彼女はこのベッドに来るつもりだろうかと考えた。目を閉じてそのことを想像してみて、どうしてもイヤってことはないわね、と思った。きっと彼女は私をいい気持ちにさせてくれてくれるだろう、そして豪奢で心地よい環境を与えてくれるだろう。そのまましばらくウトウトした。
やがて彼女はベッドから抜け出して自分の荷物をまとめ、メモ用紙をちぎって簡単なメッセージを書いた。『親切にしてくれてありがとう。でも私はもう一度女王になるより、自由でいる方がいいわ』
寝室の窓から抜け出したあと、イレーンは暗い通りを駅の方へ向かって歩いていった。夜の公園を囲む鉄柵の前を背の高い男性のシルエットが歩いていたが、イレーンが彼に気づいた時、向こうも気づいて足を止めた。
「また会ったわね。どこへ行くの?」
それはロフトで会ったシェフだった。「家へ帰るところです、マドモアゼル」
「マドモアゼルはやめて。あなた、名前はなんていうの?」
「シーザー」
「なつかしい名前だわ」イレーンはシーザーの手を取った。「私はクレオパトラ。かつてナイルの支配者だった、もう遠い昔のことだけれど」
夜の闇が深くなった気がした。その向こうから熱気と、かすかなざわめきが聞こえてきた。かつて幾星霜も前、あのナイルのほとりがそうだったように。「私たち、もしかしたら前に会ったことがあるかも」
シーザーはうなずいたかも知れないし、そうでなかったかも知れない。この時二人が交わしたいくつかの短い言葉は、ただ夜の中に吸い込まれて消えた。それから二人は手を繋いだまま、同じ方向へ向かって歩き出した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
