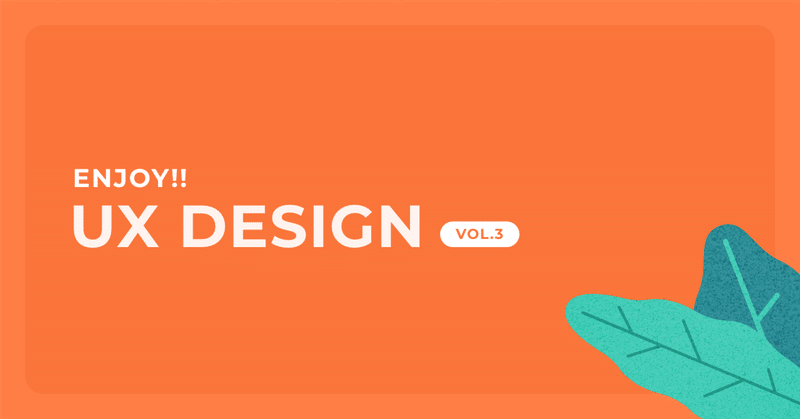
【ENJOY!!UX DESIGN】ユーザーは"実際に"どのようにWEBを見るか
かけだしUXデザイナーの横山です。
前回の記事からかなり期間があいた投稿になってしまいました。
さて今回は、最近書籍より学んだことを記事にしてみようと思います。
脳・行動のパターンを知る
WEBやUIなどを作るなかで人間の行動・認知のしくみについて学びたいと思い、『超明快 Webユーザビリティ ―ユーザーに「考えさせない」デザインの法則』という書籍を読み進めています。
この書籍はユーザービリティ専門家Steve Krug氏の『Don't Make Me Think』の日本語版です。優れたUXを作るための方法を掲載しており、UXデザイナーにおけるバイブル本のような一冊となっています。(英語レベルが中学生で止まっている私には大変ありがたい1冊です)
書籍の序盤で、WEB製作者にとって知っておいて方がいい、実際のユーザーの行動について紹介されていました。設計者(作り手)とユーザー(受け手)の考え方を行き来しながら読むとなかなかに興味深く、ご紹介したいと思います。
1. 人はページを読まない。ざっと見るだけ。
人はWEBページを読むことにほとんど時間を割かない。WEB利用の実態に関する十分な裏付けがとれた極めて数少ない事実のひとつである。読む代わりに、目を引く言葉やフレーズやを探してページを斜め読みするのである。
WEBをつくる人間にとって、書籍の冒頭部分からなんとも耳が痛いお話。。
どうして人は斜め読みする?
何か目的があるから
全部読む必要がないことを知っているから
人は斜め読みに慣れているから
人が斜め読みするには、上記3つの理由があるようです。
サイトでの行動目的に対し、早く成し遂げようとしている。また、目的を達成するに必要・興味のある情報だけを抜き出し、ページのごく一部しか関心も持たない。これが斜め読みを行う理由とのことでした。
自身も一人の人間ではあるため、ユーザーの立場でサイトを閲覧する際はたしかに目的以外のこと・情報には一切目を向けていないかもと、腑に落ちる内容でした。興味関心あることには目を向かないことは、設計者視点に偏ってしまうとこの思考はつい忘れがちになってしまいます。はやく用事を済ませたいユーザーにとっては、情報過多やゆったりとしたサイトは時間を浪費させてしまうのであまり好ましくないと感じました。
2. 人は最良な選択をしない。適当なところで満足する。
人は最初に目についた妥当な選択肢を選ぶ。これは満足化と呼ばれる戦略だ。 探しているものにつながりそうなリンクを見つけた場合、たいていのユーザーはとりあえずクリックする。
どうして人は最良な選択肢を探さない?
たいてい急いでいるから
見当違いをしても対してペナルティはないから
比較検討をしても正解率が上がらないから
推測する方が楽しいから
一人の人間としてサイト利用時のことを考えてみた。
「た、たしかに…」とこちらも腑に落ちる内容でありました。
WEBサイト上ではどんなに間違った選択をしたとしても、興味本位での選択であったとしても、<戻る>ボタンを押します。これにより見当違いの場合は戻ればいいし、WEBサイト内では間違っても怒られる体験はほぼないので、その方が早いし手っ取り早いですよね。
選択肢を有する場合は、やり直しや最初の地点に戻れるように、回遊性のあるサイト設計にしておくのが重要だと感じました。
3. 人は物事の仕組みを理解しようとしない。行き当たりばったりでやる。
ユーザービリティテストをしていれば、人は自分が使っているものの仕組みを理解していない、あるいはまったく勘違いしていることを知るだろう。
わざわざ時間をかけて説明書を読む人は極めて少ない。たいてい行き当たりばったりで試行錯誤しながら、自分達のしていることや、それでどうしてうまくいっているかについて、もっともらしく聞こえる自説をでっち上げていく。
数年前にはじめてIKEAでテーブルを購入した際に、説明書を読まないでとりあえず組み立てたことがありました。IKEA商品を購入したことがある人はご存知かもしれないですが、とにかく組み立てが難しいのです。脚と天板をくっつけるだけだろうと思っていたので、とにかく力技で乗り切ろうとしたのを思い出しました。(結局全然できなくて一から説明書を読み、何度もやり直しました)確かに行き当たりばったりなことをしたなと急な内省モード。
どうしてこのようなことが起こるのか?
知らなくても大した問題にならないから
一度うまくいったらやり方を変えなくなるから
こちらも一人の人間視点として考えると、たしかに納得できます。。
仕組みなんか知らなくても無事ゴールに辿りつければなんでもよかったりするし、うまくいった!というポジティブな体験があるのであれば、やり方を探そうとせず、それを突き通す気がします。
3つの事実を知ると、じゃあどうすれば…と頭を悩ませてしまいました。
たとえ仕組みなどがわからなくてもユーザーはなんとかなるのでそのままで良いかとゆうかとそうではなく、「わかってもらう」ことも大事らしいのです。
ユーザーが「わかる」ことで生まれる利点!
ユーザーの探し物が見つかる可能性が増える。
ユーザーがたまたま見た部分ではなくサイトのサービス全てを理解してくれる。
見てほしい部分にユーザーを誘導できる可能性が増える。
ユーザーは自分が賢くなった気分になり、サイトを繰り返し使ってくれるようになる。
たしかに”やり方”や”行き先”が「わかる」ほうが、効率的だし間違いも起きにくい。何より目的地に辿り着くスピードがグッと速くなる気がします。
サイト制作をする際、どうしても設計者視点に偏りが生じてしまうため、ユーザーの行動を綺麗事化してしまったり丁寧に描きすぎてしまう癖が入ってしまいます。でも実際はもっとシンプルな行動がほとんどなんだと、書籍を読んで気がついたポイントでした。ユーザーと設計者ではかなり現実のギャップが大きいというこの事実を意識し、いかに速くかつわかりやすくゴールに辿り着けるWEBをつくるのがユーザーにとって良い体験につながるのだと感じました。引き続き書籍を読み、ユーザーの行動について理解を深めていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
