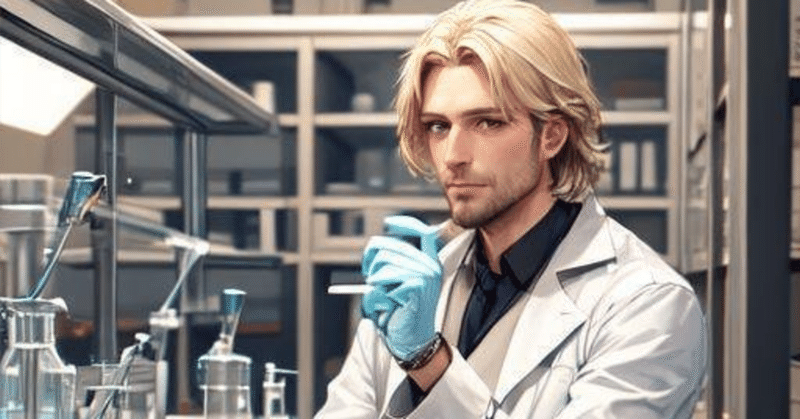
「ウィルス人工説」を理解するための初心者向けの基礎知識(新章追加)
※この記事は、いつ「デマ記事」として削除されるかわかりませんので、興味のある方はダウンロードするか、プリントアウトしておくことをお勧めします(本当に「デマ」かどうかの判断は、皆様のご賢察に委ねます)。
※仮に削除された場合、むしろ「情報が真実である」ことの太鼓判になるかも。もし将来、一冊の書籍としてまとめられれば、発売する際に帯にでかでかと「正し過ぎて口を封じられた!」と宣伝文句を入れられそうですね。
1.はじめに
「新型コロナウィルスは研究室で作られた人工ウィルスである」
それだけ聞くと、メディアの言う「陰謀論」の最たるもののように思われるかもしれません。
でも、ここで注意すべきは、「人工ウィルス説」が「オカルト愛好家」や「超常現象研究家」といった、うさん臭い肩書の連中ではなく、主に専門の研究者たちの間から立ち昇ってきたことです。
その道のプロが疑うからには、SNSに投稿される「素人の思いつき」とは次元が違います。れっきとした科学的根拠があっての「人工説」なのですが、これを理解するには、「遺伝子」や「突然変異」の基礎知識がどうしても不可欠。
高校時代に「生物」を選択した方ならともかく、「物理」や「化学」に進んだ方には、つい敬遠したくなるような話題でしょう。
そういう方のために、あるいは典型的な「非理系人」のために、できる限りかみ砕き、あくまで「文系の文脈」で「ウィルス人工説」の根拠を解説していきたいと思います。
2.DNAの基礎知識
まず、基本中の基本から始めましょう。
あらゆる生物は「蛋白質」によって形づくられています。
「蛋白質」には膨大な種類(一説には数百億)があり、皆さんご存じのコラーゲン(皮膚)、ヘモグロビン(血液)、ケラチン(毛髪や爪)なんかもその一つ。
「蛋白質」の原材料となるのが「アミノ酸」です。種々の「アミノ酸」の組み合わせ(結合)によって、異なる「蛋白質」が作り出されるのです。
我々のDNAは、しばしば「生命の設計図」に例えられますが、より正確には「蛋白質を構成するアミノ酸の設計図」です。アミノ酸が結合することで、晴れて「蛋白質」となるからです。
DNAには、「どのアミノ酸を、どのタイミングで、どれくらいの量作るか」といった重要なプログラムが刻まれています。
たいていの場合、この「アミノ酸製造作業」はスムーズに行われますが、ごくまれに「手違い」が起こり、「遺伝子異常」「遺伝子疾患」といったトラブルが発生します。不必要な時期に不必要なアミノ酸を作り過ぎてしまったり、逆にアミノ酸の量が不足するために適切な「蛋白質」が得られず、「健康異常」が生じるわけです。
話はがらっと変わって、皆さんはこのようなパズルをご存じでしょうか。

「温泉旅館に泊まったとき、部屋に置いてあって遊んだ」という方もいらっしゃるかもしれません。形の違うブロックを組み合わせて、「花」や「家」「犬」などのお題に沿った図形をこしらえる遊びです。
この「組み合わせパズル」をイメージすると、DNAについて、きっと理解しやすくなるはず。
DNAは、「塩基」と呼ばれる,たった4種類の部品で構成されています。ちょうど三角形、四角形、台形などのパズルのブロックのような感じです。
A:アデニン
G:グアニン
C:シトシン
T:チミン
この4種類の「ブロック(塩基)」が鎖状にずらっとつながったものがDNA。4種類の「ブロック」の組み合わせ方しだいで、「花」になったり「家」になったり「犬」になったりと、異なる「アミノ酸」が生成されるのです。
よく刑事物のドラマや映画を観ていると、科捜研のコンピュータ画面に
AGGCATTCGC……
と長いアルファベットの文字列が表示される場面がありますが、あれはまさしくDNAの「塩基配列」を分析しているところです。
さて、この「アミノ酸の設計図」を読み解くには、一つのルールがあります。それは、「文字3個を1セットにする」というもの。言い換えれば、「塩基3個ごとに1つのアミノ酸が作られる」ということです。
この「3個1セット」の単位を「コドン」といいます。
ここからは、ほんのちょっと数学的になりますが、我慢してお付き合いください。
A・G・C・Tの4種類の「ブロック(塩基)」が取り得る「コドン」のパターンは64通り(4×4×4)ですが、人体で生成される「アミノ酸」は20種類しかありません。
つまり、並びが変わっても同じ「アミノ酸」が作られる組み合わせ(重複)があるということ。単純に割り返せば、同じ種類の「アミノ酸」を作るのに、3~4種類の組み合わせが存在することになります。
実際に、「A・T・T」「A・T・G」「A・T・A」の3通りの組み合わせ(コドン)からは、同じアミノ酸「イソロイシン」が作られます。興味を持たれた方は、ネットで「コドン表」を検索してみてください(実際のコドン表ではT(チミン)ではなくU(ウラシル)になっていますが、解説の便宜上「T」を使用)。
DNAは、細胞分裂のたびに複製(コピー)されていきますが、何度も分裂を繰り返すうちに、時おり「複製ミス」が生じます。「A」が「G」になったり、「T」が「C」になったりと、塩基の1か所が違う塩基に置き換わってしまう場合があります。
これを「突然変異」(あるいは単に「変異」)といいます。
前述したとおり、「アミノ酸」の設計パターンにはダブりがあるので、ほとんどの「変異」において、作り出されるアミノ酸自体は変わりません。同じ意味(意義)を持つ「変異」なので、「同義置換(同義変異)」といいます。
アミノ酸が変わらなければ、その結合によって作られる「蛋白質」も変わらないので、「変異前」と「変異後」の両者は仲良く共存していくことができます。
一方、「複製ミス」により「塩基配列」が乱れたことで、違うアミノ酸が作り出される場合もあります。
「イソロイシン」の設計図である「A・T・T」の真ん中の「T」が何かの拍子に「C」に置き換わってしまうと、「A・C・T」となり、「トレオニン」という別のアミノ酸を作りだすようになります。一つの「変異」のせいで、まるで別の「製品」ができてしまうというわけです。
こちらは、違う意味(意義)を持つ「変異」なので、「非同義置換(非同義変異)」といいます。
こうして違う「蛋白質」が作られると、生物の性質自体にも差異が生まれ、カーン!とゴングが鳴って「生存競争」が開始されます。その結果、より環境にマッチしているほうが勝ち上がり、敗者は満身創痍で競技場を去っていくはめになります。
これこそが「自然淘汰」の仕組みです。

既存のチャンピオンに対して、次々と「変異(挑戦者)」が現れ、激しいバトルを繰り返す様子は、格闘技のトーナメント戦そっくり。チャンピオンが王座を防衛することもあれば、挑戦者が見事勝利して新チャンピオンとなることもあるのです。
と、ここまでが「ウィルス人工説」を理解するための基礎知識。ここから、いよいよ今回のウィルスの「不自然な変異」についての本題に入っていきます。
3.あまりに不自然な「変異」
今回の「パンデミック」で、これまでそんなものにはまるで関心のなかった方々も、「ウィルスの変異」に興味を抱かれたことでしょう。
「ワクチンが効かなくなったのはウィルスが変異したから」とか「接種してもコロナにかかるのは免疫をすり抜ける変異が生じたから」という言い訳(?)を、少なからず耳にしたことがあるはずです。
……妙な話ですね。私を含め、新型コロナワクチンに懐疑的だった人たちは、初めから「コロナウィルスはすぐに変異するからワクチンでは対処できない」と(研究者なら誰でも知っている)事実を指摘していたのに、「推奨派」はそれをガン無視していました。
そうそう、「2回接種を完了すれば10年は大丈夫」と豪語した医師や大臣もいましたっけ。
ところが、何度打ってもワクチンが効かないことが明らかになったとたん、手のひらを返すように「変異のせい」と連呼するようになったのです。
メディアでは連日、「専門家」を名乗る人たちが「ウィルスの変異」について、さまざま解説していました。でも、はっきり言って、どいつもこいつも「変異」「自然淘汰」を曲解している輩ばかり……失礼、言葉が乱暴になりました。
とにかく、曲がりなりにも「専門家」であるなら、「変異」について知らないのは明らかに勉強不足ですし、知っているのなら、何らかの意図があって、あえて嘘をついていることになります。
いずれにせよ、「変異」を正しく解説している「専門家」は、私の見る限り、ほぼゼロでした。
コロナウィルスは、「一本鎖RNAウィルス」というものに分類されます。
「RNA(リボ核酸)」と「DNA(デオキシリボ核酸)」は、どちらも「アミノ酸の設計図」であり、同じものと考えていただいて構いません。
ただし、DNAがいわゆる「二重らせん構造」であるのと違い、RNAは1本だけの単純な構造になっています。その単純さから、塩基の「置き換わり」や「挿入・欠損」などが頻繁に起こります。
DNAでも「変異」は起こりますが、より複雑な二重構造のため、仮に片方に「置き換わり」が生じても、もう片方が正しい塩基に修正する「更正作業」が行われます(「相補性」という)。
新型コロナの塩基数は約3万個。A・G・C・U……が合計3万個、米西部を走る貨物列車のように1列にずらっとつながっているわけですが、「変異」はあくまでもランダムに発生します。理論上、3万個のどの部分でも「同じ確率」で起こり得ます。
「変異には2種類ある」と前述しました。作られるアミノ酸自体は変わらない場合(同義置換)と、アミノ酸がまったく変わってしまう場合(非同義置換)です。
「非同義置換」が生じたDNAの間では、環境に対する「優劣」が生まれ、「生存競争(自然淘汰)」が始まります。そして、ウィナー(勝者)が生き残り、ルーザー(敗者)の系統はそこで途絶えてしまいます。
いっぽう、「同義置換」の変異では「自然淘汰」が生じないので、複数のDNAが互いに変異を抱えつつ、仲良く共存することが可能です。
最初の「武漢株」と「オミクロン株」の塩基配列を照合・比較することで、ウィルスがどのような道筋をたどってきたかがわかります。
まず、原株に対して1か所の変異(a)を持つ新株が登場します。少したつと、その新株に新たな変異(b)が生じ、原株に対して2か所の変異(a+b)を持つ新々株が現れます。その後も、時がたつごとに変異(c)(d)……をプラスした新顔が登場してきます。
つまり、最新の変異株には、これまでに起こった変異(a、b、c、d……)がしっかり刻印(蓄積)されているということ。「非同義置換」が生じても、その時点までの「同義置換」の痕跡はRNAに保持されています。
逆に、原株に対して最も変異の多い「最新株」から、より変異箇所の少ないものへと、時を遡って追跡することも可能であるということ。だから、「系統図」「樹形図」を描けるわけです。
蓄積された変異を数えることで、登場から経過した時間も、ある程度推測することができます。というのも、それぞれのウィルスには「何コピーにつき1回の割合で変異が起こる」という、だいたいの確率があるから。これにウィルスの増殖速度を掛け合わせれば、おおよその時間経過を知ることができます。
これを「変異速度」といいます。
ちなみに、インフルエンザウィルスの「変異速度」は、コロナウィルスのおよそ2倍という厚生労働省の研究結果があります。それは、インフルエンザウィルスに対するmRNAワクチンの製造が事実上不可能であることの証明になります。
だって、半分の変異速度しかないコロナウィルスですら、たちまちワクチンが「型遅れ」になってしまっていたのに、さらに変異速度の速いインフルエンザウィルス相手では、とてもワクチン製造が間に合うわけないじゃないですか。
工場で生産され、医療現場に届くころには、とっくに何周も「周回遅れ」になっているという次第。
この問題を回避するには、前もって「これから起こるであろう変異」を予期したRNA配列のワクチンを製造するしかありません。ですが、変異はあくまで偶然の産物であり、どの箇所でどういう変異が生じるかは神様でもわからない(言うまでもなく、「誰かが設計・改変したウィルス」の場合は、その限りではない)。
仮に、どんな変異にも対応できるオールマイティ・ワクチンを製造するとしたら、スパイク蛋白部分だけでなく、ウィルスのほぼ全ゲノムを用いたmRNAワクチンを設計しなければならなくなります。そうすれば、どこかに変異が生じても、変異していない部分に対して抗体が働くことになるのですが……
「ウィルスの全ゲノムを用いたmRNAワクチン」とは、つまり「ウィルスそのもの」であり、体内に取り込めば「感染」したのとまったく同じ状態になります。
「ワクチン接種」=「自然感染」なら、予防接種の意味がなくなってしまいます。
こうした点を理解したうえで、改めてオミクロン株の塩基配列を眺めると、明らかに不自然・不可解な点があることがわかります。
以下、私が感じる主に2点の「不自然さ」について述べていきます。
①時間と数の不整合
武漢株をスタート地点とする「系統図」「樹形図」を、皆さんもどこかでご覧になったことがあると思います。早い時点で二手に分かれ、一方はデルタ株へ、もう一方はオミクロン株へと変異していく図です。
オミクロンとデルタは、同じ「原株(武漢株)」から出発し、それぞれ別の道をたどっていったとされています。
オミクロンはデルタと比べ、30か所以上の変異を持っています。これが、どう考えてもおかしい。もしオミクロンがデルタと同じ「武漢株の変異種」であるなら、変異の起こる確率に両者で違いはないはずです。
「変異する部位」は違えども、デルタとオミクロンの「変異箇所数」に、そこまで大きな差異が生じるわけがありません。両者は同じ「変異速度」を持っているからです。
先ほど貨物列車の例を持ち出したので、ここもわかりやすく、「列車の旅」に例えてみましょう。
日本に上陸したインバウンドの「原株(武漢株)」が、「東京駅」からそれぞれ
東北新幹線(デルタ系統)
東海道・山陽新幹線(オミクロン系統)
に乗って、別方向へ同時に出発したとします。

「変異」を途中の停車駅と考えれば、16回の変異(途中停車)を経由すると、デルタは17駅目の「盛岡駅」に到着します。そのころ、オミクロンのほうは、やはり17駅目の「新神戸駅」に着くはずです。多少の差はあるとしても、せいぜい「京都駅」~「姫路駅」のあたりにいなければおかしい。
なのに、オミクロンが現れたのは、ずっと先の「広島駅」でした。
実際に駅名を並べると、不自然さが一目瞭然。
デルタ号:
東京→①上野→②大宮→③小山→④宇都宮→⑤那須塩原→⑥新白河→⑦郡山→⑧福島→⑨白石蔵王→⑩仙台→⑪古川→⑫くりこま高原→⑬一ノ関→⑭水沢江刺→⑮北上→⑯新花巻→⑰盛岡
オミクロン号:
東京→①品川→②新横浜→③小田原→④熱海→⑤三島→⑥新富士→⑦静岡→⑧掛川→⑨浜松→⑩豊橋→⑪三河安城→⑫名古屋→⑬岐阜羽島→⑭米原→⑮京都→⑯新大阪→⑰新神戸→⑱西明石→⑲姫路→⑳相生→㉑岡山→㉒新倉敷→⑳福山→㉑新尾道→㉒三原→㉓東広島→㉔広島
デルタとオミクロンが同一株(「東京駅」)からスタートし、ほぼ同じ確率で変異(途中停車)を起こしたとしたら、計算がまるで合いません。
新型コロナは2週間に1度の割合で変異すると考えられています。だとすると、オミクロンがデルタより30回余計に変異するには60週、何と1年以上(1年は52週)の時間が必要になるのです。
30か所を超える変異が生じるというのは、それほどおかしなこと。もちろん、両者が絶対に同じサイクルで変異を起こすとは限りませんが、それにしても変異差があまりに大き過ぎます。
この矛盾を説明するために、私は「オミクロンの原株は武漢株ではなく、1年以上前に日本に上陸していた別のコロナウィルス(別の風邪)ではないか」と考えました。
だって、デルタが「東京駅」を出発するころに、オミクロンは、とっくに「浜松駅」「豊橋駅」あたりにいなければいけないのですから。
この着想には、別の傍証もありました。
オミクロンは「広島駅」に現れるまで、誰にも一度も姿を見られていなかったのです。まるで新幹線を使わず、わざわざ在来線(あるいは高速バス)を乗り継いできたみたいに。
でも、PCR検査が多用されるようになる以前から静かに国内に広がっていたのであれば、今まで発見されなかった謎も解けます。
また、「上気道で増殖し重症化しにくい(感染しやすく病原性が低い)」というオミクロンの特性も、デルタより人間社会に長期間存在し、ヒトのライフスタイルに適応進化していることを意味します。
時間をかけて、宿主を傷つけることなく「よりヒトに感染しやすい形態」へと変異を遂げてきたということです。
私の知識では、その時点で観測される事実を矛盾なく説明できる仮説は、それしかありませんでした。
しかし、そんな私の素人的発想をあっさり打ち砕いたのが、荒川央先生(ミラノ分子腫瘍学研究所)がnoteで提示されたオミクロンのゲノム解析結果でした(実際は、それ以前にもnoteのコメント欄で「あらゆる(新型コロナが人工物である)可能性を排除すべきでない」とのご助言を頂いていました)。
②変異の偏り
新型コロナのゲノム解析は、とにかく衝撃的なものでした。
本来「同じ確率」で起こるはずの「変異」が、3万個ある塩基配列のごく一部分だけに集中しているのです。それは何と、「細胞への侵入(感染)」に関わるスパイク蛋白の蛋白の部分。なので、変異のたびに「感染力」が飛躍的に上がっていったわけです。それ以外の部分では、ほとんど「変異」が認められないのです。
これは、確率的にあり得ないことです。理論上、変異は3万塩基のどこでも同一割合で起こらなければいけません。なのに、ほかの場所には変異がなく、ほんの数パーセントの狭い部分だけに変異が集中するなんて。
東京ドームに3万人集めて大ビンゴ大会を開催するとして、チケット代が高額の最前列の人たちばかりが次々とビンゴ達成したら、どんなにお人好しでも、さすがに「おいおい、ヤラセじゃないか?」と疑うでしょう。
大事なことなので繰り返しますが、作られるアミノ酸が変わらないということは、ウィルスの性質も変わらないということなので、新旧両者の間で「競争(淘汰)」は起こらず、仲良く共存していくことになります。逆に、「ウィルスの性質」に違いがあると「淘汰」が生じ、より環境にマッチしているほうが相手を駆逐していきます。
なので、性質が変わらない「同義置換」はRNAに保持・蓄積され、「履歴」を遡っていけるはずなのですが、オミクロンには「その他の変異」が認められません。感染力を増強するための「非同義置換」だけが繰り返し起こっているのです。
「変異(進化)」は、テーマパークにある巨大迷路のアトラクションようなもの。何度も行き止まりに阻まれながらも、少しずつ少しずつ進んでいきます。展望台から眺めれば、右往左往しながら行きつ戻りつする入場者の姿が観察できるでしょう。
ところがオミクロンは、一度も迷うことなく、一直線にゴールへとダッシュしているのです。まるで、あらかじめ正解の道筋を知っているかのように。
このような「目標に向かっての直線的変異(進化)」には、明らかに何者かの「意志」が作用しています。自然界では絶対に起こり得ません。
もし自然に起こるはずのない現象が確認されたなら、そこには必ず「人為」が絡んでいます。これが「人工ウィルス」が疑われる大きな根拠になっているのです。
もう一つ、オミクロンのみならず新型コロナウィルスには、「人為的」と考えざるを得ない「異変」があります。それは、「フーリン切断部位」と呼ばれる特殊な領域を備えていることです。
「フーリン切断部位」をざっくり説明すると、細胞に感染するためのステップが一つ省略されるということ。例えるなら、我々が人のお宅にお邪魔するとき、玄関で靴を脱いで外向きにそろえるというひと手間がありますが、何も気にせず土足でずかずか上がっていくようなものです。
それにより、受容体からやすやすと宿主の細胞に入り込むことができ、感染力が大幅にアップするというわけです。
インフルエンザウィルスには、この領域が存在することが知られていますが、既知(旧型)の6種類のコロナウィルスにはありません。なのに、どういうわけか、新型コロナウィルスだけは「フーリン切断部位」を持っているのです。
果たして、新型コロナウィルスは、いったいいつの時点で、旧型のコロナウィルスにはない「フーリン切断部位」を獲得したのでしょうか。ここがいっさい不明なのです。
過渡期に当たる中間種は、ミッシングリンクとなっています。

「そもそも人工的にウィルスを作ることは可能なの?」
その問いに対する答えは、人気番組『アメリカズ・ゴット・タレント』の審査員並みの「イエス!」。
クリスパーキャス9という最新技術を使えば、研究室でRNAを簡単にいじくることができます。
例えば、インフルエンザウィルスの「フーリン切断部位」を切り取り、コロナウィルスに「挿入」することも可能。その結果、飛び抜けて感染力の高い「ハイブリッド・ウィルス」を作り出すこともできるのです。
これをウィルスの「機能獲得研究」といい、もっぱら「生物兵器」の開発に用いられているようです。
4.「すり抜ける変異」は必然
「このウィルスは免疫をすり抜ける変異を起こす」
ワクチン効果が「期待外れ」とわかったとたん、さんざん推奨してきた「感染症専門医」の先生方は、まるで新型コロナウィルスが「狡猾な小悪魔」であるかのように言い始め(そして、推奨した責任逃れを始め)ました。
本当にそうなのでしょうか。
ウィルスに意思や感情などなく、単に「進化の法則」「自然の摂理」に従っているだけなので、こうしたウィルスを擬人化した「情緒的表現」は、まさしく「印象操作」と言えるでしょう。
ウィルスに変異が生じ、新たな変異種が広がる場合、その変異は必ず「免疫をすり抜ける」ものになります。
「変異の仕組み」をきちんと理解していれば、不思議でも何でもありません。私としては、「当然そうなるよね」としか言いようがありません。まったくもって予想どおりの「必然的帰結」というやつです。
変異は、ウィルスのRNAのあらゆる部分でランダムに起こります。それがスパイク蛋白に影響(変化)を与えない「同義置換」なら、接種者の体内で作られる抗体がちゃんと捕捉してくれるので、ウィルスは排除され、増殖できなくなります。
いっぽう、スパイク蛋白の性状を変えてしまう「非同義置換」が起これば、接種者の抗体では捕まえることができず、ウィルスは細胞に侵入し、増殖を開始することになります。
つまり、抗体に捕まってしまった株の系統はそこでおしまい。抗体に捕まらない(すり抜けられる)変異株だけが生き延びて増殖することができるのです。
「免疫をすり抜ける変異を起こす」は完全な間違いで、むしろ「抗体が免疫を回避する変異を招いている」のです。
進化の系統樹がある方向へ伸びようとするのを阻止する力を「淘汰圧」と呼びます。「淘汰圧」がかかると、系統樹はそれ以上進めないため、別方向へと枝を伸ばし始めます。
皆さんも、車を運転中に道路が通行止めになっていたら、迂回路を探すでしょう。それと同じ。変異と自然淘汰を推し進める圧力なので「淘汰圧」です。
「ワクチン抗体が淘汰圧となって(抗体を回避する)変異を促進する」のは、初めからわかっていたこと。
もしかして「感染症専門医」のお偉い先生方は、そんな「初歩中の初歩」もご存じなかったのでしょうか。
日本では、政府とメディア総ぐるみの「接種キャンペーン」により、全国民の実に8割(1億人弱)が新型コロナmRNAワクチンを接種してしまいました。
どう考えても、この作戦は「大・大・大失敗」。
このワクチンは同じ設計図に基づいて作成されているため、接種者全員が「同じワクチン抗体」を持つことになります。その結果として、変異株の「感染爆発」を招いたのです。
1億人もがワクチンを接種すれば、遅かれ早かれ、ワクチン接種後に感染した誰かの体内で「抗体をすり抜ける変異」が生じるのは必至。確率論からいって当たり前です。
この変異株は、みんなが同じ抗体を持っているおかげで、すべての接種者の抗体をするりとスルーできます。テーマパークのフリーパス状態。なので、あっという間に勢力を拡大(感染爆発)していったというわけです。
新型コロナには、「若年者は感染してもほぼ発症しない」という特徴がありました。これは、メディアの煽り報道とは真逆に「このウィルスが極めて病原性の弱いウィルスである」ことの明白な証明なのですが、ここでは触れません。
ともかく、発症しなかったり、ごく軽い症状で済む若年者がもしワクチンを接種していなかったら、どうなっていたでしょう。
彼らは自然感染しても、自前の免疫でウィルスに打ち勝てます。そして、自然感染した後には、ワクチンのようにスパイク蛋白部分に特化・限定したものではなく、ウィルス全体に対する「広範な抗体」を持つことになります。
仮に接種者の体内で生じた「抗体をすり抜ける変異株」を吸い込んでも、「RNAの変異していない部分」に反応して、ウィルスを捕まえることできるのです。
すると、彼らが「防波堤」となり、接種者だけの集団では感染爆発が起きてしまう「抗体をすり抜ける変異株」を食い止められ、感染拡大がそこで止まります。
「集団の全員が同一抗体を持ってしまう」ことの危険性がおわかりいただけたでしょうか。
「多様性」は、生命の灯をつないでいくうえで極めて重要な要素です。さまざまな非常事態に対処するためのリスクヘッジなのです。
それなのに、「SDGs」だの「多様性」だのを唱える国際組織や各国政府が、こぞってワクチン接種という「個体の均質化」に固執・邁進しているのは、いったいいかなる理由でしょうか。
「多様性」の真意を理解していないのか、それとも何か別の目的があるのか……
以上、駆け足で「ウィルス人工説」について述べてきました。
専門の研究者から見たら、誤解や説明不足な点もあろうかと思いますが、とにかく「非理系」の方の「イメージしやすさ」を最優先に執筆しました。
こうしたイメージを持つことができれば、専門家による難解な解説も多少は理解しやすくなるはずです。
なお、この記事は、「ウィルスの専門家」ではない筆者が知識を積むことで随時更新・加筆修正する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
