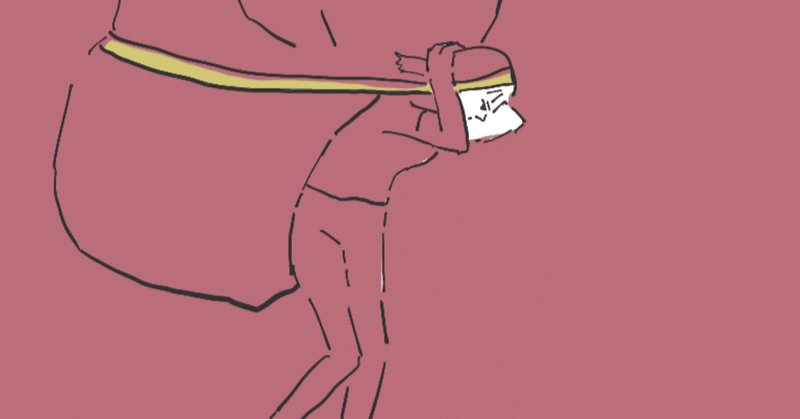
今の人に苦しみしか与えない「伝統」なんて
伝統を重んじる
とか、言いますね。
伝統芸能、と呼ばれる歌舞伎がわたしは好きですし、伝統建造物とか伝統工芸品、などと言われると「ほう」と思って見に行きたくなってしまうので、長く受け継がれてきたものを尊ぶ、という精神は嫌いではありません。
いや、好きです。わたしは伝統が好きです。
残していきたい。積極的に。
でも同時にわたしは、今ここに生きている人に苦しみしか与えない「伝統」なんて投げ捨ててしまえ、とも思うのです。
大体、人が「伝統」を持ち出すときは怪しいのですよ。
なぜこんなにも面倒で大変なことを、無理しながら、しかも無報酬で行っているのか?などということに理論的な根拠を示すことが出来ないから、苦し紛れに「昔から決まっていることだから」「伝統だから」とか言い出す場合が多いと思うのです。
今は伝統とされていることだって、始めたときは最先端だったはずです。
下手をすると、始めた人は半ば冗談だった可能性すらありますよね。
シャレで適当に思いついたことをやってみた。
家族にウケるかなと思って。
そしたら近所の人が「これはいい」とか寄ってきて「真似していい?」「いいよ」なんてことになった。
ご近所さんと家族だけで、内輪ノリで面白がっていたら、村の和尚さんがやってきて「これはいい、来年も同じ時期に村のみんなでやろう」なんてことを言い出して、来年も、再来年も、そのまた次の年も、思いついた人が死んだら次の世代に受け継がれて、いつしか「伝統」になった。
そして誰もやめられなくなった。
なんてことが、あるような気がするのです。
翻って現在、そうして作られた「伝統」は町内会で持ち回りで担当することになっていて、みんなそれぞれフルタイムの仕事を持っているから、帰ってきて夜中に準備して何週間も寝不足で仕事に行くことを強いられて、心身にストレスを抱えるようになった。
そうして苦労して成し遂げても、結局あんまり誰も喜んでいない。順番が回ってくるのが億劫でしょうがない。
続ける理由は「伝統だから」一択。
そんな姿を、その「伝統」とやらを始めた人が見たら
「えっそんな大変ならやめれば?やめなよ!」と言う気がします。
由緒ある伝統行事でも
何百年も続いている家系でも
開校当時から続いている校則でも
今、ここに生きている人に苦しみしか生み出さないならやめちまえ。
わたしはそう思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
