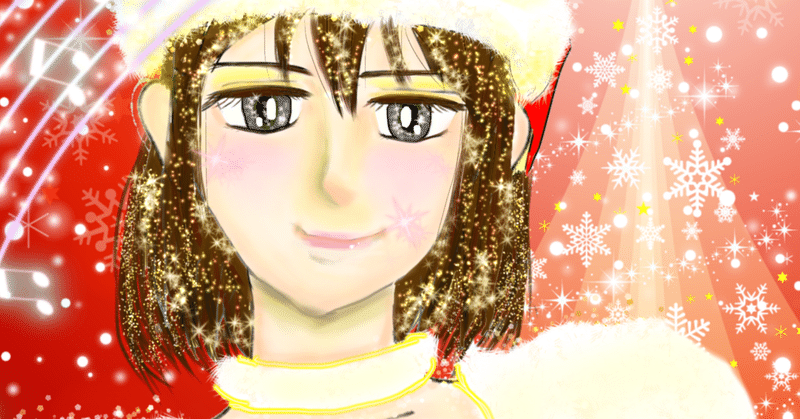
僕は君になりたい。 第24話「聖夜の夢 聖夜の僕は主役になれた?」
#24
メンバーたちから、プレゼントをもらった。
『のどケアセット』だという。
吸入器とハチミツとのど飴だ。カンパして買ったらしい。
それと、個々からもそれぞれもらった。
美咲は、紺の手袋とペンケースだった。なぜその組み合わせになったのかは分からないが、ペンケースは汚れてきていて、そろそろ買い替えようと思っていたのでちょうど良かった。デニム地の丈夫そうなものだ。
あかりは、陶芸教室で作ったというマグカップをくれた。シンプルな白無地の作品だと思っていたが、よく見ると薄い黄色のローマ字と英語で「LUIPYON SMILE JUMP!」と細かく筆書きしてあった。底には細い魚みたいな絵が書いてあったが…どういう意味なんだろうか?
綾香は、手編みのニット帽をくれた。黄土色と白を基調としたボーダー柄で僕のイニシャルの「R.S」が青い糸で控えめに房の側に刺繍してあった。それに青っぽいチェック柄のハンカチのセットだった。
「あ、ありがとう…悪いな。オレ、みんなの誕生日に何もあげてないのに」
「アハハ。だって、みんな、まだだもん」
「え?」
「まだ出会って1年経ってないでしょ? あんたが1番早いんだよ。あかりは3月だし、私は4月だし、綾香だって5月の半ばだからね」
美咲が言った。
そうなのか…なら仕方ないのか。
でも、そうすると、この後、僕も3人にプレゼントをやらなきゃいけないってわけか。
な、なんか、プレッシャー…。
多数の女の子たちに囲まれ、僕はさながら大奥にやってきている「上様」のような感じなわけだが、そんな扱いをする者はだれもいない。
だが。
「流伊さまー。お久しぶりでございますわー!」
「お久しぶりでございますわー!」
…出た。
お嬢様姉妹、津雲ツインズ。
もうすぐグループ名『AIR REAL』としてデビューする予定の双子のアイドルだ。大手企業ツクモホームの社長令嬢でもある。
僕より1つ年下だ。
「この度は、お誕生日おめでとうございます♪ わたくしたちもささやかながら、プレゼントをご用意いたしましたので、受け取っていただければ幸いでございます!」
「誠に幸いに存じますわ!」
白いリボンの瑛里亜に続いて、紫リボンの愛里亜が頭を下げながら叫ぶ。
お嬢様たちからプレゼント?
注目が集まる。
どんな高級品が来るのかと、周囲も目を見張る。
「お恥ずかしい限りですが、一足早くチョコレートを手作りいたしました! バレンタインデーの時期はわたくしたちもデビュー直前にてお渡しできるチャンスがないかもしれないと思いまして…」
愛里亜が切実な視線で僕を見ると、瑛里亜もまた引き継ぐように言葉をつなぐ。
「このような素人の作った稚拙なお菓子が、流伊さまのお口に合うか不安ですけれども、これでもフランスのショコラティエに指導を受けましたので大丈夫かと…」
そして、2人息を合わせて僕に言う。
「どうかお召し上がりくださいませ!」
差し出されたそれは、光沢のあるゴールドの包み紙に、黄色のリボンを掛けた細長い少し大きめの箱だった。
ひとまず、宝石とかの「高級品」ではないようだったので、安心して受け取る。
「ありがとう、2人とも」
「まぁ…流伊さまぁ〜。お礼のお言葉、返って恐縮なのでございます!」
「こんな駄菓子をお受け取り下さって、こちらこそ、感謝感激!光栄なのでございます!」
2人は手を取り合って涙する。
感情の振り幅の大きさに、ちょっと着いていけないが、喜んでるみたいだから、まあ…いいか。
僕は「これから頑張ってね」と励ましの声をかけ、姉妹を労う。
「はい! ありがとうございます」
彼女たちは、明るく笑った。
☆
宴もたけなわだった。
津雲姉妹が来ていたとき、少し席を離れていたカオルンが戻って来た。
色紙を2枚どこからか調達してきたようだ。
1枚を僕に渡した後、サインペンのフタをぽんと抜き、きれいな字で「あじさいガールズ♥︎黛薫」と書いたものを僕にくれた。
僕も「STAR☆CANDLE 月城琉唯」と書いたが緊張して字がさざ波立ち、そのうえバランスがすごく悪い。
「ごめん…なんか失敗しっちゃって」
「全然、変じゃないよ。丁寧に書いてくれてありがとう」
「いや…カオルンの上手な字を見たら、恥ずかしくて…」
「大丈夫だよ」
少し首を傾けて歯を見せずに笑う。
近くで見ると、髪の毛が細くサラサラで、キラキラと光っている。
ふと、フローラル系の香りを感じた僕は、そういう香りの石鹸で髪や身体を洗ってるんだな…などと妄想した。
そこへ、美咲とあかりが冷やかしに来た。
「カオルンさん、今日はウチの悪ガキの相手をしてくださって、有難うございますー」
美咲は会釈するカオルンに挨拶すると、僕に言った。
「流伊〜、ちゃんと楽しんでるかー?」
「あ…ああ、まあ」
「今日はたくさん、お喋りしときやー!」
あかりは、ほぼ酔っ払いのオヤジだ。
メンバー2人は赤ら顔をニヤニヤさせて、肩を組み、ゲハゲハ笑いながら去っていく。
笑いすぎて体温が上がっているのか?
それとも、本当に酒飲んだのか?
「…いい仲間ね」
「…あ、うん。まあ、それはね。小バカにしてくるときもあるけどさ」
「仲が良い証拠よ」
「そうかな」
「そうよ。優しいお姉さんたちじゃない」
「ははは…」
一時期不仲になり、解散の危機にあったという『あじさいガールズ』。今は戻りつつあると聞いたが、実際のところどうなんだろう?
僕は、訊けなかった。
☆
僕はトイレに行くため、会場の外に出た。
「ふーっ…ちょっと、疲れたな」
僕はつぶやいて、廊下を歩いてトイレに向かう。途中に自販機のある『休憩室』がある。本当はこの隣の『食堂』でパーティーをする予定だった。
だが、出席希望者が多かったので、さっき出てきた広い『練習室』を会場にすることになったと、あかりから聞いた。
何気なくその横を通り過ぎようとしたとき、だれもいないはずの『食堂』にふと人の気配を感じた。
だれだ?
そこまで気になったわけではなかったが、何となくドアをわずかに開けてみた。
「…お前、何してんの?」
中にいたのは、綾香だった。
向こうを向いてテーブルに腕を伸ばして突っ伏している。
僕の声に驚いて、ガバッと跳ね起きた彼女は「何でもないよ」と言ったが、そうであるわけがなかった。
「流伊くん、なんでここに…?」
「…トイレに行く途中だよ。なんか、人の気配がしたから何となく気になってさ」
「カオルンは?」
「え? 女子と連れションするわけないだろ。会場にいるよ、サイン交換した」
「そっか…」
「それよりさ」
僕は『食堂』の中に入っていき、綾香の近くまで行く。彼女は少しだけ怯えているように見えた。
手紙を持ってくれば良かったな、と思ったが仕方がない。
苦労して書いた手紙だったのだが…。
僕は、自分の口で言うことにした。
「…“迷惑”だなんて思ってない。思ってないけど、ちょっと待って欲しいんだ、オレ…こういうのなんていうかさ…その、まだ分かんなくてさ」
だが、しどろもどろだ。
やっぱり、手紙のほうが男らしく言えているなと今更ながら思った。
「カオルンのことだって…初恋っていうか、憧れっていうか、とにかくホントのそういうのと違うんだ…たぶん」
「流伊くん、トイレは…?」
「は?」
「行く途中でしょ? 遅くなると、変に思われちゃうよ」
「そんなの、何とでもなんだろ」
「主役なんだから、ダメだよ…」
「…なんだよ、話してんのに」
涙を浮かべている女の子を、1人にして出ていけるようなヤツだと思ってるのか?
「流伊くんは、主役。私は、脇役なんだ。いいんだ、それで」
「そうじゃねーだろ…。とりあえずトイレに行くけど、行ったら、一緒に来いよな。仲間だろ!」
半ば怒りながら、僕はトイレに行った。
そして、戻ってくると。
…綾香は、いなかった。
「あいつ…」
1人で会場に戻ったのだろう。
僕は舌打ちをした。
…なぜ、舌打ちをしたんだろう?
彼女が、待ってなかったからか?
“好き”だとは告げられたが、まだ付き合っているわけでもない。「待ってろ」とも言ってない。「一緒に来いよな。仲間だろ!」とは言ったが、それはここに1人でいるなという意味だ。会場に戻ったのなら、それでいいんじゃないのか?
なのに、なんで僕は…。
僕はその無人の部屋を出て、会場に戻った。
綾香はいた。
美咲やあかり、別グループのアイドルたちの輪の中にいて…笑っていた。
「どうしたの? ちょっと遅かったね」
またチキンをかじっていたカオルンに問いかけられ、僕は苦笑する。
「なんか、お腹いっぱいで…休んでたんだ」
「あんまり食べてないのに。少食なんだね、私これでチキン5個目だよ」
「オレも、4個は食べたよ」
「そう? もっと食べていいのに、今日の主役なんだから」
「あ、うん…」
まあ、確かに今日の主役は僕なのだ。
僕の誕生日を祝う会、なのだから…。
《流伊くんは、主役。私は、脇役なんだ。いいんだ、それで》
でも、あの言葉はそういう意味ではなかったように思う。
もっと、根本的な。
「あら、もう終わりの時間ね」
だれかが言った。
時計はもうすぐ8時になろうとしていた。
僕はサラミとピーマンに粒コーンをばらまいた6等分のピザの2カット分を一気に頬張った。それを炭酸レモンで流し込む。一生懸命に飲み込んだ。それにフライドポテトやチョコバナナを口の中に突っ込む。
「流伊くん? お腹いっぱいなんじゃ…」
カオルンが心配したが、僕は止まらなかった。
目を白黒させながら、僕はとにかく食べた。
腹がはち切れそうになるのも構わずに、無心に食べ続けた。
…大好きな人の前で、醜い自分を見せつけるように。
…いや、違う。
自分のこの訳の分からない気持ちを、食べることで紛らわそうとしていた。
…結局、お前は退くのかよ。
だったら、なんで手紙なんか…。
「……オエッ!」
「流伊くん!!」
僕は、トイレに走った。
そして、血の気が引き、青ざめた僕は。
今日食べたものの殆どを、吐いていた…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
