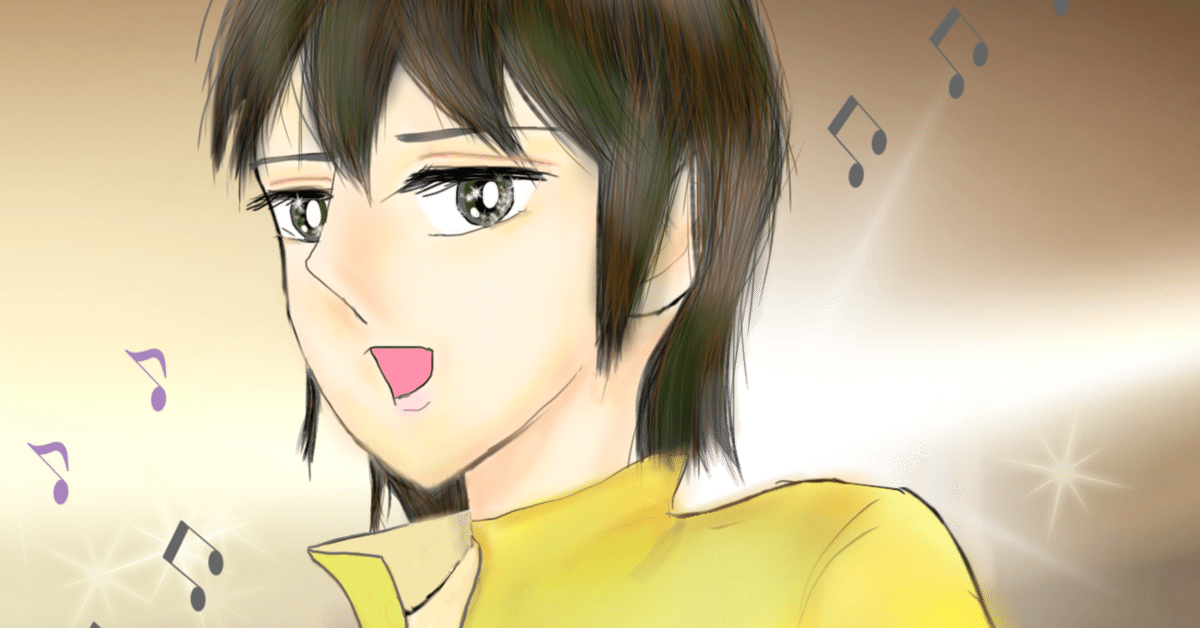
僕は君になりたい。 第12話「ルイのうた 僕の焦りと熱」
#12
事務所の休憩室で、ソファーに座って1人でゆったりと自販機で買った炭酸レモンを飲んでいた。
「く〜ッ」
のどがスカッとした感覚を堪能していたところ、誰かがドアを開けて入ってきた。
「あっ! ルイルイじゃん。珍しいね、休憩室に来るなんて」
「あ、すみません。お邪魔してます。もう退散しますんで」
「何言ってんのさ。先の人が優先だよ。遠慮しなくていいの、いいの!」
入ってきたのは、ガールズバンド『ピンクバタフライ』のボーカルである毬谷ナギさんだった。確か22歳になる。
以前、急性肺炎で入院して予定のステージに出演できなくなった彼女の代役として『星キャン』が出させてもらった経緯がある。
それ以来、なんとなく気にかけてもらっている感じだ。
髪をピンクに染めて、それをポニーテールに結び、左の目尻の下に小さなピンクの蝶々形のペイントをしている。
そして、いかにもロックな革ジャンとスキニージーンズでいつも決めていた。
今日は黒地に白いドクロのTシャツを革ジャンの下に着ていた。
「ありがとうございます、ナギさん」
「べつに、ここ共有場所なんだからぁ。構わないって! 会いたかったよー、ルイルイ。君、女子に遠慮しすぎ!」
「はあ、すいません」
言いながら、ナギさんは僕の横に腰掛けて、フランクに僕の肩を抱く。
「あ、あの…」
「カワイイなあ…。どこの馬鹿がこんなカワイイ子にツバ吐けるわけ? 鏡見たら気づくだろうに。勝てっこないってさ、諦めろよなぁ。出来が違うんだからさぁ」
僕の横顔をまじまじと眺めて、ナギさんはひとつ溜息を吐く。
「ルイルイ、覚えときな。なんだかんだ言って、この世界は"顔"なんだよ。ましてアイドルを名乗るんだったら、顔が悪くちゃ始まらない。逆に言えば、顔さえ良ければ、あとは愛嬌だけなんだ。歌が上手いの、ダンスが上手いのは、二の次さ。だから私はアイドルじゃない、バンドを選んだ。バンドは"歌"が良ければある程度は認められるからね。私くらいな顔でも、ルイルイにこうして肩を並べられるんだ」
自分の歌に自信があるから、こんなことが言えるのだろう。
僕は彼女に訊いてみた。
「血の滲むような練習をしてるんですか」
「してるよ。でも、のどのケアも大事でね、蒸気を当てたりハチミツ舐めたり…それも仕事のうちだと思ってる。特に私なんかはのどが壊れたら、仕事になんないからね」
「そうなんですね…オレも歌もっと上手くなりたいんですけど、諦めたほうがいいのかなって思うときもあって」
「ふーん、頑張り屋だねぇ、ルイルイは。カワイイだけじゃないって言われたいよねー」
「…はあ」
それで、何かアドバイスをくれるのかな、と思っていたが、彼女は少し意地悪そうな目を向けて微笑んだだけだった。
「じゃ、私はそろそろ行くね。新曲PVの打合せなんだ。またね、ルイルイ」
「あ、はい…」
「私も負けてらんないからね、ルイルイ。肺炎の時は本当に辛かったよ…身体大事にしながら、頑張んな」
ドアの前で振り返り、それだけ言ってナギさんは出ていった。
迫力のあるハスキーボイス。
女性らしからぬ激しいシャウト。
切ないバラードも歌いこなす、女ロッカー。
とにかくカッコいい。
『ピンクバタフライ』。
略して『PB』とも呼ばれている。
蝶々プロ、唯一無二のガールズバンド。
そのボーカルにして、リーダーだ。
憧れるよな…。
だが、僕には到底彼女の歌は歌えない。
あんな感情をぶつけるようには歌えない…。
僕は飲んでいた炭酸レモンの空になりかけたペットボトルを見つめる。
「明日はハチミツ入りのハーブティーにするかな…」
その後すぐ、ナギさんと入れ替わるように、あかりが休憩室に顔を出した。
「あ、琉唯ぴょん。西山先生が呼んでるよ」
と、僕を呼ぶ。
「…あ、うん。ごめん、今行くよ」
僕は立ち上がり、待っているあかりのほうに急ぐ。西山先生はボイトレの先生だ。新曲の手解きもしてくれている。
扉の前まで来ると、そこに立っていたあかりが不意に僕に言った。
「な…琉唯ぴょん、あの、な、ハグしてもいいかな」
「ハグ? なんで?」
「…ええやろ、仲間のキズナを深めるためや」
「え、そうなの?」
女子たちはこういうのが普通なのだろうか?
だが、僕は女のフリをした男だ。
女のあかりから言うのだから、構わないのだろうけど…。
「うちとなんか、イヤかな?」
「いや、そんなことはないけど…」
「じゃいくよ」
ふんわりといい匂いがした。
シャンプーの香りってやつだろうか。
まっさらなキレイな首筋が見えた。
でも、なんかこれ…やばくない?
あかりは離れると、優しく笑った。
ほんのりと桃色に頬を染めて、大きな瞳を潤ませていた。
「…ありがとな、琉唯ぴょん」
「えと…なにが?」
彼女は答えなかった。
踵を返し、レッスン室へ僕を促す。
「遅れると、怒られるよ〜。急げ〜!」
いつもの明るい声をあげて走り出す。
「待ってよー」
「こらー、走るなー!」
それをボイトレのレッスン室からドアを開けて見ていた美咲が怒鳴る。
「わあ! 怒られたわ!」
笑いながら、あかりが頭をかく。
「もう、なにやってるのよ。先生がいらっしゃるのに」
「ごめんなぁ、美咲ちゃん」
「…ごめんなさい」
僕も謝る。
ナギさんと話し込んでいたせいもあり、先生が早めに来ると言っていたのを忘れていた。
「はいはい。揃ったなら、話を始めますよ」
中にいた西山恭子先生が、仕方なさそうに息を吐く。
「先日、花岡先生がいらしたと思うけど、先生のご要望で、今日から個別レッスンも取り入れていくことになりました。全員で30分やった後、今日はあかり、残って下さい。次回は綾香、その次は美咲の順です…あと、琉唯は特にやらなくてもいいそうです。曲ができてから、ということです」
「え…僕は無しですか? 1番必要じゃないですか?」
「花岡先生の指示です。とりあえず、全員練習のとき頑張ってやりなさい」
「あ、はい…」
なに考えてるんだろう。
あのふんふんおじさん…。
僕があのとき素直に本名を名乗らなかったから、嫌がらせしているのか?
どう考えたって、僕が1番声が安定してないだろう。
「いいなあ、居残りなしで」
綾香がうらやましそうに呟くが、僕は不安でならなかった。
ハイトーンはどこまで出せるか訊かれ、ソだと答えたものの、安定して出せるかと言われたら自信がない。
…自分でやるしかないか。
何とか、高い声が出せるように、自分でのどを潰さない程度にトレーニングしよう。
「琉唯、始めますよ」
集中していない僕に、先生が注意する。
「すみません」
「…では、大きく息を吸って。吐いて」
とにかく今はレッスンに集中しよう。
そう思うのだが。
僕は、なかなか集中できなかった。
☆
中間テストが始まった。
もうすぐ、希望の進路調査を提出する時期にも来ていた。
僕は勉強にもあまり集中できていなかった。
国語と社会は教科書を読み込んでいたので、あまり苦労はなかったが。
「流伊。お前、本当に大丈夫か?」
高柳が終礼のチャイムが鳴り、数学のテストが回収されるなり、僕の横にやってきた。
「…なにが?」
こいつに心配されるほど悪くないと思うのだけれども、高柳は眉間をひそめた。
「問3の答え、あれ絶対②だろ。お前、③にしてたじゃん」
「…勝手に人の答案見るな」
「わざわざ見たんじゃないって。偶然見えちゃったの!」
「…あれは、③だろ? な、斎藤」
僕は前の席の斎藤賢一に確認する。メガネをかけたクラスメートはくるりと振り返り、僕に言う。
「いや、あれは②だ。高柳が正解。③は引っかけだよ」
「そら、見ろ!」
高柳が得意気に僕を見下ろす。
斎藤は、学年でも1番か2番を争う秀才だ。
悔しいが、恐らくそちらが正解だろう。
「マジか…」
「めずらしいな、榊原。お前がそんなイージーミスするなんて」
斎藤にまで言われてしまった。
僕は落ち込んだ。
「そうだぞ、流伊。それでも、学年トップ10から落ちたことない男かよ? 情けないなぁ」
なんで、お前が "上"から言うんだよ。
「…だったら、次からノートは斎藤に借りろよな」
僕が恨みがましい目で睨むと、高柳は少し慌てて僕を宥めた。
「いや、総合点ではお前のほうがはるかに上だって。問3に関してだけの話だよ〜」
「分かんないぞ、そんなの。バカな引っかけに引っかかってるようなオレだぞ。もしかしたら今回は赤点かもしれない…」
そう、自信があった問題で間違えている時点でヤバい気がする。
「…ん?」
そのとき、不意に体がブルっと震えた。
「流伊? どうした?」
「なんか寒い…」
高柳が、僕のおでこに触れる。
「おい、お前…熱あるじゃん!」
「え…熱?」
いくら昨日から今日にかけて徹夜で勉強してたからって。
1日くらい寝なくたって、何とかなると思ったんだけど…。
「お前、今日ずっと具合悪かったんじゃねーの? マジ大丈夫かよ? 家まで送るよ」
高柳が僕の背を撫でる。
「平気だってば。1人で帰れるよ」
「なんだよ。ちょっとは甘えろよ、オレに。こんなときしか役に立たないぞ」
「いいってば!」
僕は自分が情けなくて、少しヤケクソになっていた。
「流伊…」
悲しそうな彼の声。
「そんなに頼りないか、オレ…」
視線を僕から逸らし、高柳は唇を震わせて右手をぐっと握ったまま、僕に背を向けた。
「あ、駿…ごめ」
「いいよ、もう。1人で帰れよ」
ホームルームが終わり、僕は高柳の姿をすぐ追ったが、席が僕よりドアに近い彼は僕が声をかけるより先にもう廊下に出て、1人で帰ってしまっていた。
僕は彼を追いかけようとしたが、慌てたせいで机に足をぶつけ、また熱のせいでクラクラして転んでしまった。
…こんなとき、高柳はいつもすぐに来てくれて、僕を抱き起こしてくれた。
僕は自力で立ち上がり、ぶつけた足をさすりながら廊下に出るが、当然彼はいない。
僕は更に落ち込み、高熱で重たい身体と自己嫌悪の暗い心を引きずりながら、靴を履き替える。
もちろん、そこにも高柳の姿はなく。
僕は、独り静かに帰途についた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
