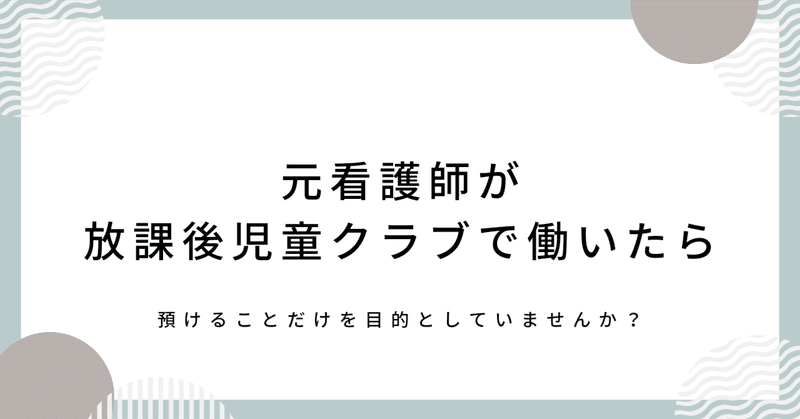
〈123〉本来の学童なんてものはあるのか①
過去、"学童保育とは"を追求するというよりは、その地域独特のやり方で子どもたちに向き合ってきた筆者の放課後児童クラブ。
筆者含め支援員が入れ替わってからは、前任者が引き継ぎもせず辞めたこともあって、古い概念が残りつつ、一から模索する状態でした。
"学童保育とは"の答えを求めながら、数年かけて一つひとつ本質にそぐわない慣習を改めてきました。
組織としてはこれからという時に、主力支援員や学童保育に一生懸命向き合ってくれた支援員が、この地域の学童保育に絶望してやめていきました。
そして縁あって、他の自治体で療育や学童保育を経験してきた支援員が、ヘルプという立ち位置で入ってくれました。
つまりこの支援員は来年度もいてくれるとは限らない。その可能性ははるかに低いのです。
いるうちに保育技術を吸収したい。
学童保育について議論したい。
本来あるべき学童保育と筆者の放課後児童クラブの差は何か知りたい。
どう組織作りをしていけばいいのか教えてほしい。
見本を見せてほしい。
そう思って実際にやってもらっているわけですが、やはり違うんですよね。
出欠確認というものも、もちろん原則は同じなのですが…
全員着席して名前を呼ぶ。
そういうものです?
まるで学校の朝のシーン。
その流れで宿題をする時間が設けられる。
座位の保持、集中力の程度、態度、学校での様子が丸わかり。
本当に丸わかりなんです。担任の先生の立ち振舞いまで手に取るようにわかります。
出欠確認、たったこれだけでも衝撃でした。
朝の会のような時間、宿題をする習慣化、試みたことはもちろんあります。
しかし、あまりの荒れ散らかしや学習への抵抗感の強さ、発達特性上の困難さに直面する中で、"やらせる"ことの必要性への疑問が生じ、"自分で選択する""自由意思の尊重"を重視するようになった筆者の放課後児童クラブ。
学校で、家庭で様々な摩擦に晒される子どもたちが、本当にただ自分でいる場になることに重きをおいてきたのです。
(それはそれでとんでもない事態や苦労があるわけですけどね…)
そのため、そもそも"学童で子どもたちが全員で座っいる状態を作る必要があるのか"という疑問に苛まれているわけです。
また、学童保育が学校に追随するとか、学校生活のための練習を学童でする必要はないのでは、とも思うのです。
学童での座位の保持機会や練習が学校での学習場面に役立つとか、学童で学習の習慣化させる意義って本当にあるのか、本当に必要なのか。子どもたちは学童にそれを望んでいるのか、ということです。
実際、1年生は出欠、宿題の時間に座っています。
立ち歩きなど注意されながら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
