
「まずは自然養鶏のやり方を勉強」 シネマアミーゴの庭先養鶏 #2
前の記事で紹介したsho farmさんのワークショップに自分は参加していないのでまずは自然養鶏のやり方の勉強にとりかかる。
参考にした本はこの2冊。
中島正著「自然卵養鶏法」。
1980年にかかれたもので自然養鶏が全国に広がったきっかけになり自然養鶏のバイブルと呼ばれているそう。
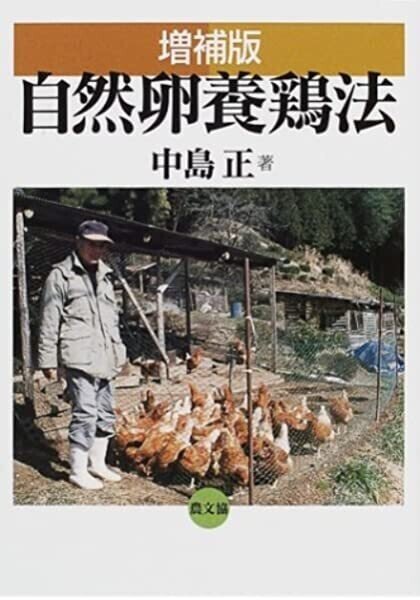
笹村出著「発酵利用の自然養鶏」。
こちらは2004年に書かれた本で「発酵」というキーワードに惹かれて読んでみた。
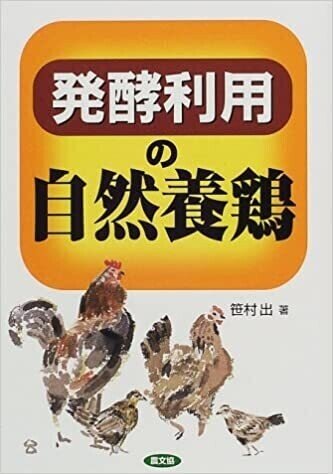
「自然卵養鶏法」は書かれた時代背景もあり「現代社会への警鐘」系の文章が多く、散々そういったドキュメンタリー等を上映してきた自分にとっては知識の重複が多く読み辛かった。
もちろんそういった背景の哲学も大事だとは思う。
ただ「自然養鶏のやり方」の情報に特化するのであれば「発酵利用の自然養鶏」の方が自分には読みやすかった。
どちらもメソッドに違いがあるので両方読んで良かったと思っている。
これまで読んできた自然農系の著作の中で共通することがある。
:色々なメソッドはあれども最後はそれぞれの土地や環境や規模にあったものを観察しながら自分のやりかたを作り上げるしかない。
:育てようとする対象の植物なり動物なりのもともと野生の状態や原産国の環境がどうだったかを参考にすること。
2冊読んだ限り自然養鶏に関しても同じことが言えそうだ。
今回で言えば野生のニワトリが本来どういった生態系をしていたかを参考にしたりしながらそれぞれの著者のやり方が紹介されている。
問題があるとすればどちらの本も「自然養鶏家」を目指す人に向けて書かれているということだ。
家庭でできる庭先養鶏に関しては終わりの方に数ページ触れられているだけ。
ここは庭先養鶏向きのアレンジが必要そうだ。
sho farmさんのワークショップで庭先養鶏を始めた人のネットワークもうまれたのでそこで情報共有しながら自分なりの形を模索することにした。
何かに集中すると一気にやるけれどもルーティンワークは苦手な自分の性分に合わせてできるだけシンプルしたい。そこで以下の二つを意識してあとは雑でいくことにした。
「餌は買わない、基本は残飯」
自分は別に卵を売る養鶏家を目指しているわけではない。
売る卵を作ろうと思ったら本に出てくる養鶏家の様に地域から出る様々な残渣などをうまく発酵させたりなど一手間かけて餌集めをしなければいけないのだろうけどそういった労力はかけたくない。
継続して発酵飼料をつくる自信がないので基本は残飯そのまま。
昔の農家のニワトリもわざわざ餌を考えて用意していたわけでもないらしいのでそこまで繊細にならずとも育つのではなかろうか。
さてさて家庭やお店の営業の中で出てくる残飯でどこまで行けるのだろう?
「鶏舎の床は発酵させる」
どうやら床下が発酵さえしてれば他が雑でもある程度健康で匂いも出ない養鶏ができそうだ。
餌が足りない時でも地面さえ発酵してればそれを食べてしのぐようだし、病気にも強くなるらしい。
冬場も発酵熱で床下も暖かくなるから冬も乗り切れるだろう。
落ち葉を集めて20〜50cm(諸説あり)積み上げれば発酵するとも聞くのでそれを試してみることにした。落ち葉を集めて積み上げるだけならそれほど労力もかからないのではなかろうか?
ということで、ものぐさ自然養鶏でどこまで行けるかトライします。
ちなみに私はあくまで家畜とのつきあいでペットとして飼う気はないので最終的にはお肉もいただく予定です。
方針が決まったところで次はひよこを手に入れる段取りの話を書きます。
ただいまCINEMA AMIGOがコロナの影響で休業中です。 地域のカルチャーを作ってゆく発信を続けていきたいと思います。 もし記事の購入でサポートいただけたら大変助かります。
