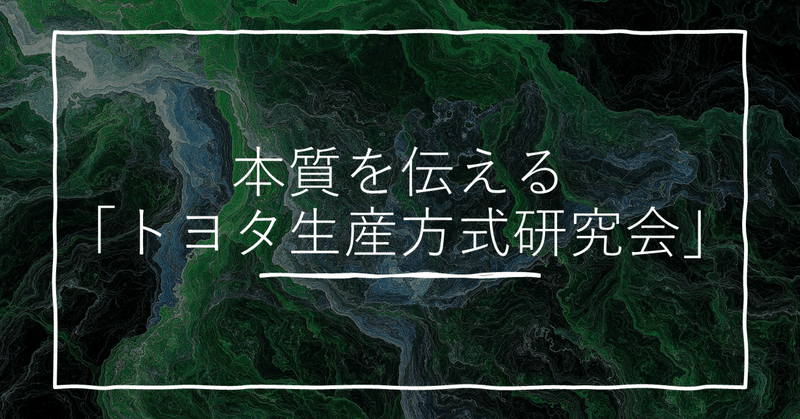
「トヨタ生産方式」の本質を伝え続ける研究会
1977年に発足した「トヨタ生産方式研究会」。
この研究会は、「改善の進め方」講座と「作業改善」実習の2つのプログラムから成り立っています。
「改善の進め方」講座は、トヨタ自動車(株)のTPS本部をはじめトヨタグループ各社で、トヨタ生産方式を実践している現役リーダーの方々によるテーマごとの解説と質疑応答が行われます。
「作業改善」実習は、前講座を受講し、自社にて必ず改善業務を行った経験者のみが参加可能です。この改善実習は、トヨタグループ企業の実稼働ラインでの6泊6日で行われ、参加者にとっては厳しいけれどそれだけに得られるものも大きい実習です。
今回は、この研究会が発足した経緯も含めてご紹介します。
「トヨタ生産方式研究会」の発足
本研究会は1977年11月に当時のトヨタ自動車㈱の大野耐一副社長にご講演をいただいて発足しました。

トヨタ自動車工業(株) 大野耐一副社長(当時)
当時、オイルショックにおけるトヨタの業績の下げ幅は他社より少なく、また立ち直りも早かったと言われています。そのことから何かトヨタには「秘密」があるのではないか、と世間の注目が集まった時期でした。
そこで、トヨタがものづくりにおいて、「何に注力をしているのか」を公開しよう、と当時の大野耐一副社長が本研究会の発足を決められたと推測されています。
手法だけではなく本質の理解を
本研究会の発足にあたり、当時の中部産業連盟 高仲専務理事は次のように語っています。
トヨタ自動車工業(当時)の「トヨタ生産方式」が注目を集め、これを導入したり、導入しようと考えている企業が多くあるようだ。しかし、導入を意図したが失敗した企業があったり、またこの方式を批判する人もないとは言えない。このような原因は以下のようなところにあると考える。
●トヨタ生産方式の根底にある基本理念を理解せずに、単なる方法・手法と考え、しかもそれを中途半端にしか理解していない。
●トヨタ生産方式は、トヨタ自工(当時)や関連企業の30年余にわたる苦闘の成果であり、それを導入企業のトップが本方式の基本理念も理解せず、しかも自工の特殊要因も考慮せず、そのうえトヨタ自工以上の努力を傾注することもなく安易に取り組んでいる。
●「かんばん」は管理の道具であるが、これはトヨタ生産方式の核心をなすものであり、このような前提条件ないしは必須の環境要件の整備を考えずに、ただ「かんばん」のみを無理矢理取り入れようとする場合がある。
さらにトヨタ自動車㈱の大野耐一副社長(当時)も同様に当時の本研究会で以下のように講演をされています。
『かんばん方式』という事の方が先行して世間に知られてしまい、『トヨタ生産方式』とごっちゃにして理解されている向きが一般に多いようでありますが、本来この『かんばん方式』というのは、一つの『管理のシステム』というふうに考えていただきたい。
われわれが言っております『トヨタ生産方式』というのは、物をつくる『つくり方の方式』であります。
この『トヨタ生産方式』をやっていただいて、『かんばん方式』のかんばんで管理すると非常に効果が出るのであって、『かんばん方式』だけを先行しますと弊害がおきる場合が非常に多いと思うので、『トヨタ生産方式』そのものをまず理解しておいていただくことがいちばん大事なことではないかと思います。
特別なことではなく
この研究会の講座では、当時も今も変わらず語られるもう一つの事があります。
それは、次のような内容です。
当時のトヨタは、資金も資材も乏しく、9倍、10倍とも言われる欧米の生産性に対抗しようにも、わからないことばかりだった。決して不自由なく改善が進んだわけではない。
だから現場に出て皆で一生懸命考えた。皆で現場で考えれば、何が問題で、その問題を解決するためにどうしていけば良いかが分かり、トライ&エラーができた。だから「現場で考えることが大切」。
現代ではITの発達により瞬時にデータの収集が実施できる。この技術を駆使しない手はない。しかし、ITはデータを収集できるが問題は解決してはくれない。
問題を見つけ解決するのは、やはり人である。「どれだけ先進的な技術が出ても、<現場を見て、事実をつかみ、改善する>ことは大切であり、何も特別なことではなく、そこから始めれば良いのだ」。
このように「現場をみる」ことの重要性を、先人の方々の体験やお考えも交えて繰り返し強調されています。
実践をとおしてのみ
現在、先行き不透明な状況の中、企業経営においては新たなる活路をいかに見出していくかが喫緊の課題となっており、「トヨタ生産方式」は製造業にとどまることなく、官公庁、病院、サービス業へも業種を超えてその基本的な考え方が普及し、多くの関心を集めています。
しかし、単なる手法として紹介されることはあっても、その根底にある本質を理解せずに語られることも少なくありません。
現在、トヨタ自動車(株)ではものづくりの現場だけでなく、事務作業や営業・技術開発などの職場でも「トヨタ生産方式」の考え方に基づいて業務改善を行っています。この改善は、業務の目的を再定義し、現地・現物で仕事のプロセスを可視化しながら問題を顕在化させ、関係部門が一緒になって改善を実践しています。
「トヨタ生産方式」の本質は、実践をとおして「改善できる人」を育てることにあります。
すべての現場において日々の改善を重ねる限り、人間集団である会社も職場もまた日々自発的に進化を遂げることができるはずです。その意味で「トヨタ生産方式」は、あらゆる環境変化に敏感に適応しやすい構造を備える「進化の武器」であると言えます。

さいごに
「トヨタ生産方式」を手法やテクニックだけで解釈することなく、実践をとおして理解できるように作られたのがこの研究会です。
毎年、春(PARTⅠ:5月、PARTⅡ:6月)と秋(PARTⅠ:10月、PARTⅡ:11月)の年2回開催されています。
具体的なプログラムの内容は、下記の中産連のHPを是非ご覧いただきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
