
バス停山

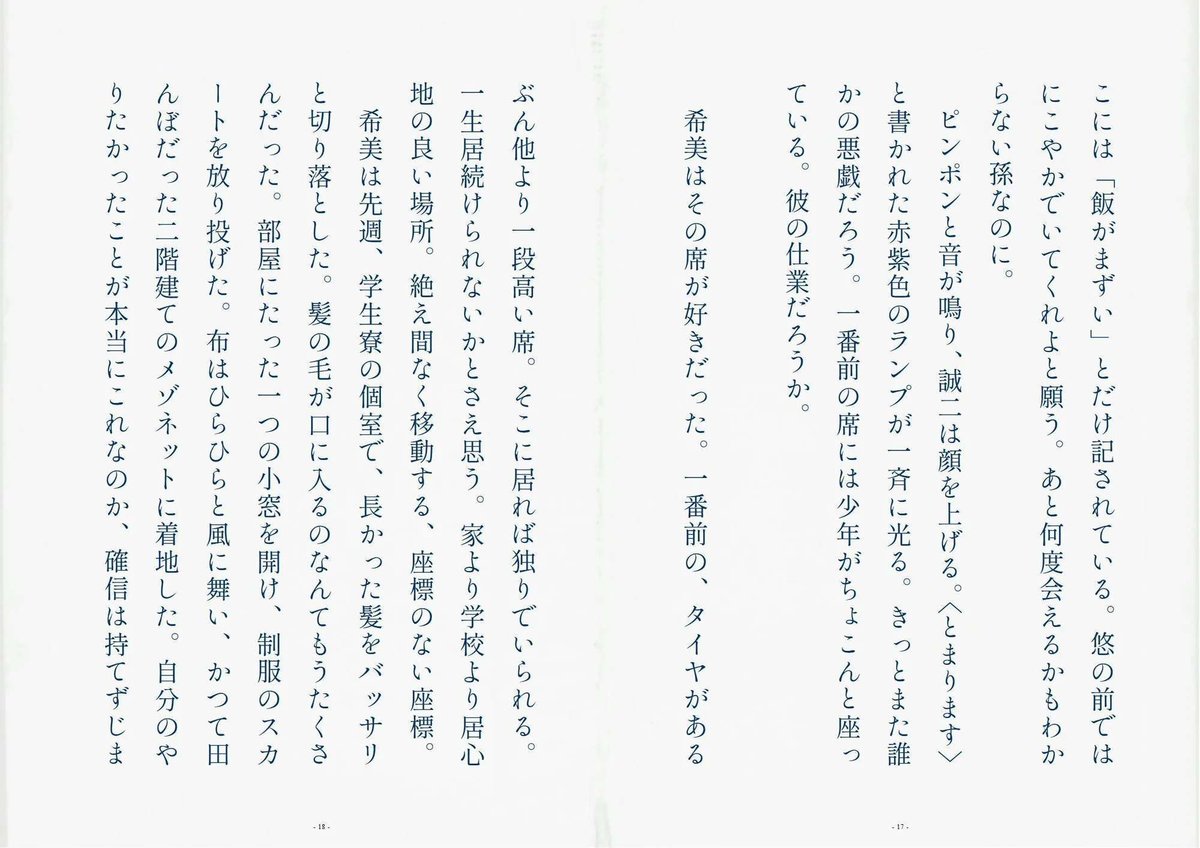




ガタンとも言わずに車体は揺れた。運転席のちょうど背中にある〈急停車に注意〉の表示が点灯した。ブーとブザー音が鳴って、前側の扉が開く。一番後ろの席がいいとはしゃいだ悠も、今は目を瞑って窓にもたれかかっている。窓の、悠の頭の当たった所だけが、うっすらと白く曇る。運転手が後ろを向く。
「降りる人おられませんね。いいんですね」
声にいら立ちが混じっていた。三回目ともなると仕方がない。駅前行きのバスは先ほどから、降りる客もいないのに降車ボタンを押され、その都度律儀に停まり続けている。
誠二はスマホを開いて、入院中の親父にメールをする。「面会遅れるかも」と送信した傍から返信は届いて、そこには「飯がまずい」とだけ記されている。悠の前ではにこやかでいてくれよと願う。あと何度会えるかもわからない孫なのに。
ピンポンと音が鳴り、誠二は顔を上げる。〈とまります〉と書かれた赤紫色のランプが一斉に光る。きっとまた誰かの悪戯だろう。一番前の席には少年がちょこんと座っている。彼の仕業だろうか。
希美はその席が好きだった。一番前の、タイヤがあるぶん他より一段高い席。そこに居れば独りでいられる。一生居続けられないかとさえ思う。家より学校より居心地の良い場所。絶え間なく移動する、座標のない座標。
希美は先週、学生寮の個室で、長かった髪をバッサリと切り落とした。髪の毛が口に入るのなんてもうたくさんだった。部屋にたった一つの小窓を開け、制服のスカートを放り投げた。布はひらひらと風に舞い、かつて田んぼだった二階建てのメゾネットに着地した。自分のやりたかったことが本当にこれなのか、確信は持てずじまいだった。腹いせと言われればそれまでかもしれない。ベリーショートにスラックスの希美を、希美の母親はまだ知らない。サッカーをやめ、ピアノを習い、全寮制の女子校を受けるより他なかった希美に、その人は何度も「恵まれている」と言った。
「あなたは恵まれているの」「家にも健康にもお金にも」「もっと選択肢のない人もたくさんいるのよ」
呪いは強固だった。対抗するのに十分なことばを、希美はまだ持ち合わせていなかった。バスはずっと走っている。窓の外が暗くなる。実家までそう遠くないはずだった。でも、いずれは目的地に着くのだろう。だから希美は感謝する。降りもしないのにボタンを押す誰かを、ちょっと親切な人だと思っている。
バスは細い県道に入り、トンネルをくぐった。電灯がてっぺんに一列しか点いていない、古いトンネルだった。駅前行きのバスがこんな道を通っただろうかと思いつつ、幸一は親切というものを見失っていた。
今朝、職場の前の横断歩道で、幸一は歩行者ボタンを押した。黄色い方だけでなく、白い方も、何度も押した。歩行者信号は青になり、少し音程のずれた〈とおりゃんせ〉が流れ出すと、白杖の男が幸一に話しかけた。
「親切にどうもありがとう。ボタン、気が付かなかったもんで」
「いえ、私が押したかっただけです」
そう言って幸一は、足早にその場を去り、拘置所の門をくぐった。
幸一の言葉は、謙遜でも、気障な自意識でもなく、ただ真実だった。自宅のインターホン、ファミレスの呼び鈴、歩行者信号のボタン。刑務官として執行に携わるその前後、幸一は目についたありとあらゆるボタンを押した。押さずにはいられなかった。それは本番を自然にこなせるように練習する、素振りのようなものだった。
その日、何か欲しいものはないか、食べたいものはないか、言い残したことはないか、と聞くと、相手は一言、温泉に行きたいと呟いた。むかし妻と行った、山奥の温泉が忘れられないんだ。言ったきり、彼は何も語らなかった。結局彼の願いを叶えることはできずに、幸一は本番のボタンを押した。
仕事が終わっても、幸一の指はボタンを求めた。バスに乗り、二人乗りの座席に深く腰掛け、自分のそばに降車ボタンを見つけた時、震える指先は自然とボタンへ吸い寄せられた。
けれども彼がボタンを押すことはなかった。指がボタンに触れる直前にランプは点灯した。次も、その次も、その次も、幸一はボタンを押し損ねた。幸一はやがて手を伸ばすのを止め、外套のポケットに突っ込んだ。そしてこれが罰なのか、救いなのかを問い始めた。
悠は、ほんとうは眠ってなんかいなかった。パパがスマホに夢中なのを見計らって、こっそりと降車ボタンを押していたのは、十歳に満たない小さな手だった。バスはダムの上を渡り、あたりに人家は見えなくなった。行先を知っているのは悠だけだった。
悠はどきどきしていた。だってこのバスはバス停山に向かってる。昔、パパが話してくれた、とてもこわい話。いらなくなった人をバス停山に捨てちゃう話。今日のパパは、あの話をした時と同じ目をしていた。だから間違いない。このバスはバス停山に向かってる。
悠にはけれども確信があった。捨てられるのは僕じゃない。だって僕はまだ小さくて、かわいがられて、とても幸せだもん。だから僕は捨てられない。でも、他の人はどうだろう。誰かがバス停山に置いていかれるかもしれない。そんなのは嫌だ。みんなにはおりてほしい。少しでも早くおりてほしい。だから悠はボタンを押す。名前も知らない誰かの、おりられるチャンスを増やしていく。
どこかで衣擦れの音がする。靴紐を結び直す音もする。ボタンは冷たくはないが温かくもない。押すとランプが点灯し、「次、停まります」と、優しい声でアナウンスが流れる。
●2022年 ブンゲイファイトクラブ4の準決勝作品です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
