
十円

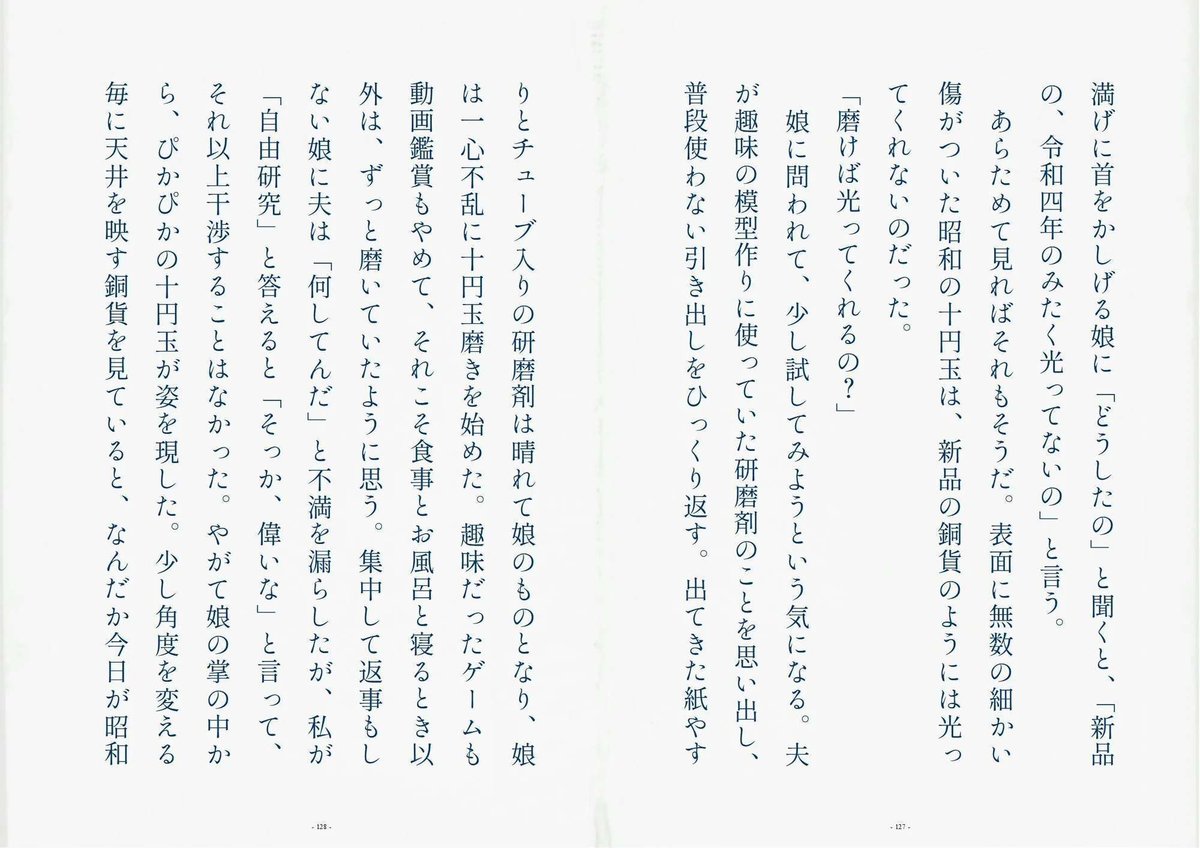




娘が夏休みの自由研究に困っているというので、手助けしたのが半年前のことだった。「十円玉にレモン汁をつけるとぴかぴかになるんだよ」と言うと、娘は目を輝かせ貯金箱へと向かった。私はレモン汁の他に、ケチャップ、ラー油、米酢などを用意して机に並べた。綿棒につけて十円玉をこすると、あるものは色を変え、あるものは変わらなかった。「どうしてピカピカになるのと、ならないのがあるんだろうね」「それぞれの調味料にどんな材料が使われてるか、調べてみよっか」 実験は順調に進んでいた。写真を印刷し、模造紙に下書きし、清書をし、百均で買ったアクリルケースに十円玉を並べた。 けれども娘は納得しなかった。並べた十円玉を見て不満げに首をかしげる娘に「どうしたの」と聞くと、「新品の、令和四年のみたく光ってないの」と言う。 あらためて見ればそれもそうだ。表面に無数の細かい傷がついた昭和の十円玉は、新品の銅貨のようには光ってくれないのだった。「磨けば光ってくれるの?」 娘に問われて、少し試してみようという気になる。夫が趣味の模型作りに使っていた研磨剤のことを思い出し、普段使わない引き出しをひっくり返す。出てきた紙やすりとチューブ入りの研磨剤は晴れて娘のものとなり、娘は一心不乱に十円玉磨きを始めた。趣味だったゲームも動画鑑賞もやめて、それこそ食事とお風呂と寝るとき以外は、ずっと磨いていたように思う。集中して返事もしない娘に夫は「何してんだ」と不満を漏らしたが、私が「自由研究」と答えると「そっか、偉いな」と言って、それ以上干渉することはなかった。やがて娘の掌の中から、ぴかぴかの十円玉が姿を現した。少し角度を変える毎に天井を映す銅貨を見ていると、なんだか今日が昭和五十三年の八月であるかのような錯覚に陥った。 けれども娘はまだ止まらなかった。新学期に入り授業が始まっても、幼い指は研磨を続け、次第にその技術を高めていった。一枚に三日かかっていた作業は一日に短縮され、学習机の引き出しには、生まれたばかりの昭和や平成が積み重なっていった。 娘のクラスで十円玉磨きがブームになっていると知ったのは、ひと月後の事だった。買い物先で偶然会った悠太君のママから、おすすめの研磨剤は何かしら、と尋ねられたのがきっかけだった。「そんなに流行ってんの?」「もうみんなやってるのよ。悠太はいま三位なの。先月まで二位だったんだけど……」「三位?」 聞くところによると、娘のクラスでは十円玉の枚数で、生徒の力関係が決まるらしかった。光る十円をたくさん持っている子は強く、持っていない子の発言力は無いに等しいのだと言う。また上位の生徒には担当の「造幣年」があるらしく、例えば平成元年を担当する悠太君は、 平成元年の十円玉を友達に与えることで、勢力傘下に加えるのだそうだ。だから子どもたちはお小遣いを全部十円玉にしてもらったり、十円玉の多いお釣りのもらい方をしたりして、目当ての年の銅貨を必死に集めているようだった。 話を聞いてから家に帰るまで、ずっと十円の事を考えていた。さすがに教育に悪影響がなかろうか。非行を誘発しないだろうか。子どもたちの貴重な時間が奪われてはいないだろうか。様々に思いはめぐったが、結局気がかりなのは、娘の順位が今、どのあたりなのかという事だった。家に帰っても娘は娘のままでいる。以前ほど頻繁には磨かなくなって、空いた時間でユーチューブを開き、外国人が何かを磨く動画に見入っている。その顔に曇りはない。虐げられている様子もない。現状に満足なのだろうか。それともクラスの頂点にいるのだろうか。なんだか不満を覚えた自分がいた。少しでも上位を目指し、上に立つなら寝首をかかれないよう気を張らなければならないんじゃないか。そういう思考が、出来事の本質をぼやかしていった。 回覧板に「造墓」という見慣れない単語を見つけたのは、年が明けての事だった。井上家のペットが亡くなったので墳丘を造るというお達しで、要請として我が家を含む複数の家が指名されていた。うろたえて娘の方を見ると、娘は顔色一つ変えずに「だってリカちゃんとこの猫だよ」と言う。どうやら娘は井上リカちゃんの影響下にあるらしかった。 当日、身支度を済ませて指定の場所に着くと、もう随分作業は進んでいた。山のように盛られた土が丸太で打ち固められ、それを覆うように、白い石が敷き詰められていく。山のてっぺんは平たくなっていて、縁には六年生が図工の時間に作ったという素焼きの人形が等間隔に並べられる。周囲の堀には水が張られて、ひと作業を終えた男たちが、シャベルや缶コーヒーを片手に談笑していた。悠太君のママが駆け寄ってきて、間に合ってよかったわねと耳打ちした。担任や校長の姿もある。会社に行ったはずの夫もいる。リカちゃんと言うのはよほどの強者らしかった。 やがて笛の音が流れてきて、あたりの人々は一斉にかしずいた。私もつられて跪。頭を下げる際、隣にいた娘は私に、こっそりと十円玉を手渡した。 リカちゃんは制服にポニーテールでやってきた。布でくるまれた骸の丘をゆっくりと上がり、私たちもそれに続いた。大男が五人がかりで石棺の蓋を開けた。そこに骸が納まると、今度は娘を筆頭に、ひとり一枚ずつ、銅貨を棺へと投じていった。骸の周りは十円玉で埋め尽くされ、日の光をうけて夕時の麦畑のように輝いた。 私の番がやってきた。腕を棺へと伸ばすと、少しひんやりした。指先が底に触れ、私の十円は皆の中に加わった。そうして何を手放し、何を得るのかは分からなかった。ただほんのりとした安寧だけが指先に残っていた。
●2022年BFC(ブンゲイファイトクラブ)4 一回戦の出場作品です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
