
かばんをぬいぬい
このあいだ名古屋帯にした着物の生地がまだ余っているので、なににしようかと頭を悩ませた結果、着物のときに使える取っ手短めのカバンにすることにしました。
帯とかばんが同じって、かっこいいかなと思って。
理想としては、
・ペットボトル500mlが横倒しで入る
・文庫本とミニ財布、ミニ化粧ポーチが入る
・あと少し余裕がある
・縫うのがラクな形(最重要)
というわけで、見切り発車で開始。
大丈夫、袋物を縫う程度の知識と技術はありますし、型紙がなくてもどうにでもなります。
だって四角く縫って底作って裏表合わせて、取っ手つければいいんでしょ?
こういうとき、洋裁だろうと裁縫の知識があるって便利だなと思います。
一応、脳内ではこんな感じ、というのはありました。
袖で作ればいいかな、と思って、とりあえず5尺分くらい(=150cm)の接着芯と、針と本革のかばん持ち手をユザワヤで買ってきました。
取っ手を買ってこれるという楽さ、プライスレス。
まずはものを準備しましょう
今回用意した材料はこちら
・着物のあまり生地
・接着芯 中厚地50cm巾150cm
・縫い針 厚地用の強いやつ
・手縫い糸 前回の残り、細いので2本どりで使う
・本革製 かばん取っ手黒
手元にペットボトルと普段使いやすいかばんを用意して、サイズを測ります。
そうすると、横幅はともかく、底の広さとバッグの高さ自体はそれほどないことがわかりました。
反物の幅が35cmなので、縫い代を1.5cmずつとって高さは18〜20cm、底は10cmくらいかな、と思って袖を測ったところ、長さが結構余ることがわかりました。
できるだけ布を切りたくない、というのが心情です。
だって、切り刻んでしまったらどうしようもないのだもの。
ほかの生地を確認していると、前回帯を作る際に切った見頃の残りの短い方が、ちょうど高さ18cm、底8cmくらい取れる長さであることがわかりました。
よし、これを裏地にしよう。
今回は型紙も構成も考えながらなので、とりあえず仕付け糸で軽く成形してみます。
躾は楽でいいですよね。
すぐに縫えます。
そしてそれにあわせて、もう一方の残りの身頃も縫い合わせてみたのですが……
袖より短い生地とはいえ、裏地用よりもものすごく長い。
革の持ち手をつけるし、補強用として折り返して縫ってもいいかなあ……
そんなふうに考えながら折り紙をしていると、ピピっと閃きました。
これ、外側に折り返してポケットにしたらいいじゃない!
今回は(面倒なので)内ポケットをつける予定はなかったのですが、ポケットがあるというのはとにかく便利です。
試しに縫い代分を除いて折り返してみると、ちょうどスマホが横向きで入るくらいの深さが取れることがわかりました。

そしてその両脇に持ち手をつけると、ちょっと手がきついかもしれないけれど、どうにか形になりそうです。
着物のときは、かばんは手に持つか手首に引っ掛けるだけなので、取っ手は短い方がいいので。



方向性が決まったので、ようやく縫い始めます。
作り方手順
1.接着芯を貼る
生地の裁断は不要なので、生地にそのまま接着芯をあててアイロンをかけていきます。
ドライの中温で、じっくりじっくり。
布目が曲がらないようにきをつけます。
接着芯がついたら、余りの接着芯を切り取って、もう一枚のほうも接着芯をつけます。
2.印をつける
ここで前回同様、ヘラと定規、和裁ボードの登場です。
生地を半分に折って、まずは片方の端から1.5cmのところにヘラで印をつけます。
反対側も、1.5cmのところで印をつけます。
ヘラにするのは、チャコペンなど水で色落ちする系のものを使っても、今後洗う予定がないからです。
それにヘラのほうが、なんだかしっくりくるんですよね。
これは本当に個人的な好みの問題です。
3.まち針を打つ
まずは片方だけまち針をうちます。
折り返しがわのほうから、適当に感覚を開けて。
上側と下側の生地がずれないように気をつけます。
4.縫う
今回は中厚地の芯を使い、二重以上で縫うことを想定して、太めの縫い針を買ってきました。
木綿厚地用のものです。
本当は縫い糸もそれに合わせた太さの方がいいのでしょうが、前回の糸の色が気に入っていたしもったいないので、細い手縫い糸を二本どりで縫うことにしました。
はじをくけ台で固定して、半返し縫いでやや細かめ(個人比)で縫います。
この間、めのまえにはパソコンをデデンと置いて、動画を垂れ流しながら作業をします。
手縫のいいところは、ミシン縫いより神経を集中させなくていいところですね。

5.もう片方を縫う
片方が縫い終わったら、もう片方にまち針をうちます。先にしておかなかったのはどうせ邪魔になってしまうから、ということと、片方を縫ううちにたしょうの生地のずれが生じることを想定してです。手で撫で付けるようにしながら、布の余りのでないように、こちらもはじからまち針をうちます。そして同じようにくけ台を使って半返し縫い。くけ台、大活躍ですね。
6.アイロンをかける
どんな縫い物でも、完成品の出来栄えを決めるのはアイロン掛けです。
これは絶対です。
なのでまず、両端の縫い目の上からしっかりアイロンをかけて伸ばします。
ついで、縫い代を片方に倒して折り目をつけます。
縫い代を開いてアイロンをかける方法もありますが、今回は手縫なので片方に倒すことにしました。
表生地の縫い代を反対側に折れば、仕上がり上問題はないはずです。
7.底を作る
アイロンをかけ終わったら、底になる部分に印をつけていきます。
そこから4cmを両面。
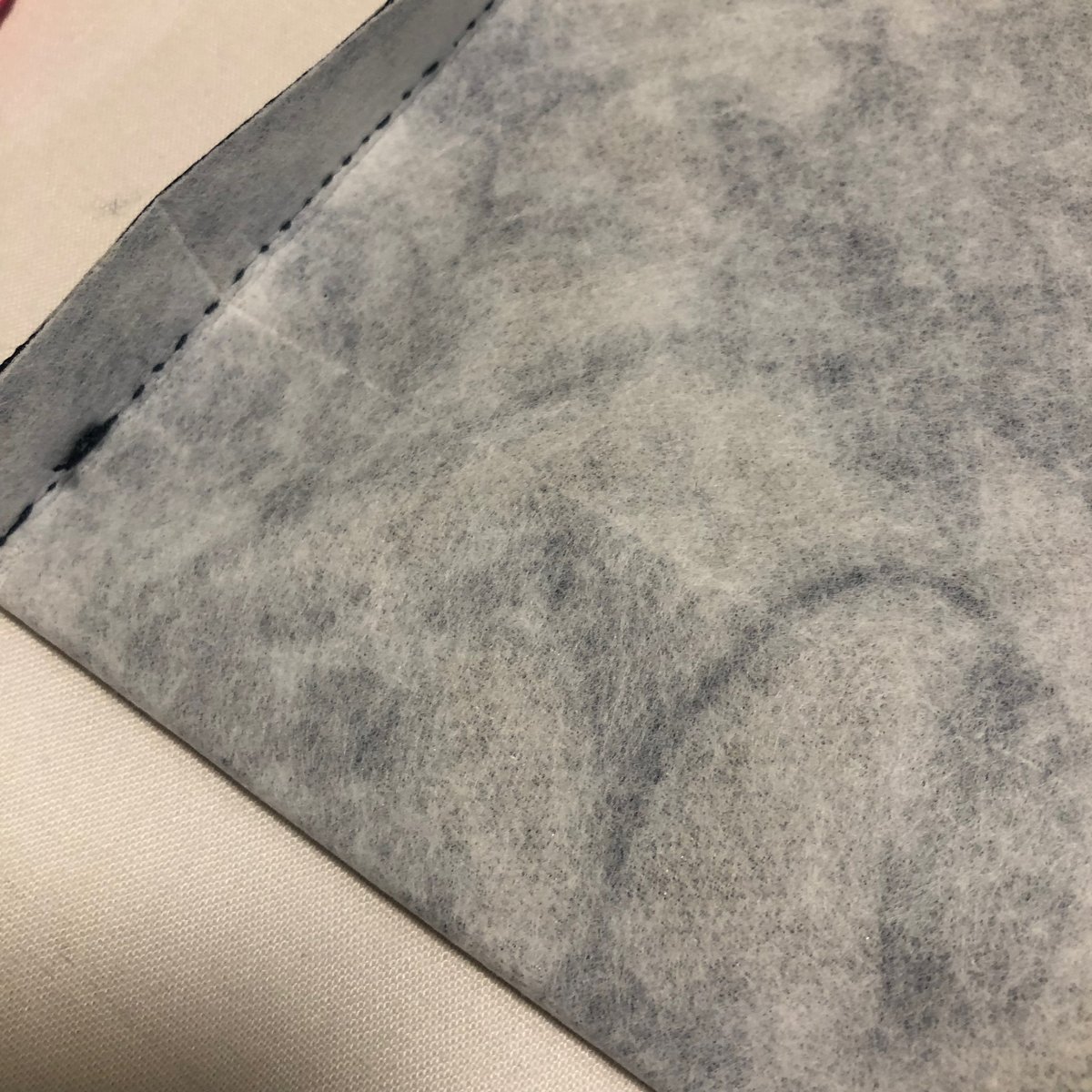
そして、ヘラの印を元に折り返し、固定するためにアイロンをかけます。そうすると、ちょうど三角形になる部分が縫う部分として残るので、印つけいらずです。この三角の部分を、それぞれまち針でとめてしっかり縫います。底なので、側面よりはしっかり目に縫い返します。
8.内側が完成!
底の三角部分にあらためてアイロンをかけます。
それから口の部分、じつは布じがそこそこ歪んでいるのですが、「底から18cm」で印をつけ、縫い代を折り返してこりらも仮にアイロンをかけます。
これで内側が完成!


みてください、きれいに縫えたでしょう?
芯地が帯と同じ厚さなので、バリっとしっかりした仕上がりです。
さあ次回、表地を縫っていきます!
縫い物楽しいよー!
もっとおやすみほしいよー!
裁縫したいよーーー!!
放っておいても好きなものを紹介しますが、サポートしていただけるともっと喜んで好きなものを推させていただきます。 ぜひわたしのことも推してください!
