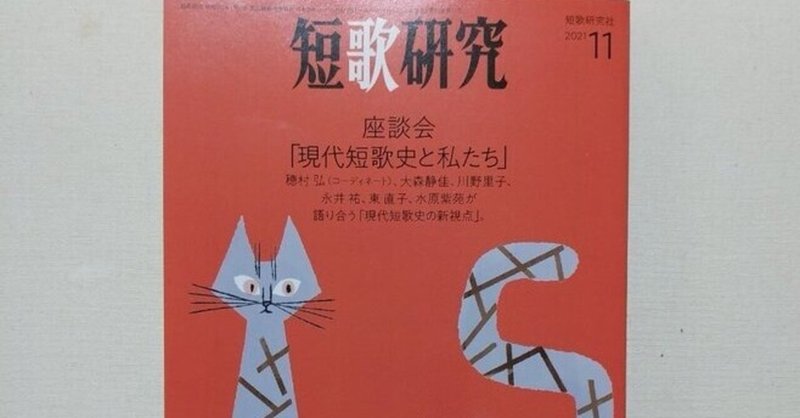
『短歌研究』2021年11月号
①みづからの重さに傷む白桃のくらぐらとして匂はする苦よ 高木佳子 初句二句、豊かに実った果物の持つ宿命のようなものを描く。傷みながら匂う果物の官能性が伝わる。物を、手触り感のある描写で描くことによって、それを見る主体の苦悩にも結びつけている。
②「座談会現代短歌史と私たち」最初に良かった点と疑問に思った点を一つずつ。良かった点は写真が無かったこと。意識的にやったのならかなり先駆的だ。元々参加者を知ってはいるが、写真が無いことで、意外なほどスムーズに内容に集中できた。視覚情報に脳は左右されるのだな。
疑問に思った点は参加者の志向がとても似通っていること。テーマにしたい五首をあらかじめ選んでいるが6人中5人が葛原妙子を選び、3人が塚本邦雄を挙げている。元のテーマに葛原や塚本が挙がっているから、そういう志向の歌人を選んだのだとしたら何も言えないが。もう少し多様性が欲しい。
短歌史を語る場なのだから、色々な方面からの意見があった方が議論が痩せないだろう。歴史って見る立場によって相当違うものだから。
③「座談会」永井祐〈私は前川佐美雄の第一歌集『植物祭』が好きで、あれは口語歌集に見えるんですよ。文語の助動詞も出てくるんですけどね。石川信雄は(…)口語短歌の先祖みたいに見える。〉口語をどう捉えているかにもよるのだが、口語短歌の始まりはもっと早いのでは。
近世和歌から近代短歌に移行する時に、短歌の用語に関する観念が変わった。それより前も狂歌を中心に口語で詠まれていたが、それが和歌と呼ばれていた分野と結びついたのだと私は理解している。
④「座談会」東直子〈人間って、その人の中にいろんな層があって(…)表面的に表れている自分が一番面白くなくて、無意識の中にうまく潜り込んでいけば、ちょっと面白いものが出てくるんじゃないかという感覚です(…)一番深いところに触れたものが一番いろんな人に響くのかな〉これは本当にそう思う。作者が全部コントロールしようとすると意外に面白くない歌になる。韻律に乗って無意識の破れ目みたいなところが見えてくるのが定型のいいところでもあり、怖いところでもある。一番深いところ、は難しいが触れたいところだ。
⑤「座談会」川野里子〈人にはいろんなものがあって、入れ替わりながら出てくるんだと思うんだけど、なぜそれが出てくるかというと、そのとき何かと向き合っているんだと思うんですよ。対話しているものによって出てくる自分は違うと思います。〉同意。何に真剣に向き合うか、だ。
⑥「座談会」東直子〈愛誦性というか、自分が好きで、折に触れて思い出すのは、永井陽子さんとか小池純代さんの、意味性のないような歌なんですよね。永井陽子さんは、前衛短歌とかニューウェーブに匹敵するような実験的なことをしてるんだけど、短歌史の歴史の上ではちょっと無視されがちなところがあって、それは何でなんだろうというのはずっと考えてる。〉『歌壇』9月号で中津昌子が指摘したことにも通じる。現在、短歌史と思われているものは、取り上げられている歌人が偏っているのが一つの原因では。皆が同じ人ばかり論じている。
永井陽子はもっと取り上げられてもいい歌人の一人だろう。少しも古びていないし、現在、短歌でよく取り上げられる虚構や私性などの論点も、永井陽子を通して見ればずいぶん違った捉え方ができるのではないか。
⑦「座談会」川野里子〈いま危ういなと思うのは、短歌の中だけで語っている感じがどんどん濃密になっていくときに、プロ好み、玄人好みの歌だけが、どんどん選ばれて表に出ていく。〉これは例が欲しいところ。表とは?むしろ、今までと違う価値軸が出来ている気がするのだが。
東直子〈でもツイッターでバズらせているのは、未知の読者ですよね。〉〈確かに歌集を扱う出版社が徐々に増えてきましたね。それが千部とか二千部とか、市場にある程度出回るようになってきた。だから純粋読者はいるということだよね。〉作者=読者ではない読者は増えているように思う。
川野の言うような歌人だけの濃密な関りも分かるし、東の言う純粋読者も分かる。その二つが完全に分かれているわけではないとも思う。そこに歌集の寄贈文化と、出版社の販売に対する意欲の問題も絡んでくる。読者はどこにいるのか、というのも結構大きな問題だと思った。
⑧影の方がなべてきはやかからまつたまま枯れてゆく蔓草だつて 魚村晋太郎 冬日を浴びて、実体より影の方がはっきりと際立っている。何もかもが枯れてゆく中で、蔓草が絡まりながら枯れてゆく。何かに依存して成長する蔓草。枯れる時も何かに絡んだまま枯れてゆくのだ。
⑨日のひかりひしめき立てり彼岸花のさしかはしたる爪のあはひを 小原奈実 日の光が、彼岸花の花の細い花びらの間に射し、ひしめき合いながら立っている。彼岸花の花びらを、差し交す爪、と捉えたのがこの歌の魅力。さらにそこに射す陽を、ひしめき立つ、と把握したことも。
⑩ほたほたと花を落としてゆくやうな四十代の後半を生く 佐藤モニカ 「ほたほたと」におっとりした感じを受けた。ゆっくりほんわりと花を落としてゆく。落とすのだから上り調子ではないが、どこか余裕を持って生きている。時間の過ぎるのがとても早く感じられる年代ではあるが。
⑪接種痕あらぬかひなを陽にさらす(恐れるな)だれもかれもこはれかけ 柳澤美晴 コロナワクチンは痕が残らないから、BCGの接種痕が無い世代と読んだ。主体は何らかの予防接種を受けていないが、皆壊れかけだから恐れることは無いと自分に言う。( )内の語りかけが強い。
⑫吾亦紅ゆるれば草に影のゆれひとりひとつらなりの骨持つ 横山未来子 吾亦紅の揺れも草の影の揺れも儚く弱い。一人が一連なりの骨を持っていることが非常に頼りないことのように感じられてしまう。その感覚は生の儚さに繋がるのだろう。「ひと」という音の繰り返しが印象的。
⑬篠弘インタビュー〈もっとも恥ずべきものはその宣誓文です。(…)いまあらためて読んでも歌人たちがこんな宣誓文を書いていたのかあるいは書かざるを得なかったことに慄然とします〉篠弘渾身の言葉に満ちた最終回。こうしたタテマエ的な文はすぐ日常に食い込んで来そうで怖い。
⑭吉川宏志「1970年代短歌史 小野茂樹の死」〈小野茂樹も結婚することになり、青山雅子に報告に行く。ところが久しぶりの再会がきっかけになり、二人はひそかに交際するようになる。〉これはよく知られた話?あんまり知りたくなかったような。小野茂樹の歌は好きなのだけれど。
〈必ずしも「カオスが捨象」されているのではなくて、どろどろとした愛欲を抱えつつも、表現としては明晰さを保っているところに、小野の歌の特質があったのではないか。(…)繊細な内面性が、歌の社会性が問われた時代には、十分に理解されなかったのである。〉小野の歌と時代の関りを解く。
〈恋人を抱きつつ葛藤する歌は、小野以前にはあまりなかったように思われる。(…)『羊雲離散』の恋人と一体になりたくてなれない悲しみは、一九七〇年代の恋の歌に確かに継承されているように感じるのだ。〉小野茂樹の歌が後代に与えた影響を、実際の歌に当たりながら考察する。
⑯今井恵子「書評 川本千栄『森へ行った日』」〈個人の郷愁をこえて、時代や社会が共有していた時間や空間の記憶を蘇生させる。〉とてもうれしい評だった。特に「塩」の看板を詠った歌に注目していただいた文には感激した。今後も一首一首大切に詠んでいきたい。深く感謝します。
2021.12.23.~26.Twitterより編集再掲
