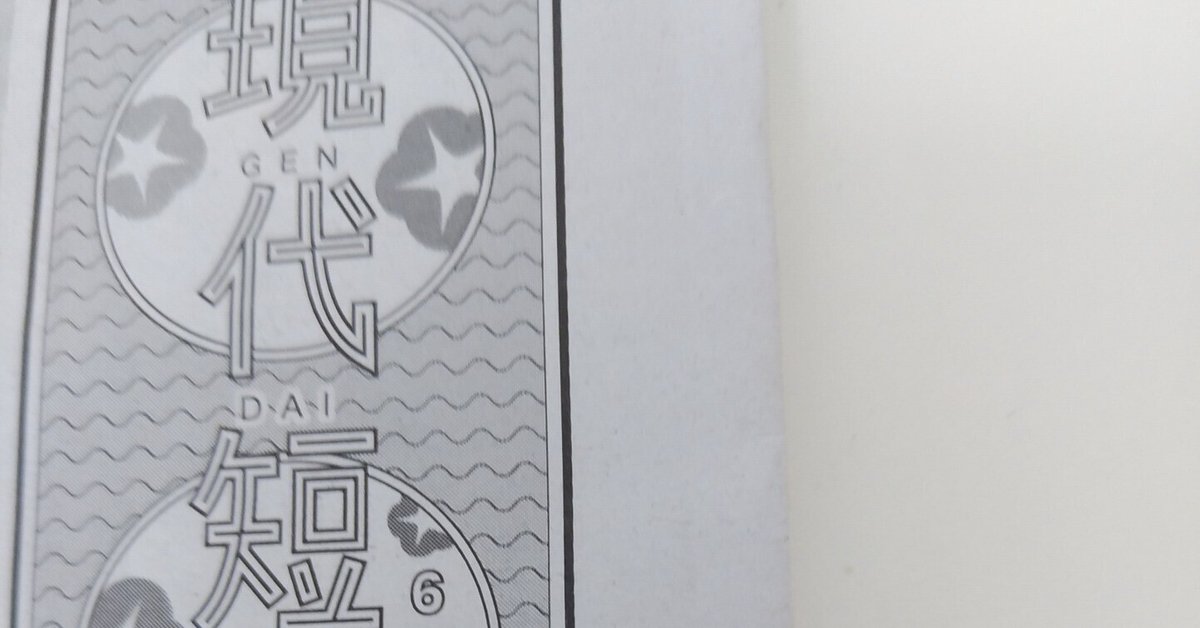
『現代短歌新聞』2022年6月号
①「大下一真氏に聞く」迢空賞ご受賞おめでとうございます!〈(斎藤)茂吉が写生の説を「実相に観入して自然・自己一元の生を写す」と言うでしょう。写すのは生命なんです。その生命が実は自他一元のものである、と。私とかあなたとかに分かれてしまった、そのそれぞれを超える大きな命というものがある。茂吉はそれを見よ、と言ってるんですけど、あれをわかるのは禅僧ぐらいだとうそぶいているんですけどね。(笑)〉今まで読んだ中で一番分かりやすい「実相観入」。禅問答に近かったのか。
②大下一真〈繊細な自然を詠むことはおのずと脱放代になるんですよね。(山崎)方代は眼がほとんど見えませんでしたから、自然を描写するというのはなかったわけです。〉それはそうだ…!でも何だか見落としていたような気がする。方代の自然描写の歌は観念的なものだったのだなあ。
③いまがいちばんかわいい時期ね、そんなこと言われつづけていまがかわいい 大松達知 子育てマジックワード。いや、そう思わなきゃやってられませんよ、っていうか、本気で思ってるんですけどね。第二のマジックワードは「(子育ては)もうすぐ楽になるよ」…ならないけど。
④島内景二「辞世のうた」散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ 細川ガラシャ〈この歌の係り結びも、特殊である。「こそ」という係助詞の結びが、「花なれ」「人なれ」と二つが並立している。〉ガラシャの辞世は三首伝わっているらしい。これはとても潔い歌。
⑤小塩卓哉「短歌文法道場」
〈古典文法では、過去の助動詞に、「き」と「けり」があります。「き」が話し手が直接体験したことの回想に用いるのに対して、「けり」は伝承された過去の事実を回想することに用います。〉
短歌は自分の体験を述べるので「き」が多用される、と。
〈現代語の助動詞「た」を文語に置き換えた感覚で用いられることも多く、その際は、「た」のもつ完了や存続の意味を表すようです。(…)「し」は、現代の文語短歌に使用されるうちに、その意味の範囲を広げてきました。〉
コレね、問題な件。私はこういうのを「創作文語」と呼んでいる。
もう少し厳密に言うと、文語の「創作用法」とでも呼ぶべきか。文語を使っているうちに死語のはずの文語を口語に倣って活用してしまうのだ。これについては、私が現在準備中の、文語口語問題を扱った評論集でも、詳しく触れています。
⑥生前といふきりぎしに立つてゐるひどく寡黙な夕闇連れて 澄田広枝 とても不思議な雰囲気の歌。きりぎしに立つ不安さ。生と死の狭間、昼と夜の狭間にいるような感覚。何も語ってくれない夕闇。主体が自分の心の中を言語化するのを押しとどめるかのようだ。
2022.7.4.Twitterより編集再掲
