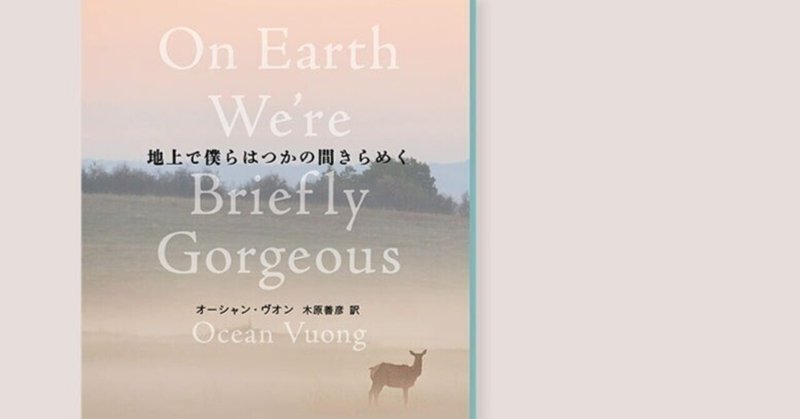
地上で僕らはつかの間きらめく(感想)_数多の痛みに耐えながら、美しい表現で自己肯定する
『地上で僕らはつかの間きらめく』は、新潮社から2021年に刊行されたオーシャン・ヴオンの小説で訳者は木原善彦。
黄色人種、性的マイノリティなどの生まれついてのこと、または薬物依存、PTSDなど場当たり的な対処によって後からじわじわ影響がくること。そういう社会の片隅で澱んでいるひずみについて、様々なメタファーを織り交ぜながら綴られることで心に沁みてくる。そんな小説だった。
以下、ネタバレを含む感想などを。

哀しみの中から、歓びをすくい取る
ベトナム戦争後、家族でアメリカのハートフォードへ移住して以降の物語となっており、構成は少年の子供時代、ハイスクール、大学入学をきっかけに移住して詩人となってからとおよそ3つの時期に分かれている。また、母に宛てた手紙という形式の小説になっているがそもそも母は英語を満足に読めない。
少年は母からの暴力、父親の不在、黄色人種、同性愛と生きるのに困難な状況だが辛い現実を受け止めて卑屈になることはなく、そんな中からでもほんの僅かな歓びを見出して、俯瞰的に淡々と綴られる文章はため息が出るほど美しく、翻訳の良さも感じられる。
この小説には筆者の自伝的なエピソードを多数含んでいると思われ、薬物依存、労働搾取、PTSDなど、アメリカの抱える社会病理についても考えさせられる。
家族の通訳となる少年
少年時代では、主に祖母、母、少年での3人の暮らしが語られ、ベトナム戦争の爪痕が残るホーチミンからハートフォードへ移住した家族には、辛い現実があった。
家族3人の生計は母のネイリストの仕事で立てられている。その母には優しい面もあるのだが、4歳の頃から少年に暴力を振るうようになる。
ショッピングモールでゴディバのチョコを買って幸せな時間を過ごした後、駐車場で大声を出しながら、げんこつで殴られるエピソードなどは、前触れ無くはじまる様子から母が情緒不安定な様子がうかがえ、ベトナム戦争によるPTSDが影響している。
さらに、少年は母のドレスを着ているところを近所の子供に見られたことで、「おかま」「変態」「ホモ」と呼ばれ、暴力を振るう母と自分の性癖を怪物であると、自分たちを異質の存在と認識しているのだが、どちらも本人たちに非はない。
ランおばあちゃんとのエピソードには心の安らぐことがあり、ジャスミンティーを注いだ茶漬けを交代で食べる情景には、素朴な食事がとても美味しそうに感じられて、なんともいえない幸福感と安らぎがあった。
辛い日常を過ごしているからこそ、こういうささやかなことでも幸せを噛みしめることが出来る。
ランおばあちゃんが湯気の立つご飯を二杯、藍色の唐草模様で縁取られたどんぶりに盛るのを見た。おばあちゃんは茶瓶を手に取って、そこにジャスミンティーを注いだ ― 淡い琥珀色の湯からご飯粒が少しだけ覗くぎりぎりのところまで。僕たちは床に腰を下ろして、いい匂いのする熱々の茶漬けを交代交代に食べた。それは、花を潰して食べたらこんな味がするだろうと想像するのと同じ味がした。
牛の尻尾を買いに肉屋を訪れるも、英語が通じないために買えず、代わりに気分に応じて色が変わるとされる安価な指輪(ムードリング)を3つ購入して、家でマッサージしながら「私は幸せ?」と訊いてくるエピソードも家族の絆による幸せを感じることが出来て良かった。
同時に少年が家族の公式通訳となる決意したのは、遊びたい盛りの子どものままでいられないことも意味するのだが。
同性愛と母の堕胎の記憶
少年がたばこ畑で働くようになってからは、親友であり恋人にもなるトレヴァーと出会う。
トレヴァーの父親はアル中でトレーラーハウスに住まう貧困家庭で、母親は不在だ。トレヴァーが白人であったので、人種の違いによるためらいはあったが、辛さを分かち合うことが出来るからこそ惹かれ合った。
少年はダンキンドーナツで母に同性愛者であることをカミングアウトして、受け入れてもらえるも。少年の産まれる以前、母が17歳のときに中絶した際の辛さを訊かされる。
読点の形が胎児に似ていることを引き合いにして、哀しみや辛さを背負ってもそれでも生きていくしかないと、自己の存在を肯定しているかのようだ。
平均的な胎盤の重さは約六百八十グラム。栄養、ホルモン、老廃物を母体と胎児の間でやりとりする使い捨ての器官。だからある意味、胎盤は一種の言語だ―ひょっとすると最初の言語、真の母語。妊娠四か月から五か月の状態にあった兄の胎盤は既に出来上がっていた。母さんと兄さんは話をしていいた ― 血液の発話を通じて。
<中略>
母さん、読点の形が胎児に似ているのは偶然じゃない ― 継続を表すあの曲線。僕たちは皆、かつては母親の中にいて、言葉を発することなく、曲線を描く全身を使って「もっと、もっと」と言っていたんだ。
大切な二人の亡くなる喪失感
「僕」がニューヨークの大学へ進学後では、トレヴァーとおばあちゃんの死について語られる。
若くして亡くなったトレヴァーの死因は15歳の時に病院から投与されたオキシコンチンを投与されたことで薬物依存症になっていたから。
アメリカでは製薬会社による「常習性が低く安全」という誇大広告によってオピオイド系医療用麻薬が普及し、製薬会社は莫大な利益を手にした。しかし実際には、依存性の高い薬の過剰摂取によって命を亡くす若者たちが多数いる。
誰もが痛い目に遭っているというのは既に了解されていて―当然の事実で―それはいわば皮膚のようなものだった。だから、「いいことあった?」と訊くのは、そこから喜びへと一歩踏み出す行為だった。避けられないもののことは脇へ置き、例外的なものに手を伸ばすのだ。
ハートフォーフォの人々は互いに「いいことあった?」と尋ね合い、その内容は、五ドルで買えるピザや、子供の誕生日に映画を借りられるだけのお金を持っていたりとささやか。そうして、トレヴァーが僕に「おまえはいい。」と言ってくれたことが耳に残っているのが切ない。
おばあちゃんとの思い出では、フェンスをよじのぼって紫色の花を摘みにいくエピソードが素敵だった。フェンスを歯で破って助けてやるという突拍子も無い言葉と、美しいものには命をかける価値がある、という学び。
オオカバマダラ、バッファロー、アカゲザルと動物たちの哀しい話しを引用して、自らの痛みや喪失感を深掘りする物語には読後になんとも言えない余韻が残って、それは遠い国の他人のことだと割り切れない共感があるから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
