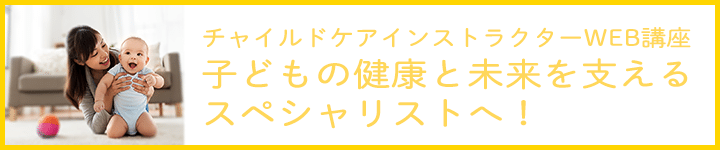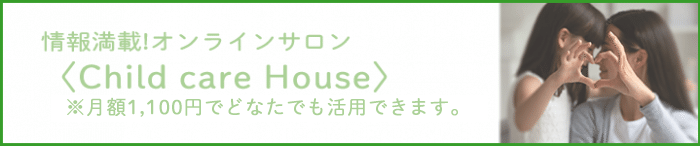素敵なあの人から「みる・きく」を学ぶ /自分と他者の幸せのためのコミュニケーション マインドセラピスト小泉美智子さん
※本投稿はオンラインサロン<ChildcareHOUSE>内の掲載記事を、一般公開用に縮小したダイジェスト版です。
プロフィール
小泉美智子(こいずみみちこ)

大学卒業後、ユニ・チャーム株式会社で社長秘書に従事、結婚のため退職。その4か月後、社長より任命をうけ、子会社設立に携わる。事業は順調に推移するが、出産、子どもが小学校入学前に離婚。退職。子どもが小学校入学したころに学校に行きたがらない日々が続き、悩んでいた時に、コミュニケーションスキルをトレーニングするゴードン・メソッドに出会い、その効果を実感する。さらに、子育てで難しくなる思春期の時期に、再び学ぶ機会を得たことで、主体性をもった自立できる関係は、幸せな人間関係を築くうえで最も重要なことと気づき、コミュニケーションの指導とともに、人と人をつなぎながら、家庭、地域の発展につなぐパイプ役として活動。また自身の介護経験の中で介護にも信頼できる人間関係が充実した人生につながると感じ、ケアマネージャーとしても活動し、日々多世代のサポートに全力で注いでいる。
未来へつなぐコミュニケーションカレッジ「コミュラボ」代表
品川・八潮♡多世代交流プロジェクト共同代表
けめとも子ども食堂主催
マインドセラピスト
親業インストラクター
介護支援専門員(ケアマネージャー)
https://www.commurabo.jp/
コミュニケーションとは、社会生活を営む人間の間で行われる知覚・感情・思考の伝達のことを言います。簡単に言えば、考えや感情を表現し、理解し合うことです。他者と関わっていくために大切な手段のひとつです。誰もがその必要性を感じているので、世の中にはコミュニケーションスキルを上げるためのノウハウがたくさん出ています。コロナ禍でコミュニケーション能力が高まるどころか、「ソーシャルディスタンス」という言葉が日常化し、人との距離は離れる一方です。学校や塾、職場だけではなく、対面せずにリモートという手段が当たり前になりつつあります。人と触れ合うことに神経質になり、一方的な伝達が増えているなか、「コミュニケーション」についてもう一度考える必要があるでしょう。
コロナ禍で生活様式が変わり、人との関係性が不安定になっています。だからこそ、もう一度本来の人との関り方を見直し、コミュニケーション力をしっかり身に着けて、信頼関係を高めていく必要があります。人と距離は離れても、心の距離は離れずにしっかりとそばにあることですね。今回は、コミュニケーションスキルを高めるためのノウハウを指導するだけではなく、そのコミュニケーションスキルを実際に地域や社会に貢献し、人と人、人と地域、人と社会のつながりを円滑にしながら、それぞれが豊かに幸せになることをサポートされている小泉美智子さんにお話をお聞きしました。小泉さんは、子育てマインドセラピストとして、子育てに悩む親御さんの相談をはじめ、ケアマネージャーとして介護職に携わりながら、地域の子ども食堂やフードパントリーなど開催するなど、多世代と様々な地域で積極的に活動されています。ノウハウを熟知しながら、さまざまな現場を知り尽くしている小泉さんから、よりよい関係づくりと幸せ作りのヒントを教えていただきました。
インタビュアー :チャイルドケア教育協会本部講師 松本美佳
――― 小泉さんは、たくさんの肩書をお持ちで本当に幅広くご活動されていますが、現在の活動を教えてください。

小泉さん(以下敬称略):そうですね。未来につなぐコミュケーションカレッジ「コミュラボ」の代表をしています。そこでコミュニケーションに関する講座を提供しています。そして私自身の実践の場として、ケアマネージャーとして活動しています。この2本の柱で主に活動しています。
私にとって「コミュニケーション」が活動のキーワードになっています。人と人の関係づくりであり、自分らしい人間関係の作り方ですね。一般的に教育として人間関係の築き方を学んできたことなどはないと思います。普通は、親がしていたこととか周りにいる人たちをみながら、何となく見よう見真似をしながら工夫して、コミュニケーションの取り方を身に着けてきた人がほとんどだと思います。でもそれだとあいまいですよね。実はコミュニケーションの取り方にはコツがあって、ポイントがあります。基本と言ってもいいと思いますが、これを互いに理解していないがために、躓くことがあるわけです。
例えば、どんな時に自分に焦点を当てて考えるのか、あるいは、どんな時に相手に焦点をあてて考えるのか、そしてそのときにどんな対応をして、どんな言葉を選べば効果的なのかなど、関係性を整理することからコミュニケーションは築かれます。具体的な方法もあるので、トレーニングすればコミュニケーションスキルは誰でも高められます。この方法を講座などで指導しています。そしてその実践現場としてケアマネージャーとして介護の現場でも活動しています。
コミュニケーションスキルで関係性が良好に

――― 「コミュニケーション」は、生きていくうえでとても重要だと私も思います。最近は、「人見知り」「コミュ障」とコミュニケーションが苦手なことを逆手にとって、あえて人づきあいをしない、コミュニティに属さない、あるいは、愚痴や不満をもらすだけで関係性を良くすることに消極的なっている人も増えているように思います。個人主義と言葉はよいのですが、支え合うことや助け合うことが下手になっていると思うことがあります。
小泉:実は私、人との関係性を作るのが苦手だったんです。本当に苦手で、人見知りではないんですが、子どもの頃はすべて自分の思い通りになると思っていました。相手がどうこうとかあまり考えてなかったんです。
―――では何がきっかけで「コミュニケーション」に興味を持たれたのですか?
小泉:私は娘が小学校入学前に離婚してシングルマザーになりました。それから少し経ち、子どもが小学校に上がった頃、学校に行きたくないと言い出しました。それで思い悩んでいたときに、コミュニケーションスキルを学ぶゴードン・メソッドというプログラムに出会いました。ゴードン・メソッドというのは、アメリカのトマス・ゴードン博士が創案したコミュニケーションの取り方をトレーニングするプログラムです。学んだことで、娘との関係性も変わりました。
ある日娘がお友達との関係で悩んでいるときに、学んだことを取り入れて会話をしていたら、「ママは私の気持ちをわかってくれてうれしい」と言ってくれたんです。悩んでいる内容そのものではなく、悩んでいる娘の気持ちを汲んだことによって、娘の悩んでいる気持ちが晴れたんですね。そのときにコミュニケーションの在り方に気づき、そして手ごたえを感じました。とてもうれしかったですね。
でも、時間が経つとまたせっかく学んだことも忘れて、いつも通りの私になっていました。つい娘に「あーしなさい、こうしなさい」「こうしないとあーなっちゃうよ」などと、指示命令したり、脅かしたり、叱ったり、抗議したり、非難たり、馬鹿にしたりとしてしまっていたんです。
―――心配するがあまりについ干渉しすてしまう傾向はありますよね。愛があるが故のやりすぎで悩まれている親御さんも多いですよね。愛ある親の「あるある」ですね。

小泉:でも、それをやっていたら、思春期のときに痛い目にあいました。まず言うことを聞きませんでしたね。1ミリ足りとも私の言う通りにはならない。そのときに何とかしなくてはと思いましたが何をやってもダメでした。娘も自分でいろいろ考える年になっていたので、今までの対応では難しいと考え、それで再びコミュニケーションを学び直したところ、親子関係もうまくいくようになりました。やはりノウハウは大切だと実感しました。今も、娘の成長とともに距離感を考えながら良い関係を築いているところです。
自信って何?
―――現代は、コミュニケーション能力が低下しているといわれていますね。その一因に、「自信がない」と悩まれる人がとても多いことと関係している気がします。つまりこの自信は、自分自身とのコミュニケーションがうまくいっていないということにつながっているからだと思っていますが、どうお考えになりますか?
小泉:ひとつは経験をしていないということでしょうね。そして、自分のやりたいことやこうなりたいという軸が定まっていないのでしょう。それと自己責任をもって取り組んでいないということもあるかもしれません。行動するのは自分です。何か行動して嫌な思いをもったとしても、自分が考えて行動したことであれば、そこに責任をもって取り組むことですね。嫌だったら避けるなり、やめるなりという選択も自分ですればいいのです。自分で決めたことであれば、自分が気持ちよく行動できるように努力してみるということです。
ケアマネージャーとしての活動
―――小泉さんは、マインドセラピストとしてだけではなく、ケアマネージャーとして介護職にも携わっていらっしゃいますね。

小泉:そうですね。父を看取ったときにもう少し自分でできることがあったのではないかという思いがあったのと、自分がやってきたコミュニケーションスキルの研究と実践の場としてケアマネージャーとして活動しています。
私の人生のアップダウンの軌跡ですね。私自身は、いろいろどん底の体験をしています。つらい時というのは、とても孤独なんです。誰もわかってくれないとか、みんな同じ思いをしているんだからと思ったり・・・・。人に相談すれば行政に相談したら?と言われ、実際に行きましたけど全然役に立たない(笑) ただ、私の性格上転んでもただでは起き上がらない(笑) 今、私と同じような思いをしている人はいる、あるいはこれから先同じような思いをする人がきっといるから、私はこれを乗り越えて、その人たちの力になろうというのが原動力なんです。だからいろいろなことをやってきました。
―――地域の福祉活動も活発にされていますよね。子ども食堂やフードパントリーなどもされていますね。
小泉:私がしているというよりは、地域の方や団体、行政の方などのパイプ役となり、やりたいこと、やって欲しいことなどの声を聞き、そのパイプ役となって、おつなぎして、皆さんと一緒に活動しているだけです。それぞれできることが違いますし、得意なことも違いますから、役割分担をして活動しています。それもお互い活かしあえていてとても楽しいんです。
―――コミュニケーションスキルは、まさに人だけではなく、地域や企業との関係をつなぐパイプラインとして役立つということですね。コミュニケーションスキルが高まれば、世界も広がり、関係性も広がり、良い循環が生まれてきますね。
小泉:コミュニケーションスキルは、幸せな人生をおくるためにとても必要なことです。特に子どもを育てている親御さんたちに理解してもらいたいです。子どもは自然に親のその姿をみて学ぶからです。親の影響はとても大きいですから。そうやって子どもたちが自然にコミュニケーションスキルを高めていくことで、その子どもの周りにも影響し、より良い人間関係と幸せな生活と人生がおくれると思います。そう願っています。
―――素敵なお話、尽きることがありませんが、今日はコミュニケーションの大切さを改めることができました。ありがとうございました。
~Child care~
▼チャイルドケア公式HP
https://www.childcare-jp.com/
▼チャイルドケア・インストラクターという職業の選択肢
▼チャイルドケア共育協会運営オンラインサロン
▼チャイルドケアの魅力を丸ごと一冊に詰め込みました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?