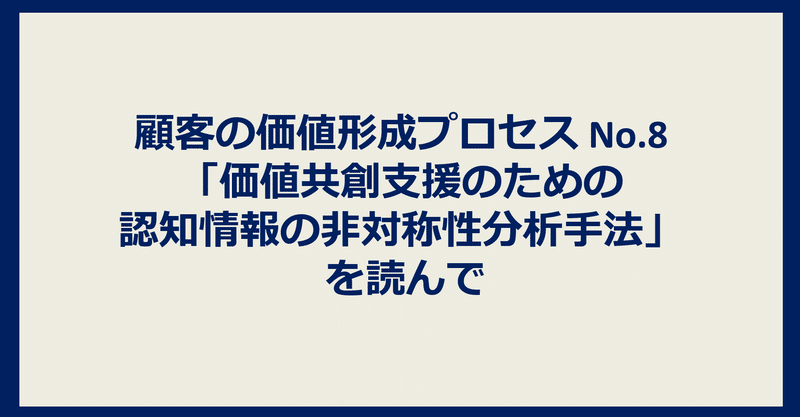
顧客の価値形成プロセス No.8 「価値共創支援のための認知情報の非対称性分析手法」 を読んで
今回取り上げる論文は、価値の発信者と受信者との間に存在する齟齬をどう理解するか?ということが主題だ。2ページと大変短く、事例も大学食堂と一見ビジネスとは関係なさそうだが、学べることは、ビジネスにも応用できるのでは?と思う。
論文の要約
内容としてはシンプルで、「大学側が考えていた食堂の役割と、学生側が考えていたそれに、実は齟齬があった」という話だ。このような「メッセージの受け手の解釈が、送り手とどのように異なるのか?」を理解するための手法が、論文内で提示されている。
論文の感想
結論だけ読んでしまえば、「まあそういうこともあるか」という話だ。だがここで、「どうやって齟齬を特定するか」ではなく、「なぜ齟齬が起きるのか?」ということについて考えてみたい。
例えば今回の論文では、認知を「人間の情報処理の過程や結果」ととらえており、「自身の経験の積み重ねにより形成され、独自に操作可能であるため、同じ対象に対する理解内容に齟齬が生じるという特徴を有する」としている。つまり、認知の齟齬は
●積み重ねる経験
●経験の処理
のいずれかもしくは両方が異なることよって生まれている。認知をアウトプットとしたときに、インプットとプロセスが違いを生む、と考えれば、極めて一般的なことだ。
上記を踏まえると、例えば「認知度の向上」を目的としたマーケティング施策を考えるにあたって、「誰からの・どのような」認知獲得を目指すか?という目標を設定した後は、
●どのような経験を提供するか?
●その経験をどのように処理してもらうか?
ということに留意しながら、実際の施策に落とし込んでいく必要がある。上記を理解しようと思うと、今回の対象顧客は「過去にどのような経験をして、どのような処理を行ってきたか?」ということも踏まえて考えるべきだろう。積み重ねられた経験と処理の繰り返しこそが、現在の人の認知に影響を与えるのである。
今回の論文のテーマに戻ろう。学生にとって、食堂の飲食スペースは「食事以外の目的では利用不可」という認知であった(それに対して、生協食堂部は「食事以外の目的でも利用可能」)。これに対し論文内での考察では、「自然に目につきやすい広報手段で食事以外での目的の利用を促す」ことを提示している。
だが、これまでの考察を踏まえると、上記では不十分であろう。おそらくだが、高校生までは、食事スペースは「食事以外での利用は不可」だったという経験(とそれに伴う情報の処理)が、食堂の飲食スペースの認知に影響を与えていると考えられる。であれば、例えば、「大学の(高校と比べたときの)自由度」を訴えることを念頭においた認知施策を考えることで、学生側と生協側との認知のズレを解消させることができるのではないだろうか。
上記の例でも分かるように、ただ「認知されていないから改善しよう」だけでなく、「どんな経験を提供して、どのように処理してもらって認知してもらおう」「そもそも対象顧客はどのような経験と情報処理のループを経てきたのだろう」ということに目を向けることで、より効率的・効果的に認知を獲得することができるのではないだろうか。
最後までお読みくださりありがとうございました。Twitterもやっていますので、よろしければフォローお願いします!
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
