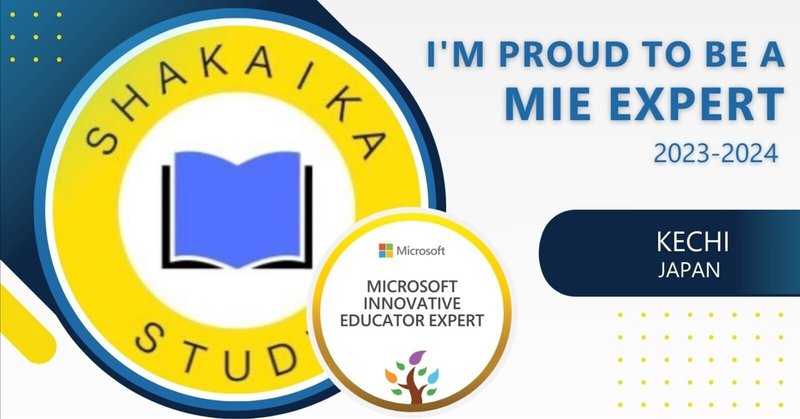
「やりたい」の先にAIがある!
一昨日に引き続き、昨日はこちらのイベントに参加しました。
Microsoft認定教育イノベーター(MIEE)の有志の方々によって企画されたイベントで、今年度は、「AI×教育」というテーマで行われました。ちょうど1年前のChatGPTの登場から、1年間の間に瞬く間に進化を遂げているAIですが、そのスピードの速さに頭の中がなかなか追いついていない状況です。でも、わからないことをわかるようにするにはその中に飛び込んでいくことも必要だと思います。今回も、どのような学びがあるのがワクワクしながら会場に向かいました。
Microsoftの田中達彦氏によるオープニングセッションでは、Microsoft製品とAIのコラボレーションを実演していただきました。この機能が実装されれば、これまで使っていた時間が削減されて、別のことに使える時間が増えるわけです。MicrosoftのAIは、「copilot」つまり副操縦士で、操縦士は自分自身です。AIはあくまでAIなので、自分で動くわけではありません。(現時点では。)自分が「pilot」操縦士として、どのように操縦していくのかを決めていくわけです。そういう意味でも、AIを使っていくスタートは、人間の「こうしたい」という思いになるのだと思います。
引き続き行われたセッションでは、AIを使ったアプリを多数作り出している、AIdea Labの冨平準喜氏によるご講演でした。一般企業の方の話を聞く機会は、教員をしているとそうそう多くはありません。貴重な機会となります
冨平氏の話から、自分が目にしているものは、ほんの一部でしかないということを目の当たりにしました。世の中にはAIを使う、使おうとしているところはたくさんあり、教育はその中のほんの一部であるということです。教育をするのに、教育だけではダメだというところを再認識しました。
続いて、AIを使った授業実践をされている3名の先生方からの発表でした。青山学院中等部の安藤先生は、最近授業をされていないということで、お忙しいのかと思ったら、AIが授業をしているのでしていないということでした。AIが先生の授業を分析して、それをもとに子どもたちに個別最適な形で授業を提供していく姿は、今まで一人の先生で30人の子どもたちに接していたところを、30人の先生で30名の子どもたちに接することができるので、単純に接する時間が30倍になるわけです。もちろん、まだAIが全てをできるわけではないですが、そういう日も近いのだと思います。
東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木先生、小池先生のお二人は、日常的にAIを使った授業に取り組まれていました。鈴木先生の社会科の実践では、導入で使ったり、問いをまとめるのに使ったりと、他教科でも応用可能な形ででの活用でした。小池先生は、低学年での図工や学活で活用もあり、同じ低学年担任として、すぐ活用していきたいと思うようなご実践でした。
それぞれのご実践に冨平氏がコメントしつつトークセッションが行われたのですが、その中で話題になったのが、好きになったことをとことん突き詰めていく「オタク力」ということでした。これは、千葉大学の藤川大祐教授のご研究で、好きなことを突き詰めていくことで、その後学力の向上につながっていくというもので、こちらを引用しながらのトークでした。オタクには色々なイメージがあるのかと思いますが、好きなことを極めていくということは、その後のいろいろな発展につながる重要な要素で、「何が好きなの?」という気持ちと、それを「やりたい」という意欲が何よりも重要だと感じました。
その後、ランチセッションではMIEEの方々による実践発表、午後のワークショップではCanva認定教育アンバサダーの吉川先生と関口先生によるAIを使ったクリスマスの絵本づくり、そしてエデュテイメントプロデューサーとして昨日に引き続き、正頭先生によるCanvaを使った妖怪づくりのワークショップのご講演と続きました。どれも「子どもたちとやりたい!」の連続でした。
AIを使うのは人間。その人間に、「やりたい」という気持ちがないと、AIを動かしていくことはできません。あくまで人間のやりたいことを助けてくれる、そんなAIの未来を感じた日でした。
お読みいただき、ありがとうございました、ご参考になれば嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
