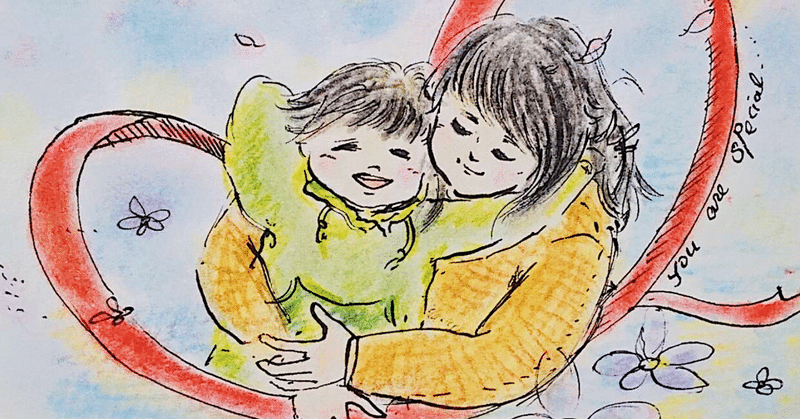
安全基地と愛着〜そして居場所の確保へ〜
『子どもが自由に〝不確実性〟を探索するための手助けを後ろからしてあげるということなんです。』
茂木健一郎
●我が家の日常
「明日は学校を休もうかな。」
「少し頭と心が疲れているから。」
素直な気持ちを母親に打ち明けてくれる3年生の息子。
このサインに答えてあげたい。
我が家では、週の半ばの「週1ホームスクーリング」を設けています。
学校のある平日。
息子を連れてレストランへ。
895円のオムライス。
240円の学校給食の約4倍の値段。
今日の給食は高くついたなぁ。
家に帰宅してきゅうりの飾り切りをして、親子でいっぱいお喋りして、
ダンボールでガチャポン作って動画配信して。
幸せそうだなぁ。
「ママはいつまでも君のエジソンママができるわけじゃないんだよ。」
心の中でそう呟きながらも、
「今与えられている息子とのこんな時間も大切だな。愛おしいな。」
と思える今日この頃です。



●「学校に行かないという選択肢」は「不登校」?
不登校予備軍。
そもそも「学校に行かない」という選択をした子どもの呼び名は本当に「不登校児」でよいのだろうか。ネガティブかポジティブか。
言葉の概念。
子ども達の発達と環境について語れば語るほど状況は見えにくくなる。
フリースクール。
ホームスクーリング。
多様な学び方が認められても世間の目はまだまだ冷たい。
その現実を街ゆく人達の視線から感じたのは私だけなのだろうか。

●緊急事態宣言解除後の子ども達の姿
緊急事態宣言が解除され、子ども達の学校生活も日常を取り戻しつつある。
我が子の通う公立小学校は通常授業が始まり早2週間。児童発達支援センターの子ども達を見ていても、
学校内外パトロール中の子ども達を見ていても、ストレス反応システムはMAXに達してきている。
※**ストレス反応システムと小児期逆境体験について書いた記事↓ **
https://note.com/chiemaru7/n/ne3fa8633b807

明らかに三密を避けられていない集団登校班。
「おばちゃん、昨日ぼく21時まで塾やってん。
寝たの23時すぎてた。遅刻しそうになった。」
と話してくれた4年生の男の子。
「しんどいなぁ。休みたいなぁ。」
と呟く6年生の女の子。
泣きわめく1年生の男の子の手を引き、
「早く行きなさい!」と怒鳴りつけるお母さん。
ちょっと頑張り過ぎている。
大人も子どもも。
子ども達のエネルギーを大人の都合で
無駄遣いさせちゃいけない。
保護者と先生のメンタルももっと守られなければいけない。
アフターコロナ。
まだ何も変わっちゃいない。
変わる兆しさえ見えない。
では変えていくきっかけは何なのだろう。
またそのきっかけをつくるヒントは
一体どこにあるのだろうか。

●子ども達のストレス反応システムを緩和するヒント
現段階で私のヒントになっているのは脳科学者の茂木健一郎さんのクオリア日記とオーディオブックです。
「イギリスのギャップイヤー習慣」↓
http://kenmogi.cocolog-nifty.com/qualia/2010/04/post-8f35.html

これまでコロナの影響で活動停止していたアートハウスを再開することにしました。
やはり動き出さなければならない。
※居場所づくり事業「アートハウス」の
詳細はこちら↓
https://www.arthouse-nishinomiya.com/
これから求められてくるのは学校以外の居場所の充実。子ども達がふんだんに内面対話できる環境とその環境を整えていく大人。
発達心理学と脳科学的視点からその確信が持てました。


●愛着と不確実性と安全基地
前述した確信のきっかけ。それは、
ボルビーのアタッチメント(愛着)セオリーです。
イギリスで戦争孤児を収容する施設でボランティアをしていたボルビーが、ティーンエイジャーの問題行動と愛着の関係を科学的に調査したものです。
深刻な問題行動を引き起こす子ども達に共通する点は、
〝安心して自分探しができる環境〟が与えられてこなかったということなのです。
安心して自分探しができる環境。
安全基地。
冒頭で少し紹介した茂木健一郎さんの言葉は
安全基地の必要性をより明確にしてくれます。
**
『子どもは全てが不確実な中で生きています。
不確実性。これにどうしても立ち向かっていかなければならないのです。でも1人では出来ません。
保護者が安全基地という安心感をつくってやる。
それは過保護に囲むことではなく、やること指示するということではありません。
〝子どもが自由に不確実性を探索するための手助け〟を後ろからしてあげるということなんです。
〝安全基地がある〟という安心感がないと子どもは安心して不確実性を探索することができません。
この基地を与えてくれる保護者に対して子どもは愛着を持ちます。
これは人間の心理において、世界を自由に探索するために極めて重要な意味を持ちます。
必要な安全基地を提供してくれる者に愛着を持つということなんですね。』**
子ども達が自然発生的に作り出す秘密基地は
「安心できる場所がほしいよ。」という顕著な心のサインであり、同時に自分探しの過程(アイデンティティ感覚「私は私であるという感覚」を獲得していく作業)であることが分かります。


保護者が確保する安全基地に加え、自由に創造性を育むことができる居場所やツール。
今日の記事がこれらについて考えていくきっかけとなれば幸いです。
大人の図工塾管理人
居場所づくり事業「アートハウス」幹事
米光智恵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
