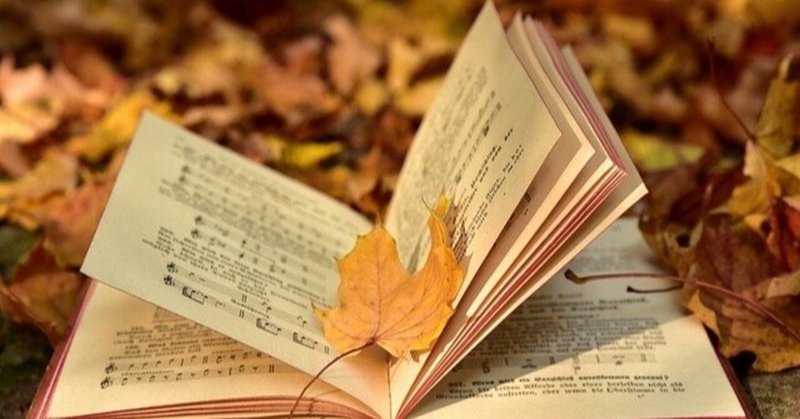
この世は人が紡ぎだした物語でできている
最近、必要があってロバート・J・シラー著『ナラティブ経済学』を読んだ。
実のところは、読んだ、と言い切れるかはわからない。本の内容がしっかりと理解できたわけではないから。だいたい大まかに目を通した、という方がしっくりくるかな。
それでも、この本に書かれていることの端ばしに気づきがあったし、これまでわたしが、何となくそうだろうと感じてきたことへの答えだと感じるものがあった。
『ナラティブ経済学』というタイトルすべてを日本語にすると、『物語経済学』となるだろうか。でもそうするとナラティブの意味合いが伝わりにくい。
日本語の「物語」は、英語では「ストーリー」とも訳される。ストーリーには主人公と登場人物がいて、出来事のはじまりから終わりまでの起承転結、筋書きがある。
ナラティブは、起承転結がはっきりとしたストーリーとはちがい、語り手の感情や考えによってかわっていく会話のようなものもふくむ。はっきりとした終わりがあるわけでもなく曖昧さがあり、ストーリーよりももっと広い意味での物語をさす。
このナラティブと経済学を結びつけた考え方、この本のタイトルをみるだけでも、ハッと目を開かされるのではないだろうか。わたしはそうだった。
確かに、経済とは人の営みと直につながって動いているのだから、合理的な理論だけでは語れないはずだ。実際に商売をしている人は、経験からすでにわかっている事実だろうと思う。
人は理屈ではなく感情で買い物をすることもおおい。わたしもお店で買い物をするときに、店員さんが気持ちよく相談にのってくれるとすんなりと買い物をするけれど、感じがよくなかったらそのお店では買いたくならないときもある。
人間は機械ではなく、もっと繊細で複雑で、感情をもった生き物だから。
けれども、学問として市場の動きを判断するのには、これまであまり心理的な要因をふくめては考えられてこなかった。シラー氏の考えは画期的だ。
とても刺激をうけておもしろかった、けれども、その本の内容をここで語るほどわたしは消化できていないので、ここまでにして。
*************
わたしはこの本を読んで、「人が紡ぎだしたナラティブが、この社会をそしてこの世界をつくっている」というしくみをより深く意識しはじめた。
これまで、自分のなかの思いこみ(ナラティブ)が自分自身の体験や見えている現実をつくっている、という個人のしくみは自分なりに腑に落ちていた。
いまのわたしにとっては、自分のまわりで起こる出来事をとおして自分の内側にある思いこみを知り、その書き換えをする、というのは習慣になっている。
この世もそうだろう、とは漠然と感じて、頭の隅っこでもわかってはいたけれど。
これまで漠然としていた頭の隅っこに明るい電灯がともったように、わたしはあらためて今回ハッキリとわかったのだ。
「この世は、これまで生きた人々が紡ぎだしたナラティブで構成されている」
「複雑にからみあった過去からつづくナラティブのなかに個人は生まれる。そこに根をはやしながら、今を生きる自分という生き方:つまり自分のナラティブをくわえて物語を変化させる。そして、また次の世代へとつないでいく。」
ということを。
**********
めんめんとつづく地域、家系、両親のクセ、というパターンに無意識に支配され、自分の中の生命力からのメッセージに耳をふさいで生きるのは、過去のナラティブのなかで眠ったように生きる、ということになるだろうね。
本来、生命力とは、前進し、拡大し、調和へとむかう質のものだから、過去のナラティブのなかで眠るように生きることを求めてはいない。
過去のナラティブに、今を生きる生命力による変化をくわえて、物語を変化させながら世代をこえて引き継いでいく、というしくみが本来の姿なんじゃないかな。
過去のナラティブは集合無意識にうずめられている。それは神話や伝説のなかに秘められている。もっと表面にあるものは常識や、社会であたりまえ、とされているものだろうか。
神話や伝説が本来の人間の営みから生まれでたナラティブだとしたら、公然と残された「歴史」は、誰かが意識して何らかの目的のために編集した「ストーリー」なんだろう。
とまあ、ここから色々と関心が湧きでてきています。ひとつひとつ調べて、これから考えてみたいテーマです。
**********
前回の記事で、イメージワークに出てきた人魚について書いた。この人魚のイメージが、ここでも頭に浮かんできた。
集合意識のなかにあるナラティブ=海 と考えると、
下半身を海にひたし、上半身を空にもちあげる人魚は、
「複雑にからみあった過去からつづくナラティブのなかに個人は生まれ、そこに根をはやしながら、今を生きる自分という生き方:つまり自分のナラティブをくわえて物語を変化させて、また次の世代へとつないでいく。」
人間の本来の姿、ともいえるんじゃないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
