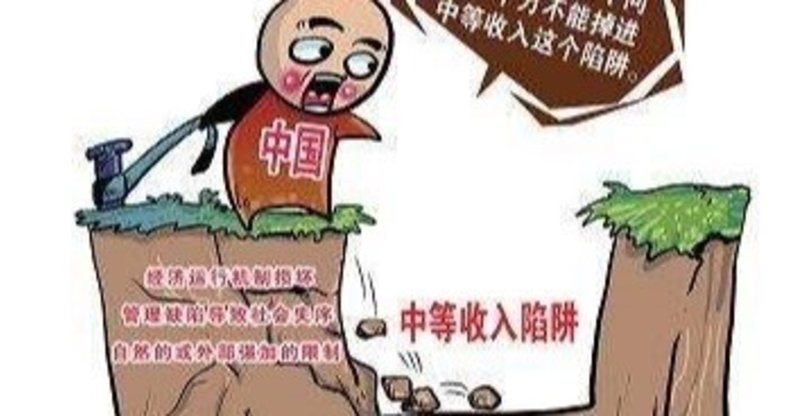
「中所得国の罠」という言説に惑わされるな
習近平主席は元旦の祝辞で「中国の国内総生産(GDP)は100兆元に近づき、国民1人あたり総所得(GNI)の平均は1万米ドルの大台に進みつつある」と語った。それを受け、GNI平均1万米ドル突破がメディアの話題をさそい、そこには歓呼と憂慮があった。中国経済は「中所得国の罠」を突破して、高所得国レベルに到達できるのか否かの正念場をむかえている。
「中所得国の罠」の概念は、世界銀行が2007年に「東アジアのルネサンス――経済成長の理念」で報告したものだ。世銀が定めた基準は、GNI平均975米ドル以下を低所得国、976〜3855米ドルを中所得国、3856〜11905米ドルを中高所得国、そして11905米ドル以上を高所得国とする。中所得国に仲間入りして一定の経済発展をしても、高所得国の隊列に加わることができないうちに「中所得国の罠」に陥る可能性があるという考え方だ。
この概念は国際的に広く流布し、学術界でも熱い議論の的(まと)となっている。しかし率直に言って、それ自体には決して大きな学術的価値や現実的な意義はない。
その理由は、まず、第二次世界大戦以来、たしかに高所得国の仲間入りを果たした国はごく少数で、ほとんどは中高所得国になると経済は停滞して前に進まなかった。しかしその原因を仔細に研究しても、経済が停滞した国の間に、成長を阻んだいかなる「共通項」も見出すことはできなかったことだ。
第2に、経済発展がどこまで進んだら停滞するのか、という法則性はまず存在しない。全世界の200に近い国や地域を見わたしても、大多数の国が経済の高度成長を経験しているが、その成長期間はそれぞれに異なり、10年、20年、あるいは中国や日本のように30年間の長きにわたり、もっと長いのは40年間という例もある。欧米諸国のような高所得国になった国のどのような要素が経済を停滞させるのか、といういかなる根拠もないのである。
さらに、経済発展の歴史が示しているように、経済がずっと高度成長を維持できないのは常識だ。経済の規模や産業構造、抱える社会矛盾の変化により、成長速度が高速から減速安定に移るのは正常で、成長が鈍化することを「罠」と断定することはできない。
最後に、経済成長のあとで停滞に陥った各国の原因を調べてゆくと、それらの多くが収入の伸び悩みに原因があったのではなく、分配やイノベーション、および包括的な改革過程における時間枠の取り方がうまくゆかず、中高所得国から高所得国への転換に失敗したことが原因だった。こうした経済の停滞現象は「収入の罠」とされるが、それは正確ではない。
中国経済について言えば、「中所得国の罠」という概念はまったく心配するに及ばない。必要なのはラテン・アメリカ諸国などの収入分配を手本にし、包括的な改革や制度構築の不備からもたらされる巨大な機会喪失の教訓を汲み取ることだ。
「中所得国の罠」言説は正しくない。経済成長が新たな段階に入ったあと、分配格差の現実や産業イノベーションの必要、成長エンジンの更新、改革のさらなる深化や制度構築などの問題に対して、いかに正しい対応をするかが肝要だろう。
いわゆる「中所得国の罠」言説の本質は国家改革と制度構築が経済発展に追いついてゆけるかどうかで、それが経済発展の追い風になるのか、それとも阻害力になるのかということである。
中国のような巨大な経済体で、40年間にわたった経済成長の後にその成長速度が減速するのは正常なことだ。中国の台頭は世界の政治と経済を変え、世界がそれを認めるか否かということである。いわゆる「百年の大変革」は中国が新たな台頭を果たしたあと、経済発展や国際ガバナンスでいかなる役割を担ってゆけるのかという問題につきる。
中国にとって重要なのは、新たな発展段階を見すえることだ。経済成長、産業構造、発展エンジンの更新、そしてガバナンスに必要な制度的な枠組みは過去40年とは異なり、中国は改革と制度構築で必要な対応をとるべきあり、それが「中所得国の罠」を乗り越える鍵となるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
