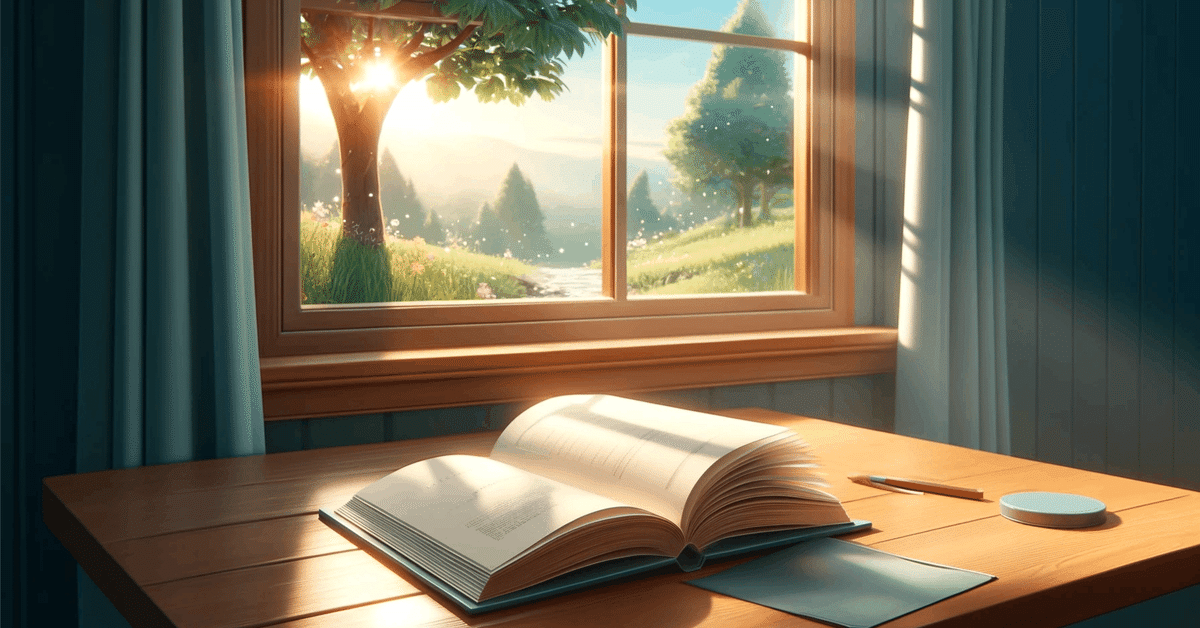
読書記録 202405
「クララとお日様」 カズオイシグロ
「パッとしない子」 辻村深月
「続ける思考」 井上新八
・「続ける」ということは「やめない」ということなので、毎日細々とでよいので「続ける」のが一番続く。
・またいつ「辞めて」もいいと思っていることで、意外と続くという反面性もある。
・細切れに、5分刻みでもいいのでやる。それすらやる気のない時はやるふりをする
・やめるなら明日から、はじめるなら今日から
・やったことを記録できると良い。(ハビットトラッカーみたいなものですね)
・朝早起きして時間を作るのが一番良い
・コーヒーを入れるときに○○、など何かと抱き合わせのセットでやる
・何か小さなミッションを一行書いておくと、ただの地道な作業も楽しくなる。
・雑談は3番目にはまっていること。
この本を読んで、いろんな種類の納豆を食べてプチ発信しています。今まで見過ごしていた事にも注意深くなり、語れるようになるらしいです。私は小粒より中粒の食べ応えがすきなことも判明しました。
「きみのお金は誰のため」 田中学
書店でやたら平積みしてあったこの本を聞きました。13歳の地政学のようにストーリー仕立てになっていて読みやすかったです。
年を取るにつれて、自分たちの輪を広げて考える人になりたいものです。
「板上に咲くーMunakata beyond Van Goghー」 原田マハ
久しぶりの原田マハさん❤️しかも渡辺えりさんの朗読。これだからAudibleはいいですね。贅沢な時間でした。
マハさんの本は手放さずに残しています。
MoMAやMETに行った時も小説をお供に旅しました✨
先月から読書記録をつけるようになってファン魂に火が付き、自分のマハさん専用読書リストをエクセルで作成しました。まだ読んでいない本の方が多い♪ 楽しみを発見できるし、どこまで記録が続くかわかりませんが、やってみたいと思います。
浮世絵がお皿包む緩衝材に使われていたくらいの日本では、西洋のジャポニズムで改めて浮世絵の価値を逆輸入したみたいに、当時版画はあまり芸術的価値がないとみなされていたところを棟方さんが爆発的に活動されて、、
という。風神雷神もまだ読んでいないのにおこがましいですが、風姿花伝も書いてほしいです。
棟方志功さんの芸術家としての軌跡が妻ちやの目線で語られているのですが、棟方さんが家族への愛にも溢れていて、何度もホッとさせられます。柳宗悦の影響力もすごくて、やはり誰といるかって大事なのだと思わされました。ちやという響きが私の実名にも聞こえて親しみやすかったです。
昔の時代を書いてはいますが、今の時代を生きる私たちから見ても、かっこいい女性だと感じてほしい。経済的、物理的というよりも、誰かの精神的な心の支えになれることが、昔も今も一番大切なことだと思っています。
「バナナの魅力を100文字で伝えてください」 柿内尚文
・「ど真ん中を質問する」
今や有名になった。料理家の人に「なぜあなたの料理はそんなにおいしいのですか?」とド直球な質問をすることで意外と話が広がる。
・「関連する物事を横に質問するのではなく、縦に質問する」
マラソンが趣味の人に対してどこどこマラソン大会には出られるんですか?とか、最近ランナーの間で流行ってる靴があるって聞きましたが持っていますか?などのイエス/ノークエスチョンでは会話は広がりにくいので、お勧めのランニングコースはありますか?とかどのくらいの距離を一日のどのタイミングで走っているんですか?などあなたに関心があるよ、という態度が必要
・「伝えるのが面倒な人への対処」
あきらめる、ゴールを先に共有する、感情を切り離す(怒らない)こと。
「アメリカで3ヶ月でネイリスト」ちゃまな
ネイリストとして働くことで長期旅行者という感覚から移民として社会参加というところに感動しました。フロリダでは高齢者が清潔を保ち、社交と生活のハリを求めてネイルに通うそうで、通う人それぞれのニーズがあり、提供する側もどこを得意とするかを伸ばせばよいという考えに共感しました。
「ゆるく考えよう」ちきりん
共感しすぎてメモが止まらない!2011年発行のちきりんさんのブログの書籍化。日本の友人に多数派と違う人生の選択を説明する時に、このように歯切れよく説明したいもの。同調圧力や自身へのブレインロックを強く感じたときに繰り返し読み返したい一冊です。
「不老不死の研究」
糖質脂質を体に蓄えていたのね。冬眠して消費しなかった人間の私は、春になってもそれが落ちずに困っています。中性脂肪→動脈硬化→腎臓病で進んでいくので、予防治療の観点からもこのお肉を落とさねば。座りっぱなしの現代人の生活では腎臓に負担がかかるのです。添加物のリン酸塩も避ける。
生活習慣病から老い、婦人科、不妊、性も含め生きることについて網羅されている本。中高生は保健もしくは家庭科の授業にこれを読めばよいのでは?と思わされました。200年生きることを目標としている成瀬さんもきっとこのホリエモンの本を読んでいるはず。
人工冬眠はSFの世界だけの話ではなさそうです。
忘れる読書 落合陽一
落合陽一さんの講演を聞きにいったことがあるのですが、話の圧縮率が高くてついていけないのです。Youtubeもそうですが、マニアックな笑いのツボにもついていけないけど憧れがあるので接していたい、眺めていたい。ついていけないけど、落合さんに影響を与えた書籍を垣間見たい。そんな私に自分のペースで何回でも読めばいいんだよ。どこが引っかかるかはその時次第。まわりまわって他の文化や思想とも絡まって戻ってくれば?と優しく語りかけてくれるファンに嬉しい書籍。
1週間で8割捨てる技術 筆子
これを聞きながら家の片づけをすると、面白いように不用品を処分できます。具体的な数字や方法が提案されており、端から試してみたくなる。筆者の言うようにモノに触ってしまうとまた愛着が沸くので、なるべく触らないで処分。6月から前職に戻り、生活が一変するので短期間で家をカスタマイズしたい今日この頃。音楽のようにリピートしながらなんとかモノを減らしたい。
ぜんぶ、すてれば 中野善壽
こちらも新生活へのカスタマイズの後押しになるかと、読みました。ですが、こちらは日々のティップスというよりは人生訓。日本の経営者にこのような考えの方がいらっしゃったかと小気味良くなりました。アートをもっとカジュアルに、というところも共感します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
