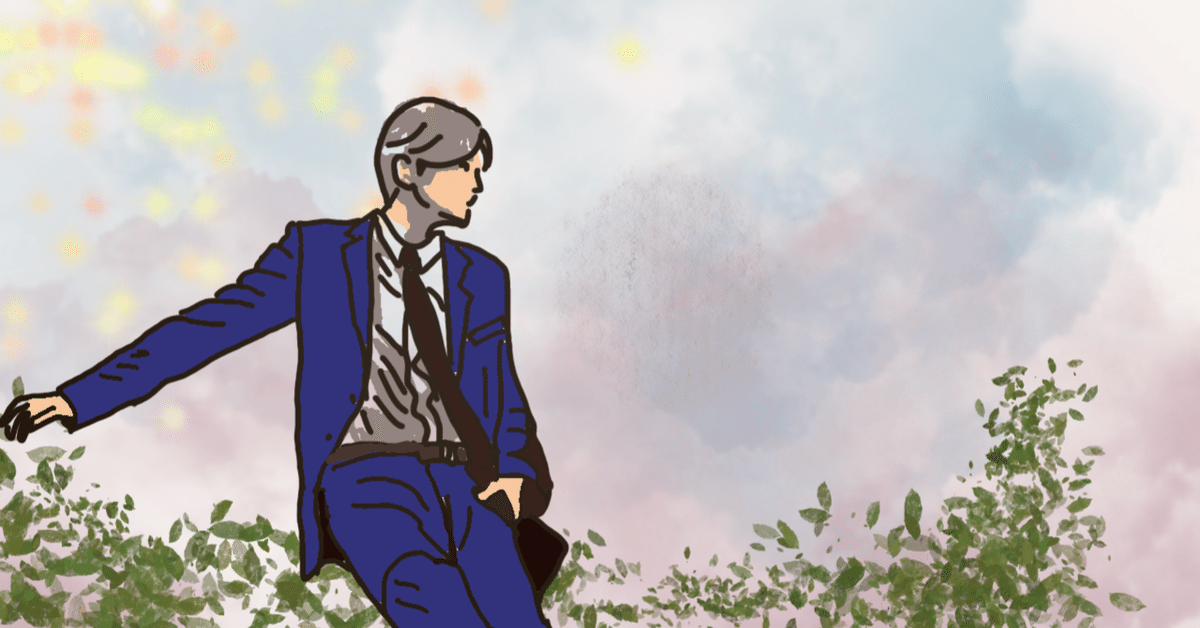
『大学4年間の経営学見るだけノート』
タイトルの書籍は、とても分かりやすく、図式化しながら、高校生やもしかすると中学生にも分かりやすく、経営とは何か、そして自分で事業を起こすとしたら何が必要なのかについて、コンパクトに記載してあります。
この本の中では、経営という概念、市場の見方、マーケティングの仕方まで、とても詳しく書いてあるのですが、その中でも「経営戦略って何?」のパートが、とくに心に残りました。その理由は、戦略はまず「ミッション」(使命)から始まっているからです。分かりやすく、図で表されているのですが、線分の最初のステップが、「使命」になっています。その後、経営理念を立て、そしてどんな経営を具体的にしたいのか、サービスをしたいのか、さらにはお客様には何が伝えたいのかを組み立てていくことが重要と、経営の縦軸を描いています。
横の軸は、実際にその縦軸の概念をどのように行動に移すかです。実店舗を出すなら、周りにどんな店舗があるのかという市場調査、どんなニーズが満たされていないのかという顧客調査、さらには協賛してくれる他の企業、NPOであれば協賛企業がいるかどうかなどを考えていきます。
一つの自分のアイデアを、共感してくれる人とともに具体化していき、大きく社会を変えていくことは、経営という言葉の中でなくても、学校での活動でも、同じようなことが言えるはずです。例えば、以前こちらで紹介させて頂いた「スノーフレークリーダーシップ」は、生徒にとってのお昼休みをより良いものにするために、改革を行った小学生の話です。興味のある方は、以下の『コミュニティ・オーガナイジング』がお勧めです。
話を『大学4年間の経営学見るだけノート』に戻しますが、この中の「経営戦略って何?」の説明が、「使命」(ミッション)から始まるというのは、とても面白いことだと思います。なぜなら、今まで日本は大企業などへの就職をまず考え、大きく資本を動かすことが、大きな成功であり、理想的な経営者だったからです。それが、ミッションという社会変革を目指す姿勢から始まる経営が、このように一般的に大学でも教えられ、本でも書かれるようになってくることは、多くの人が自分で周りへの問題意識からビジネスを始めることができ、人との出会いの中で豊かにしていけるということです。
多くの企業が、SDGsに取り組むようになりました。賛否両論があり、大企業が自社のアピールに用いるだけのように見えるところもあります。しかし、そのSDGsによって、ミッションを基にしてビジネスを始めることへの敷居が社会全体として下がり、スポンサーも取りやすくなっているのも事実だと思います。こうした取り組みが、世の中に広がるために、経営学があるとすれば、伝統的な経営学の見方は、大きく変わってくると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
