
クルーズ客船評論家ダグラス・ワード
日本人でも客船評論家としてクルーズ愛好者にとってダグラス・ワード氏の名前を知っているかと思われます。
彼は趣味ではなく職業として、クルーズ客船の「格付け」をスタートし、業界に一石を投じていたのです。
世界のクルーズ客船約300隻に対して 彼独自の500項目のチェックポイントをもとに格付けし、その後、世界的なクルーズ業界の権威者として頭角を現してきたのです。
Inc. Berlitz International
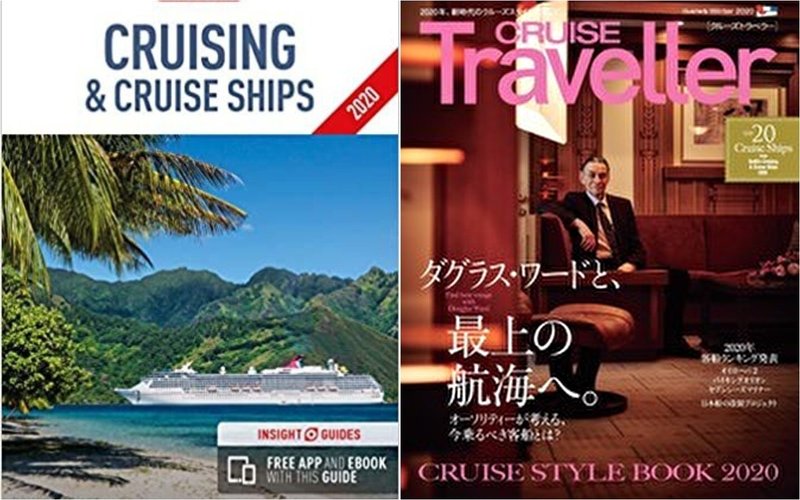
ダグラス・ワード氏は数十ペ ージのクルーズ客船乗船記を書いて小冊子にし、希望者に配布することを仕事にしていたように思われていたのです。
そしてクルーズ客船の分析をできるだけ客観的で、 科学的な手法を取り入れる評価を売りにしていたのです。
当時の業界の動向や、ハード・ソフトの両面に おけるクルーズ会社の内容を把握するのに、非常に役立ったのです。

ダグラス・ワード氏の市場観
マーケットは二分化しつつある。一つはリピーターを中心としたラグジュアリー、そして客船ビギナーや比較的低バジェットのプレミアムおよびカジュアルマーケットである。
日本郵船がクリスタル・クルーズ社を起業する際に当たって、ダグラスワード氏からのアドバイスを受けた際、アメリカ市場で勝負するのなら、ハパグ・ロイド社の「オイローパ」号の先例を研究することを示唆していたのです。今後日本円の強さを背景とした日本人船客が増えると予想。
その場合に、現在のリピ ーターがどのように反応するかを充分検証した上で日本マーケットの対応を考えるべきであろう。クルーズの船上プロダクトの対象はターゲットとした、より多数の客層が中心となると思われたのです。

文化的に差別的な商品でもあるハパグ・ロイド社は、ドイツのマルクが強くなり、急激にドイツ人マーケットが拡大。特に上層階に集中したのです。
その結果、アメリカの旅行代理店は「オイローパ」を売らなくなってしまった。結局「オイローパ」はアメリカマーケットでは敗退し、 ドイツマーケットに特化することになったのです。日本最大級のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」も同様に日本マーケットに特化することで、コンスタントな集客があるようです。
アメリカのベビーブーマー層は、自分の払う金の価値が本当にあるのか自問自答する世代でもある。
もし、ラグジュアリー・マーケット層を狙うのであれば、特に客層の主力は、旅行経験の豊富なリピーターであり、このマーケットに特化した旅行代理店の優良見込み客です。
彼らの評価は厳しいもので、このようなニッチ・マーケットのセグメントは、上記のリピーターと旅行代理店のメンタル、つまり心理的側面に追うことが大きく、きめ細やかな対応を求められているのです。
クルーズ業界、特にプロ集団である旅行代理店の最大の販売のパートナーは極めてメディア指向であり、一度、新会社の「誤解」と「間違った情報」のイメージが定着すると回復が極めて難しいのです。
最初の乗り出した時に、いかにラグジュアリー・マーケットのニーズ を吸収し、クリスタル・クルーズ社の方向性を納得させることが最重要とのこと。ここで失敗すると、回復に数年の時間を要すと示唆。

1980年代後半のマーケットでの失敗例は、キュナード社に見られる。傘下に三様の戦隊を持っていた。
クイーン・エリザベスII号(ウルトラ・ラグジュアリー・ライナー)、
キュナ ード・プリンセス号(カジュアルマーケット)
フィヨルド・タイプ船(NAC 社:ラグジュアリー)
これらは全く異なったマーケットであるが、これを一元コントロールしようとしている。
しかし旅行代理店からすればターゲットが不明瞭かで極めて売りづらい状況にあったのです。
フィヨルド・タイプにしても本船のソフトとリピーターのロイヤリティでどうにかなるものの、会社としての次の 10 年のビジョンを描けていないので、新規の旅行者を他社から引き剥がすことができないのです。船体が 大きいクイーン・エリザベスII号に力を入れると、マス・マーケットの値段で勝負するキュナー ド・プリンセスとの相打ちになる。
旅行代理店は、自分が抱えるリピーターに対して、ラグジュアリーから売ることを考えており、同じ会社に三種のプロダクトがあるのは好ましくない。もし それを認めるなら、大手のホテルと同様にホールディング解釈としてキュナードを持ち、運航などは独自に展開するのが重要だという意見があったのです。

清潔感と安心感が得られるから、これは、北欧系ホテル部門のマネージメントが長年に渡り築いた傾向と、クルーズ船客のわがままな選択以外何物でもないかもしれなかったのです。
北欧系乗組員とホテルスタッフは清潔感と安心感が得られるイメージがあります。これは、北欧系ホテル部門のマネージメントが長年に渡り築いた傾向と、クルーズ船客のわがままな選択以外何物でもないかもしれなかったのです。これはマーケットや船客が作ってくれたバイアスなのかも知れないが否定はできないのです。
イタリア人従業員は、カジュアルマーケット的なイメージが定着している。親しみが持て、気楽な雰囲気を持っているがラグジュアリーのイメージではない。ホテル部門ではやはり北欧系かオーストラリア系の方が人気が高いのです。
ホテル部門でフィリピン人、ポルトガル人が増えているが、これは語学力や陽気さ、および接待力によるところが大きい。今後増えると予想します。
ダイニングサービスにおける気安さや落ち着き、スタッフの笑顔やサービスする能力などは、クルーズ会社が、プロダクトそのものをいかに考えているかを示すものになっているのです。
ホテル・スタッフの教育および運航会社の組織指示体制が、7〜80%の評価比重を占めるのです。
船上での不快な経験は、下船後直ちに旅行代理店を経由して運航会社の方に伝わるし、その対応を誤れば、船客の仲間を通して、ネガテイブな情報として流れてしまう傾向があります。
飛行機の旅行と違い、滞在型の旅行である事を認識し、この対応処理システムの整備が必要でした。
リピーターは、ますますわがままになり、事前に決められた時間や席につきたがらない。
「いつも同じ客とは嫌」
と言う乗客も増えてきた。
クルーズ船客は同席した本船側のキースタッフの人物評価が好きだ。キースタッ フの身なり・ 社交性・接遇・話題の豊富さや性格に関する話題も多く、これらも船やサービスを分析する際には重要な項目である。
船内設備やサービス
船上での居住性、即ちキャビンおよび客室の広さ(スペース・レイシオ)サー ビスの質、コストパフォーマンス感、エンタティンメント、フィット・ ネス施設の質、寄港地観光の組み方も重要な評価の分かれ目であるのです。
食事の質や船客の受け、およびサービスの仕方などから見ると、欧州イタリア系基調のメインコ ースの評判が良い。また、肉食主導から植物性食事に変わりつつあったのです。
ダグラスワードにとって日本食の見解は、将来面白いだろうが、即受け入れられるかは不明ということでした。
ニューヨークの高級日本レストランで見られる鉄板焼きやすき焼きは一般的にセルフ・スタイルに近く、ライフスタイル型クルーズには向かない。
また、料理をつくるときに危険度が高く、クレームの対象になりやすい。衣装の汚れ、においが残る。これらは洗濯代請求のクレームにつながりやすい。日本食も含めて肉料理は敬遠される傾向が強いのです。ルームサービスで弁当、うどんや冷やし麺なども興味深かったのです。

ただし、しょうゆなどの日本的なにおいには注意を要するという意見。なぜなら欧米人の中には醤油を先天的に受け入れない人たちもいるのです。
日本食の場合、ベビーブーマー 世代には、寿司あるいはうどん・そば類が受け入れられるだろう。食事の定食・弁当化は避け、多岐にわたるメニューを選択させる仕掛けが必要かと思われます。
また、 日本食が、あまりにも日本人好みになり、日本人ゲストがそこを占領しだと、 アメリカ人客からは違和感や疎外感をクレームしてくるので要注意。
当時のロイヤル・バイキング社、プリンセス・クルーズ社のロイヤルプリンセス号のマーケットを狙うなら、北欧船員を前面に出すのは、アメリカのマーケットの現状では絶対必須"である。5~10 年 の長いレンジで日本人従業員(乗組員) の露出を考えたほうがよいのです。
もちろん、そのころには日本人 従業員がアメリ カ人船客に日常生活の話題や文化論を話せるエンターテイメント能力があることが必要です。
プロダクトがマーケットに出て、新会社のイメージが定着すると、この時期を早めることも可能でした。
そして最後にダグラスワード曰く
「いずれにせよ、 最初が肝心だ」と
乗組員に関して
乗組員・ホテル従業員など ・リピーターは、一般的にハイプロファイル指向の人たちで、自分が差別的に特別扱いされていることを好むリピーター・クラブのメンバーとして存在しているのです。
ヘビーリピータまだ行っていない寄港地に行きたい観光地の就航航路や船長や幹部船員は誰か、乗組員に関しては、乗船前の問い合わせも多い傾向があります。
本船の幹部乗組員には、食事中の2時間以上の場を取り成す会話力や、社交・ 接遇力が重要で、 クルーズ船客と直接物理的に接するダンスなどのサービスは、専門家に任せるのが現代の時流である。
特に、船の従業員や船長などの船客とのダンスは、船客間の批評・噂の対象になりやすく、 その距離感も重要になります。

クルーズ船客とのボデイタッチや、船に対するセクハラなどのクレーム にもなりやすいので、ロイヤル・バイキング社などは、専門のダンスも出来るホストを乗せている。 この傾向は、ますます顕著になっている。
マーケットが認知していない段階では、日本人従業員の過度な露出を宣伝するのは逆効果になるかも知れない。日本人が、モノ造りの世界で、優秀なのは知っているが、ホスピタリティの世界で、アメリカ人や英国人にはいまだユニフォーム姿の日本人従業員をレジャーな気分で受け入れるところまではいっていないだろう。
特にラグジュアリー・クルーズではユダヤ系の船客が多く、難しい挑戦となると予想していたのです。
これは、世界でも有数なクルーズ客船で あるドイツの「オイロ ーパ」という前例がラグジュアリークルーズのお手本となる。日本の「飛鳥Ⅱ」も「オイローパ」を参考にして業績を上げていることを見受けられます。
ドイツ船には映画で脳裏に刻まれた、U ボートのドイツ制服姿などが連想され、英国人は自腹を切ってまで乗らないのと同じ心理があります。
外交辞令と本音はまったく異なるのです。
貨物輸送などのように利便性や車のようにモノが、 高品質であることが実証でき、そのモノの価値がわかり易い世界と違い、人間の「主観的な」心理 に影響される業界であることを認識しなければ、この事業は成功しないと示唆。
幹部乗組員の混乗方式も、串刺し方式は乗客にとっては奇異に映るだけで、どちらかというと運航者側の都合で決まっている方式てと思われたのです。
初めは、上級は A 国・中級は B 国などにランクで船員の国籍を分ける方法もあるが、いままで の他の船の例でいえば、仕事の仕方が国ごとに異なったり、 英語理解力の問題があったりで上手く行ったこと試しがないようである。
乗組員との円滑な関係を築くには様々な課題があるようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
