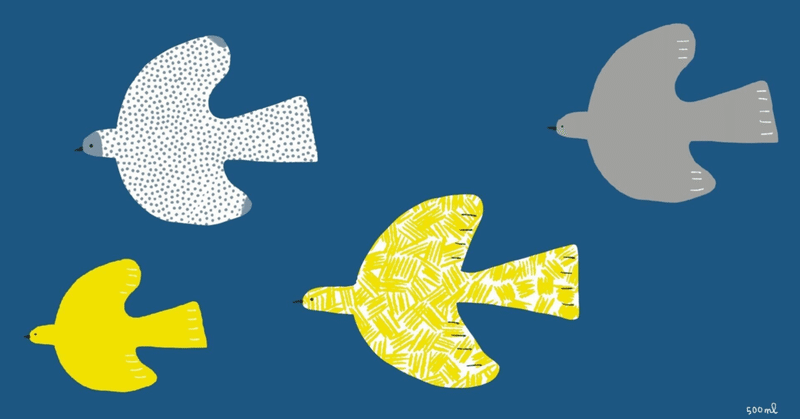
『時間の終わりまで』 ブライアン・グリーン
「我思う、故に我在り」とは言うが、そんな我とは何ぞや?
太陽の周りを周る地球の上に存在する人間という生命体、分子の集合体である有機物が、思う、その思いとは何から作れどこに存在するのか。
そんな、考えてみたら不思議なことについて、改めてじっくり考えるための、こっくりと濃密な手引き書がここにある。
壮大なテーマを扱う本書は、次のような筋立てで書かれている。
・エントロピーの法則
・宇宙の誕生と生命の進化
・意識、言語、宗教、芸術
・宇宙と生命の終焉
・存在の尊さ
まずは、熱力学と物理学の基礎をじっくりと。
インフレーションからビッグバンを経て恒星が出来ていったというのが、宇宙誕生の有名な定説だ。
だが考えてみると、ビッグバン後の混沌から水素の塵が集まって丸く固まり光を発する球になるというのは、無秩序から秩序への流れであり、「エントロピーは時間とともに増大する」という熱力学の大法則に反してはいないか?
実は、一見そう見えて、決して法則に反してはいないのである。
その辺の解説がのっけから面白く、かなり高度な解説ながら楽しく読める。
なるほどと腑に落ちて気持ちがいい。
だがちょっと話が難しくて頭が痛いという人は、ここは飛ばして5章の意識についての話から読んでも大丈夫だ。
意識があるからこそ、自分は自分だという認識がある。それなのに意識は目に見えないし、実体もない。
そんな意識というものの特別感から、「私」という意識を持って思考したり複雑な感情を抱くことは、例えば上に投げたボールが落ちてくるような物理的な現象と比べると、何か高次元の、人知を超えた奇蹟的なもののように感じる。
が、それは買い被った考えなのかもしれない。
地球上の生命は元はといえば単純なひとつの細胞からはじまったものであり、それが進化して複雑化したのがヒトであるとすると、その最も複雑なパートである脳で起きている現象も、元を辿るならば最初のひとつの細胞に至り、さらに遡れば粒子と原子核になる。
カタツムリがツノをつつかれて引っ込めるのも、ヒトが上司に叱られて翌日までクヨクヨ引きずるのも、超ミクロの世界では粒子の配置が外からの刺激に反応しているという意味では同じことなのだ。
あなたを特別なものにしているのは、あなたの内なる運動が組織化されていて、外なる刺激に対する応答として、実にさまざまな行動を取りうるという可能性の豊かさなのだ。
私達一人一人の考え方や感じ方、行動の選択というのは、持って生まれた粒子配置の個性と経験からの学習による粒子の反応の多様性によって、唯一無二の自分だけのものとして感じられるのである。
意識に続いて、言語の発祥、人はなぜ物語りを作るのか、宗教、そして芸術を俎上に上げる6章、7章、8章は、科学的でありながら大いに人文的な内容になっている。
特に音楽について書かれた箇所では、著者の磨かれた感受性と音楽への愛が垣間見られて感動的だ。(8章はぜひベートーヴェンを聴きながら読んでいただきたい)
人間が想像の世界を物語り、信仰を持ち、芸術活動にいそしむことは、DNAに刻印された、生き残るための活動だとする、様々な学者による議論を紹介しつつ、それが科学的に真実だとは著者は言い切らない。
しかし彼の筆致は、決して科学至上主義ではなく、人間の想像力や創造性への畏敬の念が溢れている。
生物として適応していることが、価値を決める唯一の基準ではないのだ。・・・想像力を振るい、美しいもの、心を騒がすもの、胸を引き裂くものを表現できるようになることは、生き残るのと同じくらい素晴らしいことだ。
作詞家エドガー・イップ・ハーバーグ(有名なSomewhere over the rainbow…の作詞家)の、「言葉はあなたに思考を考えさせ、音楽はあなたに感覚を感じさせる。しかし、歌はあなたに思考を感じさせる」という言葉は、著者にとって、芸術的な真実のエッセンスを捉えるものだという。
知覚を通して思考と感情が混じり合うとき、つまりわれわれが思考を考えるだけでなく、それを感じもするとき、その経験は機械論的な説明の境界を大きく越えた領域に入る。そしてわれわれは、さもなければ海図もなかったであろう世界を航行する手段を手に入れる。・・・それは賞賛に値することだ。
さらに9章、10章では、宇宙の終焉、そしてそれよりも恐ろしく感じる「意識」の終焉という、興味深くもどこまでも暗いテーマを扱う。
そして、11章では、大きな気づきを与えてくれる。与えてくれると言っても、壇上から教えるのではなく、彼自身が気づき、愕然とし、目を開いた体験を共有することによって。
本書の科学的な部分は、きわめて公正な立場から書かれているため、読者をぐいぐい引っ張って引き込むタイプの本ではない。その代わりに、多角的な材料を示し、読者自身の自発的な思考を刺激してくれる。
科学について、芸術について、著者の真摯な思いが伝わる感動的な科学書である。
最後に、随所に出てくる深淵な言葉のうち、特に気に入ったものをメモしておく。
エントロピーが低いということは、その秩序は、強力な組織化力を持つ何者かによって作られたことを示唆するのである。
何かに慣れ親しんでいるということは、何が馬鹿げていて、何が馬鹿げていないのかを判断するわれわれの感覚をゆがめる場合がある
「科学的な目」を持つことは、雑音、圧力、まやかしに満ちたこの世界を生きていく上で、非常に大切なことだ。
