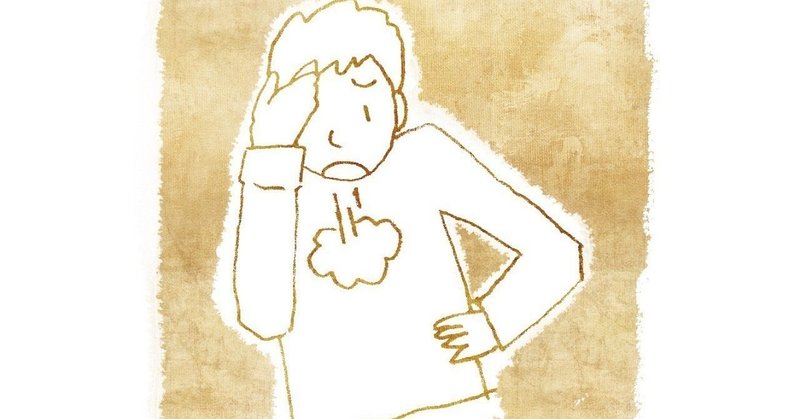
教えてちゃんが多すぎないかい?
研究者や心理士は、研究だけでなくて、クライエントや学生(生徒)教える教育者としての立場も並行する仕事だ。これらの公的な仕事以外でも、自分でコンテンツを作ってそれを教える立場である。
だから、「教える仕事」なのだけど、仕事だとしても「これをわたしに聞く?」と、言いたくなるような、おんぶにだっこな「教えてちゃん」に出会うことがある。
その質問をした相手に対して、自分の時間を削ってその質問に向き合うことは(読んだり、聞いたり)わたしの貴重な24時間の内の何分かを奪う時間泥棒とさえ思う。
※時間泥棒:ミヒャエル・エンデ「モモ」に出てくる、人から時間を奪っていく泥棒から転じたビジネス用語
「せんせー、なんて書いてあるのかわかりません」
などは、己の字の乱雑さ故に非はわたしにあるので、素直に詫びて訂正する。
けれど、
「せんせー、黒板の字が速すぎて写せません!」
「せんせーの喋っているパワーポイントを全部レジュメにしてください」
などは、それまでの学習スタイルへの適応の能力のなさ、学ぶ力のなさを露呈していることに気づいてはいないのではないか?と、危機感を覚える。
学ぶ力=学力を分けると、「聞く」「書く」「話す」「計算する」「推論する」に分けられる。
あなたは、これらの力を学校という教育機関に行って集団で学ぶ力がある、と認められたから(就学前健診というものがある)、学校に入ってきているのだからさ、その力は伸びるものだし、自分で伸ばすものなのよ。
時間泥棒は、学生でなくても社会人にたくさんいる
それが小学生、いやもっと言えば、中学生の義務教育ならばわかる。そうではなく、小学校1年生から中学3年までの義務教育を終えて、それ以降は自由なハズなのに、「敢えて」自分から入学試験を受けて合格して入ってきたのだからさ、それ、自分の「選択だよ」。それに、そこまでの学力を伸ばさずに来たのはあなた側の問題ではないかい?
そもそも、義務教育と高等教育(高校から大学院)とは学びの種別が違うんだってば!と、基礎学力の衰えを訴えてみたところで、わたしはゼミを担当しているわけではないし、たった90分の1コマでしか学生たちと対峙していないから、そこまで教育できないジレンマを感じた。
もっと言えば、言葉の使い方って、子どもの環境=家庭環境で左右されるから、家庭教育のレベルが一目瞭然なのだ。つまり、どんな言葉を養育者が選択して使ってきたかがバレバレなのだ。
どうやって人にものをたずねたらよいか(質問スタイル)、どうやったら人にわかりやすく伝えられるか、どうやって人とコミュニケーションをとるか。これらは、養育者の言語能力と等しいという研究データがたくさんあるのだ。
さらに、社会に出て、社会人(お仕事しているしていないに関わらず、学校を卒業したならば社会人だ)として生活する中で、いつまでも受け身の学生と同じ態度でいたらそれは違うと思うのだ。
でも、学生ならまだいい。わたしは教員という教える立場だから、教えることは仕事だ。また、わたしの私的な授業の受講生さんでも、同じだ。それは受講前に受講契約を取り交わしているからだ。
縁あって、去年の秋からあるモノをご紹介させていただく機会があって、たくさんのご感想とご質問をいただく。
だけども、わたしは、別の仕事も同時にたくさんしているので、とてもじゃないけれど、全てのご質問などに対応できない。
・ブログに書いてあるよ!
・招待したクローズドのグループページに書いてあるよ!
・メーカーのホームページに書いてあるよ!
そもそも、それ、わたしでなくてもよくない?
教育とは、学ぶ力をサポートし、生徒を育てる仕事であり、同時に、「質問の質」をあげることも仕事だ。
なんでもかんでも手取り足取り、「教える」ことが「教えること」ではない。それは、自分の子育てでも同じだ。
手取り足取り教えることは簡単だけども(時間と手間をかける労力は相当だけど)、自ら学ぶ「自学自習」の力も同時に育てるのが教える立場の人の役目で、それは家庭教育も同じ。
さらには、教育は専門知識という一次情報をただ伝えているのではなく、先生という教える側が情報を集めて精査して、そして自分なりの結論をまとめた、二次情報、三次情報を伝える(売っている)仕事だ。
※一次情報、二次情報は、情報学(図書館学)で習う専門用語で、久しぶりに思い出した!
そして、その2次情報を伝えて、それをもとに一緒に体験する学びの場を提供する、体験型が授業なのだ。
自ら調べる時間を惜しんで、よそからいいとこどりしてハックするのは
時間泥棒な上に、それは罪になる。
論文でそれをすると盗用になるから、投稿論文ではそれはご法度だ。引用あるいは参考論文として必ず書くことは、学校の指導で習ったと思う。
悪い意味で、インターネットがクリックすればすぐ答えが出てくる、便利だけど、1問1答式の機械的な世界を作ってしまった。
ものごとはいいことづくめではなくて、必ず弊害もあるってことも、クリティカルシンキングで習ったと思う。
「習ったでしょ!」と、オットー先生に言うと、途端に嫌な顔になるので、こういう言い方はしたくないのだけど、「授業聞いとけよ!こっちは必死に授業してんだぞ!」と、教える立場だと思ってしまう。
「質問の質」を考えよう
自分で検索すればわかるようなことを他の人に聞くのって、相手の貴重な
時間と答える労力を奪っていることになり、失礼な行為だ。
誰かに聞く態度は、素晴らしいことだ。だけども、同時に質問力も必要だ。
「このページに書いていないのだけど、わたしは●●って思うのだけど
どう思う?」
という質問なら、それは2次情報に昇華していることがわかるから、そういいう質問なら、先生として大歓迎だ。
そうではなくて、ググればわかるような一次情報をわたしに聞かないで欲しい。だって、わたしでなくてもできることだから。
あまりに、教えてちゃんが多すぎて、「これってわたしの仕事だっけ?」と思うことが多すぎたので、何様?と思われるかもしれないけれど、あえて書きました。
情報はタダではありません!そこんとこ、よろしく!
論文や所見書き、心理面接にまみれているカシ丸の言葉の力で、読んだ人をほっとエンパワメントできたら嬉しく思います。
