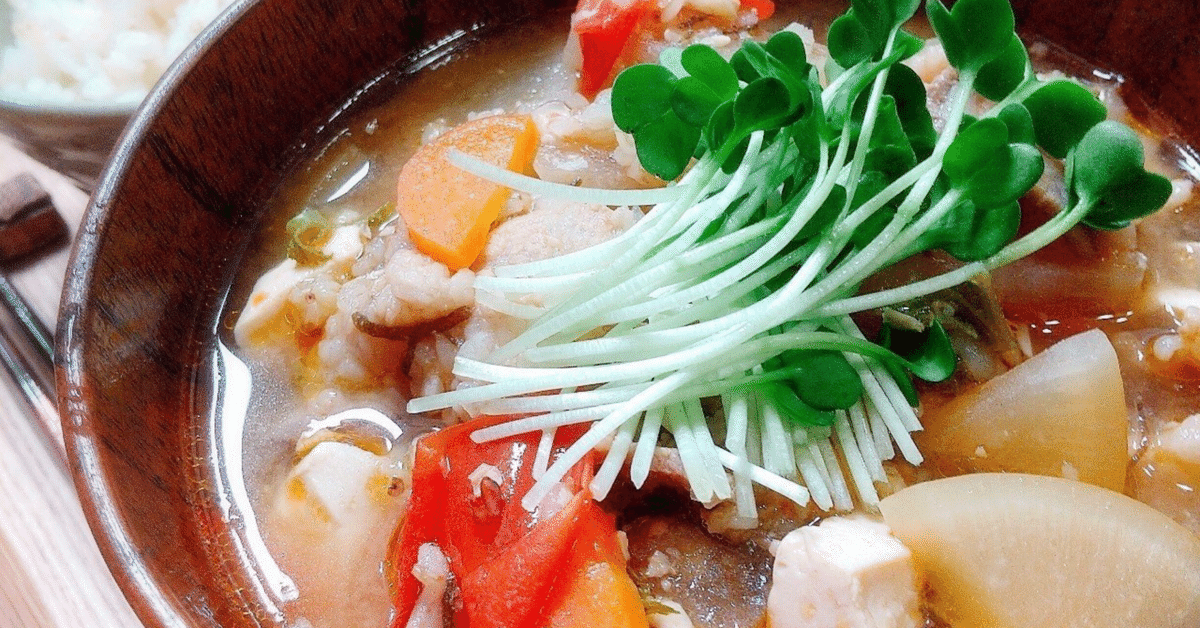
【リハ科医師の必須知識】栄養スクリーニングツールを解説!!【完全版】
病院では、入院患者の多くが低栄養のリスクを抱えています💦
特に私たちの主戦場である回復期リハビリテーション病棟はリハによるカロリー消費が多いのにもかかわらずそれに合わせた食事量を提供で来ていないことが多く、入院患者のうち、20%から50%が何らかの形で低栄養状態にあると報告されています 。
栄養スクリーニングとアセスメントツールは、患者の栄養状態を評価し、適切な栄養管理を行うために使用されます!
それぞれのツールについて初学者にもわかりやすく解説してみます!
ちなみに私は、CONUT値でスクリーニングを行った後にGLIM基準でフォローアップを行います!低栄養の場合は基礎代謝と活動代謝を計算し直して、食事量のアップを検討します!
あなたはどのスクリーニングツールを使いますか?!
主観的包括的栄養評価(SGA: Subjective Global Assessment)
概要
SGAは、臨床評価に基づいて患者の栄養状態を評価するツールです。身体計測データや血液検査結果を必要とせず、患者や介護者からの情報と医師の臨床判断に基づいて行われます。
評価項目
1. 病歴:食欲不振、体重減少、消化器症状、機能的能力低下の有無
2. 身体診察:皮下脂肪、筋肉量、浮腫、アスサイトの評価
メリット
- 短時間で実施可能
- 特殊な機器や検査が不要
デメリット
- 評価者の経験に依存
- 主観的要素が強い
MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short Form)
概要
MNA-SFは、高齢者の栄養状態を迅速に評価するためのツールです。全体の栄養評価を行うMNA(Mini Nutritional Assessment)の短縮版で、短時間で実施可能です。
評価項目
1. 食事摂取量:食事量の減少や質の低下
2. 体重減少:過去3か月間の体重減少
3. 移動能力:自立性や移動の難易度
4. 急性疾患や心理的ストレスの有無**
5. 神経心理学的問題:** 認知症やうつ病の有無
6. BMI:身体質量指数
メリット
- 短時間で簡単に実施可能
- 高齢者に特化した評価
デメリット
- 他の年齢層には適用が限定的
CONUT (Controlling Nutritional Status)
概要
CONUTは、血液検査の結果を用いて栄養状態を評価するツールです。特に病院での入院患者の栄養状態を管理するのに有用です。
↓詳細はこちら↓
評価項目
1. アルブミン値:栄養状態の指標
2. 総リンパ球数:免疫機能の指標
3. 総コレステロール値:栄養状態とエネルギー供給の指標
メリット
- 客観的な数値に基づく評価
- 血液検査データがあれば容易に実施可能
デメリット:
- 血液検査が必要
- 血液検査結果が直ちに利用できない場合がある
NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002)
概要
NRS-2002は、入院患者の栄養リスクを評価するために設計されたツールです。患者の栄養状態と病気の重症度に基づいて評価します。
評価項目
1. BMI:身体質量指数
2. 体重減少:過去3か月の体重減少
3. 食事摂取量の変化:最近の食事摂取量の変化
4. 病気の重症度:病気の種類とその重症度
メリット
- 栄養リスクの迅速な評価が可能
- 入院患者の管理に適している
デメリット
- 一部の評価項目が主観的
- 初診時の情報に基づくため、変化を追跡しにくい
MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)
概要
MUSTは、成人の栄養不良リスクを評価するための簡便なツールです。病院、在宅ケアで広く使用されます。
評価項目
1. BMI:身体質量指数
2. 体重減少:過去3~6か月の体重減少
3. 急性疾患による栄養摂取不足の有無
メリット
- 簡単で迅速な評価が可能
- 幅広い環境で使用可能
デメリット
- 一部の評価項目が主観的
- 高齢者や特定の病態に特化していない
GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index)
概要
GNRIは、高齢者の栄養リスクを評価するために設計されたツールです。主に体重と血清アルブミン値に基づいて算出されます。
評価項目
1. 体重:現在の体重と理想体重の比率
2. 血清アルブミン値:栄養状態の指標
メリット
- 簡便で計算が容易
- 高齢者に特化している
デメリット
- 血清アルブミン値が影響を受けやすい(急性期の影響など)
- 他の詳細な栄養評価と併用する必要がある場合がある
これらのツールを適切に使用することで、患者の栄養状態を評価し、適切な介入を行うことができます!各ツールの特性を理解し、患者の状況に応じて使い分けることが重要です!
上のスクリーニングツールで低栄養だとされた患者は、GLIM基準にてフォローを行います!
では、GLIM基準について解説します!
GLIM基準
概要
(Global Leadership Initiative on Malnutrition)は、栄養不良の統一的な診断基準として国際的に用いられています!
この基準は、現症3項目と病因2項目を組み合わせて栄養不良の診断を行います!以下はその項目と、アジア人のカットオフ値です!
【現象】
1、体重変化(減少)
過去6ヶ月間で5%以上、または半年以上前と比較して10%以上の体重減少
2、低BMI
70歳未満で18.5kg/㎡未満、70歳以上では20kg/㎡未満
3、筋肉量減少
-DXA:男性く7.0kg/㎡、女性<5.4kg/㎡
-BIA:男性<7.0kg/㎡、女性く5.7kg/㎡
-FFMI:男性<17.0kg/㎡、女性<15.0kg/㎡
【病因】
1、食事摂取量減少または消化吸収不良
1週間を超えて50%以上の栄養摂取不足が続く、または2週間を超えて栄養摂取不足
2、疾患と炎症:急性または慢性の炎症反応の存在(感染症、慢性疾患、外傷などに伴う)
【診断方法】
- GLIM基準では、上記の主要項目のうち、1つ以上の表現型基準と1つ以上の病因論的基準を満たす場合に栄養不良と診断されます。
【GLIM基準のメリット】
- 国際的に統一された基準:世界中で統一的に栄養不良を診断できるため、研究や臨床実践での比較が容易。
- 包括的評価:身体的な変化と病因論的要因を両方考慮するため、より包括的な評価が可能。
- 多様な評価方法の利用:体重、BMI、筋肉量など複数の指標を使用し、個々の患者の状況に応じた柔軟な評価ができる。
患者が低栄養と判断された場合はどうする?
基礎代謝量と活動代謝量を計算し、栄養師と相談します!
(↓私がバタバタしている時に使っている無料の計算ツールはこちら!↓)
低栄養のままリハビリテーション行うと、逆に筋肉が崩壊して逆効果になることもあります💦
認知症患者など食べてくれない患者さんも多いですが、、、みんなで頑張って低栄養を克服しましょう!!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
