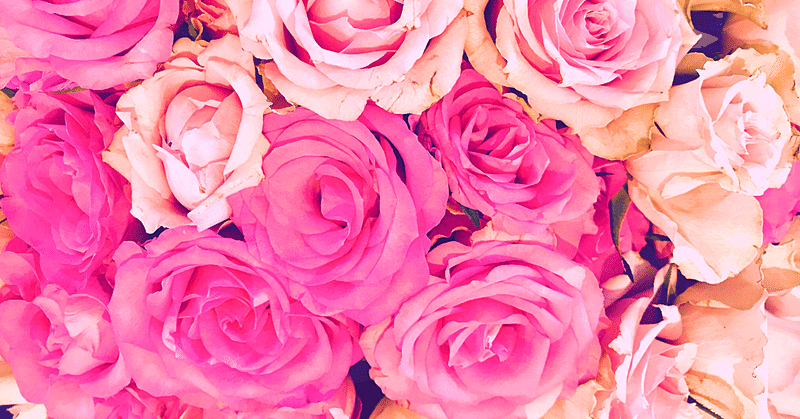
999本の薔薇を貴女に(注:中途半端小説)
未完の小説シリーズ2
若〜い頃に書いた甘々系ファンタジー。
たまにはこういうのもいいかな? と投稿する。
カテゴリとしては「やり直し系」かな。
*****「999本のバラを貴女に」
それは、とても強い焦燥。
何故、貴方のような人がこの世に存在するのか────と。
その時、息を飲んだ私を…貴方は知る由もないでしょう。
思い返せば、初めての出会い。
そして、名を明かした時の、黒髪の白(フィオナ)!と嘲笑われた、最高に憎らしく、同じだけ愛おしい思い出。
隣国との思わぬ小競り合いにて、あわや大陸戦争を招くかと思われた先の一戦では、並み居る兵士、魔法士の中で、一際強く、高潔で。たくさんの人の心を奪った、あの眩い黄金色。
それに対して、自分はなんて欲深で低俗だったのか……。
大陸の一大陸路の中継国、国土にして三番目の広さを誇るクレオティス王国の、魔導士団の一個大隊を管理する【地の第四位( クアトル・テッラ)】。
三十九を迎えたばかりの若き魔導士、庶出としてそこまで登りつめ、多くの民に夢を与えた黒髪のフィオナ・イングラムは、この良き日にそっと辞表を出して、昼過ぎには隣の国にある、時の神を奉る大聖堂に立っていた。
今頃、隣の故国では、自分の辞表を見つけた部下がてんてこ舞いになっている────訳もなく。ただ粛々と処理がなされて、既に後任として立っておろう、と。
庶出なんて、所詮、そんなものだ、と。
たくさんの苦味と共に、隙あらばやれ行き遅れ、そもそも貴族が庶民がと口うるさく言っていた、地の第四位(クアトル・テッラ)の副隊長の、黙っていればお綺麗な、渋面を浮かべて飲み込んだ。
魔導士団の隊長として、上から四番目。フィオナは別段、その地位に固執していた訳じゃない。それでも少しは浅ましかったと、痛いところを語るなら、おおよそ二十数年来の、好いた相手に近かったから、だ。
今も昔を思い出しては鈍く痛む初恋の人は、十二の頃に初等校で出会ったことを発端として、十五から始まった中等校を共にした。
十八からはそれぞれ専門の学び舎へと別れて、二十の頃に激化した隣国との小競り合いにて、それぞれ派遣の命が下って戦場で再会を果たす。
国お抱えの騎士団と魔導士団は様子見で、本腰を入れねばならぬ見極めをしながらも、とりあえずまだ死ぬ確率は低かろうということで、専門校の成績優秀者を対象として、武系から五十名、魔系から五十名、合わせて百ばかりの生徒を兵士として戦線に投下した。
……尤も、ただの小競り合いとて、命の天秤には掛かるもの。その時、選出されたのは、主に庶出の学生だった。貴族の籍を持つものたちは、親がこっそりお金を積んで派遣を見送らせたらしい、と。不満のあった学生たちが、まことしやかに囁いていたのだ。
だから、戦場で彼を見たとき、心の底から驚いた。
王家の信頼厚き系譜で、親類関係も持つと言われる国内きっての大貴族。その嫡子として生を受けた彼の名は、アルベルト。黄金の髪にアイスブルーの瞳を持った、立ち振る舞いも美しい、眉目秀麗な男性だ。
容姿、家柄共に良く、たくさんの女性の心を優しい笑みで奪った彼は、学生時代、庶民…と言うより、黒髪の白(フィオナ)を厭うた事が同窓の間では有名だった。
お互い、視線を絡めてしまって硬直する事、数十秒。
何故、お前がいるんだ、と、何故、貴方がいるのか、と。
奇しくも零れた呟きが、ピタリと重なり合ってしまって、周りに妙な緊張を生んだ。まぁ、ここの細かい所は、またそのうち語る事として。
結局、その時の小競り合いは、大戦に発展する前に、彼の機転と伝手により大々的なものにはならず、間も無く平和な終わりを迎え、フィオナも無傷で学徒に戻る。
それでも二十数名の死者、負傷者を出してしまったが、彼がいなければ泥沼に陥っただろうこともあり、戦線に出ていた学生はもちろん、先に派遣されていた少数の軍人たちも、彼に対する覚えはめでたく……。
半年後、二十一で卒業するなり、彼は騎士団の小隊長に。
平騎士を経ずに隊長職とは、お貴族様には恐れ入った……と。平魔法士として国軍に下っ端就職を果たした彼女は、正直、彼に嫉妬した。が、彼が有能であることは学生時代に嫌という程、感じていたことなので。嫉妬心の倍以上には、妙な誇らしさもあったのだ。
私が惚れた男性は、こんなにすごい人だったのだ、と。
騎士服につける勲章を授かった人を遠目に見やり、騎士団の頂上である将軍たちと、魔導士団の頂上である第四位までのお偉方を見て、もし、あそこまで登って行けたら、今よりずっと近くで彼を見ることができるだろうか、と。
その日からフィオナの目標は、適性があった大地の魔導士団長、【地の第四位( クアトル・テッラ)】……は無理だとしても、副長くらいになれればいいな、と。そんな風に変わっていった。
フィオナはそこそこ人目をひく容姿だったが、いっそ清々しいほどに禁欲的で、男性の影もなく、寡黙で真面目。コツコツ努力をするかと思えば、不意に大きな発見もする。
そこそこ年次が上がってきたら、今度は学生時代から続く交遊関係が効いてきた。大貴族であるアルベルトに匹敵するほど力を持った、十年来の大親友、サラこと、サラエラ・クシュナトルの名が、折を見て庶出のフィオナの位を上げた。
そこからトントン拍子にて、老齢であった地の第四位( クアトル・テッラ)が引退し、後任は当時副長だった三十代の貴族女性。空いた副長の席次に何故か、フィオナの名前が載せられる。
前任の貴族女性は既婚者で二人の子持ち。職を勤めて三年ほど過ぎたある日の朝のこと、三人目が出来たから、フィオナちゃん、後、よろしくね♪ と。自身の体力の限界を熱弁し、その日の昼にはクアトル・テッラとして、フィオナは判を押していた。
ここまで望んでいた訳では……と、始めはフィオナも困惑したが、前任者の仕事に対する適当さ────何せ、団長しか見ない書類に不備があり過ぎた────を目の当たりにしてしまったら。
生来の生真面目さが全面に出てしまい、内容、提出期限とも守られるようになった書類の山に、文官達には喜ばれるは、当然貴族出の十倍はいるだろう庶出の団員達に羨望のような視線で見られて、本音は貴族が殆どのお偉方が占める会議やら、かなり居心地が悪い訳だが、ある意味、彼らの目標だったり、日々の励みになるのなら…と。
学生時代、アルベルトとぶつかりまくったあたりから、徐々に消えてしまったような己の表情筋。一部の貴族出の魔導士やら騎士やら文官やらから、嫌味や嫌がらせを受ける日々さえ躱してしまう、動かぬ柔い筋肉のおかげで、三十手前で受けた団長位を、十年あまり勤め上げてきた。
そう、こうしてあっさりと辞表を出してしまえる理由について、十年ほど座った椅子に愛着がなかった訳ではないのだ。
仕事はそこそこ難しく、それでもやりがいのある内容だった。
殆ど書類仕事だったが、魔導士の職としての年に一度の魔法大会では、日々温めていた魔法に関する試行錯誤を披露するのが楽しかったし、大親友のサラと、こちらも付き合いが大変長い、友人のルーカスがこさえた幼子たちに、定期的に出前の魔法教室を開くのも、子供達が二人に似ていてとても可愛く、非常に楽しいものだったのだ。
役職につく権限で、行こうと思えば騎士団の建物だって理由もなく入り放題だったし、何より当初の目的であるアルベルトの華々しい経歴と、それに伴う大出世、勲章を授かる式典などでは、彼に下心を持つ令嬢たちの誰よりも近しい場所で、彼の勇姿を見ることができたのだから。
年を重ねて、益々逞しく、端正になる、彼は常に輝いて見えた。
年を重ねて、段々と締まらなくなっていく下腹やら、下がり始めた口角や、刻まれた目尻の小皺。
毎日ご丁寧にも行き遅れと言ってくる、任期中二人目の副長である貴族男子のおかげか、余計なお世話かで、三十五を迎えた頃には結婚の意思はかなり薄らぎ、また、憧れの彼も未だに独身である事に、ある種の共感と安心感をフィオナは勝手に見い出していた。
ただ、やはり彼女がきちんと分かっていなかったのは、男性と、女性の性差、というものか……。
さる名門貴族のご令嬢との結婚話、ついに年貢の納め時が来た、レクイアス家のアルベルト。
城勤めの侍女達が興味津々で運ぶ話を、人の気配の薄い回廊でフィオナは初めて耳にして。つい、感情が急いてしまって、地の諜報魔法を使う。
石造りの廊下や壁や、庭や城壁に至るまで。
火の第一位(ウヌス・イグニオ)、水の第二位(ドゥオ・アキュラ)、風の第三位(トレス・ヴァン)の三隊長に、気取られぬよう魔力を注ぎ。
半刻後、花に埋もれるフィオナを発見したのは、書類に判が必要で城中を探し回っていた副長の嫌味な貴族。
彼女にとって残酷な例の噂は、どうやら陛下すら関わっている本腰の入ったものだった、と。目を閉じ、静かに涙していた彼女の目元は、感情に引きつられ小さく魔力暴走して生まれた花々に、埋もれて、既に乾いていたけれど。
「っ!? 隊長!? フィオナ・イングラム!! フィオナ!!」
「うるさい」
ぼんやり瞳を開けたフィオナに、副長の貴族男子は真に迫る様子を見せて。
「あ、な、なんですか…! 驚かせないで下さい! どうしてすぐに戻って来ないんですか!? 只でさえ仕事が溜まっているのに! そんな“のろま”だから同期のレクイアスに先に結婚を決められるんですよ!? 散々行き遅れだと助言してあげているのに! ま、まぁ? どうせ貴女ほどの年増では貰い手がいないでしょうから。どうしてもとおっしゃるのなら、僕が貰って差し上げても……」
と。
後半、キリッとメガネを押し上げる、見ようによってはキレイな男に、ふふっ、と笑いがこみ上げてきて。
「お気遣いありがとう。こんな年増を若い貴族様に押し付けるなんて出来ませんので。でも貴方、意外と優しいのね」
そもそも、もう、子供も産めそうにないし……と。
齢二十と囁かれている彼の結婚相手を思い、よっ、と掛け声をかけ地面から体を起こす。
スタスタと歩き始めた後方で、べ、別に僕は三男ですしっ、こっ、子供なんか居なくてもっ、と何やらブツブツ聞こえてきたが。
四十を迎えても、彼は大貴族の嫡子であって。
男性は死ぬまで子が成せるから。
そうか、同じ境遇の人だとちょっと安心していたけれど……やはり、あの人は遠かったのだ……私はこの年になるまで、一体何をして来たのだろう。気づいたらもう子供も産めそうにない歳で……その代わりになる何か、とか。何か一つでも成し遂げて来られたのだろうか、と。
とても、そんな大それたものには、思い至らない訳だけど。
そもそも、彼に会った時、おめでとうとちゃんと言えるだろうか?
死んでしまった表情筋だが、付き合いの長い彼らには、自分が何を考えているのか、だいたいバレてしまうのだ。
いつの間にか末席とはいえ将軍職まで上り詰めた彼と、同じ会議に出席し、つまらなくしていると、終わった後に「大事な会議でつまらなそうな顔などするな」と、もれなく嫌味が入ってくる程度には。
こんな気持ちで、めでたい言葉など、口に出して言えるのだろうか。
いや、無理だな。無理、無理、だ。言えない。おめでとう、なんて言えない。だって結婚おめでとうだなんて、ひとかけらも思えないのだもの。
下手をしたら二十歳のうら若き乙女に対し、恨み言を言ってしまうかもしれない……なんて。いや、そんなことも言えないけれど。そもそも相手も大貴族様、深窓の令嬢様だ。会うことすら無理ってやつだ。
あぁ、色々と、面倒臭い……と、空を一度仰いで見せて。ようやく我に帰ったらしい嫌味な副長をちらりと見遣り。
「ねぇ、そろそろ、出世してみる?」
その時の男の顔は、これまた傑作なほど、両目が見開かれていたなぁ、と。
そしてフィオナは、誰にも語らず着々と準備を重ね、彼の結婚式であるこの日に、辞表を出して国を出た。
クレオティス王国は、およそ四十年生きた、それなりに愛しい国だった。
大親友のサラとルーカス、彼らには少ししてから手紙を書こう。何も言わずに出て来てしまった、私をどうか許してください、と。
白百合で飾られた大聖堂の偶像を前に、フィオナは心から彼らに詫びた。
十二で彼に一目惚れしてから、ここまでで二十数年も。
もう、ほとほと想い疲れた。
おめでとうと、たった一言の祝福を贈る気力もない。
まして、間近で幸せそうに、我が子を抱くだろう彼らの姿を、目に入れて耐えられようはずがない。
無理だ。想像だけで泣きそうなのに。
踏まれても伸びると揶揄される、ど根性魂の庶民だけれど。どうにもそれだけは出来そうにない。
お前も早く結婚しろ、と本人に言われたら、災害級の魔力暴走を起こす自信もある。本人ではないが、たくさんの嫌味な貴族にアルベルトを引き合いにして、辞表を出すまでのわずかな期間にも、散々からかわれてしまったのだ。
あんなに嫌な人間のいる国など、いっそ滅んでしまえ……など。心のどこかで思っていたのもまた事実であるからに。
そもそも婚約から結婚までが一ヶ月ってどうかしている。
私はいつでも辞められるけど。一ヶ月って。
そんなに……そんなに、早く結婚をしたかったのか……!!
くわっ、と目を見開いた先には、慈悲深そうな神の絵が。
そもそも、ここって、どなたの聖堂だったっけ? あぁ、時の神。時の女神様。
ふと、そういやせっかくだから、観光でもと思って入り、そこまでは記憶にあるんだよなぁ、とフィオナは絵画をじっと見つめた。
回る歯車を背景にして、長いひらひらを靡かせて、女神は優しく万人に微笑んだ。さぁ、私に回帰しなさいと言っていそうな、絶妙な腕の開き具合だ。
お母さん。
まぁ、会ったこともない人だけど。
ねぇ、時の女神様、もし、もしもあの時に戻してくださるのなら。
今度は後悔しないよう、彼に楯突いたりしませんし……ちゃんと他の人にも恋をして、それで、それで……彼とはよき友人になりたいです。
あの、でも、欲を言うのなら……学生時代にちょっとでいいから、恋人になれるように頑張りたい。
今ならおしゃれも少しは分かるし、お化粧も上手にできると思う。
だってね、ほんとは、ほんとうは……! 初等校の卒業式で、タイの取り合いに混ざりたかった……!!
中等校の卒業式でも、彼は並んだ全員と踊ってくれたんだ、って……!
後から聞いてっ……わ、私も、並べばよかったと思っています!!
そもそもちゃんと卒業式に出席すれば良かったな、って。
卒業パーティ、興味なかったから……ドレスを買うお金も貯めてなかった。きっと聞いてもすぐには入れなかったし……それを教えてくれる友達も作っていなかった。
だから、もし、もう一度、やり直せるならば!
頑張って仕事してドレスのお金、貯めるのでっ!
だから、一度でいいから、彼と踊ってみたい! こ、恋人とか、友達が無理でもね、仲さえ悪くなければ、微笑んでくれるんですよ。
女性には優しい、ってもっぱら評判だったから。
私には一度もなかったことなんですけどね……はははっ。自分で言ってて悲しいや。
心底、嫌われてたなぁ、私。
きっといいとこがなかったんだ。
そんなフィオナの心中を聞いてもらえば、彼女がいかに見た目と中身が剥離した人間だったのか、を察してもらえるだろうか、と。少し注釈をいれてみて。
およそ四十歳にして、未だに白髪の一本もない、黒々とした長髪と、整った愛らしい顔。
ただ、無表情である故に、その心根さえ神がかり、崇高な意思を滲ませる……外見詐欺な彼女はいっそ、真剣に恋を拗らせていた。
でも……でも……好きだったんだ。
誰よりも、誰よりも。
魂が、震える程に……。
は、とフィオナはため息をついて、二、三度瞬いた。
そして、祈りの本腰を入れて、強く瞼を閉じて俯く。
直接は言えないけれど。
女神様……どうか、彼が末長く、幸せでありますように────。
私は心が狭いから、伴侶の女性のことまでは祈れない。
けれど。
彼のことだったなら、遠くからなら、祈れる……から。
そうして彼女はお祈りを終了すると、ふらりと祭壇前を後にした。
後方の人がずいぶん長いお祈りだったな、と。不思議そうに美しい顔の黒髪の女性の背中を見やる。
フィオナが、これからどうしようか、とセカンドライフの計画を立て、入口の天井にあるステンドグラスを見上げた時だ。
太陽の象徴であるステンドグラスの丸みの奥から、強い光がこちらに向かって降り注ぐ様をぼんやり見遣る。
今日はこんなに強烈な晴れの日だったんだなぁ、など。これまたどこか壮大にズレた感想を持つ彼女であった。
な〜んか、眩しいなぁ、と。
光が目前まで迫った時に、めまいを覚えてこめかみを押さえ。
な〜んか、気持ち悪いなぁ、と。
そのまま礼拝の椅子に手をつき、カクン、と膝が折れてから。
フィオナは痛む頭を前に、多分、意識を失った。
再び意識が浮上した時、ずいぶん懐かしい匂いがするな、と。
彼女はしばらく天井を見上げ、そろりと視線を動かした。
あ、ここ、初等校の寮の部屋。
思い出したら、つられるようにベッドを跳ねて机に向かう。
机の上には配布されたばかりの真新しい教科書と、学用品として支給されていた指定カバンや、安い文房具の束やらが無造作に置かれていた。
そう、普段はピシッと背筋を伸ばし、指先の一本までも気取って動かしているのだが、フィオナは誰も見ていない場所で、ひたすら怠ける癖がある。
それが、卓上に無造作に置かれた学用品の数々である。彼女はそんな机を見下ろし、信じられないものを見たように、大きく空色の目を見開いた。
そこそこ記憶力も頭も良かった彼女は、当時からトップクラスの成績を出していたのだが、少ししてすぐに仲が良くなる親友のサラエラが、彼女の成績の良さの秘訣を知りたいと、無理やりこの部屋に押し入って来た時に、「い、意外なものを見ましたわ。フィオナ、貴女、これは少し酷すぎましてよ? 少しは整頓なさったらいかが?」と、美しい顔を歪めて苦言を呈してきたのである。
それ以来、フィオナは一応、文具を引き出しにしまうようになるのだが……あのサラエラにもう一度会いたくて……このままにしておけば、もしかしたらまた彼女に会えるのではないだろうか、と、フィオナは乱雑な机の上をそのままにする事にした。
さて、時の大聖堂を観光していたはずなのだが、何故自分は此処にいるのか? と。
次に目に入ったのは廊下へと通じるドアノブだ。
確か、此処を出ていくと臙脂色の絨毯の床が。突き当たりには古臭いサイドテーブルと、その上には日々異なる花が活けてあった記憶が浮かぶ。
道なりに角を曲がれば、寮母室と談話室、その正面にはこれまた古〜い作りではあるけれど、一階の隅々を臨めるような手すり付きの小広い廊下と、一階中央にある玄関へ向かう階段が、両サイドから丸みを持って降りていくような景色が浮かぶ。
まぁ、どうせなら、学生気分をもう一度味わおう。
フィオナはドアノブに手をかけて、ここで再び目を見開いた。ドアノブに対する自身の右手が、気のせいではなく小さいのである。
これではまるで……子供の手だ、と。
ふと思って、思ってフィオナは、ドアノブを最大に回すと、小走りでその廊下を駆け抜けた。
彼女の古い記憶によると、寮母室の隣の談話室には、共用の大きな姿見が掛けてあるはずだったのだ。
果たして、その場に着けば、彼女は本日三度目となる空色の瞳を見開いた。鏡に映った自分の姿が、幼いのである。何もかも。
身長も確かにこの頃は、魔法の才能のある孤児として国に引き取られたばかりであって、同世代の子女より一回りは小柄であったし、この頃にはまだアルベルトと出会っておらず、相反する葛藤を持ちつつ、彼とぶつかってもいないため、表情筋も少しはあった。
要するに、この頃はまだ、純粋に微笑むことができたのだ。
試しに、ニコッとしてみると、子供故の大きな瞳と、上がる口角の効果があって、我ながら可愛らしいと思えるほど。
プニプニの頬を両手でグニグニ回せば、少し赤みも差してきて、我ながら美少女じゃないか、とフィオナはだいぶ愉快になった。思い通りに動く筋肉は、これほど素晴らしいものだったのだな、と。
そうだ、聖堂に行こう。
鏡に映った談話室の端の、花瓶にあった白ユリを見て思う。
初等校にも聖堂があり、それまできらびやかな世界を全く知らずに育ったフィオナは、キラキラなもので飾られた聖堂が大好きだった。
そうだ、仕事で忙しくなり、もう十数年ご無沙汰なのだが、そもそも聖堂が好きだったのだ、と彼女は記憶を掘り起こす。
特に、初等校の聖堂は、大切な思い出が詰まった特別な場所である。好きにできる夢ならば、その大切な思い出に浸りに行こうではないか、と。
フィオナは人の気配が薄い構内を、足取り軽く進んでいった。
目的の聖堂は、塀と木々に囲まれた初等校の構内の、割と端の方にある。
壁は歳月のせいで黒ずんできていたが、それでも偉大な神の威光を外まで醸し出す、立派な造りをした建物だった。
けど、果たして……今日がその日だっただろうか? と。
自分の心を震わせた、この世で唯一と言える姿を……あの頃はまだ小さかった清廉な姿を見つけて、フィオナの足は動きを止めた。
思わず挙動不審な態度で、視線を左右に振ってしまうが。
でも……。
徐に振り返る、少年の顔を見て。
あぁ……懐かしい……ここで、初めて出会った日、私は己の自尊心の高さから、彼の言葉を受け入れられずに、彼との間に埋められない溝を作っていったのだ。
階級の知識もないのか、平民が。ジロジロ見るな。この青のタイが目に入らないのか? と。
目の前の少年は、記憶の通り、驚きの顔を浮かべて、しばしフィオナを見たようだ。
来たる無遠慮な彼の言葉を予見しながら、フィオナは非常な懐かしさと、未だ彼に対してだけ弱くなる心を守るよう、意を決して冷たい瞳に対峙するのだが……。
「あ……いや……その、だな」
アルベルトは歯切れも悪く、アイスブルーの視線を右へ左へと泳がせる。
「きっ、綺麗な、髪だな……! な、名前を聞いてもいいかっ……!」
………え?
である。
フィオナは瞬いた。
しかもこの間、かなりの、間が空いた。
思考停止から、耳を疑い、呆然として見上げれば。
「だっ、だから! お前の、名前!!」
「……フィ……フィオナ、です、けど……」
この頃はまだ、姓を貰ってはいなかったので、イングラムの姓は名乗れない……はずだ。
やはり呆然として名を告げ終えると、彼はアイスブルーの目元をほのかに染めて。
確か、次に掛けられるのは、黒髪のくせに白(フィオナ)とは! 全く、傑作な名前だな! お前の親の無知が知れる、ハハハッ、だ。
物心がついた頃には既に居ない両親だったが、あぁも面と向かって蔑まれると、さすがに頭にくるものがあったのだ。
いくら国立の教育機関とはいえ、学力の高さで取ってくれるものとは言えど、所詮、庶出の自分である。
無知な平民などいくらでもいるし、例えフィオナの両親が言われるように無知だったとて、それを笑うところまでする貴族様とは如何なものか。
だが。
同じ轍は踏まぬと、固く誓ったフィオナである。
彼にどんなに酷い言葉を掛けられようと、此処で怒りに任せてしまってはいけないのである。フィオナの親が無知だったのは、そう、単なる事実なのだから。
しかし、二度目の彼は違った。
「そ、そうか。俺はアルベルト。アルベルト・レクイアス。この学園では、青のタイは貴族を示している────」
緑のタイの平民風情はそんなことも知らんのか。これだから卑しい身分の生まれは。
いつまで不躾に見ているつもりだ。気持ち悪くて反吐がでる。
これからは青のタイの生徒を見たら、頭を垂れて端に寄れ。
罷り間違っても庶出の生徒は、貴族に気安く声を掛けるな。
────それが、記憶の中の声。
より無意識に体が強張り、来たる言葉に身構える。
と。
彼はいっそう恥ずかしそうに、けれど視線を外さずに言う。
「だ、だ、だが、な。こんなもの、ただの飾りに過ぎん。ここで会ったのも何かの縁だ。もし何か困ったことがあったなら、いつでも……そう、いつでもいいから、声をかけてくれて構わない、から!」
そこまで早口で言い終えると、吐き捨てるように体を反転。逃げるように去っていく。
フィオナは驚き、瞬きをして。
「あ、あの! レクイアスさま……!」
結局、最後まで呼んだことのない名前で呼べる訳もなく。
呆けたような顔を浮かべてピタリと足を止めた彼へと。
「あ、あの……ありがとう、ございます。髪を褒めて貰ったのは、その、初めてで……嬉しいです」
と、思いがけず染まった頬を、隠すように頭を下げれば。
「っ!? き、綺麗なものは、綺麗だろう! それにっ、アルベルトだ! 家名じゃなくて、アルベルトと呼べ! 様もいらない!」
また、何故か吐き捨てるように、逃げるように去っていく。
一年のうちにおよそ四度しか顔を合わせない将軍が。
貴族の中の貴族として、庶民と太い一線を最後まで画した将軍が。
風の噂で、やはり名門貴族のご息女と結婚すると……想像の中で奥方になられた若い女性と並ぶ姿を思い……何が起きたのか分からない、この夢のような世界において。
再び……もし二度目を繰り返すなら、限りなく陰鬱になりそうだったこの初めての出会いを終えて、一度目とは全く異なるお互いの言動を、やはり、自分に都合のいい夢の世界なのかしら? もしかしたなら知らない場所で、私は一度死んだのかしら? と。フィオナが不安になっても仕方ないこと。
深い後悔しか残らなかったあちらの世界では、一目惚れの焦燥と、認められない自尊心、それでも努力と幸運を重ね、ほんの後ろ姿くらいなら見える場所まで登ってみれば。
そもそも彼とは住む世界が遠すぎたことを実感し、どうあがいても近づけなかった理由を確と認識し、それでもせめて、友としてでも近くに居てみたかったのだ……と。
正直に言えば、一日でもいい、恋人になってみたかった。
もっと欲をかくならば、そう、あの女性と同じ場所、彼の伴侶になりたかった……と、心がギュウッと締め付けられる。
彼に対して情けないほどの劣情を抱いていたのだと、己の身の程を知り……馬鹿な期待をしたものだ、と。
大きく落胆した後は……結局、消化しきれなかった燻る淡い初恋を、死ぬまで表に出してはならぬと、蓋をして、重石を乗せた。
思い返しても、そこそこ長い……長い、付き合いだったと思う。
ここだけは少しだけ、自惚れてもいいはずだ。
一切の接触がなかった訳でもないのだし……ただ、共通の友よりも、暖かな交流が無かっただけで。
十二の初等教育間ではクラスが重なることもなく。
十五の中等教育間では、能力に応じた実技クラスで顔を合わせはしたものの、共通の友がいない場所では毎度のように嫌味の応酬。
あれを世間一般に、一目惚れと言うのだと、これを世間一般に、初恋と言うのだと。己の自尊心が高過ぎて、気づいた頃には既に埋められぬ溝が間に出来ていた訳で……。
なのに。
この世界の彼は、あんなに優しい人なのだな……と。
フィオナは胸が詰まる思いがして、胸を押さえた。
これまで良い生活を送ってきたのだろう。これからも良い生活だけを送る予定の人ではあるが。
年の割には体つきもしっかりしていたし、上背もこの頃からあったのだ。
しかも、益々、体つきはしっかりしてくるし、身長もかなり上まで伸びるのだ。
本当に理想的な男性なのだ。金の髪はツヤツヤしているし、自分のものよりもっと薄くて上品な、アイスブルーのあの瞳。
あの瞳に見つめられたら、太陽だって姿を隠すと本気で思っているほどだ。フィオナはあれほど完璧な男性を他に見たことがない。それに対して、自分はなんてみすぼらしい女なのだろうか、と。
あの頃も、そう。
いつも、アルベルトと嫌味の応酬をした後に、自己嫌悪に浸っていたのだ。
彼があまりに眩くて。
制服は共通だったが、さりげなくつけているコロンはいつも上品な香りがしたし、アクセサリーも控えめながらオシャレ感が満載で。
持ち物だって常に一級品。
憧れていた筆のお店の付けペンを持つ姿を見たとき、危うく理性の蓋が壊れて、見せて欲しいと強請ってしまうところであった。
まぁ、あれは程なく相手にバレて、勝ち誇ったような顔をされ、庶民には手が出るまいと、小馬鹿にされた記憶もあるが。
いいんだ。
悔しくて地団駄を踏んだが、次の誕生日の朝に、サラがその付けペンをくれたんだ。
心の奥で大事にしていた。
だって、お揃いだったんだ。
サラは気づいていなかったけど、アルベルトと同じシリーズの……色違いだったんだ、もらったペンは。
そうか、十年以上も愛用してきたペンも…今は、存在すらしないんだな、と。フィオナは無意識に胸ポケットを見下ろした。
どんな制服を着ることになっても、あのペンは常にここにあったから。
ついでに緑のタイが目に入り、やっぱり、夢の中でも自分は平民なのだな、と。少し落胆したのは、仕方ないこと。
どうせなら、彼と同じくらいの大貴族に生まれたかったなぁ、などと、夢の中で夢想して、それはそれで欲張りすぎか、とフィオナはクスッと笑みをこぼした。
そういえば、いつでも声をかけていいと今回は言われたな。
いいのだろうか。
初対面ではああだったけど、中等機関で別れてからは、庶民派路線になったと聞いた。
幼年時代は他の貴族と同じで、庶民を見下していた素振りだったから……その三年で何があったのか。
少し、騎士学部をのぞいてみたい、と思ってしまったフィオナだった。
互いに敷地は広いのだが、隣接していたのだ、二つの建物は。
会おうと思えば、広場で会えた。
少し森へ入ったところの柵の近くなどは、格好の逢引場所だった。
そうした噂はよく聞いた。
アルベルトの顔を無意識に三年も思い浮かべていた程だ。
もしかしたらそこへ行ったら彼の姿が見えるかも、と。あの時はなぜそんなことを考えてしまっているのか理解できていなかったのだが、四十まで生きてしまえば、諸々の機微が理解できる。
こんなに好きだったんだな、と。
またここでも寂しくなるフィオナであった。
一方で────。
その日、彼の心の中は激昂、そして大荒れだった。
国内きっての大貴族。レクイアス家に長子として生まれついてしまった彼の名は、アルベルト。
下に弟が一人と、妹が二人いた。
家は裕福、貴族の中の貴族としての教育を受け、けれど、庶民あってのものと確と言い聞かせられてきた彼の人生最大の失敗は、ある才覚ある一人の女性を、己の自尊心の高さから、初対面でこき下ろし、馬鹿にしてしまったことから始まった。
それは初等校の入校式後の事だった。
物心ついてからずっと煩わしく思っていた、不特定多数の貴族女子からの積極的なアプローチ。思春期に入ろうかという時分において、その煩わしさは彼の人生の中で最高潮に達していたのだ。
けれど、貴族の中の貴族として、振る舞いは完璧にせねばならい。
せめて息抜きをと選んだ先は、人の気配の薄い聖堂だった。
夜にはパーティが開かれるため、貴族の女子はその為に、昼過ぎより準備に入るのだ。だから、誰にも会うまい、と。疲れ切って無表情にさえなっていた彼の視線の先に、不意に先客が映り込む。
その後ろ姿は鮮烈だった。
高潔にして、純粋、可憐。
これほどの覇気を纏った女子というのは、いっそ、貴族の世界でもお目にかかった事がない。
彼の気配に振り返り、気だるげな瞳と重なった時。
後ろ姿より美しい、彼女のかんばせに息を飲む。
制服のタイに目が行ったのは、後から思えば、大きな期待ゆえだったのだろう。そう、それが平民を意味する緑色をしていた事に、一瞬で彼は落胆し、落胆しながら、ここまで己の心を奪うその相手への激情で、思いもしない感情が口をついて出てしまう。
彼女は目を見開いて、驚いた顔をしていたか、と。
思い返しても、酷い出会いだ。
悲しそうな顔をして、けれどキッと睨んだそれも、美しいと思った自分は、あの時から魅入られていた、と。
彼女だけでなく、彼女の親をも侮辱する言葉が零れてしまって、心惹かれてしまった自分を隠したかっただけなのに、決定的な溝が生まれた、最大の不幸の始まりだった。
彼女は見目が麗しいだけでなく、才能もあり、努力家だった。
いつも素晴らしい機転を発揮するたびに、忌々しげな顔をしながらも、内心は誇りでいっぱいだったアルベルトは、黒髪の白の名を持つ平民の女性、フィオナを、人知れず想い続けていた。
けれど彼女を前にした時、暴走する内心の照れや、抱きしめたい葛藤や、独り占めにしたい欲求や。同じ学び舎にいる平民の男性たちとの仲の良さ、彼らからの羨望や、伴侶にと望む気持ちをありありと目にするごとに、嫉妬や矜持、傲慢さが前面に出てしまい、本来なら別へと向くはずの悪感情が、なぜか全てフィオナへと向いてしまうという悪循環。
喧嘩するたび、家で大いに落ち込む事になるのだが、ある意味頭の悪かった彼は、それでも、きっと、いつかは……と、フィオナを抱ける時が来るはずだ、そう信じて疑わなかった。
果たして、それを信じ続けておおよそ二十数年後。
後継を作らぬ彼にごうを煮やしてしまった陛下から、無視できない命令が降りてきた。
よく知りもしない二十も下の、どこかの娘を充てがわれてしまった、という。どうにもならない憤怒の行方は、その日、唐突に辞表を出して雲隠れしてしまったフィオナの話を聞いて、深い、それは深い、落胆へと変わっていったのである。
彼の想いびとであり続けたその娘は、一部の貴族男性の中でも高嶺の花だった。
貴族女性に劣らぬほどの見目麗しさ。寡黙さと貞淑さ。二十代にして地の第四位(クアトル・テッラ)まで上り詰めた才覚と、レクイアス家と引けを取らない大貴族、クシュナトル家のサラエラとの交流と。
汚点をいうなら、まさにままならぬ、自分との相性の悪さだが。
そう、あれは、少しだけ良かった事もあるから、大義名分として語っておきたい。
同性との摩擦を避けられなさそうな彼女の運命は、不本意ながら、自分が“さも”彼女を疎んでいると態度に出す事で、多くの貴族女性の共感を誘い、そこまで酷いいじめにはならなかったのだ。
貴族女性の陰湿さは、心底引くレベルであるからに。
彼が彼女を嫌いだと態度に出した事で、それが大いに貴族女性の慰めとなり、あっても陰口や嫌味程度で抑えられていたのである。
いっそ同世代の貴族男性たちへも、フィオナを手に入れる事でレクイアス家に睨まれる、という暗黙の図式を示せたために、想いびとを取られる事にもならなかった幸運はあるが。
それでもフィオナは平民とはいえ、アルベルトの目の届かぬ所では、どこまでも絶大な人気があったのだ。
事実、二人目の副隊長はフィオナより十も年下のくせに、人目を憚らず堂々と口説き続けていて……同世代の男にしか牽制が効かない、という焦りも大いにあったのだけど。誰がどう見てもフィオナにはそんな気がなかった為に、許していたんだからな、とアルベルトは内心すごむ。
一方で、心のどこかでは、わかっていたつもりだったのだ。
家は弟が継げばいい、と心底思って、フィオナのことを想い続けてきたが。
あの頭の良い弟は、兄の威光に隠れまくって、とうの昔にそちらはそちらで気に入った平民女性と、さっさと夫婦になっていたりする。
息子がいるのに娘が家を継げようはずもなく、年高ではあれ、独身のこちらに、これまた名門貴族の女性をあてがって、せめて正当な後継を作らせよう、という動き。
これでも貴族の中の貴族であるからに、ままにある話であると、冷めた心では理解していた。
ようは、子供さえ居れば良いので。
相手には悪いと思うが、子供は作らせてもらう事にして。
だけど、想いびとはフィオナのままだ、と。これまた悪い頭で妙な一途さを出した所へ、舞い込んできた、突然の、失踪。
あいつは、そう、いつだって、ずるい、と。
勝手にトントン拍子にて、魔道士の隊長職についてしまったものだから。
せめてそこは自分が先に将軍になりたかった、など。
ここでも自尊心を傷つけられたアルベルトである。
好きな娘の前でだけ、ちょっとは偉そうにしたかったのだ。
すごいと思ってもらったり、尊敬されたりしたかったのだ。
それで少しでもあの瞳に映り込むことができたなら、本望だったのだ、未だに幼い彼の心の中では。
フィオナの前では常にかっこいい男でありたかったのに、あっさりその機会を潰されてしまった過去だった。
必死に登って将軍職に就けた時には、ここでも人知れず自室で嬉し涙を流したほどである。
これで同じ会議に出られる、魔道士塔にも入り放題、これからは堂々と話しかける事ができるぞ、と。
この辺りでわかるように、アルベルトも外見と中身が剥離した、残念な部類の男であった。
初等校の卒業式では、自分のタイを望んで集まる女子どもの中に、彼女の姿が無かった事に大いに落胆し。
中等校での合同卒業パーティでは、すでに拗れていたけれど、それでも堂々とフィオナと踊れるようにと、並んだ女性全員と踊る、と予め噂になるように小細工までしたというのに。
目的の彼女は卒業式にさえ出ない、という暴挙に出たのだった。
大量に居る彼女のファンの男どもと同じように、彼女のドレス姿を楽しみにしていた彼は、その日、シャワーを浴びながらひたすら涙を流すのだった。
後日、サラエラとの会話を盗み聞きした彼は、ドレスを作るお金が無かったという彼女の何気無い声を聞き、それならなぜ俺に頼まなかったのだ、と憤慨までしていたようだ。
ちなみにその後、高等校の卒業式や、魔道士団への入団パーティ、その他、彼女が関わりそうなたくさんのパーティがあるたびに、都度、こっそりと彼女に着せたいと願ったドレスを新調していたアルベルトである。
もちろん一度も使われたことが無かったのだが、それらのドレスは未来の彼の奥方の為の部屋に、そっとしまわれていたりする。
地の第四位(クアトル・テッラ)に就任し、二人目の副隊長が着くまでは、目に余る安物ドレスのオンパレードだったのだけど、その点については……あの男は大嫌いなのだが、こと、彼女に似合うドレスを都度用意してくれた功績を讃える点だけは、アルベルトはそいつのことを好いていた。
ドレスを用意するのが自分であったのなら、それに越したことは無かったのだが。ついぞ頼まれる事はなく、それでも、あの男が選んだドレス姿は美しかったし……四十にもなるというのに、あの若々しさや、かたや落ち着いた大人の女性の艶のある様子といったら……どれだけ夢の中で彼女を汚したことだろう、と罪悪感も少し、ある。
まぁ、こんなに執着心の強い彼だったのだけど、暴走せずに済んだのは、彼女に嫌われているという周知の事実と、彼女が一度も男をそばに置いたことが無かったという、その貞淑さにあるのだろう。
あれほど美しい娘だったのに、フィオナは誰も選ばなかったのだ。
それにホッとしていたし、救われていた。
もちろん、貴族側からの彼女へのアプローチは、小さい芽のうちに、睨みを効かせて全て潰してきたアルベルトである。
レクイアスの睨みに耐えたのは、クシュナトル家のサラエラだけだった。サラエラは女だし、フィオナのことを折に触れては助けてくれていた訳で、恩義に報いるようにそれとなく、クシュナトル家の事業の手助けをしていた訳だが……あの聡い貴族女性は、果たして彼の想いびとが彼女であった事に、気づいていたのか、いないのか。
アルベルトは本当に、フィオナに惹かれていたのだった。
恥ずかしいほど、彼女が好きで。嫌われることをした自分さえ、当然と思いながらも、いつかきっとと奇跡に縋って生きてきた大馬鹿者だった。
抱きたくて、抱きたくて、彼女との子供がいたら、どんなに幸せな人生だっただろうか、と。
海の向こうでは四十を過ぎても子供が産める、という書物を抱え、そろそろ声をかけてもいいだろうかと、プロポーズの準備さえしていた彼である。
まぁ、相変わらずそっけない相手の態度に、毎度深く落ち込んでいた彼であったのだけれども。
だから、彼にとっての神の御技は、後悔だらけの半生を変える、まさに奇跡の所業だったのだ。
好きでもない女の横で、永遠の愛などという、安っぽい誓いを言わされそうになる直前。
聖堂に祀られた神に、心の底から祈りを捧げていた彼である。
神よ、どうか、願いを聞いて頂けるなら。
愛していたのに、ずっと酷い態度を取ってしまった彼女との関係を、一からやり直させて下さいませんか、と。
もし、もう一度チャンスを頂けるというのなら、今度は絶対に、彼女と仲良くします、と。
傷つける言葉は絶対に言いません。
未だに言えない愛の言葉も、きっと口にしてみせますし、彼女と結婚もしたいから……そう、色々頑張ります。
真剣に。
真剣に。
人生で初めて神に縋った、残念な男の祈りであった。
きっとこれが、
*****
そして途切れる、中途半端小説の笑い(笑
わーお。
ここで終わるのか。
でも甘さを感じられて良かったですよね? と、読者様に無茶振りをして結ぶ私でありました。
お洒落な本を作るのが夢です* いただいたサポートは製作費に回させていただきます**
