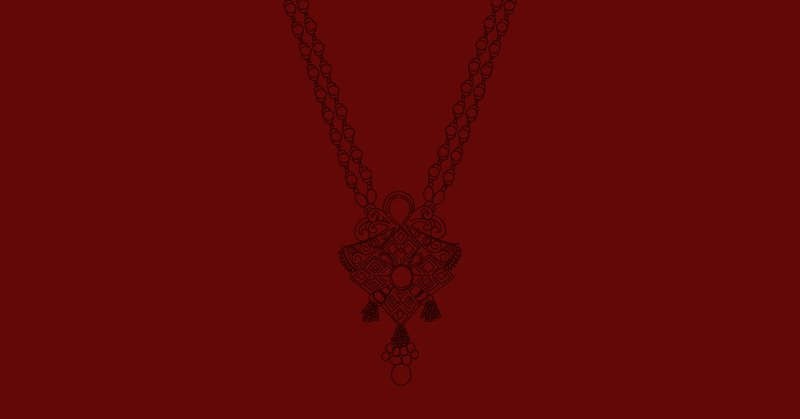
斜陽の紅玉と
紅い陽が斜めに差した聖堂の一室で、僕は同級生の吉瀬(きせ)の逞しい腕に抱かれながら、敢えて低く、くぐもる声で、愛おしそうに名を呼んだ。
「吉瀬……」
「もう黙れ、真朱(まそほ)」
乱れた制服と、解かれた臙脂(えんじ)のタイ、ベルトも申し訳程度にボトムの穴に通っただけで、いかにも直前の様相だ。
誰よりも信頼している相手だけれど、僕の心臓は不安で早鐘を打っていた。もうそこまで聞こえる複数の足音に、気付かないふりをして吉瀬の首に抱きついた。
ガチャリ、と回った後に、重々しい扉の音が鳴る。びくりと震えた僕の体を抱き留めるようにして、吉瀬は部屋を訪れた相手に視線を向けたのだろう。赤い革張りのソファーの上で、横目で見遣った吉瀬を見る。
それからゆっくりと、同じ扉を向いた自分だ。若いのに白髪みたいな、シルバーブロンドの男を見遣る。俺達の情事を見ても、眉ひとつ動かさない、昔からいけ好かない男が立っていた。
「これは……吉瀬様。邪魔をしてしまったようですね」
白髪の男の前に立つ、黒髪の御堂(みどう)が口を開いた。後ろに控える鳳翔(ほうしょう)の付き人の一人であって、壁も雑用も夜の相手もこなす、五堂家の一である。
冷静なふりをして、実は血気盛んな御堂隆久(みどう・たかひさ)は、吉瀬に組み敷かれた僕を見て、軽蔑するような顔を浮かべた。前々から気に入らない奴だと思っていたが、本当に気に入らない奴だな、と。心の底から思ったような顔である。
後ろに控える鳳翔は、何も感じた気配がない。気配はないが厳しい奴だ。きっと僕の目的は達することが出来たのだろう、そう思って吉瀬の芝居に流されることにする。
「いや。いいよ。別にここじゃなくても。見たところ俺の方が邪魔したみたいだし。真朱、俺の部屋に行こう」
「ん……」
甘い声を出す。
吉瀬は良い体格だけど、細めに引き締まった男だから、見た目では同じ男の僕を持ち上げるのは大変そうだ。だけど、この国の「鬼」らしく、持っている力は申し分ない。軽々と衣類がはだけた僕を抱き上げ、「邪魔したな、鳳翔」と、横をすり抜けて去っていける。
吉瀬家は鳳翔家に並ぶ鬼の家系だ。数百年前に外から来た鳳翔家に対し、純国産の権威ある強靭な家である。代々、力を落とすことなく続いている三家の並びで、ここに灰綬(はいじゅ)家が加わって鬼の三家と呼び習う。
つまり鳳翔の家の子に対し、対等を示し得る、吉瀬家の継嗣、それが吉瀬瑤千(きせ・ようぜん)だ。
吉瀬は僕を抱いたまま、予定通り聖堂を後にする。重たいドアを抜けた時、やっと息が吸えた気がした僕だった。誰でも使える聖堂だけど、この学舎の中ならば、鳳翔家の縄張り感がある場所だから。
「はぁ〜〜〜……助かった……ありがとうね、よっちゃん」
ぎゅう、と首に抱きついて、僕はお礼の声を出す。
よっちゃん、瑤千(ようぜん)は、「まだ気ぃ抜くな」と注意した。
「そのまま首にくっついてろよ。寮に戻るまで気ぃ抜くな」
「うん……」
でも本当にありがとう。小声は彼にだけ届いただろう。僕はそのまま横抱きで、男子寮へ連れられていく。
戻ってきたのは吉瀬の部屋だ。一棟丸々、吉瀬の縁者で占められている。僕は最上階のスイートルームと言える、吉瀬の寮部屋の一室を借りている。そこまで戻って、やっと床に下ろされた。
「重くなかった?」
「お前はもっと食べた方がいい」
また痩せたんじゃないか? と、はだけた胸元を触られた。
同じように上から下へ自分で撫でて、肋の骨の浮きを見る。
「そうかも。だってすごいストレスだったんだ。でも、今日からは前くらい食べられるような気がするよ」
細く笑った僕の頭を、わしゃわしゃと撫でつけた吉瀬だった。
時刻は夕刻で、食事を持て、と、吉瀬が食堂に電話する。僕たち鬼の家系の主食は血だけれど、普通の人と同じような食事を補足的に取っている。吸血行為は忌避されるので、仕方なく自分達で回す風だ。だから山奥の特殊な学舎で、成人するまで篭って過ごす。私学であるので普通の人間は、滅多に入れない。血の濃い薄いはあるけれど、ほぼ全員が鬼である。対外的には偏差値高めの、得体の知れない学校だ。
山奥の男子校。甘美な響きかも知れないが、まぁ、確かに甘美なものが、ないわけじゃない実情だ。外の仕組みに合わせると、僕は高校一年生。吉瀬も鳳翔も御堂も同じ。たまたま学年が重なった。もう一つの灰綬(はいじゅ)の人は、高校三年生、先輩に居て、今、この学舎の学生会長だ。
成長期である男子二人のために、料理が次々と運ばれる。この山奥でどうやって? と思うくらいの豪華さだ。もちろん、この寮の料理長も吉瀬家の縁者であって、吉瀬の世話をやく先輩達も吉瀬家に仕える人たちだ。
流石に僕も先輩方にお世話されるのは怖いから、料理が運ばれてくる時は自分の部屋へ篭って過ごす。吉瀬は非常にフレンドリーに見えるけど、本家を継ぐ予定の長男だ。だから意外と仕事もあって、そういう話は耳に入れないように、僕は僕なりに気を使い、この部屋で暮らしている。
僕の姓は紅堂(こうどう)だ。紅堂真朱(こうどう・まそほ)。堂で気付いてもらえるように、鳳翔家を支える五堂家の一である。そうした目で見ると如何にも僕は、鳳翔家からのスパイに見える。だからそこから分かるように、僕は吉瀬家の従者達から、冷めた目で見られているのが日常だ。鳳翔家にも仕えない僕は、そちらからも嫌われている。特に同じ学年に生まれついた御堂には、虫ケラを見るより冷たく、嫌悪されている風である。
実家からも絶縁というか、勘当されている。理由は鳳翔を拒絶したからだ。そんな僕を拾ってくれた吉瀬である。もちろんタダではないけれど、過分な優しさに守られて、僕は苦しい僕の人生を、足掻きながら生きている。
嫌ったのはあいつじゃないか。そんな痛みを抱えながら。それまでに募らせた憧れと愛しさの分が、憎悪と嫌悪に変わっただけである。流石に分別はついているし、だから、この気持ちの行き先は、自分の中にだけ留めるもので、だから……僕は家を出た。
一人じゃ食べていけない中学生。鳳翔に下らなければ、生活も学費も面倒を見ないと言われた僕は、一縷の望みを賭けて吉瀬に頭を下げたのだ。高校を終えるまで面倒を見てほしい、と。その先は人の社会で人に混ざって生きるから、と。血を飲まなければ発狂するし、定期的に必要になってしまうものだけど、そこから先はどうにか自分で対処しようと考えた。せめて人間の社会に溶け込める年齢になるまでは、誰かの助けが必要だったのだ。子供の頃から採血されるたび、お前の血は美味い、と言われていたこともある。だから吉瀬には血と体を捧げるつもりで、二人きりになった時、土下座して頼み込んだ。僕には誰にも負けない「位」の、特別な保護者が必要だった。鳳翔に立ち並び、僕の親にも負けない人が。
小さなベッドにうつ伏せに倒れた僕は、いつもこの悔しさを押し込める。一人では生活できないことや、吉瀬の善意にぶら下がっていること。実際、吉瀬は血を飲むものの、僕を夜の相手には選ばない。僕たちは血を飲むと興奮するから、結局そっちとセットになる雰囲気だ。なのに血を分けてくれるし、何から何まで面倒を見てくれる。対外的な立ち位置としては、僕は吉瀬の恋人だ。もうずっと側に置いている、特別に大切な恋人だ。吉瀬の一番か二番あたりの従者には気づかれていそうだが、そこから先には睨まれるので、黙って貰っていると認識できる。吉瀬の周りは吉瀬に似て、いい人が多いと思うのだ。その人達にも僕は結局、甘えているということだ。
さて、食欲が戻ると言ったけど、僕には食欲なんてあるはずもなく。けれど食べなきゃと苦笑して、ごろりと転がり天井を見遣る。少なくとも僕のことを匿ってくれる吉瀬のために、自分の血を少しでも美味しいものにしなければ。準備が出来た旨の言葉を聞いて、豪華な食事が犇めきあった、ダイニングへ向かった僕は、今日も感嘆の息を吐く。
「いつも凄く豪華だね」
「そうか? いつも通りって風だけど」
尋常じゃない桁を動かす御坊ちゃまである彼にしてみれば、当たり前の待遇のようで、これだから金持ちは、と。苦笑した僕のことを、さっさと見切ったように、早く食べよう、と誘っていって好きに箸をつけていく。粗野かと思えば食べ方は美しく、やっぱ良い生まれなんだよな、と、僕は小さく嫉妬した。
使われる方じゃなく、使う方に生まれたら。
そんなことも掠めるが、僕にはそこまでの器はない。
反逆のようなことをして見せてはいるけれど、僕には自分の本質が、捧げる方であるのが分かる。吉瀬に何をされても良いから、庇護して欲しいと願ったように。捧げたかった自分の主に、裏切られたと思ったあの日から。僕はまた今回も、全力で逃げに走るのだ。
「どうかなぁ? あれで鳳翔、諦めてくれたかな?」
「ん?」
「一応、真朱(まそほ)の事は、承(しょう)にも頼んであるけれど」
力づくでこられたら、真朱には悪いけど、承に怪我されたら困るから、引けって言ってある。茶碗を持って黙々と白米をたべる傍に、吉瀬はそう呟いて報告をしてくれる。そう。あれはパフォーマンス。僕と吉瀬の仲がどれだけ良いか、見せつけるためのものである。
「鳳翔は別に僕には興味はないよ。諦めてないのは僕の親だけ」
それも御堂が正しく報告してくれると思っているし、そろそろ流石に諦めてくれるかと。
そう、ことの発端は、ちょっとした噂話から。僕を家から追い出して、勘当した体を装う両親が、僕の「使い勝手」を諦めきれず、復縁を迫ろうとしているらしい、と聞いたから。
その復縁の方法が鳳翔との婚約で……どこをどう持ってきたらそうなるんだ? と疑問だらけだ。下の家が上の家の住人へ、婚約してくれ、なんて頼んでも、無視されるだけだと思える鬼社会の話である。だからそれは僕の親の、いわば、夢物語なのである。
「そもそも、僕と鳳翔の気持ちの開きとか、御堂が散々、五堂家の会合で、ネチネチちくってくれてる筈なんだけど。ワンチャン、僕の血を鳳翔が気に入るかも知れない、って。諦めきれないらしい、馬鹿な両親なんだよね」
因みに鬼社会では、男同士でも結婚できる。流石に子供は女性が要るけど、血の好みで生きる僕たちは、結婚するだけならば同姓でも忌避はない。それぞれの家の家長は生まれた子供のうちで、最も強いものを据える風習だ。だけど、大体、初めに生まれる男が強いので、ほぼ長男の世襲制を繋いでいく雰囲気だった。長男教ではないけれど、実際恵まれる率が高いから、そこは仕方ないんじゃないかと思うのだ。
僕もこれでも紅堂家の初めの男。ガリガリで弱そうだけど、頭の方だけは恵まれている。恵まれていると言っても奨学生になれる程度だ。世の中と……の前に吉瀬と張り合おうと思っても、あっさり負ける程度の「頭」しかないけれど、それでも本気を出していない吉瀬達だから、学年では上から三番目くらいには入れている。
学舎は吉瀬と鳳翔と灰綬(はいじゅ)の三家で運営されている。だから僕が生家から勘当されていたとして、関係ない、というのが有難い場所である。例え鳳翔が多少なりとも僕の家に興味があって、僕の裏切りとも言える行動に怒りを感じても、残りの二家が吽(うん)と言わないと、放逐するのは無理なのだ。在籍を許されていることからも、僕はそう動きを読んでいる。まぁ、そもそも鳳翔が「僕に興味ない」のは知っているし、そういうことだよ、と両親に伝えたいのは山々だけど……聞く耳がないのでは全て無駄、だと思ってる。
吉瀬は僕の話を聞いて、ふーん、とだけ答えたようだ。僕は小さい笑いを浮かべた。結局、吉瀬も興味がない話であって、それにも救われている僕である。
「ご馳走様でした」
「ご馳走様」
「吉瀬、飲む?」
「風呂上がりにな」
「わかった。じゃあ僕、先に、風呂に入っとくからさ。良い時に部屋にきて」
「ん。了解」
とはいえ、風呂なんて面倒だから、シャワーを浴びるだけだけど。自分の部屋に据え付けられた、風呂場に直行した僕だった。吉瀬が来るまでに風呂を済ませて、教科書と参考書を開いていく。天才じゃない僕は、こうして地味な努力をするしかない。遊ぶ友達もずっといないし、ある意味これが友達だ。僕を裏切らない、信頼できる友達だ。
黙々と文字を追い、数式を応用していると、部屋のドアが開いて吉瀬が来た。不安になる人にはそうなのだろうけど、僕が与えられている部屋は鍵がかからない。鍵は吉瀬の部屋の側にある。吉瀬は僕を閉じ込められるけど、僕は自分の領地を守れない。変だと思うかもしれないが、これが鬼社会の通例だ。愛玩は主人に管理されるものであり、それが一方通行だとして、反抗するのは許されない。この部屋は吉瀬の愛玩のための部屋の一つだ。鍵を掛けられたことはないし、愛玩になれない僕が占領してしまっているけれど。吉瀬を頼ろうと思った僕は、吉瀬が誰よりも「まとも」に見えたから、一縷の望みをかけてそうした部分が大きいわけだ。
「真朱(まそほ)、いい?」
「うん、いいよ」
椅子から立ち上がり、ベッドへ腰を下ろした。吉瀬のことは信頼している。だから食われてもいいと思ってる。そう思うからベッドへ行くが、押し倒されたことはない。
「体勢とか、いつも通りでいい?」
「いい。ほら、壁に手ぇついて」
吉瀬は僕がベッドの上で壁に両手をついていき、中腰の姿勢を取ると後ろから抱きついた。壁に押し付けるようにして、僕が逃げないようにする。逃げたりなんかしないけど、吉瀬の好みはこれらしい。
吐息が後ろの首に届いて、ざらりとした舌が動く感触。ぷちりと牙が肉を刺し、舐め取るように舌が動いた。僕は首の後ろが弱い。知ってか知らでかで、吉瀬は執拗にそこを嬲った。甘い声を出すには罪悪感が勝るのだ。必死に声を押し殺す僕のことを、吉瀬が笑って見ているのを僕は知らない。手早く飲んでしまわずに、滲む血をちびちびと嗜んでいる、吉瀬のある種、特殊な「趣味」も、何も知らない僕だった。僕の中では吉瀬だけが吸血の相手であって、そうやって嗜むものだと刷り込まれている部分があった。だから僕が吉瀬の血を飲ませてもらう時、同じようにすることを、可愛いものとして見られているという、そうした部分も知らないで過ごしていたのだ。流石に吉瀬は体格がいいので、同じように後ろから吸わせてもらうことはしないけど。
口を離した吉瀬に対して、僕は変わらぬ問いをする。
「変な味、しなかった?」
「いや? いつも通り美味いけど」
「そうなんだ……美味いなら、いいけどさ」
「真朱も飲むか?」
「僕はまだ大丈夫。そんなに理性も飛ばないし」
足りなくなってくると、狂い始めるのが分かるから。何から何まで面倒を見てくれている吉瀬の肌に、牙を立てるのには遠慮があった。だから狂いそうになる直前に、申し訳ない気持ちで頼むのだ。それだって心苦しい行為な訳で、僕には沢山の罪悪感が浮かんでる。発狂したらそっちの方が迷惑をかけるから、罪悪感と迷惑を天秤にかけて頼むのだ。
吉瀬は「そうか?」と言うだけで、邪魔したな、と帰っていった。吉瀬が興奮した姿とか見たことがない僕は、僕程度じゃ無理なんだな、と思ってた。吉瀬に恋をしている訳ではないが、良い気持ちにさせてあげられないのは申し訳なさが上回る。
ため息をつくでもなく、肩を落として、ひりつく首を忘れるように机に戻る。深夜まで続けるとキリのいいところでやめて、冷たいベッドに入るのだ。これが日常。飼ってもらってる僕の日常。朝になり、学舎へ行っても、吉瀬以外の誰かと話をすることもない。特殊な私学だからグループ学習のようなものもなく、教師と生徒の一対一で済む授業だけ。
友達が出来たらいいとか期待していた訳じゃない。攻撃されなければいいだけで、生家と縁が切れればいいだけで。学舎もクラスも吉瀬の縄張りであるわけで、僕を攻撃したそうに見え、誰も手を出せない雰囲気だった。傷をつけて吉瀬に目をつけられるのは怖いから。
だけど、どうだろう。僕が勝手に死んだなら。それなら誰のせいでもない訳で、だから、こういうことになる訳で。
「しくじった……」
悔し紛れに、小さく悪態をついた僕だった。
学舎と寮とは反対側の山の中だ。極端に元気がなくなると、一人で遊びにくるような場所である。これでも僕は五堂家出身なんだ。その辺のクラスメイトよりは力が強い。気配にも敏感だし、つけられていないかの確認もした。僕と同じレベルの奴が手を下しにくるとも思ってなくて……せいぜい切り捨てられる程度の手下がくると思ってた。
前日、吉瀬に吸わせた首の傷跡の他、岩にぶつけて折れた腕や、その周りの組織から、じわじわと流れ出る血を眺めていたら諦めがついてきた。僕は元気を出すために訪れた山の崖の上から、縁ありそうな人物に突き落とされてしまったらしい。体をひねって着地する間もないような、力強さだった記憶が強い。振り仰いでも顔が見えず、また、気配は飛び退くように消えていた。外国の鬼の話じゃなくて、この国の話である。僕に蝙蝠に化けるような能力がある訳もなく、落ちた場所が運悪く、風穴(ふうけつ)のような場所だったことも。
「…………」
死ぬしかないか、と、肩を落とした。元気を出すために来た筈だけど、だからこそ気力が消えかけていたのである。もっと運が悪いことに、自分の血が流れたことで、吉瀬の血がほしい……と、理性が揺れ始めたのを知ったのだ。
「はぁ……」
こんなことならば、昨日、飲ませて貰えばよかった、と。痩せ我慢なんかせず、お願いしていたら少しは、と。
自分達は鬼だから、多少の怪我や傷はすぐ治る。だけど発狂はどうにもできない。足りない血で治癒が早まるわけもない。理性を無くして誰かに襲い掛かるのは嫌なんだ。それは自分が想像し得る、一番最低な死に方だった。狂った鬼は仲間内で、処分されるのが常だから。鳳翔を蹴った挙句、生家からは勘当されて、理性を失い処分をされた、馬鹿な奴、という称号がつく。自分だけならいいけれど、お世話になった吉瀬とかに、キズをつけるのは憚られた。
「…………」
痛い、なんて言葉は吐きたくない、と強がった。
左腕だけじゃなく、左足もおかしいが、激痛を無視するように這うように奥へ行く。風穴は岩だらけ。進めば進むほど肌が擦れて血が垂れる。制服は紺だから、血の滲みは見えにくい。だけど生ぬるいもので濡れていくから、どんどん自分の血液が失われていくのがわかるのだ。
僕は狭くなる方へ急いで這った。痛いのとか意識が飛びそうなことは、無視するように奥へ急いだ。丁度良さそうな壁を叩くと、出口を塞いでしまう。このくらいは簡単にできる鬼の剛力というやつだ。崩れた側面は、上手く出口を覆ってくれた。念には念を入れ、狂う前に死んでしまおうと、制服の内ポケットに入れた十徳ナイフを取り出した。
好きだよ、僕も男だし。色々ついていて便利なんだ。何がいいってこういう時のため、小さいナイフが付いているから。何にも使えそうにないナイフだけれど、自分の力があれば首の血管くらいは切れる。
「はっ……はぁっ……」
少しだけ躊躇った。柔らかい首に金属の冷たさが染みる。
吉瀬を思った。吉瀬の血を飲みたい、と思う。柑橘類が好きな僕が、好ましく思う爽やかな味がする。吉瀬くらいの鬼の血ならば、少し多めに貰ったら、このくらいの怪我は数日で治るのに。
そこまで這っては戻れないから仕方ない。鳳翔を拒絶した時、こういう未来は見えていたのかも。鳳翔……と思ったら、消えかけていた僕の憎悪が戻る。腹が立って、馬鹿にされたくなくて、首に当てたナイフを思い切り突き刺していた。
痛いなんてどうでもよかった。あいつとお別れできるなら。いいよ、僕、こっそり死ぬし。誰にも見つけられなくていい。この際、自分を突き飛ばした奴が誰でもいいし、そいつのことを恨む気持ちもなくて、恨むのは鳳翔だけだった。
痛みのあった左側は冷たく鈍い感覚しかなくて、右腕も指の先から冷たくなっていくのがわかる。段々頭もぼんやりとして、鳳翔を恨む気持ちも薄くなっていた。うん。もういいのかも。やっと終われる。終われる、と。
甘い味が広がった。口いっぱいに、甘い味が。
これ、飲んだことがある……と、思って、ふっと目が開く。
「おう、大丈夫か? 真朱」
「…………吉瀬?」
「そうだぞ。お前、どうしたの? 凄ぇボロボロだったけど、何があった?」
ん……? と思って、起きあがろうとして、主に左側に激痛が走った。
「痛っ……え。僕、どうしたの?」
「裏山の下で見つかった。誰に襲われたんだよ? 俺が代わりに潰そうか?」
学舎での揉め事は、それっぽい審議会のようなものに通されることになっている。だけど、結局、頂上に三家がある訳で、彼らに直接関わるような事件なら、解決の裁量が与えられる認識だ。要は「潰し」も黙認される。とんだヤクザな世界だと思われそうだけど、それが鬼社会、完全なる縦社会である。
吉瀬があまりにも軽く言うから、聞き流しそうになったけど。僕は自分の動かない体を見下ろして「いいよ。嫌われても仕方ない立ち位置にいるんだし」と。吉瀬は眉を動かしただけのようだ。それから「暫く休め」と口にして部屋を出た。
この部屋は吉瀬に借りている部屋である。掛けられた布団の下は、相変わらず貧相な肉体だった。左側は手も足も激痛だけど、神経が戻っているから、痛みを感じる訳である。右手を動かして、刺した首の場所を触る。手当てをされていてガーゼが当ててあったけど、外して上から触ったらミミズ腫れのようになっていた。傷口は綺麗に塞がったようである。これなら残りのミミズ腫れも、数日で綺麗になるのだろう。
この状況、考えたなら、吉瀬が助けてくれたのだろう。吉瀬くらいの鬼の血ならば、多めに貰えば蘇生ができる。彼の血がいつもより甘く感じられたのは、瀕死だったからかな、と考えた。
甘い味が好きな僕は、思い出してうっとりとする。
それからざわりと体が揺れた。
「飲むと興奮するんだよな……」
はは……と苦笑した僕である。
隣室の奥の方で、吉瀬の配下の承(しょう)さんが、「言ったんですか?」と問うたのを”やめろ”と指示したらしい吉瀬である。僕の知らないその場所で、「いいんですか?」と確認したのを「いいんだよ」と笑って返し「面白いじゃねぇか」と語る。
「面白い……ですかね?」
「俺は面白いんだよ。あいつに恩を売るのも悪くねぇだろ?」
ククッと笑った吉瀬の顔は、僕が知らない顔だったらしい。
お洒落な本を作るのが夢です* いただいたサポートは製作費に回させていただきます**
