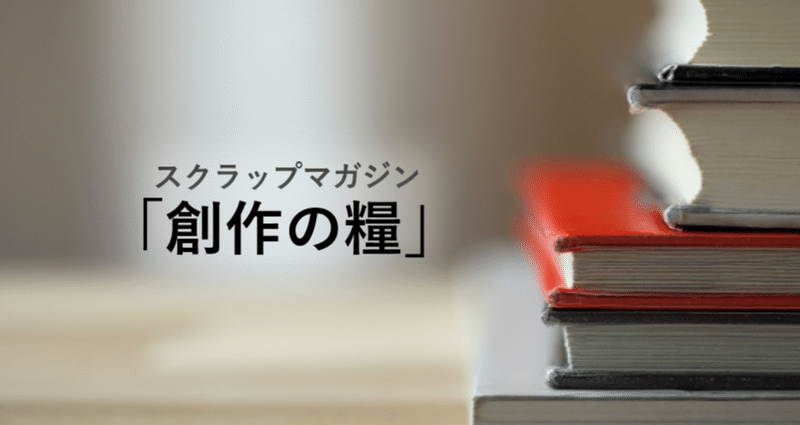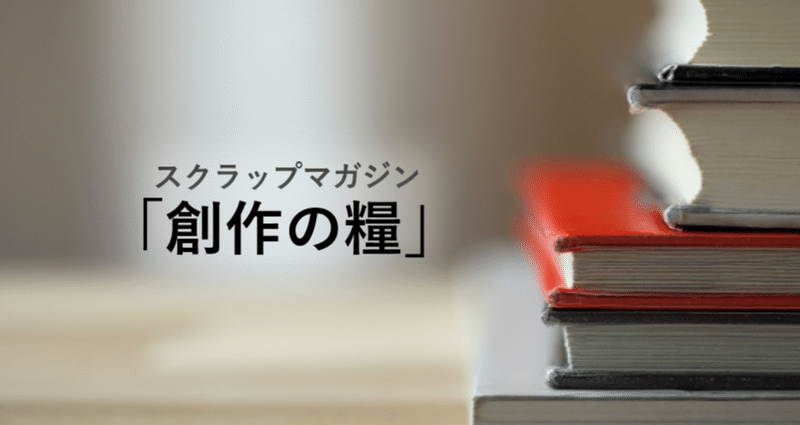「なるほど、本か!」
英国の代表的なロマン派詩人ワーズワース(William Wordsworth)の"The Tables Turned"(邦訳「発想の転換をこそ」)は、本を捨てて自然に出ようというメッセージを力いっぱいに押し出した痛快な詩である。岩波文庫の『イギリス名詩選』(平井正穂編)に収録されているこの詩に出会ったのは学生時代だったが、生活が苦しかったうえ、本分たる研究(の真似事)のための文献解読にも四苦八苦し、文字通り書物の海に圧倒されている若きわが身を朗らかに笑い飛ばしてくれたものだ