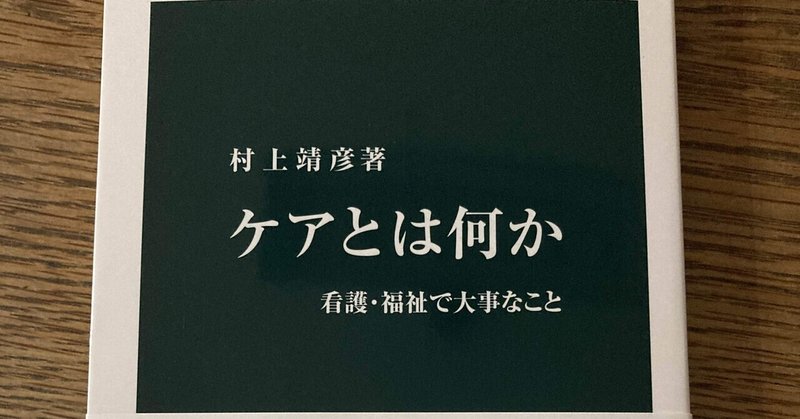
ケア
生活のなかでの願いを実現していく事は、自分自身になることなのである。ケアは、この部分に大きく関わる営みだ。
ケアとは何か
第二章〈小さな願い〉と落ち着ける場所ー「その人らしさ」をつくるケアより引用
この書籍の中で、『ケア』に関して、『生を肯定する』『小さな願いをかなえる』『ケアが共同的な営みである』ことが随所に語られている。
支援者である従事者や対人援助者の語りから、当事者とむきあい、関わる事での「ケア」の実際や支援者の葛藤や苦悩、当事者との関係性が生々しく記されている。
『ケア』はその人、そのもの生きる意味や存在を肯定すること
『ケア』はその人の小さな願いをかなえること
『ケア』は支援者と当事者との間にある人と人との営み
どの事例やエピソードからも、『ケア』と言う言葉だけではなく、人と人との繋がり、コミュニケーション、生活の継続、存在意義…。
人が人として、社会の中で人と共に生きること、生きていくことがテーマになっている様に思えた。
自分も支援者として『ケア』の実践の場に立っている。
それは、聴くことであり、癒しであり、寄り添うことであり、補うことであり、繋げることであり、繋がることであり、伝えることでもある。シュチュエーションやケースによって違いはあるが、支援者として当事者の前に立った時、それはすでに始まっているのだと思う。
ただ、その関係性は良くも悪くも、『支援者』『当事者』としての優位性にも陥りやすく、『弱者』と『強者』の関係性から、多くの問題も起こりうる。
『ケア』の現場でケアを通して起こる、困難さや当事者から発せられるネガティブなエネルギー。支援者も人間なので、心が消耗してしまう。
支援者への支援。『ケアする人をケアする』
支援者もまた支援される存在である。
コミュニケーション、願い、存在の意義、苦境への応答、ピアサポートという章立ては、一般的な教科書ではおそらく採用されない。だがこれは、私が医療・福祉の現場で学んできたことを整理するなかで、必然としてきまっていったものである。読者におかれては、いわゆる教科書的区分けとは異質なものであることをご承知いただいた上で、素人なりにゼロからケアを考えた結果として受け止めてもらえれば幸いである
あとがきに書かれた文章がとても印象的でした。ケアをゼロから考える。
全てのケアラーに読んでもらいたい一冊です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
