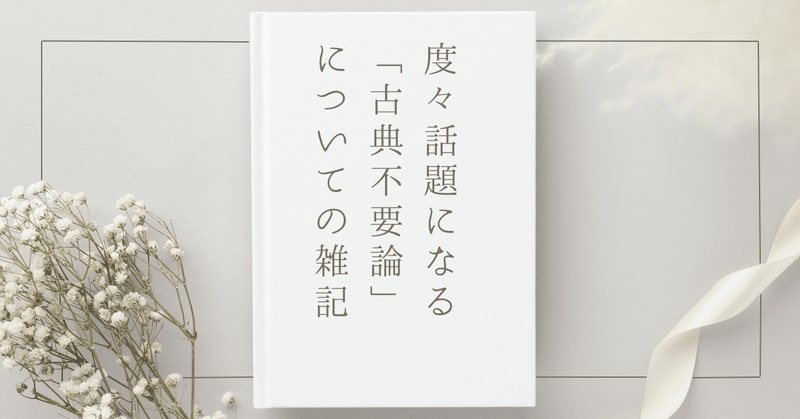
度々話題になる「古典不要論」についての雑記
しばらくの間SNSから離れていたので、周りに何が話題になっているのか、盛り上がっているのかということについて、疎くなってしまっていた(ような気がする)。
久々にTwitter(旧X)を再開したら、「古典不要論」についての発信が多く上がっているのを目にしました。この話題は、定期的にネット上で盛り上がっているように思います。今回は、カンニングの竹山さんが、「古典不要」という話を、トーク番組内でされとか。いくつかの記事もあげられていたので、その一つを示しておきます。
考え方は様々ありますし、竹山さんも古典を好きな人のことまで否定しているわけではないようなので、この発言の良し悪しについては、特に何か述べようとは思いません。ただ、その昔は古典の研究を志し、大学受験予備校で教えていた身としては色々と思うところはあります。
外国語やプログラミングのほうが、実利に繋がるだし、それらに比べたら古典なんて役に立たないし、優先順位は低いというように語られがちです。たしかに、目に見えて役に立つ立たないと考えてしまえば、古典はやはり役に立たないものと言わざるを得ないかもしれません。このように思われていおり、語られてしまう背景には、分かりやすく役立つもの以外は「不要」であるとしてしまう社会の傾向がありそうです。効率や生産性を重視し、タイパという言葉がよく言われるようになっているのも同じ傾向かと思います。
たしかに、古典ができたところで、お金を稼げたり、将来分かりやすく何かの利益に繋がったりするかと言えば、そうではないでしょう。ただ、今すぐ役に立たないもの、お金にならないものを不要としてしまってよいのか……と言えば、そんなことはないと思いますし、そのような考え方ばかりになってしまうのは危険だと思います。
古文や漢文には、日本がこれまで積み重ねてきた膨大な知があります。この「知」に直接、原文で直接的にアクセスできることの価値は計り知れません。私たちが思っているよりもつい最近まで、日本では文語が使われていました。もし、古典を原文で学ぶ機会が0になってしまうと、それらの一次資料にアクセスするすべが失われしまうことになります。いざ過去にアクセスしようと思ったとき、それができなくなってしまってからではなかなかもう一度できるようにするのは難しいことです。今、我々の世の中に残っているもののうち、数百年後、数千年後に残っているものはどれだけあるでしょうか。それだけの長い間、残り受け継がれてきたということの凄みや重みは決して無視できるものではないはずです。
また、分かりやすく役に立つものやお金になるものは、放っておいても学ぶ人がいるものです。目に見えて、重要性が分かりやすくはないものや、自然に過ごしているだけでは出会えないようなものこそ、ある時期にそういった場を設ける意義があるのではないでしょうか。古文や漢文に関しては、学校でそのような場があって、もちろん「つまらない」とか「必要ない」と思う方もたくさんいるわけですが、一方では強い興味・関心を抱く方もいるはずです。そういう営みを通して、また次の世代へ「知」が受け継がれていくのだと思います。現代を相対化して見る視点も、古典によってもたらされる面はあるはずです。そういった部分を断絶させてしまうのは、あまりにも危険です。(私も古典と出会うことができて、その面白みを知り、人生が大きく変わった一人です)。
しっかり向き合ってみると、数百年前や数千年前に、私たちが現在考えていることに通じることが、考えられていたり表現されていることにも気づきます。ビジネス・パーソンの中にも、古典や歴史をきちんと学びなおしたいという方が少なくないのも頷けます。
ちょっとまとまっていないのですが、今回の雑記はこの辺で終わろうと思います。「古典を不要と決めつけるのは危険である」というのが、私が講師として古典を教えていたときからずっと持っている考えで、今もそれは変わっていません(むしろ、より強くそう思っています)。このことに関しては、これからも考えていくでしょうし、向き合っていくでしょうし、発信していく機会を持って行きたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
