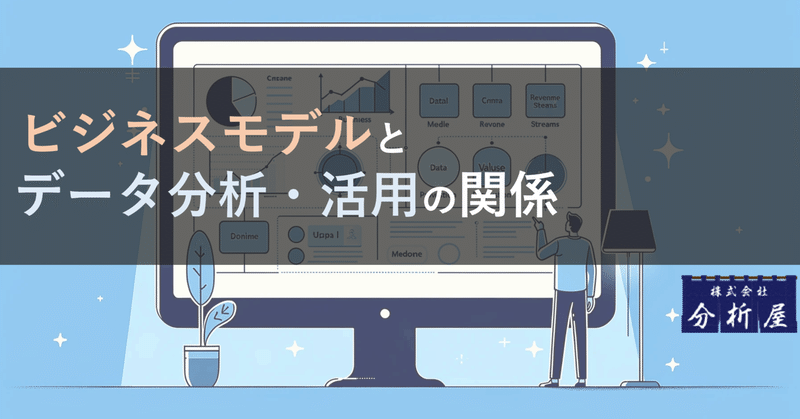
ビジネスモデルとデータ分析・活用の関係
分析屋の下滝です。
社内のチャットで話したことを少し整理して共有してみようと思いました。
テーマは、データ分析・活用の範囲を決めるものは何か、というものです。本記事では、ビジネスモデルが決まればその範囲が決まるのではないか、ということで議論したいと思います。
ただし、ビジネスモデルの定義は難しいので、ここでは例をあげながらビジネスモデル的な何かを表現したいと思います。
たとえば、スーパーマーケットとカフェでは、売るモノ自体やモノの売り方、売れ方などが異なります。スーパーマーケットでは、多くの商品がありますが、カフェではそれと比べれば少ないです。また、スーパーマーケットでは歩き回りながら購入する商品を選びますが、カフェでは、カウンターや席でのメニューをもとに選びます。さらに、スーパーマーケットではその場では消費しませんが、カフェでは消費することが多いと思います。
カフェでも、店内に席があるものと、店内になく持ち帰りやフードコートを前提としたものでは異なりそうです。店内に席があれば、回転率が気になりますが、フードコートでは恐らくそのような心配は少ないと思われます。
このような違いをビジネスモデルの違いだとして捉えたいと思います。
では、ビジネスモデルが異なれば、データ分析にどのように影響するでしょうか。本記事の疑問をより正確に言うと、ビジネスモデルが異なれば、可能なデータ分析の集合はどのように異なるでしょうか。
可能なデータ分析の集合という表現は、データ分析の種類などが数えられるものだと仮定しています。たとえば、ABC分析など名称がついているものは、分析の一つだと考えられます。一方で、名もなき分析も様々あると思われます。
さて、ある分析が、あるビジネスモデルでは存在しても、他のビジネスモデルでは存在できないケースがあると思われます。
たとえば、スーパーでの品揃えのために、ABC分析の一種として、市場データと自社の店舗での商品の売れ行きを比較することがあります。市場データでは売れている商品なのに、自社では売れていないとすると、売り方が良くなく、伸びしろがあると判断できる、というような使い方をします。
では、この種のABC分析は、カフェの商品でもできるでしょうか。ほとんどの場合、カフェの商品はその店舗独自の商品であると思われるため、市場データはありません。したがって、スーパーでできる分析が、カフェではできません。
少し形式的に書いてみるとこうなります。
bmで可能なデータ分析の集合 = D(bm)
ここで、bmは、あるビジネスモデルを意味します。たとえば、スーパーやカフェなどです。
Dは、何らかのマッピングで、bmから可能なデータ分析の集合を対応付けます。

先程のスーパーではできる分析がカフェではできないという表現は、次のように表現できます。
D(スーパー) != D(カフェ)
では、このDは具体的にはどのような存在でしょうか。ビジネスモデルのどのような構造が、可能なデータ分析の集合を決めるのでしょうか。この点を探っていくのがデータ分析と活用の理論化の一つの方向性かもしれません。
株式会社分析屋について
ホームページはこちら。
noteでの会社紹介記事はこちら。
専用の採用サイトはこちら。
求人情報はこちら。
【データ分析で日本を豊かに】
分析屋はシステム分野・ライフサイエンス分野・マーケティング分野の知見を生かし、多種多様な分野の企業様のデータ分析のご支援をさせていただいております。 「あなたの問題解決をする」をモットーに、お客様の抱える課題にあわせた解析・分析手法を用いて、問題解決へのお手伝いをいたします!
【マーケティング】
マーケティング戦略上の目的に向けて、各種のデータ統合及び加工ならびにPDCAサイクル運用全般を支援や高度なデータ分析技術により複雑な課題解決に向けての分析サービスを提供いたします。
【システム】
アプリケーション開発やデータベース構築、WEBサイト構築、運用保守業務などお客様の問題やご要望に沿ってご支援いたします。
【ライフサイエンス】
機械学習や各種アルゴリズムなどの解析アルゴリズム開発サービスを提供いたします。過去には医療系のバイタルデータを扱った解析が主でしたが、今後はそれらで培った経験・技術を工業など他の分野の企業様の問題解決にも役立てていく方針です。
【SES】
SESサービスも行っております。


