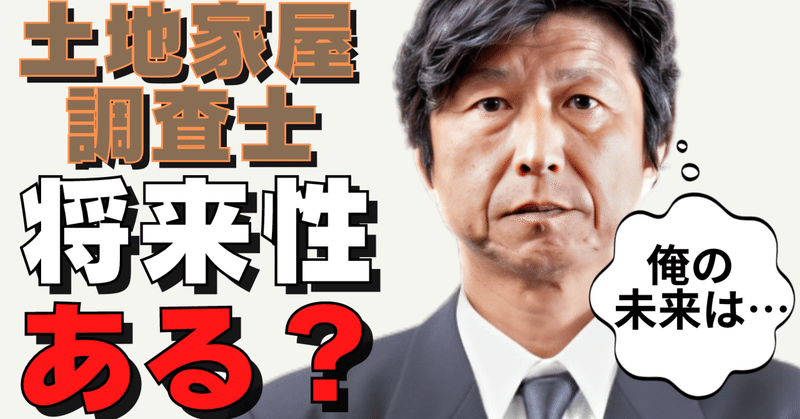
土地家屋調査士はやめとけ?需要・将来性をデータとイラストで可視化してみた【市場分析】
どもー。
分析太郎です。
今回は土地家屋調査士の
市場分析レポート完全版です。
仕事の将来性を把握する上で、
市場分析は必要不可欠です。
起業するにせよ転職するにせよ、
将来性を把握しておかないと
キャリア選択で誤った道を
選びかねません。
なので分析太郎が、
データとイラストを駆使して、
将来性を分析しました。
それでは、見ていきましょう。
【第一章】土地家屋調査士業界の需給バランス
そもそも需給バランスとは?
第一章では、土地家屋調査士業界の
需給バランス確認していきましょう。
その前に、需給バランスについて説明します。
世の中には様々な市場があり、
その中でお金が取引されています。
そして市場の中には、
供給(事業者)と需要(お客様)が
存在します。
これらを釣りで例えるなら、
市場=釣り堀
供給=釣り人
需要=狙っている魚
と言えます。

そして、需要と供給にはバランスがあります。
イラストにするとこんな感じです。

本レポートでは、
土地家屋調査士市場が4つのうち
どこに分類されるかを、
行政機関と業界団体のデータを
フル活用して考察していきます。
それでは、本題に話を移しましょう。
土地家屋調査士業界の市場規模は?
それでは最初に、
土地家屋調査士業界の
市場規模を確認しましょう。
令和3年 経済センサス活動調査(総務省・
経済産業省)のデータによれば、
2021年の土地家屋調査士の市場規模は
1,062億円でした。
他の士業と比較してみましょう。
グラフを作成しました。

※2021年の売上(収入)金額から
出典:令和3年 経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)
行政書士よりは大きいですが、
それ以外の士業よりは低い値でした。
同規模の市場には
下記が挙げられます。
みそ(1,001億円)
音楽教室(1,024億円)
レジ袋(1,098億円)
国内市場の立ち位置としてはこのあたりです。

出典:市場規模マップ
この市場で、需給バランスは
どうなっているのでしょうか。

確認していきましょう。
土地家屋調査士市場の供給は増えてるの?
それでは土地家屋調査士市場の
需給バランスを確認しましょう。
まずは供給から確認します。
土地家屋調査士白書2022(日本
土地家屋調査士会連合会)のデータによれば、
2021年の土地家屋調査士数は16,141人、
推移は減少傾向でした。
グラフを作成しました。

出典:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
最多は2002年の18,741人で、
そこから減少傾向が続いています。
考えられる最も大きな理由は
資格受験者数の減少です。
受験データのグラフを作成しました。

出典:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
受験者数は
15年間で40.8%も減少しています。
合格率を調整してなんとか
対応しているようですが、
受験者が減少しているので
合格者は増えていません。
また、土地家屋調査士の
二人に一人は60代以上のため、
今後は廃業などが相次ぐことも想定されます。
年齢構成のグラフを作りました。

出典:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
逆に言えば、
今後は土地家屋調査士が不足するので、
供給に対する需要の割合が
大きくなるかもしれません。


では、需要はどう
推移しているでしょうか。
確認していきましょう。
土地家屋調査士の需要は増えてるの?
それでは、
土地家屋調査士市場の
需要を確認しましょう。
職業情報サイト「キャリアガーデン」は、
土地家屋調査士の業務は大きく下記2つだと
説明しています。
①不動産登記
(不動産情報を法務局に登録すること)
②筆界特定
(土地と土地の境目がどこかを確定すること)
従って、
この2つの件数が
増えているかどうかを
確認してみましょう。
まずは不動産登記についてです。
登記統計(法務省)のデータによれば、
2022年の登記件数は1,054万件、
推移は減少傾向でした。
グラフを作成しました。

出典:登記統計(法務省)
2006時点から、
35.6%減少しています。
これはツラいですね…。
不動産登記は
「土地」と「建物」に
分類されますが、土地登記の
減り幅がかなり大きいようです。
1992時点を100と指数化した
値の推移を確認しましょう。
グラフを作りました。

※1992年時点を基準年とする
出典:登記統計(法務省)
不動産登記件数は減少傾向に
あることは間違いなさそうです。
では、
筆界特定件数についても
確認してみましょう。
登記統計(法務省)のデータによれば、
2022年の筆界特定_新受件数は2,106件、
推移は2018年から減少傾向でした。
グラフを作成しました。

出典:登記統計(法務省)
2006~2017年でも
件数の増減を繰り返しているので、
また件数が増えればいいのですが…。
少なくとも、2022年は16年間で
過去最低でした。
さて、データが出揃いましたね。
それでは、結論に入ろうと思います。
分析太郎の結論
まとめると、
土地家屋調査士市場の
需給バランスはこうです。
供給:資格受験者の減少により、土地家屋調査士は減少傾向
需要:不動産登記件数は減少傾向。特に土地登記の減少が激しい。筆界特定の新受件数は16年間で過去最低。
結論を出しますね。
冒頭の需給バランス四分類で言えば、
ここに当てはまりつつあるのでは
ないでしょうか。

釣り堀(=土地家屋調査士市場)の中で、
釣り人(=土地家屋調査士)が減り、
魚(=不動産登記・筆界特定件数)も
減少しているため、
このような結果になりました。
いかがでしたでしょうか。
とはいえこれは日本全体の需給バランスであり、
当然ですが地域によって偏りが生まれます。
まともに食べていけない地域もあれば、
儲かってウハウハですという地域だって
あるかもしれません。
そこで第二章からは、
都道府県別に土地家屋調査士市場の
レッドオーシャン・ブルーオーシャンの
都道府県を特定していきます。
【※】
この資料の続きのみ
ご覧になりたい方は、
買い切り版をご覧ください。
早期購入特典あります。
皆様の安定的なキャリアを、
心より願っております。
【第二章】ブルーオーシャンな都道府県を考察する
第二章について
第一章では、
日本全体の需給バランスは「過疎」に分類され、
将来性はかなり薄いことを理解しました。
第二章では、
都道府県ごとの需給バランスが
分析し、相対的に最もビジネスに
優れたブルーオーシャンな都道府県を
特定していきます。
この章でも引き続き、
「需要」と「供給」に着目します。
日本全体を俯瞰しながら、
「量」と「比率」の2つの側面から分析し、
ブルーオーシャンを特定していきます。
お住まいの地域を意識しながら、
読み進めて頂ければ幸いです。
それではいきましょう。
「需要量」の散らばり具合
では、需要について改めて確認します。
第二章でも、土地家屋調査士の需要は
下記の2つと定義します。
不動産登記件数
筆界特定_新受件数
第一章では、
2つの件数合わせて約1,054万件で
あることを理解しました。
これが供給者(=土地家屋調査士)にとって
狙うべき魚であり、
利益のもととなるものです。

ただ、この需要は
全国に散らばっており、
その散らばり具合には偏りがあります。
1054万件 ÷ 47都道府県
= 1都道府県につき22万件
というわけではありませんよね。
従って、需要(不動産登記・筆界特定件数)が
日本のどの辺りに偏っているかを確認しましょう。
偏っている地域はビジネスがしやすいと言えます。
細かい件数を見る前に、
ざっくりとした分布を確認します。
地図グラフを作成しました。

赤い部分が大きいほど、相対的な供給量が大きい
出典:登記統計(法務省)
案の定、めちゃくちゃ偏ってます。
都道府県ごとの偏り具合を偏差値にしました。

出典:登記統計(法務省)
件数は、
最小値と最大値で17.9倍の差があります。
お住いの地域はいかがでしたか?
ただ、
よく釣れるスポットに釣り人が集中するのと
同じように、需要が多いところには供給者が
集中していることが想定されます。
従って、供給量の散らばり具合を
確認しましょう。
「供給量」の散らばり具合
改めて、供給について確認します。
土地家屋調査士市場の供給は
土地家屋調査士です。
第一章で、
土地家屋調査士は2021年時点で
16,141人いることを理解しました。
この人たちがビジネス上の
ライバルであり、需要を取り合う
競争相手です。

土地家屋調査士も全国に散らばっており、
その散らばり具合には偏りがあります。
16,141人 ÷ 47都道府県
=1都道府県につき343人
というわけではありませんよね。
そこで、供給量(土地家屋調査士)が
どの辺りに偏っているかを確認しましょう。
こちらは偏っていないほうが,
ライバルが少ないので
ビジネスはしやすいと言えます。
細かい人数を見る前に、
ざっくりとした分布を確認します。
地図グラフを作成しました。

赤い部分が大きいほど、相対的な供給量が大きい
出典:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
こちらもめちゃくちゃ偏ってますね。
都道府県ごとの偏りを偏差値にしました。

出典:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
最小値と最大値で約22倍の差があります。
お住いの地域はいかがでしたか?
ここで一旦情報を整理します。
「量」で見る需要と供給
ご覧になって頂いた通り、
需要と供給の分布には大きな偏りがあり、
分布の様子もほぼ一致しています。

出典①:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
出典②:登記統計2022(法務省)
需要と供給には明らかな相関がありますね。
相関係数は0.97、もの凄く強い相関です。

出典①:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
出典②:登記統計2022(法務省)

釣れるところで釣りをする、
つまり儲かるところで事業をするのは
ビジネスの基本ですもんね。
「じゃあどこで起業しても同じじゃないか」と
言われれば、そんなことはありません。
おおよそ相関があったとはいえ、
需要に対する供給の比率は
都道府県ごとに大きく異なります。
従って、
これから見ていく項目は「比率」です。
相対的に見て、
需要に対する供給の比率が少ないエリアは
ブルーオーシャンだと言えます。
一方で、需要に対する供給の比率が多いエリアは
レッドオーシャンだと言えます。
これがどこの都道府県なのかを
考察していきます。
それではいきましょう。
需要に対する供給比率
それでは、都道府県ごとの
需要に対する供給の比率について
確認していきましょう。
供給の割合が少ないほど、
ブルーオーシャンな
都道府県だと言えます。
土地家屋調査士市場の需要は
下記2つでした。
不動産登記件数
筆界特定_新受件数
1つずつ確認していきましょう。
まずは不動産登記に関してです。
不動産登記件数に対する、
土地家屋調査士の
比率を見てみます。
これにより、不動産登記業務の
ブルーオーシャンとレッドオーシャンの
都道府県を特定することができます。
お住いの地域はどうでしょうか。
ランキング表を作りました。

出典①:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
出典②:登記統計(法務省)
需要に対し、
供給の比率が最も少ないのは和歌山県でした。
土地家屋調査士一人につき
1,026件の登記件数でした。
一方で、
供給の比率が最も多いのは愛媛県でした。
土地家屋調査士一人につき
434件の登記件数でした。
地図に落とすとこんな感じです。
ややこしくて恐縮ですが、
赤くなっているエリアが優良エリアです。

出典①:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
出典②:登記統計(法務省)
お住いの地域はいかがでしたか?
同様に、
筆界特定業務の
ブルーオーシャンも
特定していきましょう。
筆界特定業務の場合は、
司法書士は関係がないので、
供給は土地家屋調査士数で測ります。
これにより、筆界特定業務の
ブルーオーシャンとレッドオーシャンの
都道府県を特定することができます。
ランキング表を作成しました。

出典①:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
出典②:登記統計(法務省)
需要に対し、
供給の比率が最も少ないのは京都府でした。
土地家屋調査士一人につき
0.45件の登記件数でした。
一方で、
供給の比率が最も多いのは長野県でした。
土地家屋調査士一人につき
0.01件の登記件数でした。
地図に落とすとこんな感じです。
ややこしくて恐縮ですが、
赤くなっているエリアが優良エリアです。

出典①:土地家屋調査士白書2022(日本土地家屋調査士会連合会)
出典②:登記統計(法務省)
お住いの地域はいかがでしたか?
参考にして頂けると幸いです。
おわりに
今回は、土地家屋調査士業界の
市場分析を実施しました。
今後の意思決定の参考にしてもらえると
嬉しいです。
その他にも、
様々な業種を分析しています。
今後の安定的なキャリア形成のために、
一度ご覧になってください。
コラムも書いています。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
今後とも、分析太郎の活動にご期待ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
