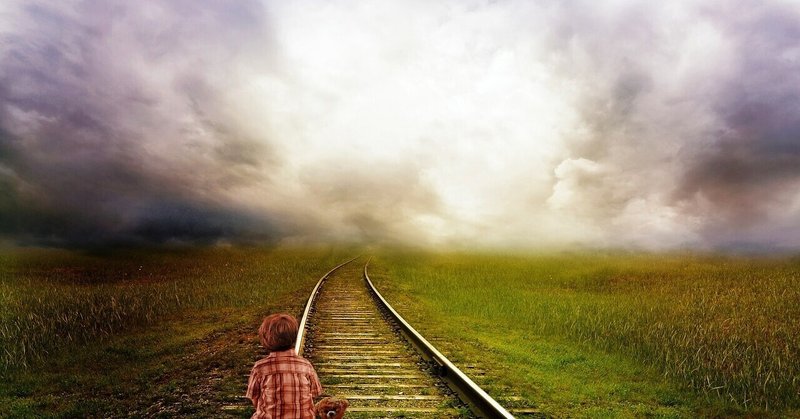
【本】円城塔「Self-Reference ENGINE」感想・レビュー・解説
時間とは何だろうか。
という問に答えることの出来る人は世界中探しても存在しないのではないか、と思う。時間というものはまだまだ謎めいたものとして認識されているのである。
そもそも時間は存在するのか、ということすら考え始めると難しい問題であると思う。
僕らは時間を認識する際に時計を使う。1時間針が進んでいれば1時間経過したのだと判断する。その間の自分自身の時間感覚に関係なく、時計というものが時間というものを教えてくれるのである。
しかし時計というのはそもそも人間が作ったものである。時計が時を刻んでいるわけではなく、存在しているだろうと思われている時を時計というものに写しているだけである。時計が存在しているからといって時間が存在しているということにはならないだろう。
そもそも時間というのはどのように定義されているか。物理的に1秒という時間はきっちりと定義されている。何かの原子が関わっていることだけは知っているのだけどきちんと覚えていなかったので調べてみた。1秒というのは、セシウム原子の振動9192631770回分の時間として定義されるものである。
しかしこれにしたって、人間がそう定義したということに過ぎない。だからどうした、という話である。1秒という時間がこういう風に決められていようと、時間が存在するということにはならない。鬼の定義を、角があって金棒を持っている、と定義したところで、鬼がいるということにはならないのと同じことである。
このように、時間の存在性ですら示すことは難しい問題なのではないか、と僕は思うのである。であれば時間の性質やなんかを知るというのはまだまだ難しいのだろうと思います。
時間に対する概念を変えたのは、やはりアインシュタインではないか、と僕は思います。
それまで人々は、時間というものはある方向にある一定の速度で進むものである、と考えていたと思います。時間はすべての人に平等であると考えていたはずだ、と思います。
しかしアインシュタインはその思想を打ち砕きました。
アインシュタインは相対性理論の中で、速度によって時間の進み方が変わる、ということを示しました。速度が光速に近づけば近づくほど時間の流れはゆっくりになっていく、というものです。
有名な話に、双子のパラドックスというものがあります。
仮想的な思考実験であるので、光速の90%近いスピードの出る宇宙船が開発されたと仮定しましょう。その宇宙船に双子の兄が乗り宇宙を旅し、弟は地球に残ることにします。
さて地球の時間で20年が経過したとしましょう。当然地球に残った弟は20歳年を取っています。しかし兄の方は、光速に近いスピードで移動していたために時間の流れが遅くなり、地球に戻ってきた時にはまだ10年ぐらいしか経過していない、というような状況になります。
この時間の流れの差というのは、僕らが普段生活をしているスケールでは現れにくいものであるのでなかなか実感することは難しいだろうと思います。ただ実際にこの差を検出する実験が行われたこともあるようです。
正確なことは覚えていませんが、航空機を地球の自転方向に飛ばした場合と、自転とは逆方向に飛ばした場合とでは、現在地球上に存在するもっとも精密な時計で計測をすれば明確に差が検出されるのだそうです。
僕らは時間というものに、まっすぐに途切れることなく続いているものであるというイメージを持っているのではないかと思います。しかし、誰もそれを確認することは出来ていません。もしかしたら時間なんてそもそも存在していないのかもしれないし、捩れたり曲がったりしているかもしれません。あるいは同時に幾本もの別々の線が伸びていて、それらが互いに平行を保っているという感じかもしれません。
僕らは普段時間というものをあまりに意識しないがために、時間というものの存在が当然であるという風に考えています。このままずっと変わりなく未来がやってくると信じています。ただ、一寸先は闇という言葉の通り、ちょっと先の未来を保証するものは何一つないわけです。1秒後に世界が滅亡していたということだってあってもおかしくはないのかもしれません。
そろそろ内容に入ろうと思います。
とは言うものの、本作は内容を紹介するのが非常に困難な作品なので大雑把な感じになると思いますが。
本作は短編集で、それぞれの短編はそれぞれ同じ世界観の元で起こっている出来事である、という繋がりがあります。まずその世界観のことを書きましょう。
本作の世界は、「イベント」というものが起こった後の世界を描いています。イベントというのは、時間の束が完全にごっちゃになってこんがらがってしまった、と説明される出来事で、それによってかなり変わった時空が構成されている世界です。
またその世界では、巨大知性体というロボット的なものが世界を運用しています。元々は人間が作ったものですが、自己進化の結果自然を支配するまでに至ったわけです。
そんな世界の中で生きる人々を描いた作品になります。
「Bullet」
日々銃を撃っている変わった女の子リタと、そんなリタに惚れてしまい、リタの頭には弾丸があるのだと信じているジェイムズの話。
「Box」
蔵の奥にある、一年に一度だけどこかの方向に倒すことになっているカラクリ箱のような箱の話。
「A to Z Theory」
世界中の数学者26人が同時に発見した、二項定理に関する大発見の話。
「Ground256」
天上から本棚が生えてくる。テーブルからテーブルが生えてくる。村の至る所からいろんなものが生えてくる。それを鉄パイプのようなもので叩き壊していく話。
「Event」
巨大知性体の誕生の話。
「Tome」
鯰の像に書かれたと言われる謎の文章。それがある一定の法則に従って消えていくという話。
「Traveling」
イベントにより発生した様々な多世界との戦闘のために戦闘機による戦闘が導入された。しかしそれは未来方向や過去方向へと移動し、また撃墜されたという過去すら改変できてしまうような話。
「Freud」
『祖母の家を解体してみたところ、床下から大量のフロイトが出てきた。』という一文から始まる話。
「Daemon」
イベントによって混乱した時間を修復するための作戦会議の話。
「Contact」
巨大知性体の不意をついて突然コンタクトを取ってきた超越知性体の話。
「Bomb」
時間束理論や過去改変などと言ったことをまったく信じない精神科医の話。
「Japanese」
分かっているだけでも120億の文字からなる、複雑で特殊な構造をもつ「日本文書」の話。
「Yedo」
巨大知性体があらゆる事態に対応できるようにと、喜劇の演算可能性について検討する仕事を与えられた八丁堀という名の巨大知性体の話。
「Sacra」
ある特殊な性質を持つ巨大知性体が崩壊しているという話。
「Infinity」
リタと祖父はゲームをすることにした。祖父はリタにちょうど一週間で解けるだろう問題を出し、それをリタは一週間掛けて解く、という話。
「Disappear」
巨大知性体はまだ存在しているしちゃんと機能もしているのだけど、しかし実は滅亡しているのだ、という話。
「Echo」
砂浜に打ち捨てられているある金属の塊りについての話。
「Return」
リタを見送りにホームまでやってきたジェイムズと僕の話。
という感じの話です。
本作を読んだ感想は一言で表すことが出来ます。
それは「クラクラする」という感じです。言葉に酔うという感じでしょうか。
あるいはさらに陳腐な表現をすれば、初めてタバコを吸った時のような感じとなるかもしれません。まあ僕はタバコを吸ったことはないのであくまでイメージですけど、タバコを吸った時のニコチンによるクラクラ感と、本作の文章を読んで感じるクラクラ感は、感覚的に近いものがあるのではないかという風に思ったりします。
それぞれの話はちょっと難しくて、正直よく分からない話もあったりしたんですけど、でもそれでも読みたいという感覚になりますね。ストーリーは難しいんだけど、これまで見たことのないような斬新な比喩があったり、あるいはスピード感のある文章だったりが、ページを繰る手を止めないという感じです。
読んでいてとにかく思ったのは、著者はとんでもなく頭がいいのだろうな、ということです。知識があるとかないとかではなく(まあ知識もあるんでしょうけど)、考え方みたいなものが普通の人よりも遥かに深いところで成立しているようなそんな感じがしました。
本作は内容的にはSf的な作品だと思いますが、しかし文学にも近い作品だと思います。ジャンルミックスというのか、境界を飛び越える作家というのはまあ多少いますけど、でもまさかSFと文学を融合できるとはすごいものだな、と思いました。確かに著者は、文学界新人賞受賞でデビューをしていて文学寄りであり、かつ確かこの著者は理系の研究者だったと思うので理系よりでもあるという、まあバランスのいい作家なんだろうな、と思います。
個々の作品についてあれこれ書くことはなかなか難しいので止めておきますが、一つだけ「Freud」という話には笑いました。さっきも書きましたが、
『祖母の家を解体してみたところ、床下から大量のフロイトが出てきた。』
という一文から始まる文章で、床下からフロイトが出てきたのだけどどうしようか、ということをひたすら家族で話し合うというだけの話です。よくもまあこんな話を思いつくものだ、という風に思いました。
というわけで、比較的話題の作品ではないか、と思います。個人的にはこのミスの1位とかになってもおかしくないかもしれないな、とか思っていますけど、特に根拠があるわけではありません。なんか結構変なのが1位になったりするんで、だったら今年はこれかな、なんて思ったり。
装丁がなかなかセンスのいい作品です。クラクラしたいという人は読んでみてください。
サポートいただけると励みになります!
