
【主催者レポート】教育の未来を語り明かす会vol.7
1月20日〜21日に第7回目となる「教育の未来を語り明かす会」(開催してきました!
教育の未来を語り明かす会(略してミラカタ)は、変わらない教育の本質とこれからの教育の方向性について語り明かすイベントです。
今回も多様な人が参加してくれて、大学生、オルタナティブスクールスタッフ、クリエイター、保育士、ゲストハウス運営者、公立の小学校の先生、学童、ユースワーカーなどなど、いろんな立場の人と語り明かすことができました。
そんなミラカタの内容をご紹介します!



感じることからはじまる学び〜SEE Learning〜
ラーンネットあーる校長のいさみさんに話していただく予定が、急遽ご家族が体調不良ということで不参加になりました。
ですが、内容は変えずに実施しました。
SEE ラーニングについては、SEEラーニングジャパンのホームページに以下のようにかいてあります。

SEE Learningとは、日本でまだあまり広がりがなく、本も一冊のみという状況です。この本を参考に今回も勧められました。
概要を聞いたあとに、実際に「わたしを感じる」ことをやってみました。
参加者の方で、愛媛から来られた方がおり、みかんをたくさん持ってきてくれていたので、そのみかんをゆっくり味わうことを通して、わたしを感じでみました。


最後に、いさみさんからのコメントも紹介がありました。
【姿】
・抽象的なことを自分なりの表現で具体的に伝えることが増えた(共通言語もできた)
・お互いの表現を尊重
・共通のニーズや違いに気付く
年末の保護者面談でも各家庭から上記含めコミュニケーション変化などたくさんのエピソードいただきました。
【実践】
・実践者が少ない。Howではないからこそ、そこで起こっていることを共有する仲間がそれなりにいるといい。
・しっかりした日本語訳はプレイブックしかない。翻訳にかけても正しい文脈で解釈できているかは微妙なところ。
・公教育での導入のハードル
【伝えたいこと】
・同じカリキュラムをやったとしても実践者やコミュニティの在り方で全く違うものになる。SEEラーニングも生き物。
感じることから始まる学びは、改めて大人もこのような時間が必要だなと気付かされる時間でした。
インクルーシブな考え方を育む
次は、箕面こどもの森学園のスタッフぶっきーによる実践紹介です。
2022年に、国連障害者権利委員会から「分離教育は分断された社会を生む」という勧告がありました。
通常学級、特別支援学級、特別支援学校という障害の程度によって通う場所が変わる医学モデル的な考えを前提にした仕組みではなく、障害はお互いの相互作用の間にあるという社会モデルの考えへシフトしていくには、どのようにしたら良いのか?ということについて、箕面こどもの森学園の実践を例に社会モデルの実践について話しました。





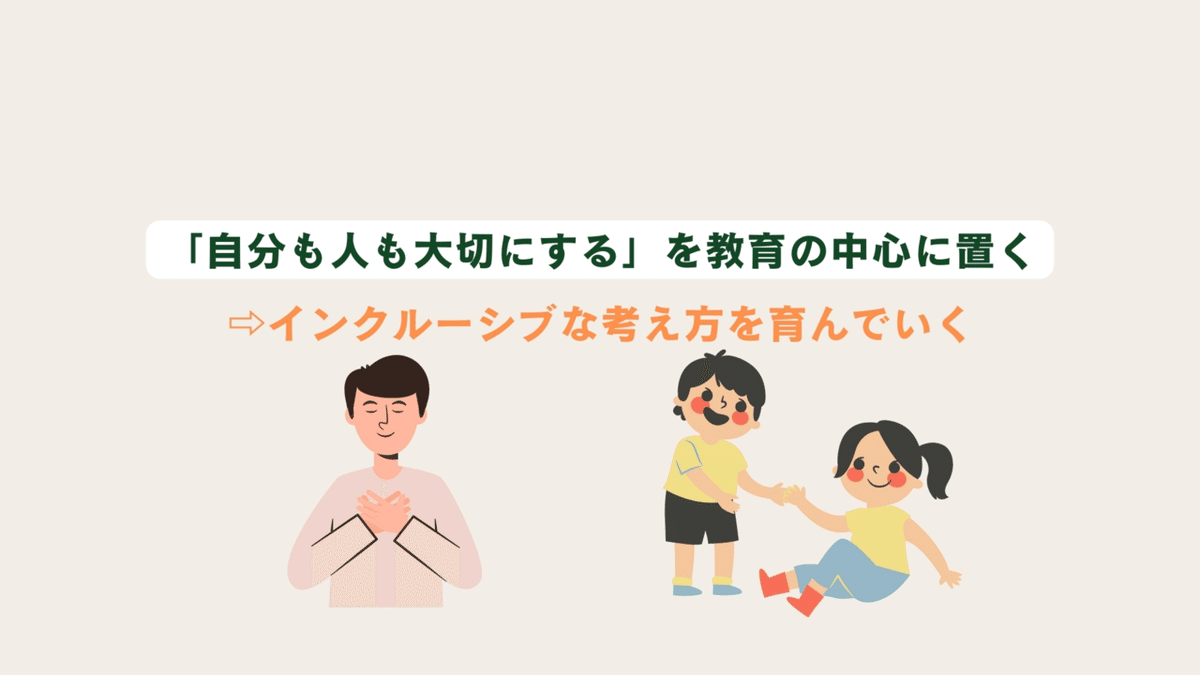


一通り話した後は、グループで話し、質問タイムにうつりました。話は段々と「安心感を感じられながらも、どうしたらはっきりと伝えあっていけるか?」という組織の話に。改めて組織の在り方を考えさせられる時間になりました。
初日のプログラムは以上です。夕食を済ませ、宿泊先に向かいます。

お楽しみの語り明かす時間へ
入浴後は、お楽しみの語り明かす時間。
話し合いテーマを持ち寄り、みんなで語り合いました。
今回出てきたテーマは以下の3つ。
教育でお金を稼ぐには?
心理的安全性をつくる環境とは?
学校とNPOの連携はどのようにする?

この3つを話したところで24時過ぎ。
ですが、ここからも話が止まりません。
ファシリテーションについて
学校が社会と連携するって?児童相談所とはどう関わる?
未来の社会はどうなっている?
それぞれの活動について聞き合う
などなど。いろんな話をしていました。
気づいたら夜中の2時。途中で寝にいく人もいましたが、最後まで残っていた人は6時くらいまで話していたそう。本当に語り明かしちゃいました!!


2日目。子どもの見取り
9時スタートの予定が、起床が9時に。語り明かしてしまったらそうなりますよね。みんなが整うまでゆっくり待って10時くらいから最後のテーマが始まりました。
話題提供者は、尼崎のNPO法人サニーサイドのキタバと、日野さん。
キタバが、学童の「つくし」に通ってきている子どもたちのシーンを取り上げ、みんなでそれについてどんな見立てができるか話し合いました。

日野さんから、身体・心・魂の3視点でみとることについて、生理学、心理学、脳科学など教育以外の分野の知見も使いながら解説してくれました。
詳しくは、日野さんのブログをご覧ください。
終わりに
改めて、7回続けてきて良かったなぁと感じています。
理由は二つあって、
一つ目は自分にとって年に一回のアウトプット日になっていること。この一年で向き合ったことをなにかしら形にする機会になっています。
今までの内容を見返すと、自分の学びの履歴を見ているようで面白い。
① 『ともにつくる』ことで起こる学びとは?ーオルタナティブスクール箕面こどもの森学園の実践ー」
② 教育に関わる自分を見つめる〜共感コミュニケーション(NVC)〜
③教育×自己肯定感
④対話ってなんだろう?
⑤子どもの興味関心から始まる学び
⑥ 学校のルールづくり〜多数決によらず、納得解をつくるために大事なことは?〜
⑦インクルーシブな考え方を育む
二つ目は、ミラカタが参加者にとって人生のターニングポイントになるきっかけをつくれているんじゃないかと思えたこと。
ミラカタを続けている理由は、自分自身が大学生のとき、泊まりのイベントがターニングポイントとなり、変化していけた感じがしたから。
参加者の方で、「ミラカタに参加していたから今の自分がある」という内容のことを話してくれた人がいて、とても嬉しかったです。
生活を共にすること。多様な人が集まって、じっくりと語り明かすことには人を変える大きな力があります。今回も参加者の最後の感想を聞いてそれを感じました。
活かしたいことが見つかった人もいれば、自分を振り返り、これからどうしようかと話す人、心の炎に薪をくべてもらったと感じる人、また来年への希望を話す人、来年はつくる側に回りたいと思ってくれている人など、いろんな感想がありました。
主催メンバーの僕自身も、改めて自分の現場だけでなく、広くいろんなところから学びたいと感じましたし、自分たちの現場で起こっていることを、一般化・概念化していろんな人と語り合いたいという気持ちが強くなりました!
2024年度も夏・秋らへんに日帰りのイベント、冬に今回のような宿泊のミラカタを実施する予定でいます!
みなさん、また語り明かしましょう〜
今年語り明かせなかった方も来年一緒に語り明かしませんか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
