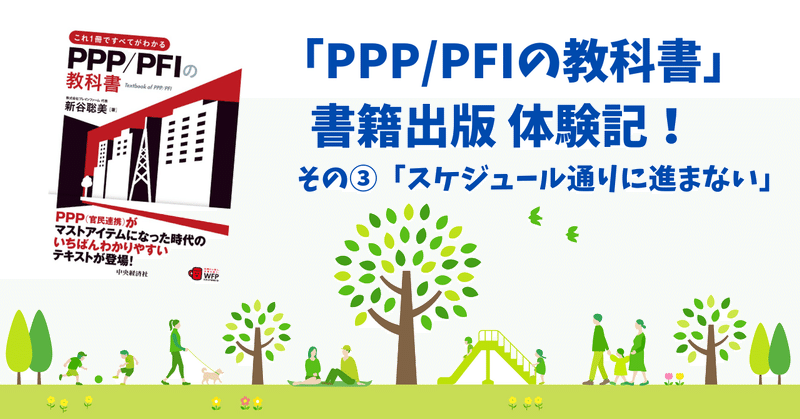
「PPP/PFIの教科書」書籍出版の体験記その③「スケジュール通りに進まない」
2024年の2月に「これ一冊ですべてわかる PPP/PFIの教科書」という解説書を中央経済社より出版しました。出版前から「書籍ができたら、それまでの取り巻くストーリーを伝えると、誰かの役に立つかもしれないよ」とアドバイスいただいていたので、何回かに分けて綴っていこうと思います。
第三回は「スケジュール通りに進まない」です。
「書籍出版には興味があるが、PPP/PFI(官民連携)って、何じゃそりゃ?」という方も、専門知識なしでもイメージいただけるようお伝えしますので、ぜひお付き合いください。
【1】ページ配分通りには、書けません
書籍出版では一般的なのか、はたまた、オンラインでお話しした時に「どうも、こいつは危ないぞ」と思われたのか、どちらが正解なのかはわかりませんが、中央経済社の担当編集長の和田さんとは、月に1回オンラインで進捗会議を行うことになりました。
最初の打合せが4月13日。原稿納品予定期日が9月末。提出までは、5か月半ほどの執筆期間があります。
さて、どうしよう…と思っていた時に、自分で書籍を出版した経験のあるナカムラさんが「全体ページを週の数で割って、毎週何ページぐらい書けばよいか、最初にページ配分をしておけばよい」とアドバイスをくれました。

「顔出してもいいですよ」とご自身が取材を受けた雑誌記事を共有してくれました。
(週刊ダイヤモンドより)
その頃には「本を書く」のが自分ゴト化していた私も、せっかく”経験者ならでは”のアドバイスをもらっても、自分が細かいルールを守ることができない性格だというのは、よくわかっています。
「さすがに、『週単位』はムリじゃ・・」と心の中でつぶやき、目次ごとのページ配分と月単位で作成するページ配分表をつくりました。
編集長の和田さんからは、「目次や索引などもあるので、本文を190ページぐらいに納めてほしい」と言われていたので、5で割ると、毎月38ページ。
「なんだ、毎日1ページちょっとなので、全然オッケーじゃないか・・!」
自分が、計画を立てただけで出来た気分になってしまう”お気楽な性格”というのを棚に上げて、『こりゃ楽勝だ…』と思っていました。
そんなこんなで、ゆるゆる書き始めたものの、楽勝気分で余裕のつもりなので、逆にあんまり進まない。
新型コロナウイルスが5類に移行し、旅行が解禁となって初めてのゴールデンウイークを迎えたこともあって、あこがれだったダイビング・ライセンスをとったりするなど、原稿作成当初は、まだまだノンビリ気分だったのです…。
【2】「教科書」の呪縛
そんなこんなで、割り振ったページ数からは絶好調に遅れつつありました。
それでも、編集長が優しいお人柄だったこともあり、4月と5月のオンライン会議では、今後の進捗を聞かれるたびに「次はダイジョウブです(自信があるふりして、ニッコリ)」で過ぎていったのです。
そしていよいよ6月に差し掛かるころ、ようやく「あと4か月しかない」「これは真剣にヤバい」と焦り始めたのでした。
さらに自分を追い詰めたのは、タイトルにつけた「教科書」。
「PPP/PFI(官民連携)に関わるすべてのヒトの入り口となるような解説書になってほしい」という思いと、「PPP/PFI(官民連携)を知らない人も『どうやら世の中のトレンドらしいから読んでおこうかな…』と感じてほしい」という考えからつけた言葉だったのですが、これがなかなかに重たい。
「教科書」というからには、分かりやすくなければならないし、全ての領域をカバーしていなければならない。
難しい/珍しい言葉の定義を明確にするのは当然だし、法的根拠も明確にしておかないといけない。
でもその上で、初学者だけではなく、ある程度知識のある人が読んでも読みごたえがあるものにしておきたい…。
単純に「分かりやすいタイトルでバッチリ!」(これなら、ちょっとは売れるカモ??)と思っていた書名が、やたら重たいものだったということに、原稿作成に真剣に向き合い始めてから、ようやく気付いたのでした。
ここからの、省庁との不思議な会話や「PPP/PFIの『教科書』」としての創意工夫は、専門的な解説が伴うので、また別の機会にお話したいと思います。
【3】地獄の日々も、好きこそものの上手なれ
執筆活動を会社業務として行っているわけではないので、「原稿を執筆するから仕事を休みます」とは言えません。9時半~18時半は通常業務を行いながら、早朝・夜間・土日祝を使っての原稿執筆が始まりました。
朝は、5時半に起きて、7時半頃には会社のそばの朝食提供があるカフェにチェックイン。夜は、なるべく定時の18時半に会社を出て、22時頃までねばれるハンバーガーショップにチェックイン。これで、朝に1時間半、夜に1時間半程度の時間を何とかひねり出すことができます。
そんなこんなで、朝はトーストを片手に、夜はハンバーガーを片手に、週末は自宅の一室か家の近くのカフェを「マイ書斎」と思い込んでの執筆の日々が始まりました。
身体は相当キツイし(ぶっちゃけ、この4か月の無茶な生活で、相当老けたと思います(笑))、情報の裏どりをしながら執筆するので、半日以上粘っても、5行くらいしか書けない時もある。
「わかりやすさ」を第一と考えていたので、10ページ近く書いてから、「この論理展開だと、分かりやすくならないな…」と気づいて、勇気を出して、その部分を全ページ削除したり…。まさに「地獄の日々」でした。
ただ、不思議と、とても楽しかったんですよね…。
まだ見ぬ読者が1人でもいることを想像して、その人に「喜んでもらおう」と思いながら原稿を書くのは、本当に楽しい作業でした。
ことわざに、「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますよね。
原稿執筆が上手になったかどうかはわかりませんが、原稿にしようと思っているテーマ(私の場合はPPP/PFI(官民連携))が好きで、日本中のどこかにいる誰かが読んでくれる姿を想像するのが好きだと、「地獄の日々」もなんとか乗り越えてしまうぐらい、モチベーションを維持するのが上手になると思います。
さて、その地獄の日々も終わり、ようやく原稿ができあがりました。
そうなると、誤字脱字をチェックする校正作業があり、目次や索引などを確認する作業があり、表紙のデザインを決めたら、あとは出版社にお任せして、印刷ができあがり書店の店頭に並ぶのを待つだけです。
ただ、そこにもいろいろドラマがありまして…そのお話はまた次回といたしましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
また次の回にもお会いできるのを、楽しみにしています!
とはいえ、「本を書く」のが自分ゴト化しているとはいえ、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
