
S・キング映画…じゃない!『ブラック・フォン』
粗筋
コロラド州、デンバー。子供の失踪事件が続発する町で、ファニー少年もまた誘拐犯の餌食となる。目を覚ましたら地下室。鍵のかかった防音扉、手の届かない天窓、屈強な犯人…脱出不可能な監禁部屋なのだが、一つだけ異物があった。
それは、断線した黒電話。掛かる筈のない電話に出てみると、受話器から死者の声が流れ始めた。
今年のホラー映画では暫定ベスト!M中です。
7月は観たい(ホラー)映画が多くて後回しにしてましたが、実際観たらぶっちぎりでした。ジュブナイルホラーとして大変良い出来。以下、全ネタバレを交えながら語ります。
ノスタルジックホラーとスティーヴン・キング
原作者、ジョー・ヒルはモダンホラーの帝王スティーヴン・キングの息子です。
原作の短編から映画化の際に大幅に肉付けされているのですが、その手つきがまさにS・キング(映画)的。特に序盤はその傾向が強いので、物語を追いがてら述べていきます。
S・キング的:舞台立て
S・キング映画で近年成功したものと言えば、何と言ってもリメイク版『IT』。今作の出だしは、あからさまに『IT』に寄せて作られています。
失踪児童の張り紙、いじめられっ子の主人公、個性豊かな仲間たち…。また、ドラマ/映画/ピンボールゲームなどで懐古ネタを仕込んである辺りもそっくり。
誘拐犯の”グラバー”は、明らかにペニーワイズを意識しているでしょう。原作描写からビジュアルを変え、「白塗りの道化師/悪魔のマスク」で観る者を圧倒。幻視シーンでは(色は黒ですが)風船を携え遠くに佇む構図もある。
フィニ―の妹グウェンが兄を探し歩くシーンは、流石に爆笑。雨が降りしきるなか、黄色のレインパーカーを着て並木道を走るのです。排水溝からピエロが出てくるんじゃないかと(勝手に)ヒヤヒヤしてました。

S・キング的:主人公像
主人公フィニ―も、矢張りキング作品的な要素で固められています。
主人公は暴力的な虐めを受けており、生育家庭も機能不全を起こしている。しかし、数少ない仲間もいる。荒くれ者だが主人公を深く理解する親友と言えば『スタンドバイミー』のクリス、仄かに恋心を寄せる女友達なら、『IT』のベバリーが想起される。序盤は、彼らとの学校生活が展開されます。
そして何より、超能力はキングワールドの根幹をなすモチーフです。フィニ―、グウェンには見えないもの/聞こえないものを感知する力がある。その能力が遺伝するというのも、まさに『キャリー』『シャイニング』通り。
「あー、はいはい。最近流行りの懐古ホラーね。70年代ネタとキングネタをブチ込んでおけば、オタクが勝手に持てはやしてくれるヤツ」…。とこちらが高を括り出した辺りで、フィニ―が誘拐されます。しかしそこからは、全く違う展開が待っていました。
ロジカルな監禁劇
思うに、面白い監禁スリラーには2種類ある。
サイコパス、生活苦の犯罪者、恨みを買った相手…。誘拐犯の心を逆撫でせずに情報と譲歩を引き出し、解決に導く会話劇タイプ。キングの『ミザリー』はこっちですね。
そしてもう一つが、「身の回りの物品・知識・自然環境などを利用し脱出する」脱獄ゲームタイプ。今作は後者に当たります。
鳴る筈のない黒電話を取ると、グラバーのかつての被害者たちが代わるがわる「アドバイス」をフィニ―に託します。
「欠けたタイルの下は土だ」
「壁から配線コードを抜いてロープにしろ」
「玄関の鍵はダイヤル式だ。壁にメモしておいた」
「便所横の壁は、物置部屋に繋がっている」
「黒電話で、アイツを殴れ」
フィニ―はアドバイスに従い、様々な脱出方法を試みます。床を掘り進める、天窓の鉄格子にロープを渡す、玄関から逃げる、冷凍庫を潜って別室へ…。しかし、いずれの手段もグラバーが手を回しており、失敗してしまう。脱出劇のスリルと同時に、フィニ―・グラバー両者の知恵比べとしても楽しめる。
ホラーとスリラーの合間で
今作は幽霊ホラーとして売り出されており、ジャンプスケアなシーンも数度出てくる。しかし注意深く観ていると、別物だと気付く筈。何故なら、実のところ超常現象は起きていないのだから。
現代ホラーの第一人者ジェームズワンの作品や、S・キング映画では、悪魔/超能力は実在するものとして描かれます。一方の今作、幻覚/幻聴/想像の範囲内で収まるものばかりです。フィニ―は誘拐された子供らをあらかじめ知っており、受話器からのアドバイスも(周囲を注意深く観て想像を巡らせば)気づけるレベルのもの。人力では動かせないものが浮遊したり、複数人が怪現象を目撃するといった客観性のある事態は、実は起きない。

そしてこれは、スコット・デリクソン監督の作家性でもある。『エミリー・ローズ』『フッテージ』『NY心霊捜査官』のいずれでも、悪魔/幽霊は物理的存在としてはハッキリ描かれない。その実在は主眼にあらず、寧ろ異常な心理状態に置かれた主人公の苦悩と克服(或いは敗北)を描くことに注力してきた監督なのです。
「グウェンの視る幻視だけは、合理的説明が付かんだろ?」…それはその通りです。しかし彼女は(原作の姉然り)、フィニ―の脱出劇に一切かかわりません。同時進行劇の醍醐味である「並行して走っていた線が合流し、一本の流れになる」瞬間は、全てが終わったラストに置かれている。脱出に役立つモノ/情報を超能力で遣り取りしたり、彼女の通報で警察が間一髪間に合うといった協力バトル展開はない。
では何故、グウェンは、グウェンの超能力設定は必要だったのか?ぶっちゃけ居なくても、話成立するんですよ?…勝手な想像ですが、幻視シーンを入れることでジュブナイル成長譚の要素を強めるためだったと思うのです。
ジュブナイル成長譚
上に挙げた過去作では、スリラー要素は陰惨さを増すために機能していました。しかし今作では、恐怖から徐々にフィニ―の成長装置へと変わっていきます。
70年代はいじめ対策などまったくない時代だった。特に男の子にとっていじめっ子から身を守る術を習得することは、誰もが経験する通過儀礼だった。デリクソンはこう語っている。「最も古い記憶は家の近所で起こった暴力です。その通りにはいじめが蔓延していて、私がいちばん年下だったんです」
さらに当時は、アメリカ中が連続殺人犯の恐怖に襲われていた。…(中略)…「私の記憶では、小学校に入った頃、少なくとも私が育ったデンバーの北部では新たな連続殺人犯が現れていた」と、デリクソンは言う。
ジョー・ヒル、デリクソン監督らが子供時代を過ごした70年代は、こうした時代だった。そのなかで、グラバーの餌食となった少年らも懸命に生きていたことが(グウェンの幻視で手際よく)示される。アジア移民はスポーツで、チビは新聞配達で、荒くれ少年らは舐められないよう徹底的に暴力で対抗して…。
しかし、フィニ―だけは(誘拐されるまでは)逃げの一手を打つ臆病者だったのです。妹であるグウェンに守られ、いじめっ子の暴力にはなすすべがなく、憧れの子にも声を掛けられない。
そんなフィニ―も、命に係わる状況で漸く変化し始める。超能力(或いは鋭敏な感性)で幽霊(若しくは幻影)から天啓を受け、懸命に脱出を図る。5人の犠牲者は彼らなりの方法で脱出を試みたが、いずれも失敗してしまった(そのディティールも、幻視シーンと繋がりがあって面白い)。その過程を一つづつ辿りながら、フィニ―は行動的になり、泣き言を止め、知恵を巡らすようになる。

それが極に達するのが、親友ロビンが最後に託すメッセージですね。
「あいつにブチかましてやれ。退がって避け、前に出て、フルスイング」
生前は疎遠になりかけていた二人が、息をピッタリ合わせてシャドーボクシングの特訓をする…。絵面はシュールなのに、胸が締め付けられるような切なさに襲われる。
敵と鏡像関係
フィニ―と重なって見えるのは、幽霊少年たちに留まりません。実は、敵であるグラバーもフィニ―と鏡像関係にあります。
話が一旦脱線しますが、S・キング小説の魅力は圧倒的なディティールにあります。登場人物のエピソードを隅々まで作り上げ、リアリティのある・感情移入出来るキャラクターとして提示する。ゆえに、キューブリックの『シャイニング』に対しては
と徹底的に貶してきました。
話を戻します。今作は、(原作が短編ということもありますが)グラバーの背景は描かれません。どういう人間で、どういう経緯や思考で誘拐殺人を行うのかは、最後まで明かされない。では、今作はキューブリックの『シャイニング』のように、無機質で冷たい映画なのか?私は違うと思います。何故なら、グラバーにもまた超能力があるように仄めかされるからです。
序盤、黒電話を見つめるフィニ―にグラバーは言います。
「あれか?断線しているから、通じるワケがない。でも、鳴ったような気がするんだ」
と。
また、グラバーの弟マックスにもまた閃きがあることが示唆されます。
しかし、グラバーもマックスも、人生は満ち足りていません。兄はこの年で手品のアルバイトで、マックスは元ヤク中の無職。思うに、彼らは(フィニ―の母が自殺したように)思春期・青春期を生き延びられなかった人間ではないでしょうか。才能はあったのに、現実に圧し潰され歪んでしまった人として、フィニ―が辿るかもしれなかった人生として登場するのです。

映画において、鏡像関係は非常にオイシイ装置です。主人公の理想像、或いはダークサイドとして出てくるからこそ、その生き様を辿る(或いは選ばない)ことで成長に繋がる。単に敵として妥当するよりも、宿命やもの哀しさが味わえるのだから。
テンションMAXのラストバトル
しかし、ラストバトルは多幸感に酔いしれること請け合いです。
グラバーがマスチフ犬を連れて来たため、特訓で学んだボクシングスタイルは使えない。地下室奥に逃げるフィニ―、追うグラバー。ここからの怒涛の伏線回収が凄い。
掘ったタイル下は落とし穴に、天窓脱出で使ったカーペットと鉄格子はトラップに、電話コードは絞首縄に…。冷凍庫編で出てきた冷凍肉も、マスチフ犬を誘う餌にする完璧さ。映像的な再回収はさることながら、「5人の犠牲があったからこそ、このシチュエーションに辿り着けた」という逆襲展開も激アツ。彼らのアドバイスは、無念の死は決して無駄ではなかった。

グラバーの死に様も、非常に味わい深い。黒電話そのもので殺すという皮肉さ、耳元に当てられた受話器から幽霊の声を聴きながら絶命する復讐展開は良い。と同時に「幽霊の声が聴けた」というのも(前述した鏡像関係からすれば)彼に対する救済だと思うのです。
フィニ―の父親が子供らを暴力的に折檻し「見えないものは見えないし、聞こえないものは聞こえないんだ!」と言ったように、彼も親から才能を否定された人生を歩んだかもしれない。事実、劇中で黒電話が鳴ったことを「聞き間違い」だと否定したのだから。しかし「受話器を置け。電話から離れろ」とフィニ―に激昂したように、彼は電話を、超能力(才能)を自覚してもいる。
それだけに、最期に声が聴けた=ありのままの自分を肯定出来た、というのは切ないものが残ります。…まあ、だいぶ捻った解釈かもしれませんが。
今作は一足早くアメリカ本国で公開され、興行・批評両面で大成功を収めました。それを受け、スコット・デリクソン監督は
キャラクターは気に入ってるし、作品もユニークだから続編は可能だろうね。確かなことは言えないけど、「続編は無理!」って感じじゃ断じてないよ。
とも発言している。スマッシュヒットしたホラーに続編が付く風潮は、『ドント・ブリーズ』『クワイエット・プレイス』然り今に至るまで衰えていない。それに、今作の制作ブラムハウスプロダクションは、続編制作に熱心な会社でもあるのだ。

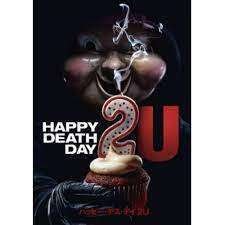
…まあぶっちゃけ駄作な続編も多いけどな!ブラムハウスは!
……それでもなお、スリラー演出が秀逸なスコット・デリクソン監督が続投してくれるなら、良い映画になってくれる筈!
彼は『ドクターストレンジ』2を蹴って、ミニマルな『ブラックフォン』を選んだという。英断だと断言できる、良い映画でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
