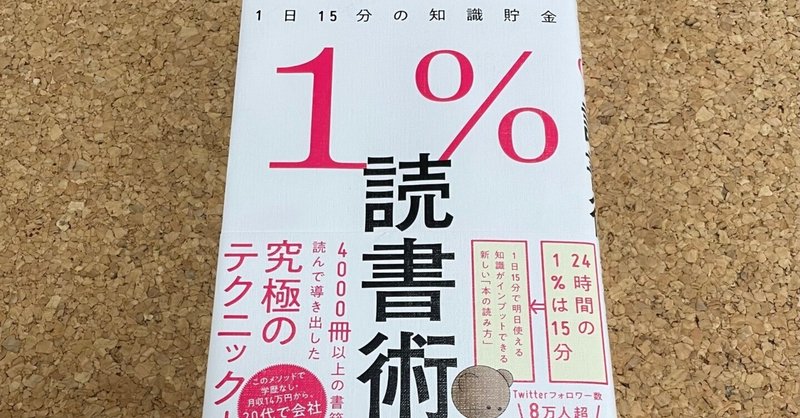
『1%読書術』【読書記録】20221024読了
【目的】
すぐに使える読書テクニックを知りたい
本の内容を定着化させるための方法を知りたい
【学び】
読むときは指をガイドにすると視線が文字に集中して読みやすくなる
(⇒指だと疲れるのでペンをガイド代わりに使おう)
ウェイクフルレスト=読書の合間に意図的にボーっとする時間を作る
適度に脳に休息を与えることで記憶の定着率が約10%アップする
(⇒ポモドーロタイマーの活用、25分読んだ後5分ボーっとする)言葉の置き換え=本の内容を自分なりの言葉にすると記憶効率が高まる。「要するに…」と言葉を置き換えてみる
想起=頭の中で読んだ内容を思い出す。
上記3つを掛け合わせると本の内容が定着しやすい
・読書のときは「要するに…」と置き換えしながら読む
・定期的に休憩をはさむ、目を閉じる
・休憩中に置き換えた言葉を思い出す(想起する)
読書に集中するための方法
・読み始めの5文字を、1文字あたり1秒かけて読む
視線を固定する(視認性が高まる)ことで集中力も高まる
・目を閉じてリラックス状態で3つの音を探す
(視覚を遮断→聴覚に五感が集中→音を探すことで意識が集中する)
速読は高速に文字を見て読んだ気になっただけ。内容の理解度は下がる。
速く読む=理解度が上がるわけではないが、たくさん読むことで理解するスピードは上がる。スキミング(=飛ばし読み)は効率的に本を読む手段
初頭効果と親近効果=人は最初の記憶と最後の記憶が最も残る
短く区切った(休憩を多く挟んだ)方が最初と最後の数が圧倒的に増えて、記憶定着率を高めることができる(⇒ウェイクフルレストを活用する)
聴く読書の恩恵=使用語彙量が増える
書籍は語彙の塊、受動的に良い言葉浴びることで語彙量が増える
速聴の恩恵(速聴は脳の言語領域を活性化させる働きがある)
・対話コミュニケーションの余裕ができる
=速聴に慣れていると対話がゆっくり感じて考える余裕ができる
・読解力が向上する
=文章を脳内で構築する速度が上がる
・言葉のつまりが減る
=説明能力が上がる。言葉がすらすら出るようになる。
速聴のやり方=聴く速度を徐々にあげていく
最初は1倍速、1週間で1.5倍速 ⇒ 1ヵ月で2倍速 ⇒ 3ヵ月で3倍速を目指す
読むスピードをアップさせる『速聴視認読書』
AIの読み上げ機能を利用する。(⇒kindleでテキスト読み上げ機能を使う)
速聴しながら画面を見て文章を読むことで
「速く読む」と「速く理解する」を両立させることができる。
アウトプットを習慣化させる
→習慣化することで考えるタスクが減ってスムーズに行動しやすくなるif-thenプランニング
=「もしAをしたら、Bをする」というルール決め
すでに習慣化できている行動(A)を習慣化したい行動(B)のきっかけにする
「ご飯を食べたら、サラダを食べる」など習慣化で反射的に行動することで、意思決定の疲れを取り除く
※決定を長時間繰り返し続けると決定の質が低下するらしい
(⇒まずは朝活でルール決めをしてみよう)
【名言】
習慣化させるために何かをやるのではなく、気まぐれをなくすためにルールを決める
「一生懸命すぎて疲れそう」と言われるけど、疲れより後悔のほうが嫌なんだ。やらなかった後悔が嫌だから挑戦する。好きに素直でいたいから本をたくさん読む。
【ひとこと感想】
本を読む目的は達成されたので読んで良かった。たくさんの本を読んで効果があったやり方を紹介しているので説得力がある。速聴とウェイクフルレストはすぐに実践してみよう。
【次に読みたい本】
アウトプット大全
インプット大全
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
