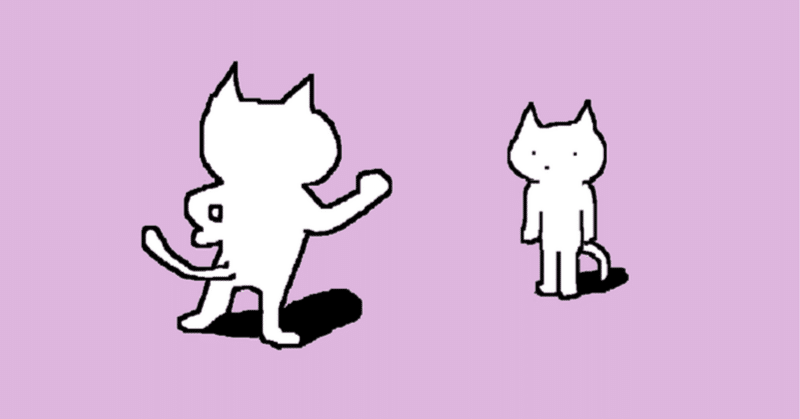
叱るもしくは注意する前に抑えておくポイント
こんにちは。
家族関係カウンセラーのひろっしーです。
今日は、「叱るもしくは注意する前に抑えておくポイント」というテーマで書いてみます。
問題行動の対応が行き過ぎたものにならないように、自分自身振り返りたくて、教科書的な内容をまとめ直します。
つまらないと思いますが、もしあなたのお役に立てるようでしたら、どうぞ。
問題行動を制止させる声掛けの問題点
では、さっそく。
福祉の仕事をしていると、問題行動にどう対応したらいいか、問われることがよくあります。
子どもでいえば、AくんがBくんを叩いたとか、大人でいえば、Cさんの遅刻が増えてきた、とかですね。
この時よく取られる対応が「いくら怒っても叩いちゃダメだよ」と叱ったり、「今後遅刻しないよう注意するように」と指導したりすることなのですが、皆さんもお心あたりあるようにそんなに(長続きする)効果はありません。
というのも、上記の声掛けには、今後具体的にどんな行動をしたらいいか、という意味のある内容が含まれていないからです。
#三振したバッターに三振するなと言ってるようなもの
問題行動の対処方法を検討する際抑えておきたいポイント
では、どのようにしたらいいか?
もし叱ったり注意したりするとしても、2つのポイントを抑えているかどうか確認してから行うといいです。
1つめは、問題とされる行動が起こる前に何があったか把握しているか、です。
もしも、AくんがBくんを叩いたきっかけがゲームに負けたことだとしたら、ゲームに勝てるように練習することがAくんがBくんを叩かなくて済む目標になるかもしれません。
そういった意味で、問題行動に対処する時のヒアリングのコツは、「どうしてBくんのことを叩いたの?」ではなく、「Bくんを叩く前に何があったの?」なのだと思います。
2つめは、うまくいっている場面にも目を向けられているか、です。
問題が生じるとどうしてもその問題をなくそうとしてしまいがちですが、実はうまくいっていることを増やした方が結果として問題とされる行動が減ることはよくあります。遅刻が増えてきたCさんであれば、遅刻を注意するよりも、Cさんの得意な仕事を意図的にお願いするとか、ですね。
今日は、ある方の支援方策を検討する際、うまく対応方法を言葉にできなかったことが悔しくて、問題行動の対応方法を整理し直させてもらいました。
問題行動の対応は、どうしても負の感情が入りやすくなるので、判断を間違いやすくなるなぁと思います。
お互いゆとりを持って関わっていきたいですね。
今日もお読み頂き、ありがとうございました!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
