
【イベントレポート】BRANDED SHORTSオンラインセミナー 『AIM』徹底解説
SSFF & ASIA 2022 秋の国際短編映画祭の一イベントとして10月12日に開催されたBRANDED SHORTSオンラインセミナーでは、今年6月に発表されたBranded Shorts of the Year 2022 ナショナルカテゴリー受賞の『AIM』(ネットギアジャパン)より、ネットギアジャパン代表杉田 哲也氏、GAZEBO監督、マツオ企画代表松尾弘匡プロデューサーをゲストに迎え、『AIM』を徹底解説すべく、社会課題のコンセプトメイキング~制作資金、SNS拡散までを深堀して聞くとともに、ケーススタディからのブランデッドムービー必勝対策についてトークを繰り広げました。
SSFF & ASIAの中で今年8回目を迎えたBRANDED SHORTSには、国内外から応募のあった企業や団体のブランデッドムービー687作品が応募され、国内、海外から1点ずつ優秀賞となるBranded Shorts of the Yearを表彰しました。

国内:ナショナルカテゴリーの優秀賞となった『AIM』はネットギアジャパンによるショートフィルム。
母親が亡くなって以来、部屋に閉じこもりゲームに明け暮れる23歳の舞と、たった一人の家族である父親の史人の関係を描くドラマです。娘との会話もなくただ部屋から聞こえてくるのは銃声ばかり。 娘の将来を案じているが自分ではどうすることもできず、インターネットに相談を投稿するというストーリー。いくつもの映画祭で受賞をしてきた本作をケーススタディに、本イベントでは、ストーリー性のある映像で企業や商材のブランディングを行うことの有効性や可能性について、企業、クリエイター、プロデューサーの各立場からの意見を聞きました。
ブランデッドムービーとは「心を掴むストーリーや映像の中に企業や商材の存在価値が感じられ、ブランドに対する認識を変容させる力を持つ映画や映像」
イベント冒頭、MCの諏訪からは改めて「ブランデッドムービー」とはどんな映像のことを指すのか、また、Branded Shortsでは映画祭としてどんな審査項目を設定して評価しているのかを説明しました。
・必然性(そのブランド、企業だからこその要素)
・認識変化力(視聴者の認識がどれだけ変化するか?)
・シェアラブル(シェアしたくなる魅力がどれだけあるか?)
・メッセージ力(強いメッセージが感じられるか?)
・視聴維持力(最後まで視聴される魅力があるか?)
・オリジナリティ(既視感の無い独自性があるか?)
・時代性(時代性がどれだけ反映されているか?)
・視聴後の想起力(視聴後、時間が経過しても、企業やブランドの想起に繋がるか?)
そのうえで、今年のBranded Shorts of the Yearナショナルカテゴリを受賞した『AIM』の受賞理由を、今年の審査員からのコメントを用いて紹介しました。
広告価値だけを意識するのではなく、まだ一部でネガティブなイメージを持たれながらも、世界的に人口が拡大するゲーマーへ寄り添うことで、最終的に自社のブランディングへ繋げていくという皆が得をする広告の作り方である点を評価
「ナショナルカテゴリーの中で最後まで評価された、いくつかの作品に共通している特徴は、企業が一方的に自社や自社ブランドの良さをアピールするのではなく、その先のステークホルダーまで寄り添う、半径が大きい作品でした。
普通、広告はユーザー以外、得しないものですが、受賞した『AIM』は、広告価値だけを意識するのではなく、まだ一部でネガティブなイメージを持たれながらも、世界的に人口が拡大するゲーマーへ寄り添うことで、最終的に自社のブランディングへ繋げていくという皆が得をする広告の作り方である点が評価されました。
更に、ゲーマーに焦点を当て、「人生こうあるべきだ」という古い価値観を一蹴し、「好きな事に夢中になって良いんだよ!」というジェネレーションギャップを突いたメッセージをストーリーと出演者の卓越した演技によって観る者を大きく認識変容させる力を持った作品であることが受賞へ繋がりました。」
面白さがブランディングにつながるのでは
3名のゲストを迎え、まずは『AIM』の制作背景をネットギアジャパン代表の杉田氏に聞きました。
杉田氏は、これまでCMやマーケティング活動をしてきたが手ごたえがなかったとし、BRANDED MOVIEがあることを知って、自社のブランディングをしていくこと、具体的には、「面白いものを見てネットギアを知ってもらうきっかけを作ろうとした」と説明しました。「広告」となるとどうしても「映画」を作りたいクリエイター側との足並みがそろわないケースが多いながら、『AIM』は企業・プロデューサー・監督、3つの立場が同じ価値観で進められたことがクオリティ高い作品制作のキーとなりました。

『AIM』のコンセプトは:プロゲーマーになる人を応援したい
また、杉田氏は、ネットギアジャパンとして、特に日本ではまだ未開拓なゲーミングルーターの市場を開拓したく、e-sportsイベントのスポンサーをしていたことなども参考にしてマツオ計画、GAZEBO監督より作品の企画提案してもらった流れを語りました。GAZEBO監督は、アメリカに本社を置くネットギアはグローバルでダイバーシティ重視の視点を持っていたこと、また、FTS*のゲームに関しては圧倒的に女性が少ない背景からも、主人公は女性にしたいとされたことを説明。
*FTS「First Person Shooter」の略称、日本語では「一人称視点のシューティングゲーム」
映像内でロゴやルーターの描写が殆どなかった点については、杉田代表より「映画の中でルーターが使われているだけで十分に効果がある」との理解から、セリフの中で物語にとって必然的な形でルーターの必要性が語られる設定にしたと、クリエイティブ優先で「面白くて見てもらえること、広告だと思わせずにストーリーの中に入らせて共感を呼ぶこと」を念頭に制作が進められたことを紹介しました。GAZEBO監督は脚本を完成させるまでに6か月かかったこと、その間にプロゲーマーにもインタビューをさせてもらい、一般的にゲームをしている人とプロゲーマーの違いが「喧嘩と武道」ほど違うことに気が付いたと述べ、日本では特に、プロゲーマーに対する意識や理解がまだまだ低いことを改めて知ったと説明しました。
当初はゲームのうまい小学生の女の子が男の子と出会う「ボーイミーツガール」ものを想定したものの、このインタビューを経て企画が大きく変化したとする監督。脚本に大きく影響を与えたポイントとして、プロゲーマーになりたい人のほとんどが直面するのが「親の説得・理解」という壁であると説明。ここをきっかけに話を作っていこうと思ったと述べました。
一方で、自身にも当時子どもが生まれ、親の気持ちになったというGAZEBO監督は、「自分の子がゲームばかりやっていたら」という視点も持っていたとし、プロゲーマーの目線と親の目線を二つ作ることで価値観の異なる、幅広い世代に見てもらえるように書いたと語りました。


作品内では、小さな家に親子で住んでいるが襖で隔たれている様子が最初に描かれます。昭和を感じるような父が生活する部屋と、ゲーム一色の部屋。襖一枚が価値観の断絶を表現しており、最後は襖が隔てていた世界が一つになる展開で、舞の目線、お父さんの目線が同じ目的(AIM)に向かって合う、二人の世界が一つになるという構成にしたと説明しました。
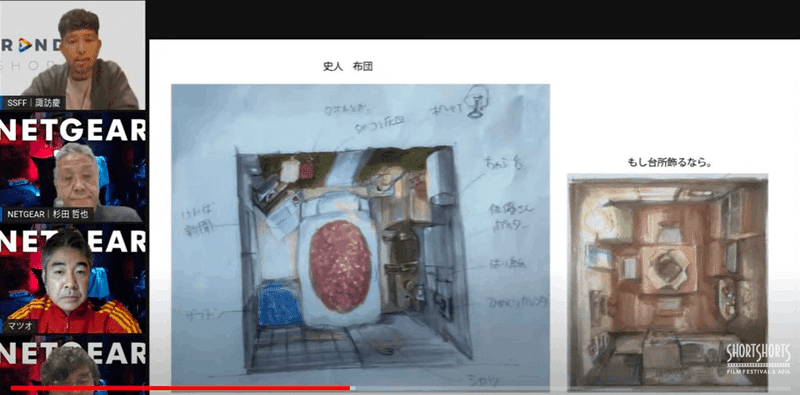
広告なのか映画なのか— 共感して好きになったら簡単には嫌いにならない
制作費用やキャストとの契約についても話が及び、『AIM』の制作費用についてはCM制作と同様の費用だったことが伝えられると、MCからはキャストとの契約についてさらに質問がありました。
プロデューサーの松尾氏からは、キャストとの契約も広告契約でもなく、商業映画でもないので、作品としての「買い取り」でお願いをしたことが説明され、この点は事務所側からも「広告じゃないのか、映画とどう違うのか」と良く問われるとし、『AIM』については上映時にお金はかからない点、ネット配信で一般の人々に多く見ていただけることや映画祭に出品しや受賞することでの出演者側のメリットを説明し理解が得られたと述べました。
また、尺についても、ネットで配信となると、5分以下にしてほしいという話もよくあるのでは?との問いに、映画祭に出せる尺で作ろうと考えていた。5分以下だと広告の要素が強くなる」と回答。SSFF & ASIAの映画祭出品基準(25分以下)を基準に考えていたことを述べました。
杉田氏はTwitterで拡散した要因についても触れ、映画祭出品の間は使用を我慢し、満を持して公開したので反響想定できたと説明。SNSで拡散するにあたっては尺が長かったのでは、という質問には、これまで『AIM』を含めて3作品ブランデッドムービーを制作してきた中で、「無理やり見せてもおもしろければ見る」ことが分かったとし、GAZEBO監督も、「最初見始めると止まらない映画」を目指したと説明しました。さらに、どうやったら拡散してもらえるか、「めっちゃ面白いから見て」とおススメしたくなるかも考えたと、エンドクレジット後にあるオチの演出についても述べました。
トーク終盤では、BRANDED MOVIEの可能性、役割について3人のゲストが一言ずつコメント。GAZEBO監督は、「映画的アプローチやストーリー重視の企画によって、広告でなくコンテンツとして見られる作品にすることで、ストーリーから入り込んでその企業の理念や哲学を理解できると、深い部分で共感し心で好きになる。1回好きになるとなかなか嫌いにはならない。」と語りました。
松尾氏は、ブランデッドムービーを3作品作ってみて、まだまだ企業側からの理解が少ない、と現状を説明。
「入口として企業が創るVP動画はあるが面白くない。後々 御社が映画を作ったという事実ができるし、短編なので映画祭に出せる。作るときは絶対面白いものしか作らない。映画祭で賞をとれれば広告宣伝としても営業にも活用できる、と説得するも、それでもなかなか理解されにくい。未来に向けて、ブランデッドムービー自体がブランドになると良いなと思う。」と述べました。
杉田氏は、「国内ではまだ知られていないレベルの起業でも、「面白い」という点で戦えば同じ目線で大企業と対等に戦える。ブランデッドムービーは資本力を超えてアイディアで勝負できる。一歩踏み出す楽しさをもっと多くの企業が感じてほしい」と期待を述べました。
オンラインセミナーのアーカイブ映像はYouTubeにてご覧いただけます。
