
「多様な価値観の世の中でいかに柔軟な対応をとれるかが鍵」創業111周年・世界中で評価される老舗刃物メーカー3代目が語るこれから
KAIグループ 代表取締役社長 遠藤宏治
米国アカデミー賞公認短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」は、2018年の創立20周年に合わせて、対談企画「Management Talk」を立ち上げました。映画祭代表の別所哲也が、様々な企業の経営者に、その経営理念やブランドについてお話を伺っていきます。
第28回のゲストは、総合刃物メーカー KAIグループ 代表取締役社長 遠藤宏治さんです。昨年110周年を迎えたKAIグループ。日本を代表する老舗企業を率いる遠藤さんに、その歴史からブランディングについての考え方まで、じっくりとお話をお伺いしました。

KAIグループ
1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とする刃物、カミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っている総合刃物メーカー。
111年間を3代で経営

別所:昨年と今年は御社にとってアニバーサリーイヤーなんですよね。おめでとうございます!
遠藤:ありがとうございます。私ども貝印グループは、今年で創業111周年を迎えました。「1」が三つも並ぶ年は滅多にないということで、節目の昨年と合わせて、数字の「110」と「111」を組み合わせたマークを作り、社内外さまざまな形でイベントやブランディングを行なっているところです。
別所:まさに老舗と呼ぶにふさわしい歴史をお持ちですね。
遠藤:ありがとうございます。私どもはこの111年間、祖父、父、私の3代という一世代あたりのタームが非常に長い形で会社を経営してまいりました。創業の地は岐阜県の関市。関の孫六に代表されるように、昔から日本刀の産地として広く知られている土地です。1908年に、私の祖父がポケットナイフを作りはじめたのが貝印グループの第一歩でした。その後、1932年には、神戸でカミソリを作っていたドイツ人から設備一式を購入し、岐阜で日本初の国産カミソリ替刃の製造を開始します。当初はなかなか簡単にはいかなかったそうですが、苦労してなんとか技術をものにしたそうです。以来長きにわたって磨き続けてきたカミソリの技術は、私たちの根源と言えるものになっています。
別所:初の国産カミソリ替刃は貝印さんだったんですね。
遠藤:そうなんです。そして、私の父の代になりますと、刃物の技術を活かして、包丁や爪切り、ハサミ、医療用刃物までを手がけるようになります。それぞれの刃物の専門メーカーは数あれど、世界中を見渡しても、私どものように総合的に刃物を製造している企業は存在しません。そこは当社の大きな特徴だと考えています。
父はさらに、当時日本で隆盛だったスーパーマーケットさんで売り場を確保するために、調理用品、化粧道具といった刃物周辺のさまざまな製品も貝印のブランドとして扱うようになりました。刃物だけを単体で売るのでは営業的になかなか厳しかったわけですね。その結果、メーカーであり、卸であり、販売会社でもあるという現在のKAIグループにつながる総合的な業態ができあがりました。現在、当社でプロデュースしている商品は、すべてを合わせると約1万アイテムにまで及んでいます。
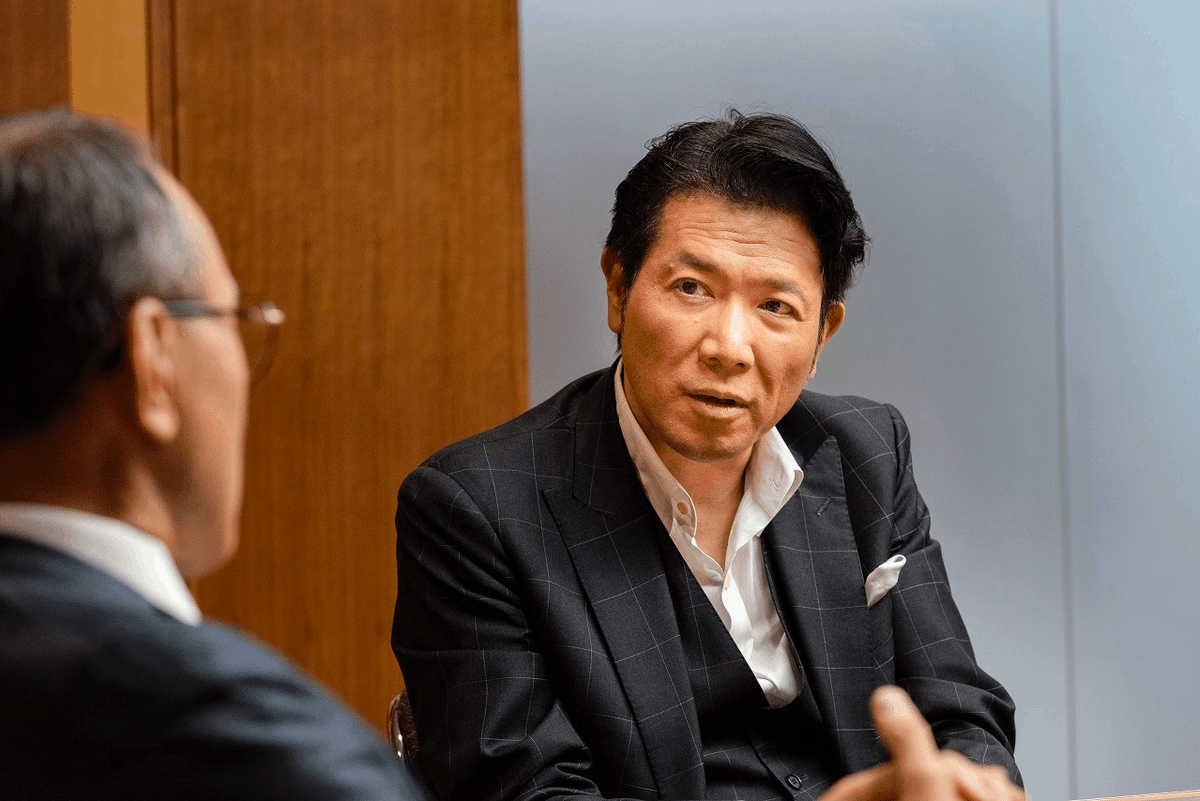
別所:1万アイテム。すごい数ですね……。そして、おじいさま、お父様からのバトンを受け継いだ3代目である遠藤さんが社長に就任されたのが平成元年。
遠藤:ええ。ちょうど平成の時代のはじまりからで、もう31年です(笑)。刃物は非常に生活に密着したものですから、ドメスティックな商品なんですけど、私の代で注力したのはやはりグローバル化です。父の代までは、ものづくりの拠点も海外にはありませんでしたし、販路も大きくは広がっていませんでした。当時、全体の売上に占める輸出の割合は15%程だったと記憶しています。それが現在では約50%にまで上がっています。
台湾では「KAI」が爪切りの代名詞に
別所:半分にまで。すごいですね。たしかに、日本の刃物は海外からの評価も非常に高いという印象があります。
遠藤:そうですね。面白いのは、刃物と一口に言っても、国や地域によって売れている商品のジャンルが違うことです。たとえばアメリカでは、包丁がもっとも好調です。20年近く前に現地で発表した「旬」というブランドで、15年ほど前から人気に火がつきました。ちょうど、映画「ラストサムライ」の公開や和食ブームの到来と重なる時期です。それまでは、アメリカで包丁といえばドイツ製のものが主流だったのですが、独特の縞模様のあるダマスカスの刃体で、ハンドルも和包丁のようなデザインの「旬」は非常に話題になり、おかげさまで累計700万丁を超える販売量を記録しています。
別所:日本ブームと相まって。アメリカ人が好きそうなデザインですし。
遠藤:ええ。そして、アメリカでのもう一つの大きな柱は、スポーティングナイフです。アメリカ人は、ポケットナイフが好きなんですよね。アウトドアでもバーベキューでも、あるいは、段ボールの開封などでもよく使われています。私どもは、40年前にアメリカのポートランドに現地法人を作り、二十数年前から工場を稼働させて、ポケットナイフやハンティングナイフを生産しています。そして、それをメイドインUSAの製品としてアメリカ軍にも納入しているんです。
別所:非常に高く評価されているわけですね。

遠藤:あとは、ハサミが全世界的に売れています。さまざまな用途向けがあるなかで、とくに私どもが得意としているのは、洋服のテイラー用のハサミや、皮を切るためのハサミといったプロフェッショナル向けのものです。最近では、高級外車のシートに使う皮を裁断するためにご使用いただき、非常に高い評判を得ています。それから、アジアですと、爪切りが評判です。インバウンドのお客様に選ばれるお土産のなかでも爪切り人気ですが、たとえば台湾では、「KAI」が爪切りの代名詞になるほど普及しています。一方で、ヨーロッパでは「KAI」がまだまだブランドとしては確立していないため、現地の大手メーカーと組んで、カミソリの刃の供給を行ったりもしています。
別所:素晴らしい。そうやって世界中で御社の刃物が受け入れられるなかで、ブランディングにたいするお考えもお伺いできればと思います。まず、原点的な話で言うと、「貝印」という社名の由来はどんなところにあったのでしょうか?
経営企画室長としてCI策定を主導
遠藤:社名の由来は諸説あるのですが(笑)、もっとも有力なのは、貝が太古の昔から刃物として使われていたから、という説です。実際、ロゴも、現在使っている「KAI」のエッジマークの前はホタテ貝のデザインでした。ただ、ホタテ貝のデザインは、競合があったため、商標的に刃物類以外のところで使えなくなってしまったこともあって、1988年にCIを導入しロゴも刷新したわけです。
別所:なるほど。
遠藤:そして、もう一つ有力な説があります。私の父は、祖父から受け継いだ「斉治朗」という名前でしたけれど、幼名を「繁」と言いました。それで、父が新しく社名を考える際、「しげる、しげる、しげる……シェル」と(笑)。そんな冗談のような由来もあります。
別所:(笑)。1988年にCIを導入した際は、どんなこだわりがあったのでしょう? 現在でもまったく古びていない素敵なロゴですよね。
遠藤:CIの策定は、当時経営企画室長だった私が担当していました。刃物メーカーですからやはり、シャープさは前面に打ち出していきたいという思いがありました。ですから、「KAI」のエッジマークは、真四角に切り込みをいれた文字を組み合わせていて。さらに「K」も「A」も「I」も実は、同一面積なんです。このデザインの原案を考えてくださったのは、ソニーでウォークマンを開発された黒木靖夫さんでした。SONYのロゴの生みの親でもある方です。
別所:超有名デザイナーが。
遠藤:黒木さんは、私どもの「ヤングT」という黄色い一枚刃のカミソリをご愛用くださっていたんです。ところが、ご自宅の近くのお店がヤングTを置かなくなったそうで、「困っている」と、当社のお客様相談室にお手紙をいただきまして。そのときはどんな方かわからないまま、担当者がヤングTをお送りしたところ、お礼のお手紙が届き、そこでご自身の身分を明かされたわけです。驚きますよね。当時、私はちょうどCI策定の真っ最中で、壁にぶつかっていたところでした。そんなときに、そのお手紙を読んで、私は傍若無人にも黒木さんに直接会いにソニーに行ったんです。そして、当社のCIに協力していただけないかとお願いをしました。すると、黒木さんは、快く原案の考案を引き受けてくださった。そして、黒木さんからいただいた直線で文字を作った原案を、当社のデザインチームがアレンジし、文字を同一面積にするといったアイデアをくわえて、現在使用しているロゴが完成したんです。

動画はこれからもっと有効に
別所:そこにも物語がありますね。僕は、ブランドを伝えるためには、物語が非常に重要だと考えていますが、遠藤社長はどうお考えでしょう?
遠藤:私たちは、ものを作り、それを販売することによって世の中にブランドをアピールしているわけですけれども、製品の開発にあたって「DUPS」というキーワードを大切にしています。つまり、「デザイン性に優れ(Design)、独自性があり(Unique)、特許に値し(Patent)、安全(Safety)&物語性(Story)」という要素を必ず盛り込むことにしているわけです。ですから、物語の重要性についてはずっと強く意識してきています。機能が良いことは当たり前の時代において、私たちの思いや姿勢を伝えていくことはとても重要ですから。
別所:素晴らしい! さらにそれをどう伝えるかも大切ですよね。私たちが運営するショートショートフィルムフェスティバル & アジアという国際短編映画祭のなかでも、企業の物語、ブランドを発信するショートフィルムを特集するブランデッドショートという部門を作っています。TVCMを流せばものが売れる時代から、インターネット上でどうコミュニケーションをするかという時代になって、動画の役割はますます重要になってきていると考えています。御社は動画コミュニケーションについてはどのようにお考えですか?
遠藤:KAIグループでもさまざまなショートムービーを製作しています。メッセージを伝えるためには、静止画だけではなかなか伝え切れない部分もありますよね。私も別所さんと同じ考えで、コミュニケーションの手段としての動画はこれからもっと有効になっていくと感じています。ただ、動画も、一本作っただけで十分というわけではないでしょう。私たちがプロデュースする約1万アイテムのなかには、さまざまなブランドがあります。貝印がこれからさらに躍進していくためには、それらのブランドをもっともっといろいろな形でアピールしていかなければなりません。それぞれのブランドが星のように一つ一つ煌めいて、その集合体である貝印が星座のように輝く、という世界を目指すことが必要だと考えています。
別所:ぜひ、たくさんのショートフィルムを作ることでそれを実現していただきたいと思います。それでは最後に、これからのKAIグループさんの展望について教えてください。
遠藤:祖父や父の時代は、どちらかといえば画一的な価値観で世の中が動いていましたし、お客様の購買活動もそれに近いものがありました。けれども、時代は変わりました。いまでは人々の価値観が多様化していますし、一人の個人のなかでもシチュエーションによって考え方が変化する時代です。そういう世の中をどのように捉え、柔軟に対応していけるか。それがこれからの企業活動において肝になってくるのではないでしょうか。私はもう60歳を超えていますから、これからの時代を担っていく社員たちが、それをどう実行していけるかが鍵になると思います。
別所:ありがとうございました。
(2019.6.20)

遠藤宏治(KAIグループ 代表取締役社長)
1955年岐阜県関市生まれ。1978年に大学卒業後、アメリカ留学を経て1980年に三和刃物(現・貝印)に入社。1986年に常務取締役・経営企画室長に就任後1988年にCI導入。1989年に代表取締役社長に就任。アメリカ、欧州、中国、ベトナム、インドなどグローバルな生産体制、販売網を構築した。1998年に世界初の3枚刃カミソリ「K-3」を発売。2000年に高級包丁「旬」を発売し、世界的にヒットさせる。
